ハベナリアの育て方

育てる環境について
育てる環境は春から秋にかけての生育期は直射日光にあたらない半日陰で雨があたらないような場所に置いておくことが大切です。室内のレースのカーテン越しなどで日光にあててあげるのが良いです。高温多湿の時期は病気にかかりやすかったり根腐れしやすかったりするので、
特に風通しを良くしておくようにします。秋頃になってから室内にとりこんであげましょう。冬の越冬温度は最低でも10度はほしいところです。もし可能であれば13度ほどあれば元気に越冬させることができます。育てる時に使うのはミックスコンポストと呼ばれる水はけと水もちが良いものを使うようにします。
例えば細かなバークを主にしてバーミキュライトや小粒の日向土、ふるった水ゴケのカスなどを混ぜ合わせたものが良いのではないでしょうか。水ゴケにそのまま植えてしまうことも可能ですが、ミックスコンポストに比べると少し湿らせ過ぎてしまうことがありますので、その辺りの調整が慣れないうちは難しいです。
もしミックスコンポストで表面が乾き過ぎてしまうようであれば、その表面部分に水ゴケを置くようにすることでフォローすることができます。これ以外も球根を植えるのは軽石や水ゴケのみで作ったものでも良いです。置く時には薄めに広げることがポイントになります。
植え付けや植え替えをする時は早い春の3月から4月頃に行うのが良いです。植え替え自体は毎年ではなく、2年か3年に一度行なうようにすれば大丈夫です。植え替えに関してはその株の様子をみながら考えるようにします。
種付けや水やり、肥料について
乾燥に弱いのがラン科の植物なので、生育期は乾かさないようにたっぷりと水を与えるようにします。開花後は休眠期に備えて少しずつ水を与える量や回数を少なくしていきます。少しだけ乾かし気味にするのがコツですが、完全に乾かしてしまうのは良くないので
土が少し湿っているかなという程度には水を与えておきます。気温が低い時にも多湿状態では根腐れを起こしやすいので注意が必要です。肥料は春の生育期の初期の頃は少量の固形の肥料を施し、それにプラスして芽が出る時期から開花が終わる頃までは液体肥料を薄めにして月に1度与えるようにしましょう。
ハベナリアは種で増やすというよりもその品種にもよりますが、株分けで増やしていくようにするのが一般的です。親株の周りに小さな子株が出来てきます。大体は1株につき子株が1つから2つできるのですが、品種によっては10個以上も子株ができてくることもあります。
それらを親株から切り離して、また土に植えつけておくことで少しずつ大きく成長していきます。あまりに小さな子株はそのままにしてもう少し大きくなるのを待ったほうがいいですが、それ以外のものは順調に栽培していれば十分に開花できるサイズです。
しかし球根自体の寿命が約2年ほどになりますから、親株から子株を株分けできる状態にしないと増やしていくどころか全滅してしまいます。なんとか増やしていくためにはやはり根などの管理をちゃんとして腐らせないようにすることが大切です。
増やし方や害虫について
ハベナリアについてくる害虫はナメクジが多いですが、アブラムシがついてしまうこともあります。アブラムシは茎や葉などの汁を吸ってあっという間に増えてしまいますので、見つけたらすぐに退治してしまうことが大切です。薬剤もありますが、
それを使用する前に下に落としたりしないように気をつけながら手などで簡単に除去することもできます。かなりの数いるのを見かけたらすぐに応急処置を施しておくのが良いです。ナメクジは外で置いておくといつの間にかくっついているものなので薬剤で駆除するか捕殺してしまうようにします。
ラン栽培ではナメクジが来ないような場所を見つけるのが第一歩だといえるほどナメクジ被害は多いのです。病気に関してはほとんどかかることはないのですが、葉っぱの組織が柔らかいことや湿度が高くなってしまっている時期に褐斑病にかかってしまうことがあります。
症状としては葉に褐色の斑点が出て広がっていきます。この病気を防ぐには定期的に薬剤を散布しておくことや風通しを良くしておくことが大切です。増やし方は基本的に株分けで増やしていきます。株分けをするのは植え替えの時期でOKです。
高さがない浅い鉢を用意するか発泡スチロールも良いです。発泡スチロールは断熱効果が高いので効果的です。鉢底には軽石か中粒の鹿沼土を敷き、次に十分吸水させてから絞った水ゴケを入れます。古い用土を取り除いた株を分けて2cmから3cm間隔で乗せていきます。その上に水ゴケを1cmくらいの厚さで乗せて完了です。
ハベナリアの歴史
ハベナリアの原産地や生息地は世界中です。特に熱帯アフリカや北半球の温帯を中心に全世界に600種から700種ほどもあります。日本国内にもその一種があり、名前はサギソウといいます。しかしサギソウは日本での自生は非常に少なくなっており、
環境省の絶滅危惧植物としてレッドリストに載せられています。ハベナリアという名前はラテン語で革ひもや手綱を意味するハベナに由来しています。これは花や器官の形からきているといわれていますが、はっきりとしたことはわかっていません。
サギソウは国内での歴史は古く、17世紀頃にはすでに栽培しているのが記録されています。ラン科の植物なのですが、その仲間はたくさんいて、花姿もいろいろあります。サギソウは真っ白で白鷺が飛び立っている姿のようにも見えますが、
花びらが4つあるタイプのものやその花色に関しても様々で、ピンク色や白色、オレンジ色などあります。しかし国内でハベナリアというとサギソウを思い浮かべられることが多いです。サギソウは学名をハベナリア・ラディアータといいます。渡来時期に関しても
それだけ品種がありますのでいつと決定づけることは難しく、品種によって様々です。しかし育て方の難易度はそれほど難しいということもなく、5段階でいえば2から3辺りになります。ハベナリアの種によっては成長するのは土ではなく樹木や岩肌に寄生して育つもの、岩の上や流水の中で成長していくものなどあります。
ハベナリアの特徴
ハベナリアはラン科の植物で、草丈は15cmから60cmほどになります。洋ランの中でもその品種が非常に多い植物でもあります。ほとんどの種は地面に根をはって育っていく地生ランで草原や湿原、林の下などで自生しています。サギソウも湿原などで自生しています。
日本にはサギソウを含めて10種ほどが存在しているといわれています。ハベナリアは基本的には根茎が地下にあって冬の間はその状態で越冬し、春になってその根茎から新しい芽を出して葉が広がり、茎も伸びて数輪の花をつけるというわけです。
そして開花後には茎や葉は枯れ、代わりに新しい根茎が出てきて再び休眠に入ります。花の形は唇弁と呼ばれる部位が大きく発達していることが多く、そこはその名の通り、リップと呼ばれることがあります。種類にはサギソウの他にもそのサギソウの仲間である
ハベナリア・メデューサやハベナリア・ミリオトリチャといわれる一見タンポポの綿毛のような細長い糸のような見た目のものもあります。基本的には鉢植えで育てるほうが移動などさせやすいので管理もしやすく、便利です。管理をしっかりとしていればかかってしまう病気も特にはなく、
ナメクジ以外は害虫もほとんど心配いりません。耐暑性はとても強いのですが、逆に耐寒性はとても弱く、冬場の管理には気をつけてあげる必要があります。開花時期はその品種にもよりますが、大体は7月から11月頃に花が咲いていることが多いでしょう。
-

-
ハイビスカスの育て方
熱帯地方や亜熱帯地方を生息地として大きな花を咲かせているハイビスカスの種類の中には古代エジプトの3000年から4000年...
-

-
ショウジョウバカマの育て方
ショウジョウバカマは日本から南千島、サハリン南部を原産地とするユリ科ショウジョウバカマ属の多年草です。北は北海道から南は...
-

-
観葉植物としても人気があるイチゴの育て方
イチゴは収穫が多く病気や虫に強いので、家庭菜園で人気です。イチゴの中でも比較的葉が多いワイルドストロベリーは観葉植物とし...
-

-
ルッコラの育て方
ガーデニングブームとともに人気になっているのが家庭菜園です。自宅に居ながらにして新鮮な野菜をたべられるというのも人気の秘...
-

-
一重咲きストック(アラセイトウ)の育て方
一重咲きストック、アラセイトウはアブラナ科の植物です。原産地は南ヨーロッパで、草丈は20センチから80センチくらいです。...
-

-
サルビア・スプレンデンスの育て方
サルビア・スプレンデンスは、ドイツ生まれの植物学者セロウによってブラジルで発見されました。彼はブラジルを中心に植物探検を...
-

-
ソラマメの栽培~ソラマメの種まきからソラマメの育て方
ソラマメの種まきは関東を標準にしますと10月下旬から11月上旬になります。地域によって種まきの適期は異なるので種袋で確認...
-

-
ホワイトレースフラワーの育て方
この植物においてはセリ科になります。ドクゼリモドキ属となっています。宿根草ですから何年も花をつけることができますが、あま...
-

-
センノウの育て方
センノウは鎌倉時代の末か室町時代の初めごろ、中国から渡来したと言われている多年草です。中国名は「剪紅紗花」と書き、センコ...
-

-
ベランダでルッコラの栽培
家庭菜園の魅力とは、自分で大切に育てた野菜を味わうことができることにあります。育てる達成感と味わう幸福感を体感してみたい...




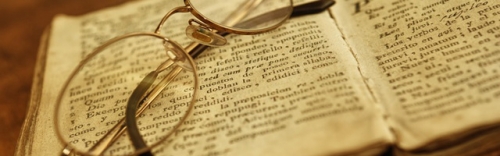





ハベナリアはラン科の植物で、草丈は15cmから60cmほどになります。洋ランの中でもその品種が非常に多い植物でもあります。ハベナリアの原産地や生息地は世界中です。特に熱帯アフリカや北半球の温帯を中心に全世界に600種から700種ほどもあります。日本国内にもその一種があり、名前はサギソウといいます。