クヌギの育て方

育てる環境について
クヌギはわんこそばで知られている都道府県以南、うどんで知られる都道府県が属している地方、ちゃんぽん麺で名が知られている都道府県が所属している地方、我が国で最西端の島が実在している都道府県を生息地としている樹木です。ただ、わんこそばで知られている都道府県、さくらんぼで知られる都道府県では南のほうに分布しているというよりは、北のほうにいっぱい分布しているようです。
原産地に関しては、外国であるとする説が実在していますが、一方で、図鑑では我が国でも化石が発見されているという記述が実在するようです。また前の段落で書いたように、植林を行なってから10年ほどで木材として利用が可能になるほど生長が早いとされています。また適度に湿った場所を好みますが、
乾燥に強いとされていて、潮の満ち引きで発生し海から吹いてくる風などに耐えられると言われています。ただ、庭で植えるには適していないとされています。というのも、生長した根っこが隣の家にまで生えてくる事態が起こりますし、住んでいる家にまで根っこが生えてきて傾く場合もあるからです。栽培する際に使われる土は肥えている土を好むと言われていますが水はけが相当悪い土でなければ、さほどこだわらなくとも大丈夫です。
鉢植えでの育てるというのも可能であり、鉢植えで育てる場合はショップで売られているような園芸用の土で野菜、鑑賞用のプラントと変わらないスタンスでも生長が可能ですし、また鉢植えで育てれば、生長しすぎて困ってしまうという事態にならなくて済みます。日光が当たる場所を好むと言われているので、栽培を行なう際は太陽の光が当たるところに置きます。
種付けや水やり、肥料について
育て方ですが、水やりは土の表面が乾燥したら、行なうのが適切ですが、鉢植えで栽培をする場合は、行なう頻度に関して、シーズンごとに回数を変えるのが適しているとされています。暑いシーズンであれば1日1回のペース、冬では2日か3日に一度のペースで行なうのが適していると言われています。
樹木になって根付いたのであれば水やりはしなくとも大丈夫だとも言われています。なお鉢植えで育てる場合は直径が30センチメートル弱の大きさ以上の鉢植えが適していて、使用する土は既述通り、園芸で使われているような培養土で事足りますが、水はけがよろしい土にしておいた方が得策です。肥料に関してですが、
冬のシーズンで与えるだけでも事足りていますし、盛んに生長が行なわれている場合には与え過ぎるのは止めておいた方が賢明です。与え過ぎるとクヌギの見栄えが悪くなったり、害虫に対する抵抗力が弱くなったりする事態になります。また鉢植えで育てる際はさほど与えない方が無難です。樹木になるまで育てる際には、すぐに生長するので、毎年枝を切り落とす行為、
2年に一回の植え替えを行なうのが大切になってきます。枝などを切り落とす行為を行なうシーズンは決められていて、クヌギの場合は冬に行なうのが適切だと言われています。謂れとしては冬は休眠するシーズンに当たるからだとされています。反対に暑くなるシーズンで行なうと樹液が流れ出て、枯れてしまうという事態が発生します。以上から冬に行なうのが賢明です。
増やし方や害虫について
クヌギは以上の記述に書かれているようにいろいろな昆虫が好む樹木ですので、害虫は言うまでもなく発生します。メインとなる害虫は以上に列挙したヤママユガの幼虫、タカサゴツマキシャチホコという蛾の幼虫、クヌギエダイガタマバチという虫などがいます。タカサゴツマキシャチホコはクヌギの葉っぱを餌にしていて、また幼虫が集まっているケースも実在しています。蛹の形態で冬を越す特質を持っています。
なお、武家政権の初代将軍を神様として祀っている神社が建てられている都道府県では絶滅の危機にさらされている蛾だとされていて、引き起こした要因としては林の管理を行なわずに放置したという要因などが列挙されています。クヌギエダイガタマバチは枝のほうに瘤を作ります。そういった瘤からは成虫が出てきます。
年に2回、成虫が実在しているという現象が発生しますが、季節により異なります。春の場合はオスとメスの両方が実在しますが、冬の場合だとメスだけが実在します。こういった害虫以外にも、アブラムシ、メイガの幼虫、カミキリムシの幼虫といった虫も発生する場合があるようです。
カミキリムシの幼虫はテッポウムシとも呼ばれていて木材などの害虫としても知られています。テッポウムシが発生しないようにするのであれば、カミキリムシの成虫を見つけ次第、取り除くというのが最適の手段です。害虫以外にもウドンコ病に気を付けるのが大切になってきます。疾患にならないようにするためにも日光が当たるところに置きます。増やし方はドングリを植えるという手段が実在しています。
クヌギの歴史
クヌギは広葉樹の一つあり、かつてはツルバミとも呼ばれていた樹です。またコナラとともにカブトムシ、クワガタムシといった昆虫類が集まる樹木であり、そういった昆虫を捕まえる際にこういう樹木をずっと見張っている者もいるくらいです。ペットショップ、ホームセンターなどでも飼育用のマットとして売られていて、
カブトムシ、クワガタムシを飼育する際に使われるケースが実在しています。また飼育用のマットだけではなく、クヌギは昔、燃料用、肥料用などとしても使われていました。植林を行なってから約10年で木材として使用するのが可能となり、木を切っても切った跡から芽が出てきて、何年も経てば再生するのでかなり有用な樹木であると言われています。
枯れ葉は腐葉土として使われていました。またもっとさかのぼれば、発見された土器と一緒に実が発見されたという訳から、食用として食べられていたと言われています。しかし、年代が経過していくにつれて、近代化が進むと農家の者などの生活のスタイルが変わっていき、ほったらかしにされるようになりました。
樹木の皮、実の殻はツルバミ染めの染料として用いられてきました。ちなみに、ツルバミ染めを施した衣服は、大昔に使われていて、色が褪せにくく丈夫な衣服でした。天皇、もしくは貴族が政治の実権を握っていた年代では身分が低い者たちが着ていた衣服でしたが、年代が進むと貴族の衣装として使われるようになりました。また詩歌でもツルバミという言葉が使われています。
クヌギの特徴
樹の高さは10メートルから20メートルほどにもなり、葉っぱの形は長細い楕円型で周りにはギザギザがついています。アベマキという別の樹木と交配するのが可能であり、交配して育った樹木はアベクヌギと呼ばれています。花は雄花と雌花とが実在していて、風を媒介として子孫を増やすという風媒花の特質を持っています。
実であるドングリは球のような形をしていて、食用にはなりますが、何らかの処理をしないで食べるというのは渋味があるので不可能であり灰汁抜きといった処理を行なわなければなりません。前に記述したようにクヌギはコナラとともに、カブトムシ、クワガタムシ、スズメバチなどが集まる樹木であり、そういった虫が樹液を求めてやってきています。
メカニズムとしてカミキリムシの一種が、産卵するために樹木に穴を開けた結果、樹液が出てくるとされてきましたが、近年の研究でボクトウガの幼虫が樹木に開けた穴の周辺を加工しているために樹液が出てきているという事実が判明したとされています。なお、ボクトウガの幼虫は集まってきた小さな昆虫、ダニなどを食べるとされています。
また樹液を吸う昆虫だけではなく、葉っぱを食べる昆虫も実在していてオオミズアオ、ヤママユガなどといったガの幼虫が列挙されています。シジミチョウの一種で幼虫になっている間、若葉を食べる蝶も実在しています。クヌギの皮は生薬にもなり、じんましん、アトピーといった疾患に効き目がある十味敗毒湯などの漢方薬と配合して使われます。
-

-
ハナショウブの育て方
ハナショウブとは6月の梅雨の時期に花を咲かせる花弁の美しいアヤメ科の多年草です。原産は日本や中国などのアジア圏になります...
-

-
ロドリゲチアの育て方
花の特徴としてはラン科になります。園芸上においてもランとしてになります。一般の花屋さんでも見つけることができますが、ラン...
-

-
ハナイカダの育て方
ハナイカダはミズキ科の植物です。とても形がユニークですので一度見ると忘れないのではないでしょうか。葉っぱだけだと普通の植...
-

-
フリチラリアの育て方
フリチラリアはユリ科の植物でフリチラリア属に属します。生息地は北半球独自の品種であることから、地中海沿岸地方から日本、カ...
-

-
にんにくの育て方
にんにくは、紀元前3000から4000年以上前から古代エジプトで栽培されていたもので、主生息地はロシアと国境を接している...
-

-
レウコフィラムの育て方
レウコフィラムという花は一昔前は珍しい花の一つでした。もともとアメリカのテキサスからメキシコにかけての原産の花で非常に乾...
-

-
ジャボチカバの育て方
ジャボチカバはブラジルを原産地とする常緑性の果樹です。熱帯植物に分類される樹木であり、その大きさは30センチ程度から3メ...
-

-
シャンツァイの育て方
シャンツァイはコリアンダーと言うセリ科の一年草で、中華料理などで利用される野菜です。コリアンダーと言うのが学名であり、シ...
-

-
イクソーラ・コキネアの育て方
この花の特徴は何といっても花です。アジサイのように小さな花が密集してひとつの花のように見えるところです。細かいことを言う...
-

-
ステルンベルギアの育て方
ステルンベルギアの名前の由来は19世紀に活躍したオーストラリアの植物学者であるシュテルンベルク氏に因んだものです。他にも...




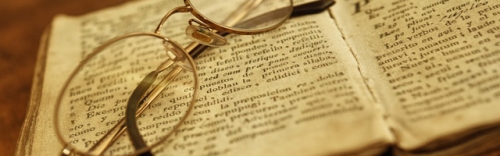




クヌギは広葉樹の一つあり、かつてはツルバミとも呼ばれていた樹です。またコナラとともにカブトムシ、クワガタムシといった昆虫類が集まる樹木であり、そういった昆虫を捕まえる際にこういう樹木をずっと見張っている者もいるくらいです。