ミントの育て方

ミントの育て方を覚えておこう
ミントは日当たりの良い場所を好みますので風通しが良く日光によくあたる場所に置いてあげるといいです。ただし日光が好きといってもあまりに強い日の光をあててしまうと葉が枯れてしまったり生育が悪くなってしまいますので注意しましょう。
春から秋頃までは風通しがいい半日陰で育てるのがポイントです。高さがない低い草丈のミントは夏の高温多湿で蒸れて枯れてしまうことがありますが、株さえ元気であれば涼しくなってきた頃に再び復活します。寒さにはとても強く、0度しかなくても越冬することができます。
霜にあたってしまった時には地上に出ている部分は枯れてしまいます。しかし根は生きていますから春になって暖かくなると新芽が出て育ち始めます。冬にも葉を収穫したければ霜対策は敷きワラなどをして防寒対策をするのが良いです。
湿り気のある土を好むので、土の表面が乾いたらたくさん水を与えましょう。特に夏は水切れをさせないように朝に水やりをして、夕方にも土が乾いてないかチェックをしておくのがいいです。乾いてると感じたら水を与えてあげます。
水切れさせると葉や茎部分が硬くなってしまうのでハーブとしては使いにくくなってしまいます。香りをキープさせたい場合は肥料は与えすぎないほうがいいので、春に新芽がでてきたらゆっくりと効果を発揮するタイプの粒状の肥料を根元に少しだけ与えておきます。
栽培する上でのコツをつかもう
ミントは庭植えしてしまった場合、かなり広範囲に繁殖してしまいますのでそうなると別のものを植えたいとなった時に駆除をするのが大変になってしまいますから、それを避けたい場合は庭植えはしないようにするか、こまめに地下茎や茎はカットして広がらないようにしたほうがいいです。
8月頃に株元でカットしておくと秋には再び新しい芽が出て収穫できるようになります。香りを重視したい場合は花がつくタイプの場合、花が咲く前に摘み取ってしまうと良いでしょう。収穫は春から秋にかけて随時することができます。
保存したい場合は株元で枝を刈り取ってしまい、風通しの良い場所で逆さに吊って十分乾燥させましょう。花もきれいですからいくつかの花茎は咲くまでとっておき、切花を楽しんでみるのもオススメです。使う土は鉢植えの場合、小粒の赤玉土を6、腐葉土を3、バーミキュライトを2の割合で混ぜ合わせたものを使うのが良いです。
庭植えにするなら植える前に腐葉土や堆肥を混ぜ込んでおくといいです。鉢植えにした場合は毎年鉢を大きくしてあげることが必要です。植え替えの時期はいつでも良いですが、夏は乾きやすいので避けます。土も新しい清潔なものを使います。ただし株をそれ以上大きくしたくないのであれば株分けをするのも良いです。
またミントは違う種類を同じ場所に植えていると交配して種を作ってしまう場合があります。交配したものを育てても香りが薄くなってしまうことが多いので、できるだけ距離を離しておくのがポイントです。かかりやすい病気やつきやすい害虫は特にはありません。
種付けをして増やすことは可能?
ミントは株分け、挿し芽、種まきで増やすことができます。株分けは植え替えするタイミングで行います。株分けする時は古い土は落として古い茎も全て取り除いてしまいます。芽を3本から4本で1つの株として分けます。茎が長く伸びてしまっている場合は先に4節ほど残してカットしてから植えつけるのが良いです。
挿し芽は茎の先端を5cmから6cmほどに切って1時間ほど水にさして水揚げをしてから用土をあらかじめ湿らせてある鉢に挿します。根が出るまでは乾かさないように半日陰の場所で管理します。種まきは4月頃と9月頃に行ないます。
花が咲き終わったら種ができるのをこまめにチェックし、下に落ちないように採取します。ただし種まきから育てた株は香りが弱くなりがちなので、そこは承知しておく必要があります。可能であれば種を購入して育てるようにしたほうが良い香りのものが育ってくれます。
ミントは自家製であれば安心して使うことができます。いろんな用途に利用してみるのもいいです。例えばハーブティーはフレッシュミントで作るとおいしくできますのでオススメです。ティーポットに摘んだばかりのミントの葉を入れて熱湯を注ぎ、5分ほど待っていると黄緑色の美しい水色になってきます。
好みで砂糖や蜂蜜を入れて飲んでもいいです。葉をどんどん摘んでも2週間ほどすれば美しい葉がまたどっさりと生えてきています。摘んだミントをきれいに洗って乾かしておき、それをホワイトラムに入れて2日ほど漬け込んでおくとおいしいミント酒が出来上がります。
出来上がったミント酒と氷に炭酸水を加えれば簡単にモヒートを楽しむことができます。お好みでシロップを入れてもおいしいです。レモンとミントをグラスに飾り付ければ本格的な雰囲気を味わえます。
ミントの歴史
ミントは3500年ほど前の古代ギリシャですでに生薬として利用されていました。歴史上でも最も古い栽培植物として知られています。日本に渡来したのはなんと2000年以上前のことで、中国から渡ってきました。
そして10世紀頃になると平安貴族の食卓に山菜として出てきていましたし、室町時代には薬として使われていたという記録が残っています。宇治の辺りでは今は有名になっているお茶よりも先に栽培されていたともいわれています。
19世紀頃になると本格的に岡山で栽培が始まり、やがて広島から新潟や群馬、山形などにも広がっていきました。1873年頃からは国内で製造された山形ハッカの取卸油がロンドンへ進出、国内初の輸出となりました。明治17年には北海道で試作が始まり、現在の旭川市永山町での成功が最初でした。
世界的にはBC3733年のギザのピラミッドの建設の際に労働者たちの食事にミントが出ていましたし、ミイラの下に敷いておくことで腐敗防止になっていました。古代ギリシャ時代にはミントは力強さの象徴として右腕につけられていました。
また9世紀にはヨーロッパ中の修道院の庭でミントが栽培されるようになっており、ミントを使ったリキュールは消化不良が起きた時などに大切に飲まれていました。16世紀になると床にミントを撒いておくことで食事の席では食欲増進にしており、寝室では良質な睡眠をとる目的がありました。
ミントの特徴
ミントの特徴といえば、やはりあのハッカ系の味でしょう。1840年頃にアメリカで本格的に商業用に栽培されるようになり、40年後にはペパーミントガムが発売されています。原産や生息地はユーラシア大陸で、こぼれ種と地下茎によって繁殖します。その繁殖力はかなりのもので、あっという間に増えていきます。
畑などに地植えしてしまうと別のものを植えたくなった時には駆除するのに難儀します。葉の部分に爽快感があり、ハーブとして料理やお菓子、カクテル、薬用酒などに使われる他、精油は香料として食品や歯磨き粉などによく使われています。モロッコではお茶と生のミントを混ぜたお茶を日常的に飲んでいます。
漢方薬としても使われており、清涼、解熱、発汗、健胃などの薬効があります。変種ができやすいという特徴があるため、その品種はじつに600種を超えるといわれています。大きくわけてペパーミント系とスペアミント系の2つがあります。ペパーミント系は香りが強いですし、メントールの含有量も多いです。
スペアミント系はそれほどではなく、香りも比較的弱いですし、甘めです。その年にできた花が咲く前に摘み取ったものを初摘みといってフレッシュで雑味がしないのが特徴的です。草丈は大体10cmほどの小さいものをよく見かけますが、大型なものですと最大1mほどにもなります。開花は6月から9月頃になります。
ハーブの育て方など植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:チャービルの育て方
タイトル:キャットミントの育て方
-

-
バイカカラマツの育て方
バイカカラマツとはキンポウゲ科の植物で、和風な見た目やその名前から、日本の植物のように考えている人も少なくありませんが、...
-

-
ハスカップの育て方
ハスカップは青紫色の実をつける植物で、スイカズラ科スイカズラ属です。落葉低木と言う事からも、庭木など観賞用で育てたいと言...
-

-
カラタチの育て方
今から約1300年前に伝来していて、和名の由来はからたちばなという言葉が略されたとする説が実在しています。ただ、からたち...
-

-
ユーフォルビアの育て方
ユーフォルビア、別名、ユーフォルビアダイヤモンドフロストは、トウダイグサ科ユーフォルビア属の植物です。生息地は世界の熱帯...
-

-
ボケの育て方
ボケはもともと中国原産の落葉低木です。梅と比べてもかなり木の丈が低く、コンパクトな印象で春の花木として人気があります。 ...
-

-
メラレウカの育て方
この植物は、フトモモ目、フトモモ科、メラルーカ属とされています。園芸として楽しまれるときは庭木、花木以外にもハーブとして...
-

-
ドルステニアの育て方
ドルステ二アはクワ科の植物で、アフリカ東部のケニアやタンザニアのあたりから、海を挟みアラビア半島の紅海沿岸が原産となり生...
-

-
ブーゲンビレアの育て方
今ではよく知られており、人気も高いブーゲンビレアは中央アメリカから南アメリカが原産地となっています。生息地はブラジルから...
-

-
プテロスティリスの育て方
プテロスティリスは、オーストラリアの南東部が主な生息地であり、ニュージーランドやニューカレドニア、パプアニューギニアと言...
-

-
キュウリの育て方について
キュウリは、夏を代表する野菜であり、カリウム・ビタミンC・カロチンなどの栄養素が豊富に含まれた野菜です。浅漬けにしたり、...




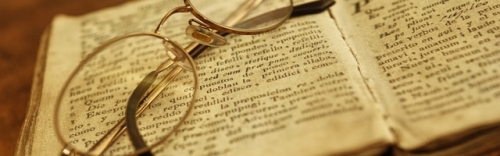





ミントは3500年ほど前の古代ギリシャですでに生薬として利用されていました。歴史上でも最も古い栽培植物として知られています。日本に渡来したのはなんと2000年以上前のことで、中国から渡ってきました。