アピオスの育て方

アピオスの育てる環境について
アピオスは、丈夫で育てやすく育て方の難易度は低いです。アンデスなどが生息地であるアピオスは極めて高い耐寒性があります。日当りがよく水はけのよい肥沃な場所を好み、乾燥には弱いため日照りが続く時には水やりが必要です。
肥沃な土を好むため、堆肥、腐葉土、化成肥料を混入した培地で栽培します。発芽までに長い時間を要するため、植え込んだ周辺の雑草の整理を行なうことが必要です。寒い地域でも植え放しでも越冬します。つる性植物で芋が土の中で育ち、花は芳香がある紫色の花を咲かせます。
根は1〜2mと長く、数珠つなぎのように約3cm程度のラグビーボール形の芋を沢山つけ、つるは約2.5m程度は伸びるためグリーンカーテンにも向きます。通常の栽培の場合、4月頃に定植して自然薯などと同じようにツルを伸ばします。6月〜8月頃に花をさかせます。
収穫は地上の葉が枯れてから、早いところで11月中旬から行ないます。掘り起こさなければ越冬できるため、収穫は3月頃まで調整しながら行ないます。葉が落ちたら収穫の時期と考えます。1株で根に50個以上の芋が収穫できます。1〜2mの長く広がった根に芋が沢山つくため、
掘り上げた時に根を切らないように注意が必要です。収穫できない芋は翌年芽を出すため注意します。アピオスは地植えだけではなく、プランター栽培も可能です。プランターで育てるとグリーンカーテンも目指すことが可能です。発芽に2ヶ月程度かかるため、グリーンカーテンとして利用するには時期を考えて植えることが必要です。
アピオスの種付けや水やり、肥料について
栽培そのものは比較的簡単で、ジャガイモやさつまいもなどと同じと考えます。栄養価が高いアピオスを作るには充分な土壌管理が必要で、土中ミネラルや成長要素を充分に吸収して、栄養価に優れた芋になる能力があります。そのため、この能力を活かせる環境を用意する必要があるのです。
種まきは3〜4月までに種芋を深さ5cm程度のところに植え込みます。発芽には約2ヶ月程度かかります。植えたまま冬を超すことができます。種芋はいつ植えても問題はありませんが、3月に植えて芽が出てくるのは4月末から5月初めです。畝は平畝で問題ありませんが、水が溜まらないように気をつけます。
地植えは酸性土を好むため、ピートモスを少量混入して、株間30cm間隔で植え込みます。65cm深型プランターでは、2〜3球を植えることが目安になります。マメ科の植物なので根粒菌が窒素を固定するため、あまり多くの肥料を必要としませんが、元肥には化成肥料を混入して、
追肥は7〜8月頃に1株につき50〜70gを与えます。リン酸、カリ、ミネラル肥料を多めに施します。平畝100cm、株間15〜20cm程度に種芋を1個ずつ植えつけます。覆土は3〜5cm程度です。蔓性植物なので、支柱を立てるかネットを張っても良いです。
除草を兼ねて培土します。中耕培土は3回行なって最終的には畝の高さが約25cm程度になるようにします。水やりは、地植えの場合は乾燥に弱いため、こまめに水やりを行ないます。鉢やプランターに植えた場合は、地表が白く乾いてきたら充分に水やりをします。水のやり過ぎは根腐れの原因になるため、やり過ぎないよう注意します。
アピオスの増やし方や害虫について
アピオスの増やし方は、種芋を切り離して植えることで増やすことが可能です。花が7月頃に開花するため摘んでハーブティーとして飲用できますが、花は早めに摘むことでプランター植えをしている場合は芋が沢山とれるようになります。
種芋を手に入れる場合はウイルス病に感染していない清潔な種芋を手に入れることが大切になります。11月中旬以降に食べる分だけを収穫します。少し早い時期にツルが枯れる可能性がありますが、ツルが枯れてから暫く経ってから食べた方が食味が増します。
土の中にそのまま入れておくと春まで置いておくことができます。春になると芽がでるため気をつけます。春までに掘らずに、そのまま芽を出させて2年目として栽培すると玉が大きくなる傾向があります。ただし、さまざまなところから芽がでるため、注意が必要になります。アピオスは殆ど発芽しますが、
種芋を入手したら、春まで待たずにすぐに植える、種芋を春まで保管するなら土の中へ埋める、ポットで苗床を発芽させてから植えるなど、複数の方法で栽培することで発芽不良や発芽遅れのリスクは軽減できます。また、植えた後は発芽まではしっかり水やりをして乾燥などに注意をします。
発芽してしまえば、後は難しいことはありません。病気にもかかりにくくいです。気をつける害虫はアブラムシです。アブラムシ対策には、ツルの伸び始めに牛乳スプレーで退治するだけで大丈夫です。万が一、アブラムシの被害にあった場合は殺虫剤が効果的です。食品成分を使用した殺虫殺菌剤を使用すれば、収穫前日まで使用することが可能です。
アピオスの歴史
アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科に属する珍しい植物です。日本には明治時代にリンゴの苗木をアメリカから輸入してた際に、アピオスはその土に混じって日本の青森に来ました。
当時はホドイモと呼ばれていました。日本には古くから自生していたホドイモとは別種であるため、アピオスはアメリカホドイモといって区別されています。アピオスは原産地の北アメリカでは古くから食べられていました。インディアンが戦いの前に食べたと言われスタミナ源として栄養価が高い食材です。
カルシウム、鉄分、タンパク質などを豊富に含んだアピオスは、現在では肥満、糖尿病などの成人病などに効果が期待できる健康食品としても注目されています。日本でもアピオスは各地で栽培されていますが、伝来の地でもある青森県が日本でトップクラスの生産量を誇っています。
離農や放棄農地が増えており、このような場所には枯れ草などによる火災や土砂崩れなどの災害が心配されます。アピオスはこのような土地でも救荒作物としても利用できます。支柱を立てない平面作付けなら栽培に手間がかからず雑草を抑え、地力を保持することができ、
土砂崩れを防ぎながら栄養豊富な芋も同時に収穫することができるのです。根茎の芋を食べるだけではなく、7月頃に紫色の花を咲かせますが、その花はお茶として使用することが可能です。その効能は血統値の上昇を抑える効果が期待できるのです。古くからネイティブアメリカンが食用としていただけあって非常に高い栄養価がある注目の野菜です。
アピオスの特徴
アピオスは食用で、肥大した根茎を食べます。根茎は根が伸びる合間に数珠のように連なってでき、肥大した部分はサツマイモなどと同じように翌年種芋として、ここから発芽します。アピオスは芋でありながらジャガイモと比較して鉄分は4倍、繊維は5倍、タンパク質は3倍、カルシウムは30倍です。
エネルギーはサツマイモの1.6倍、ジャガイモの2.6倍で、ビタミンCや芋類には含まれていないビタミンEも含まれているため栄養価の高い食物です。葉は複葉で、長さは約5cmから約7cmで、7月から9月にかけて深い紫色の蝶のような形をしたスミレに似た濃厚な香りをもった花をつけることが特徴的です。
アピオスは食物なので、選んで購入する時はしっかりと栄養を蓄えて丸くふっくらとしているものを選びます。また、アピオスは1つの株に大きいものや小さいものが混じって収穫され、味は変わらないのですが、火の通り加減や用途によって変わってくるため、なるべく大きさが揃っているものを選ぶと使いやすいです。
保存は乾燥しすぎないように、新聞紙などにくるんで冷暗所に置いておくと数日間は保存できます。さらにビニール袋に入れて冷蔵庫に入れておくとより日持ちがします。長期間保存したい場合は、3〜4分程度ゆでるか蒸してから冷凍してます。生のまま冷凍すると味が損なわれるため注意します。冬であれば種芋と同じように土に埋めておくと、春までは保存することが可能になります。
つる性植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カロライナジャスミンの育て方
-

-
セネシオ(多肉植物)の育て方
植物としては多年草に分類されます。キク科に属しており、つる植物という独特な分類になっています。これは種類が非常に豊富にあ...
-

-
トウガラシの育て方
トウガラシの原産地や生息地は中南米で、メキシコでは数千年前から食用として栽培や利用されていたのです。このことから中南米や...
-

-
ハナモモの育て方
ハナモモというのは、中国が原産地で鑑賞をするために改良がなされたモモですが、庭木などにも広く利用されいます。日本へ入って...
-

-
ブルンネラの育て方
ブルンネラはユーラシア西部を原産とするムラサキ科の多年草です。ブルンネラという名前は、スイスの植物博士であるブルナーから...
-

-
チョウノスケソウの育て方
植物の特徴としては、被子植物、双子葉植物綱になります。バラ目バラ科バラ亜科なのでまさにバラの仲間の植物といえるでしょう。...
-

-
ニオイヒバの育て方
ニオイヒバはヒノキ科 の ネズコ属に属する樹木です。原産国は北アメリカで、カナダの生息地です。日本では「香りがあるヒバ」...
-

-
アメリカハナミズキの育て方
アメリカハナミズキの歴史について言及していきます。まず、このアメリカハナミズキは原産地が、その名前からわかるとおり、アメ...
-

-
リンコスティリスの育て方
リンコスティリスはラン科の植物ですが、生息地は熱帯アジア地方に分布しています。主にインドやタイ、マレーシア、中国南部が原...
-

-
コノフィツムの育て方
コノフィツムは、アフリカ南部(南アフリカ・ナミビア南部)が原産の生息地の多肉植物です。また、ハマミズナ科コノフィツム属に...
-

-
フェイジョアの育て方
フェイジョアは1890年にフランス人の植物学者であるエドアールアンドレによってヨーロッパにもたらされた果樹です。元々は原...




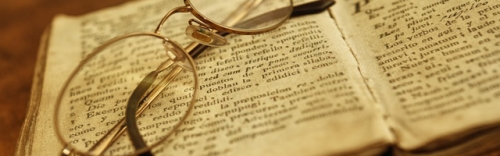





アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科に属する珍しい植物です。日本には明治時代にリンゴの苗木をアメリカから輸入してた際に、アピオスはその土に混じって日本の青森に来ました。