カレープランツの育て方

育てる環境について
カレープランツの原産は地中海海岸であり、育て方も基本は原産地に似せた環境が適しています。植物を育てる上で日当たりや気温などは重要視したい点で、切り花をはじめとする観賞目的で花を楽しむ場合にも日当たりの良さとして、日中は日に当てることが生育に影響し、花数が増えて花付きも良くなります。
日当たりは春先から冬の1年を通して半日の日照がある場所が適しているものの、花植物となるカレープランツも真夏の直射日光は秋から花を咲かせる段階の生育には向いておらず、鉢植えの場合は半日陰で管理します。カレープランツは強靭な環境にも耐えることができますが、さらに丈夫に育てるには20度から25度の気候を好む性質から、
春から秋にかけては難なく露地植えまた鉢植えで栽培でき、カレープランツは冬の気候ではマイナス2度から3度程度の寒波環境に耐えることもできるため、外での冬越しも難なくできます。注意点としては、霜による葉の傷みや霜枯れが起こるケースがあるため、軒下などの霜に影響が出ない場所に移動させて栽培します。
葉や枝ぶりが密になるカレープランツは、高温多湿な気候を若干苦手とするため、過湿にならないように蒸れを防ぐための通気性の良い環境下で管理することも必要で、特に夏は根が枯れてしまいやすく、涼しい場所で管理し、さらに増やす場合の挿し木での場合、育て方としては気温は適温となる20度から25度で、土は水はけの良い土で、さらに露地植えは湿り気のない場所が適しています。
種付けや水やり、肥料について
カレープランツは園芸店や雑貨店においてハーブ種が提供されており、種植え時期としては4月から5月の春蒔きをはじめ、9月の秋にも種蒔きによる種付けができます。種も提供されているものの、園芸店においては生育した苗も販売されており、苗を植え付けるのが一般的です。苗も種同様に春または秋植えを行いますが、適温となるのが20度からであるため、
時期よりも気温によって植え付けを行うと花付きが良くなります。種蒔きの場合には、種蒔き専用となる園芸用のビニールポットまたは2号鉢に赤玉土を入れてパラパラと重ならないように種を蒔き、その後はたっぷり水を与え、涼しい日陰で管理することで約2週間程度で発芽します。発芽した後はプランターまたは2号鉢よりも2回り大きい鉢に植え付けます。
培養土もしくはハーブ土をふんわり入れて、苗を入れた株元は若干高めにすることで水はけを良くします。水やりはたっぷり与え、肥料は他のハーブ植物同様に花付き前の春と秋に化成肥料を与えますが、液体肥料も花が咲くつぼみの段階から与えることで栄養分を吸収し、長く花を楽しむことができます。乾燥した土壌を目安とした水やりが必須で、
土が乾いてからたっぷりと与えるのですが、多湿を嫌うために与え過ぎは根腐れに影響するため、乾燥した土壌をキープし、適度な水やりが重要です。夏時期は朝と夕方の2回程度を目安とし、梅雨時は屋根のある場所へ移動させるなど直接雨が当たらないように行います。
増やし方や害虫について
カレープランツは種で増やすことは勿論できますが、切り戻し後の枝を使い挿し木で増やす方法が無駄なく一般的な増やし方です。増やす適期としては種蒔き同様に4月からの春をはじめ、9月の秋に挿し木の植え付けを行うのが適しています。一般的な挿し木での増やし方同様に、新芽の先端2節から3節の長さ約5cmから8cmほどの穂を利用して栽培を始めますが、
切り口となるカット面から栄養分を補給するために、ナイフなどの刃物を利用してカットします。挿し穂は斜めから土に挿して栽培しますが、この時に下葉がある場合には手で下葉を取り除き枚数を微調整します。というのも、下葉に栄養分が行くことにより根が回らず、さらに蒸散が行われやすくなることから腐りやすくなります。
挿し穂向けとなる用土に挿して涼しい日陰で栽培します。挿し木で増やす際には種蒔き用土が適していますが、ハーブ用土や赤玉土に腐葉土をブレンドさせて育てるのが適しており、通気性と水はけに注意します。カレープランツの場合、発根した後は1本ずつ根をほぐしてポットまたは鉢に植え替えてます。病害虫の発生は少なく、
防虫効果の高いハーブでもあるためにキク科の植物を好むてんとう虫やヘップリ虫などの害虫も寄せ付けない品種ですが、かかりやすい病気に治りにくい根腐れ病があるため、発生を防ぐための水やりは重要です。輝くシルバーリーフが害虫予防ともなりますし、食用としたい場合には殺虫剤は避け、木酢などで対処するのが適しています。
カレープランツの歴史
料理名が植物の名前に由来していることから人気となり、普及しはじめているのが常緑低木の種類にあたるカレープランツであり、学名はHelichrysumangustifoliumと言い、HelichrysumはHeliosが太陽を表しChrysosが金色を表しています。キク科でムギワラギク属に分類されており、別名には永遠を意味するエバーラスティングと言う名が付けられ、花言葉は永遠の愛です。
原産は地中海沿岸地域であり、歴史は比較的浅い常緑低木で観賞用としての利用は昔も今も同様ですが、葉や花にはそれぞれの利用法が古くから原産地をはじめ、生息地一帯で提案されていました。カレープランツは、その名前の通りに葉を触るとカレーのようなスパイシーな香りを放つため、ハーブとして利用価値の高さが古くから提案されており、
原産地では地中海料理の風味づけに乾燥させた葉を利用していた歴史が残されています。さらにキク科に分類される品種であり、その花の香りを長く楽しめるようにドライフラワーやポプリなどのクラフトに利用されており、乾燥させた状態では芳香が1年近く楽しめるため、
原産地においてはお土産物としても栽培が進められていました。さらに葉には防虫効果がありますし、近年ではエッセンシャルオイルとしても出回り、精油はアロマとしてリラックス効果に優れているため、利用価値の高さから広く栽培が進められるようになった品種でもあります。
カレープランツの特徴
カレープランツは地中海沿岸に原生しており、乾燥した岩場また砂地が生息地です。キク科で常緑低木であり、葉や茎からはカレーに似たスパイシーな香りがするためにこの名前が付けられている特徴が挙げられます。日本特有の高温多湿に弱いものの、根を張りやすいために露地栽培を可能としており、観賞用としてまた観葉植物として栽培されています。
低木の高さは60cmに成長し、株元の茎は木肌に似たゴツゴツした木質へ成長します。スパイシーな香りを放つ葉は針葉のようでシルバーグレーの葉の色をしており、9月頃に黄色のスターチスに似た小花を咲かせるハーブの一種としての特徴も持ち合わせています。枝葉を密生するように伸ばす性質があり、多年草でもあるために枝は葉をすくように切り戻しする手入れの必要のある特徴も持っています。
上記で挙げたように花や葉は鑑賞用としてはもちろん、クラフトとして使用されるのも特徴であり、シルバーリーフはカラーリーフとしても楽しまれており、近年ではキッチンガーデンとして食用ハーブの栽培目的で育てられています。生食としては苦味が強いため、胃弱作用のあるハーブティーとして利用されていますし、
葉や茎を料理の香りづけやシルバーグレーの色から彩りに利用するケースが増えています。カレーの香りがする品種であるものの、カレースパイスとしては利用されていないのも特徴の1つであり、花や葉や茎は余すことなく料理やインテリア雑貨などに利用されている魅力ある品種です。
-

-
ブラシノキの育て方
フトモモ科ブラシノキ属するブラシノキには34種類あるといわれ、オーストラリア全域からニューカレドニアが生息地です。低木か...
-

-
キアネラの育て方
キアネラの特徴について書いていきます。キアネラの原産地は南アフリカを生息地としています。ケープ南西部に9種のうち8種が生...
-

-
サザンカの育て方
サザンカは、元々日本に自生している植物です。ツバキとは種が異なりますが、属のレベルではツバキと同じですから、近縁種だと言...
-

-
グリーンカーテンの栽培方法。
地球は温暖化の一途を辿っています。日本では、温暖化対策の1つとして、グリーンカーテンを導入している家庭や市区町村が増えて...
-

-
ヘレボルス・フェチダスの育て方
特徴としてはキンポウゲ科、クリスマスローズ属、ヘルボルス族に該当するとされています。この花の特徴としてあるのは有茎種であ...
-

-
カランコエの育て方
乾燥に強い性質のある多肉植物で、育てるのに手間がかからず、鮮やかな色の花だけではなく、美しい葉そして面白い株の姿を鑑賞す...
-

-
トケイソウの育て方
原産地は、北米、ブラジルやペルーなどの熱帯アメリカです。パラグアイでは国花とされています。現在、園芸に適した品種として知...
-

-
ヒメヒオウギの育て方
現在の日本国内で「ヒメヒオウギ」と呼ばれる植物は、正式名称を「ヒメヒオウギズイセン」と言います。漢字では姫の檜の扇と書き...
-

-
植物を栽培する時のコツ
栽培や植物を育てるにはさまざまなコツがあります。また、栽培や植物の種類によっても育て方が異なってきます。例えばニンニクで...
-

-
玉レタスの育て方
サラダの食材に欠かせないレタスには幾つかの種類が在りますが、お店に行くとレタスと名の付く物が沢山店先に並んでおり、どれに...




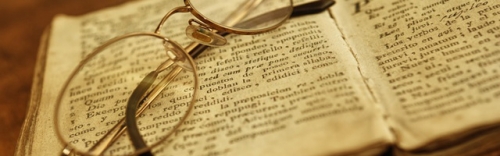





カレープランツは地中海沿岸に原生しており、乾燥した岩場また砂地が生息地です。キク科で常緑低木であり、葉や茎からはカレーに似たスパイシーな香りがするためにこの名前が付けられている特徴が挙げられます。