シマトネリコの育て方

シマトネリコの育てる環境について
シマトネリコはもともと熱帯、亜熱帯に生息していた植物です。そのため暑さには強いのですが、寒さには弱い性質があります。したがって関東から南の地域が生育に適した地とされています。もっとも最近は地球温暖化の進行により、もう少し北の地域でも条件次第では栽培が可能になる場合もあります。
寒い地域でなければ、育て方はそう難しいものではありません。ある程度日当たりの良い場所に植えておけば、それほど神経質にならなくても十分生育しますし、半日陰に植えてもそれほど心配はいりません。ただし成長が速いことには気をつける必要があります。
シマトネリコの成長の早さは庭木としての魅力の一つなのですが、大きくしたい場合は別として、敷地に制限がある場合は植える場所および剪定に気を配らなければいけません。また長所が短所になる例としては、さわやかな樹形をあげることができます。
葉の出方に余裕があることがシマトネリコの樹形の美しさの秘密なのですが、これは悪くいえば葉と葉の間がスカスカということになります。つまりシマトネリコを周囲からの目隠しとして利用することは難しいのです。単純にシンボルツリーとして使う場合は問題ありませんが、
窓際などに植えて周囲からの目隠しとして利用するのであれば、再検討が必要です。シマトネリコにかかわらず、樹木を植える際には生育環境の良いところを選ぶのは当然ですが、何らかの目的があって樹木を植える場合は、その目的に応じた品種を選ぶ必要があります。
種付けや水やり、肥料について
植え付けは春から夏にかけておこないます。初秋でも可能ですが、寒さに弱いことを考慮すると、気温の温かい時期が続く頃に植え付けを行ったほうが良いでしょう。種から育てたい場合も、4月から5月頃に種をまくのがベストです。また関東以南の地域以外で育てたい場合は、
移動が可能な鉢植えが適しています。この場合も植え付けの時期は同じですが、シマトネリコは成長が速い植物ですので、大きめの鉢を使用するのがコツです。水やりに関しては、庭に植えているのであればそう心配はいりません。乾燥には弱い品種ですので、
土の表面が乾いていれば水を与えるようにしましょう。ただし鉢植えの場合は水やりに注意が必要です。水切れは避け、鉢の土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えることが大切です。特に夏場になるとすぐに土が乾燥してしまううえ、
シマトネリコの葉も普段より多く水を吸い上げるようになるため、水切れさせないように注意を払わなければいけません。鉢植えのシマトネリコの場合、肥料は春から秋にかけて、緩行性のものを与えるようにします。化成肥料を置き肥してもいいですし、液体肥料を定期的に与えるようしてもかまいません。
庭植えのシマトネリコの場合は、2月頃に有機質の肥料を与えます。その他の時期は特に肥料は必要ありません。木が弱っていると感じた時は、土壌改良や肥料の追加をしてしまいがちですが、それらをおこなうのには適切な時期というものがありますので、そのあたりはしっかりと調べてからおこなうほうが無難です。
増やし方や害虫について
シマトネリコを増やしたい場合は、種から栽培する方法と挿し木をおこなう方法の二つから選ぶことができます。種から増やす場合は、晩秋に茶色くなった種を採取し、よく年の春に種まきをおこないます。発芽するためには気温が20度以上になることが必要ですので、
種まきは4月から5月頃にするのが適しています。最初はポットに植えておき、葉がでてきたら鉢に植え替えましょう。用土は赤玉土と腐葉土を6対4で混ぜたものを使用します。挿し木をおこなう場合は、4月から6月に行います。
挿し木は素人では難しいので、なるべく多くの数を用いておこなったほうがいいでしょう。具体的には葉の多い若い枝を採取し、5センチほどの挿し穂にします。その後葉を3、4枚ほど残し、残した葉も半分ほどに切ります。挿し穂を1時間ほど水につけ、用土に挿します。
なるべく風や直射日光に当たらないところで保管します。発根促進剤を使用してもかまいませんが、肥料を与えてはいけません。病害虫についてですが、基本的には病気に強い植物ですので、樹木を襲う病気についてはそれほど心配する必要はありません。
たまにうどんこ病を発症する場合があるので、そのような事態が起きた際には殺菌剤を添付するなどの処置をおこなわなければいけません。また害虫は発生する恐れがあります。イモムシやハマキムシが新芽を食べるために発生することがありますので、見つけ次第、薬剤などで駆除する必要があります。
シマトネリコの歴史
シマトネリコは、近年シンボルツリーとして非常に人気を集めている樹木です。トネリコと混同している人も多いですが、日本が原産のトネリコとは異なり、シマトネリコは沖縄からインドにかけての熱帯、亜熱帯を生息地としている品種です。
つまり近い種類の仲間ではありますが、厳密にいえばトネリコとは異なる品種なのです。現在はシマトネリコという名前で普及していますが、昔はタイワンシオジの別名のほうが主流でした。原産地では建築資材として使われるほどの大木で、15メートルを超える樹高のものも存在するほどです。
日本では沖縄や奄美諸島あたりから本土へ導入されたといわれており、庭木として非常に多くの人が利用されています。シマトネリコとトネリコは近い種類の樹木で、外観も似ていますが、前者は常緑高木、後者は落葉高木なので違いは歴然です。
にもかかわらずトネリコという名称がついているのは、沖縄近辺から本土に伝わったため、島で育ったトネリコの仲間というのが由来になったのだという説があります。もともとトネリコは日本人の暮らしに欠かせない植物で、トネリコに群がる虫が排出するイボタロウという白ロウは、
住居の戸の溝に塗り込んで滑りを良くするために使われていました。トネリコという名前もトニヌル木が転じて発音されるようになったとされています。育てやすい常緑高木であることはもちろんですが、古くから日本人になじみのある木に似ていることも、近年のブームとも呼べる状態を作り出した理由の一つかもしれません。
シマトネリコの特徴
シマトネリコは清涼感を持つ立ち姿が人気です。花そのものは地味な存在ですが、小さくて光沢のあるライトグリーンの葉が風に揺られてサラサラとしている姿は、見ている人をさわやかな気分にするので、気温の高い夏には特に魅力的に映ります。
常緑種によくある陰鬱とした雰囲気が皆無であることも、人気の秘密です。またもともと熱帯育ちなので、暑さに強いというのも魅力の一つです。潮風や病害虫にも強いので、栽培に手間をかける必要がありません。成長も速く樹形も美しいことから、他の種類の樹木と組み合わせなくても、
単独で十分に庭を彩るシンボルツリーとして成り立つこともシマトネリコならではの魅力です。さらにシマトネリコは洋風の家にぴったりな樹形であることも、急速な普及を後押ししている理由の一つです。最近建てられる住居をみても、従来のような和風建築の建物はすっかり少なくなっています。
ライフスタイルが大きく変化しているので、建物が洋風に変化することが仕方のないことですが、建物が洋風になれば、その庭も洋風にしなければ違和感がでてしまいます。シマトネリコは洋風の建物にもコンクリート製の建物にも良く似合う樹形をしていますので、
まさに現代のニーズにマッチした樹木ということができるでしょう。最近はシマトネリコの人気の高まりと共に品種の改良もおこなわれており、シマトネリコの特徴である美しい葉に、斑模様が入ったものも人気が高い品種です。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:エゴノキの育て方
タイトル:トキワマンサクの育て方
タイトル:スギ(杉)の育て方
-

-
美味しいゴーヤーの育て方
ゴーヤーは、沖縄料理人気から需要が高まりました。今では沖縄料理に限らず、幅広い料理に使われるようになりました。また日よけ...
-

-
アーティチョークの育て方
アーティチョークの原産地や生息地は地中海沿岸部や北アフリカで、古代から栽培されているキク科のハーブです。紀元前から高級な...
-

-
ヘビウリの育て方
インド原産のウリ科の多年草で、別名を「セイロン瓜」といいます。日本には明治末期、中国大陸を経由して渡来しました。国内では...
-

-
ウメバチソウの育て方
ウメバチソウは北半球に生息する植物です。古くから北半球に多くの地域に分布しています。品種改良が行われていて、色々な品種が...
-

-
バーベナの育て方
バーベナは、クマツヅラ科クマツヅラ属(バーベナ属とも)の植物の総称です。様々な種類があり、基本的には多年草、あるいは宿根...
-

-
真珠の木(ペルネティア)の育て方
真珠の木と呼ばれているベルネッチアは、カテゴリーとしてはツツジ科の植物になります。吊り鐘状という少し珍しい形で、春遅い時...
-

-
カンアオイの育て方
カンアオイは、ウマノスズクサ目ウマノスズクサ科カンアオイ属に属する植物です。日本名は「寒葵」と書かれ、関東葵と呼ばれるこ...
-

-
オカノリの育て方
オカノリの原産国は諸説ですが、中国が有力とみなされています。ある説ではヨーロッパが原産と考えられ、現在でもフランス料理で...
-

-
梅(ハクバイ)の育て方
梅は非常に色が豊富です。濃いピンクがありますがそれ以外には桜のような薄いピンクがあります。白っぽいピンクから真っ白のもの...
-

-
マツの仲間の育て方
マツの仲間の特徴としては、環境や種類によって様々に異なってくるものの、マツ属に含まれるものは、基本的に木本であり、草本が...




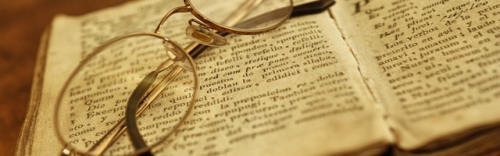





シマトネリコは、近年シンボルツリーとして非常に人気を集めている樹木です。トネリコと混同している人も多いですが、日本が原産のトネリコとは異なり、シマトネリコは沖縄からインドにかけての熱帯、亜熱帯を生息地としている品種です。