ワレモコウの育て方

育てる環境について
栽培をするときの環境としては日当たりの良い所です。日当たりが足りないと花がつきません。茎がしっかりしている花ですが、自立できないほど弱ってしまうことがあります。生息地としても比較的広い草原などで育つことが多いようです。周りに木々であったり山などがあるところではなく、その花だけがあるようなところで育ちます。
日差しがたくさん浴びることが出来るところだとどんどん育つことができそうです。日当たりに関しては特に直射日光などの管理は不用ですが、夏に関しては少し気にした方がいいかもしれません。半日陰の状態のところに置く、直射日光が当たるようであれば30パーセントから40パーセントぐらいの遮光の下に置くなどの工夫が必要になってくるかもしれません。
斑入りの品種においては直射日光が当たることで日焼けしてしまうことがあり、見た目に悪くなりますが、その心配をなくすことができます。多年草で夏に主に咲く花です。では冬はどのような環境が必要かですが、夏から秋にかけて花がさいたあとはどんどん枯れていきます。そして冬の前ぐらいには地上部分についてはきれいになくなってしまいます。
なくなったらすべてが枯れてしまっているように感じますが実際にはそうではなく根が生きたまま地面の中にいます。そして春になると再び芽が出てきます。そのために冬にも強いとされています。冬に強いからといって茎などがでているわけではなく、見た目上は枯れています。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては湿り気があって肥沃な土を用意するようにします。例として、赤玉土が3割、鹿沼土が3割、腐葉土が4割です。山野草の培養土がありますが、これだけだと少し栄養分が物足りないかもしれません。それに腐葉土を少し加えるようにしてみましょう。地植えをする時はどうするかです。湿り気が必要だからとジメジメしたようなところを選ぶかもしれませんが、あまり水はけが弱いところは良くありません。
水はけが良いようにしたうえで腐葉土を混ぜるようにして育てていきます。水やりとしては、鉢植えにおいては土の表面が乾いたときに与えていきます。地植えをしているときは根付くまでしっかりと水を与えます。根がしっかりと付くようになれば雨だけで育ちますから水を与える必要がなくなります。
花が咲く時期においては少し気にしながら様子を見ます。梅雨の時期ならそれなりに雨が降りますが、真夏になると1週間や10日全く雨がふらないようなことがあります。こうなると庭においてもかなり水分が減った状態になります。株も弱ってきますから、水を与えるようにした方がいいかもしれません。
天気予報において雨がしばらく降りそうになければ与えるようにします。肥料に関してはある程度与えることで元気を出す植物です。夏の花が咲く大事な時期において枯れることがありますが、それは肥料不足が原因になっていることがあります。春の芽が出る頃から液体肥料などを10日に1回ほど与えていきます。
増やし方や害虫について
増やしたい場合はどのようにする必要がある家ですが、株分けをすることができます。植え替えの時期としては冬眠明けの2月から3月ぐらいがいいとされています。休眠中はよくありませんし、芽が完全に成長を始めている時だと問題です。少し寒いと感じる頃でも植物においては春が始まっています。その頃に植え替えをします。
植え替えのときに株の様子を見て株分けをします。根を掘りあげ、古い土をきれいに取ります。傷んだ根については取り除き、カッターなどで切り分けて植えます。大きさについてはそれなりの大きさになっていないといけません。小さすぎないかどうかを確認しながら行います。その他には種まきで増やせます。
花の後に種ができますから、それを採取しておきます。すぐにまくのではなく取っておきます。そして翌年の4月から5月くらいにまきます。その夏に咲かすのではなく、翌年の夏に咲かすためにまきます。育てる上の作業としては、支柱立てを行うようにしましょう。健康的な株はしっかりと茎もまっすぐに伸びます。花の見た目も非常にきれいです。
でも全てがそのように成長するとは限らず、弱い株もあります。一応全てに支柱を立てておくといいでしょう。見た目が気になるならその後に外すこともできます。病気としてはウドンコ病があります。それ程多く発生しません。株に問題のある病気でもありません。害虫はハダニが出ることがあります。これも株に大きな影響を与えません。
ワレモコウの歴史
花においてはそれぞれ何らかの名前が付けられ、それについては由来があるとされています。最近発見されて名付けられた場合においてはその由来なども特に調べることなく記録されています。名づけた人がいなくてもそのことについての記載が残っていれば調べることができます。しかしそれがかなり古いことになるとなかなかそういった記載が無かったり、
いろいろなところでいろいろな呼ばれ方をすることもあります。結局本当の由来がどこにあるのかがわからなくなることがあります。名前を知るとどのように伝わってきたかなどもわかりますから非常に重要な事になります。少し変わった名前の花としてワレモコウと呼ばれる花があります。原産地としてはユーラシア大陸の温帯から亜寒帯、北米大陸の北西部から西部あたりと北半球の広い範囲とされています。
日本においては元々あったのかどうかについてはわかっていません。アラスカなどでは自生するようになっています。漢字としては吾亦紅、我吾紅、吾木香、我毛紅など様々あります。語源の一つとしてあるのがわれもこうありたいからこの名前が付けられたとする考えがあります。
花の色の議論をしているときに花が自ら自分の色は紅といったと聞こえたそうです。花が自分からそのように言うのですからそれで間違いないとのことで、そのような名前が付けられたともされています。古い言い伝えの語源から日本においては古くから咲いている花であることがわかります。
ワレモコウの特徴
この植物においてはバラ目、バラ科になります。ひと目見たところにはバラにはとても見えそうもありませんが、よく見てみるとたしかにバラに似ているようにも見えます。バラ亜目なので非常にバラに近い花といえるでしょう。園芸においては草花、山野草として分類されることになっています。咲き方としては1年を通して枯れない多年草になります。
草の丈としては1メートルぐらいになるものがあるようです。花が咲く時期は6月から秋口ぐらいまでです。花の名前を漢字で書くと紅との文字があり、赤色のように見えることもあります。非常に深い赤といえるかもしれません。人によっては茶色に見えるとする場合もあります。アラスカでも自生するようになっていることから耐寒性としてはかなりあると考えられます。
日本でも普通に育てることが出来るので耐暑性についてもあります。この花は地下茎は太くなっています。根出葉は長い柄がついていて、羽状複葉になっています。その他に小さい葉がついていて、それについては小さい楕円形です。この葉っぱに関してはギザギザ状になっています。夏から秋口にかけて花をつけるようになります。
小さい花がたくさんついているようにも見えますし、バラのようにたくさんの花びらが重なっているようにも見えます。花の咲き始めに関してはきれいな赤い色のこともありますが、時間が経ってくると徐々に色も暗くなってくるので真っ赤ではなくなります。薬としての利用もされるようです。
-

-
ポインセチアの育て方
特徴としてはなんといっても赤い花びらと緑の葉でしょう。クリスマスにピッタリの色合いです。そう考えて購入する人もいるでしょ...
-

-
グンネラの育て方
グンネラの科名は、グンネラ科 / 属名は、グンネラ属で、和名は、オニブキ(鬼蕗)となります。グンネラ属グンネラは南半球に...
-

-
ラバテラの育て方
ラバテラは原産地が南ヨーロッパ、北アフリカの植物です。アオイ科ラバテラ属の総称になります。一年草になり、日本には明治に渡...
-

-
グロリオーサの育て方
グロリオーサの育て方は簡単ではありませんが、難し過ぎるというほどでもありません。マメに手入れをする方であれば問題なく育て...
-

-
ユズ類の育て方
ゆず類に関しての特徴としては、まずはそのまま食べるのは少し難しいことです。レモンにおいても食べると非常に酸味が強いです。...
-

-
オキナワスズメウリの育て方
この植物は被子植物に該当します。バラ類、真正バラ類のウリ目、ウリ科になります。注意しないといけないのはスズメウリ属ではな...
-

-
バオバブ(Adansonia)の育て方
バオバブは古くから人類の歴史と深く関わり続けている樹木です。人類が2足歩行をする400万年前以前からフルーツや葉を食料と...
-

-
ジャックフルーツの育て方
果実の大きさは世界最大として知られています。世界最大の実をぶら下げているのは、太い幹です。大きな実をぶら下げているだけあ...
-

-
植物の栽培について アサガオの育て方
育てやすい植物の代表として挙げられるのがアサガオです。最近は色や模様も様々なものが登場しています。アサガオの育て方は比較...
-

-
アカザカズラの育て方
夏になると、近年は省エネが叫ばれ、電力の節約のためにさまざまな工夫がなされます。つる性の草のカーテンもそのひとつだと言え...




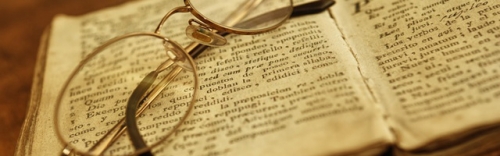




この植物においてはバラ目、バラ科になります。ひと目見たところにはバラにはとても見えそうもありませんが、よく見てみるとたしかにバラに似ているようにも見えます。バラ亜目なので非常にバラに近い花といえるでしょう。