クコ(キホウズキ)の育て方

育てる環境について
また面白い利用方法では、クコ茶もそうですが、クコ酒という酒に利用するという方法もあり、これも酒飲みには楽しめる利用方法ということになりますが、酒は実のほうで作りますが、砂糖とホワイトリガーなどを利用すると誰にでもできます。クコ茶も簡単で若葉を3日間ほど干してから、フライバンでカラカラになるまで炒るだけです。
それでもうお茶ができます。後は普通のお茶と同じように作って飲むだけです。漢方薬ということでの利用では、クコの実ばかりではなく根や葉も、それぞれ利用できますし、漢方薬での名前も違っています。実は枸杞子、根の皮は地骨皮、葉は枸杞葉というように、用途で色々な利用方法があるということですが、
根から実まで利用できるということでも、有用な植物であることがわかります。効能では血圧や血糖の低下作用、抗脂肪肝作用などがあり、ストレスなどで精神的に萎えているような場合には、強壮する作用があるということですから、ストレスが溜まった時などには、木の実を買ってくるなどして、お茶やお酒にして飲んでみるということで、
試してみると効果があるということになります。また料理に入れても同じような効果が得られるでしょう。また根の皮は抗炎症作用、解熱作用があるということで、調合されたりしているそうです。葉の方は血圧の低下作用があり、葉なのでお茶の葉と同じように利用することができるということでした。そのように色々な使い方もできます。
種付けや水やり、肥料について
また採取ということでは、若芽の場合は、4~6月と秋が旬になり、古い葉は避けるようにして、緑や赤みのある葉を採取するようにします。果実と根は秋に取ります。もし1年中落葉しない温暖な地域では、1年中採取できるので、非常に効果的に利用できるということになります。特に温暖な地域では利用すると良いということです。
育て方ということでは、これも簡単で気をつけることは日当たりと水やりだけです。その条件さえ整えば誰にでも簡単に栽培ができるということになります。木の特徴としては枝の長さは1メートルぐらいで、幹の太さは太くても1センチぐらいです。開花期は夏から初夏で夏に咲く花というのですが、果実は赤というよりもオレンジ色の細長い小さなホウズキのような感じの実になります。
ですからキホウズキという別名もあるのでしょう。そしてその実を集めて乾燥させたものが、スーパーなどで販売しているクコの実ということになります。これは買わなくてもガーデニングで花を楽しみ、その後は実を集めて乾燥させれば誰にでもできるということで、観賞用と食用とまた健康管理にも利用できる優れものの植物ということになります。
また日本では雑草ということになっていますので、その植物の強さは非常に強いことがわかりますから、そこが誰でも育てられるという所以でしょう。このようにガーデニングでは、美しい薄紫色の可憐な花が見られ、またその後は健康に非常に良い実を食べられるということでも、優れた植物ということができます。
増やし方や害虫について
そのように非常に育てやすい植物なので、育て方でも特に注意することはなく、常識的な環境の整備で、育てることができます。雑草に分類されているということでも、初心者には心強いガーデニングの植物ということができます。また最初に収穫した時には、喜びもひとしおということですが、初心者の場合には、簡単に育てられるこのような植物が良いということになります。
育て方での具体的な注意としては、特に肥料は与えなくても良いのですが、水をやりすぎても根が腐るので、環境から常識的に与えておけば良いということになりますが、バランスとしては、やや乾燥気味のほうが良いかもしれません。これもガーデニングの場所の条件によります。またあまりにも水はけの悪い粘土質の場合には、腐葉土や赤玉土、川砂などを混ぜて、改良しておきます。
またこの植物自体が北海道から沖縄まで自生していることからもわかるように、日当たりさえ良くしておけば、自然にすくすく育ちます。暑さにも寒さにも強いということが、そのことからもわかります。剪定は2月頃行います、秋に剪定すると一緒に若芽も切ってしまうからですが、どうしてもしなければならない時は、若芽は諦めるということになります。
また風通しの良いように剪定します。害虫も発生しますが、そのままでも強いので成長します。しかし見た目が悪くなるので駆除したほうが良いでしょう。害虫ではハダニが発生しやすいですし、アブラムシやテントウムシダマシなどもいます。病気では梅雨の時期にウドンコ病が発生する場合があります。
クコ(キホウズキ)の歴史
ガーデニングなどでは、色々な植物を育てることになりますが、やはり最初は育てやすくて、色々なメリットがある植物が良いのではないかということですが、そんな中でも非常に強い植物ということではキホウズキという植物も面白いですが、よく知られている名前ではクコです。
クコの実ということでスーパーなどでもドライフルーツや木の実のコーナーなどで売られています。甘酸っぱい美味しい木の実ですが、その植物です。この植物は非常に強い植物で、誰でも栽培できるということで、ガーデニングでも初心者向きです。また実も販売しているぐらいですから、食べることもできますし、漢方薬としても昔から有名で、
非常に利用価値が高い植物でもあります。この植物はナス科クコ属の落葉小低木ですが、ナスの仲間ということで、その実からは何となく似ているかなという感じですが、色はまったく違うので、知らなければ結びつかない植物です。また非常に生命力が強く、雑草に分類されてもいる外来植物ということで、今でも世界中に勢力を広めている植物でもあるそうです。
原産は中国ですが、生息地は世界中で、日本でも日本全域の原野、河川堤防、海岸などで自生するまでになっています。また名称もキホウズキの他にカラスナンバン、ノナンバンとも言われています。また漢方薬なので、木のそれぞれの部位で呼び方が違うということでも面白いですが、それほど効果がある植物ということでも、育てがいがあります。
クコ(キホウズキ)の特徴
クコの実は、食品としても非常に優れた食品で、その実自体は小さなものですが、栄養分は豊富です。あまりにも多すぎて、き出せないほどですが、いくつか書いてみると、ルチン、タンニン、ビタミンC、ビタミンB1、B2、ビタミンA、鉄分、リノレン酸、リノール酸など様々なものが含まれていますが、20種類以上になるでしょう。
それほど栄養価が高い実ということになります。また漢方薬ということでの効用も、これまたたくさんあり挙げきれないほどですが、滋養強壮や疲労回復、代謝促進や老化防止などで、アンチエイジング効果もあります。またコレステロール値や中性脂肪、血圧や血糖値を下げる効果もあります。
生活習慣病の予防や改善などや、血流を改善し、動脈硬化などの効果もあり、血行促進や免疫力向上、また冷え症改善など数え上げるときりがないほどの効果があります。昔から漢方薬として利用されてきただけのことはあります。また東南アジア圏では、おかゆやスープ類などに入れて病人などの回復期に利用したりもしています。
また薬膳料理でも定番の素材としてもアジア圏ではよく使われています。そのように非常に利用価値の高い植物ですので栽培も簡単なことから、育ててみるのも良いのではないかということになります。また飲み物としてもクコ茶などもあり、食べるだけではなく飲み物としても利用できるというすぐれものでもあります。特に甘酸っぱく癖があまりないということも良いようです。
-

-
カラジウムの育て方
カラジウム/学名・Caladium/和名・ハイモ、カラジューム/サトイモ科・ハイモ属(カラジウム属)カラジウムは、涼しげ...
-

-
トレニアの育て方
トレニアはインドシナ半島原産の植物で、東南アジア・アフリカなどの熱帯の地域を生息地として約40種が分布しています。属名t...
-

-
コチレドンの育て方
コチレドンはベンケイソウ科コチレドン属で、学名をCrassulaceae Ctyledonといいます。多肉植物の仲間の植...
-

-
アークトチスの育て方
南アフリカ、熱帯アフリカを原産地とし、そこにはおよそ65種類ものアークトチスが分布しています。その中でも日本に初めて入っ...
-

-
スパラキシスの育て方
スパラキシスはアヤメ科の秋植えの球根草として知られています。純粋に和名であるスイセンアヤメとも言います。和名が付いている...
-

-
カキツバタの育て方
日本や朝鮮半島、東シベリアなどが原産といわれるカキツバタは、7世紀頃には既に観賞用の植物として人々の目を楽しませていたと...
-

-
ムギセンノウ(アグロステンマ)の育て方
アグロステンマはナデシコ科の植物で、ナデシコのように小さな花がたくさん咲いて、また葉っぱが細長いのが特徴です。アグロステ...
-

-
ドドナエアの育て方
ドドナエアという木は葉を楽しむ木です。原産はオーストラリアでポップブッシュとも呼ばれています。生息地はもともと日本ではあ...
-

-
オルキスの育て方
このような面白い形の植物は、ラン科に多いのですが、やはりこのオルキス・イタリカもランの一種で、オルキスとはランのことで、...
-

-
バビアナの育て方
花の特徴では、被子植物、単子葉類となります。キジカクシ目、アヤメ科、ホザキアヤメ属となります。この花においては旧名、もし...




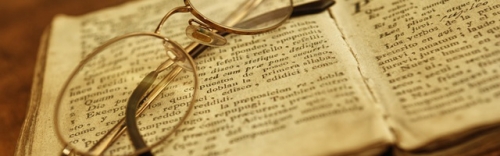





この植物はナス科クコ属の落葉小低木ですが、ナスの仲間ということで、その実からは何となく似ているかなという感じですが、色はまったく違うので、知らなければ結びつかない植物です。また名称もキホウズキの他にカラスナンバン、ノナンバンとも言われています。