イブキジャコウソウの育て方

育てる環境について
ハーブ類は生息地で誕生して成長している植物でもあるので、その地域の人たちが必要としていたものを厳選して利用していきたとう歴史があります。改良の歴史も浅く、野生に近い栽培方法が取られている植物なので、原産地の気候に適応して育てることが大切です。
日本の気候と原産地の気候が違う場合もあるので、誕生した地域との違いを調節して育てることがポイントの一つです。通気性が良く、耐水性がある土を用意して、余分な水を排出することが出来る柔らかい土を使うようにします。快適な環境は中性から弱アルカリ性なので、
腐葉土や赤玉土などを混ぜ合わせて酸性度を調節します。水はけが悪い場所で育てる場合は畑を高くしたり傾斜をつけるなどして、水の通り道を作っておくと安心です。畑や外にあるプランターではなく、室内で育てるときには日光が当たる場所や風通しが良い場所を選ぶようにします。
短い期間で収穫して、調子が悪くなったら外に出すようにすれば室内でも育てることが出来ます。またハーブはすぐに根がいっぱいになってしまう植物なので、根腐れを防ぐためにも年に1回は植え替えをするようにします。急に葉っぱの色が茶色くなったり、
元気が無くなったときには植え替えを行うようにします。完全に根付くまでは枯れやすいので、半日から1日かかえて直射日光は避けて日陰で乾燥しないように管理します。植え替えをする場所にはあらかじめ水を与えておいて、土を柔らかくするようにします。
種付けや水やり、肥料について
鉢の底に意思を敷き詰めて、種付け用の土を入れて表面を平らにしておきます。鉢の底から水が流れて出てくるくらいまで、たっぷりと水を掛けておきます。種をパラパラと重ならないように、蒔くようにします。ごく少量の土を掛けて、上から軽く押さえておきます。
水をしっかり与えることも大切ですが、種がとても軽いので流されないように工夫することが大切です。容器に水を張って、そこに鉢や容器を浸けておいて水を吸わせる方法なら流されずに済みます。またイブキジャコウソウは種付けから行うと時間が掛かってしまうことがあるので、
急いでいるときには苗を植え付けるようにします。鉢の底にネットを敷いて、石を敷き詰めて培養土を入れておきます。肥料が入っていない土を使うときには、元肥として肥料を混ぜて事前に用意しておきます。土はたくさん入れずに、スペースを2センチ程度空けておきます。
中央に穴を掘って、そこに苗をいれます。周りの土を寄せて、軽く押さえて定着するようにします。植える間隔は20センチ前後で、底から水が流れるくらいに水を与えます。肥料はそれほど必要ありませんが、収穫のたびに肥料を与えます。葉っぱと茎の間が長くなってきたら
成長し過ぎのサインなので、追肥はしないようにします。水やりは土の表面が乾燥したら、水が流れ出るくれいまで与えます。さらに湿気を嫌うので、あまりやり過ぎないように注意することが育て方のポイントでもあります。
増やし方や害虫について
イブキジャコウソウは、挿し木で増やすことが可能です。挿し木は枝をカットして、土に挿しておいて発芽させる方法です。元のハーブの性質や特徴を受け継ぐことが出来るので、香りや味も同じになります。種から育てるよりも時間が掛からず、成長も早いです。
まず数枚の葉っぱを残して、若い枝の先を7センチくらいカットします。そして、1時間程度水に挿しておきます。土に入れて、その後は半日陰で水を切らさないように注意します。梅雨の時期などに行うと湿気でカビが起きやすくなるので、風通しが良い場所に移動するようにします。
挿し木が上手くいけばどんどん増やすことができ、たくさん収穫することが出来るようになります。株分けで増やすこともでき、根を傷つけないように取り出して植え替えると増やすことが出来ます。成長期になる春の時期が株分けに向いていて、新しい芽が出やすくなります。
無農薬で育てている場合は害虫や病気が発生する可能性があるので、秋の時期に種まきすれば最低限まで抑えることが出来ます。出来るだけ風通しが良い場所を選び、ハーブを食べる虫にとって天敵になる虫が住みやすい環境を作ります。ハーブにとって害になる虫を見つけたときには、
すぐに駆除するようにします。無農薬で育てているときに大きな病気や害虫被害にあってしまったときには、迷わず薬剤を使って対処するようにします。また必要以上に肥料を与えていると虫が付きやすくなるので、適度にすることも大切なポイントです。
イブキジャコウソウの歴史
イブキジャコウソウなどのタイムの原産地は南ヨーロッパで、古代ギリシャ時代から薬用や食用として利用されています。紀元前の700年ごろには、様々な書物に栽培法などが記載されています。勇気のシンボルとしても知られる存在で、賞賛されていたという歴史があります。
イブキジャコウソウはハーブのタイムの種類の一つで、タイムは古代エジプトではミイラを作るための防腐剤としても使われていたのです。ギリシャ人はお風呂の時間や神殿で焚くためのお香として、利用されていたという歴史もあります。古代ギリシャではやる気や勇気を出すことが
出来る植物として信じられていて、中世には悪夢や寝苦しさを防いで安眠を促すために枕の下に入れられていたのです。持ち主や利用者に勇気をもたらすと信じられていたので、騎士や戦士に対して葉っぱを添えて贈り物をしています。香料としても用いられていた歴史もあり、
来世への旅路を確実にするために葬儀の際にはお棺に入れられています。紀元1世紀ごろに出版された「プリニウス博物誌」には物がはっきり見えるようにすることが出来る効果や、慢性的な咳に効くとされています。さらに酢に入れてはちみつを加えたものは、
うつの症状や精神異常に効果があると記されています。16世紀のイギリスでは咳や息切れ、肺や子宮の病気に効果があるといわれています。利用作用があること、失神したときに香りを嗅がせると効果があるとされていたのです。
イブキジャコウソウの特徴
イブキジャコウソウは日本原産のハーブでもあり、タイムの一種でもあります。伊吹山に多く生息していて、豊かな香りが特徴的なハーブです。西洋ハーブとは違った香りがあり、和風のハーブならではの香りを持っているのが最大の特徴です。
北海道から沖縄を除く九州までの日本列島と、ヒマラヤや中国、アフガニスタンにかけての温帯地域と寒帯地域に生息しています。日光が良く当たる山の岩場や草地、さらに海岸にも生えている小低木です。茎はツル状に張っていて、細いのが特徴です。
葉っぱは小さく、長さは5センチから10センチ程度です。葉っぱの先は丸い形をしていて、葉っぱの両面には小さい分泌腺があります。イブキジャコウソウに触れると、ニオイが触れた部分に移ります。夏には枝の先に小さな花を作り、淡いピンクの花が咲きます。
別名でヒャクリコウとも呼ばれていて、香りが百里四方にも届くことからこのように呼ばれています。生えている場所の近くに寄るだけでも、香りがするといわれていることからこのように呼ばれるようになったのです。薬用にも使われることがあり、花が咲いているときに地上部を採取します。
水洗いをして陰干しすることで、ハーブティーとして飲むことも可能です。香りの成分には利尿作用や発汗作用、強壮作用があります。消化を助けて血行を改善させる効果もあるので、風邪や頭痛、気管支炎などに効果があります。鎮痛薬や鎮咳薬、駆虫薬としても利用されています。
-

-
サボテンやアロエなどの多肉植物の育て方
多肉植物は、葉や茎に水分を蓄えることのできる植物です。サボテン科、アロエ科、ハマミズ科、ベンケイソウ科など様々な種類があ...
-

-
ひまわりの育て方
ひまわりはきく科に属し、日輪草(ニチリンソウ)や日車(ヒグルマ)と言う別名を持ちこれは、ひまわりが日輪のように見えること...
-

-
ジギタリスの育て方
ジギタリスの原産地は、ヨーロッパ、北東アフリカから西アジアです。およそ19種類の仲間があります。毒性があり、食用ではない...
-

-
ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する...
-

-
シネラリアの育て方
シネラリアはキク科の植物で、早春から春にかけての代表的な鉢花のひとつです。原産地は北アフリカの大西洋沖に浮かぶスペイン領...
-

-
グラジオラス(夏咲き)の育て方
園芸植物として人気の高いグラジオラスは、200種類前後の種類がある球根植物です。南アフリカのケープ地方が中心に分布してい...
-

-
ホタルブクロの育て方
ホタルブクロの特徴として、まずはキキョウ目、キキョウ科であることです。花の色としては真っ白のものがよく知られていますが、...
-

-
ペチュニアの育て方
ペチュニアは花がタバコの花に似ているためブラジルのグアラニ語で タバコを意味するの「ペチュン」という言葉が花の名前の由来...
-

-
レウイシア・コチレドンの育て方
この植物の特徴は、スベリヒユ科、レウイシア属になります。園芸上の分類としては山野草、草花となることが多くなります。花の咲...
-

-
ユキモチソウの育て方
ユキモチソウ(雪餅草)は非常にユニークな花を咲かせます。名前からも分かるように、真っ白な平皿に真っ白な餅が載せられている...




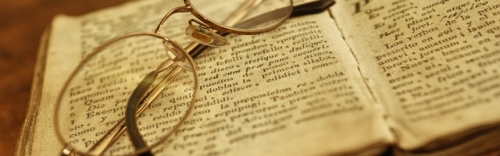





イブキジャコウソウなどのタイムの原産地は南ヨーロッパで、古代ギリシャ時代から薬用や食用として利用されています。紀元前の700年ごろには、様々な書物に栽培法などが記載されています。勇気のシンボルとしても知られる存在で、賞賛されていたという歴史があります。