イワカガミダマシの育て方

育てる環境について
イワカガミダマシは、もともと寒冷地で自生していた野草ということもあり、原則日本の夏場のような高温多湿の環境は苦手としています。そのため、難易度が高めのこの植物を上手に開花させるためには、夏場の暑さや湿度などの対策をしっかりすることが重要です。
一方で、寒いところのほうが育ちやすい性質を持っていますので、晩秋から冬にかけてはしっかりと寒い場所で冷気に当てて、休眠させるのがよいでしょう。北海道や東北地方のように、年間を通して比較的気温が低く乾燥している地域であれば育てやすい植物ですが、
夏に高温多湿になる環境下では夏を越せずに枯れることも珍しくありません。日照量は多いほうがよく、もともと日当たりの良い草原に自生していますので、できれば一年中太陽光の当たる場所を用意しましょう。ただ、夏場の直射日光はイワカガミダマシには強すぎますので、
50%遮光をするとともに、多湿を嫌いますので雨除けも施しておきます。真冬も暖かい環境の中では花芽が弱ったり傷ついたり、開花が早まることがあります。そのため、鉢植えのものも外に出しておきましょう。雪が降る地域であれば、ユキノシタで休眠させるのが理想的ですが、
都会では涼しい場所で風に当たらないよう管理しましょう。通気性と水はけのよい、鉢穴が大きくて半深鉢以上の深さがあるき締め鉢がおすすめで、厚さがあったり釉薬がかかっているものは避けましょう。用土は水もちと水はけが重要ですので、鹿沼土、日光砂、軽石の粒径2~5mmのものを5:4:1の割合で配合しましょう。
種付けや水やり、肥料について
種まき時期は1月下旬から月上旬にかけてですが、日本では種から作るのも難しいため、ポット苗を購入して栽培するというのがほとんどです。ポット苗のほとんどは寒冷地向きのエゾ砂などが使われていますので、寒冷地で育てるときにはそのまま利用できます。
しかし、エゾ砂は温暖地では傷みやすいため、購入したらまずは枯れた古葉を取り、古い土を落として根を広げ、全体を整理してから配合した用土で植えなおしたほうが成長しやすいでしょう。イワカガミダマシは株が傷みやすいため、基本的に毎年植え替えを行います。
植え付け・植え替えともに、時期は4月下旬から5月中旬と、9月下旬から10月上旬にかけてが適しています。ただし、株が弱ってきたらこの時期から外れていても植え替えたほうが再生しやすくなります。乾燥よりは水を好むものの、夏場は用土に含まれている水分によって
鉢内の温度が上昇しやすいため、湿度が高いと株が傷む危険性があります。そのため、夏場は多湿を避けて、表面が乾いているようなら気温が下がる夕方以降にたっぷりと冷水をかけましょう。イワカガミダマシの株は横に広がっていきますので、
置き肥はせずに元肥と液体肥料で管理します。液体肥料は、チッ素、リン酸、カリが等量のものを使用し、時期は4月下旬から6月下旬までと、9月下旬から11月上旬の比較的気候の穏やかな時期がよいでしょう。この時期に2週間に1回の割合で施すと成長が活発になります。
増やし方や害虫について
イワカガミダマシの増やし方は、株分けか種まきになります。地域によっては、種まきでは開花までたどり着けないことがありますので、一般的にお勧めできるのは株分けの方法です。ただ、種まきから育てたほうが暑さにややなじみやすい傾向にありますので、好みで選ぶとよいでしょう。
株分けは、植え替えをするときに行います。大きさは手で割れる程度のサイズで、根が多くつくようにしたほうが植え替えた後で成長しやすいです。種まきをするときには、1月下旬~3月上旬ころのできるだけ寒い時期にまくとよいでしょう。
病気は夏の暑さや多湿で発生する軟腐病や、立枯病に気を付けましょう。軟腐病にかかると、葉や茎がぶよぶよになって茶色く腐り落ち、成長が止まってしまいます。水分調整や気温管理などである程度防ぐことができますので、鉢植えをこまめに移動させたり、
水やりに気を使いましょう。古葉ができたらこまめに取り除き、株元の風通しを良くするのも有効です。また、芽が出たころに現れる立枯病も注意しておきましょう。株全体の生育が悪くなり、病気が進行すると下葉から黄色くなって株全体が枯れてしまいます。
土壌が汚染されますので、植え替え時期に土壌消毒をして、発病した株は抜き取って処分しましょう。害虫は、ナメクジ、アオムシ、アブラムシなどの仲間が葉を食べるので要注意です。特に、開花期にはアブラムシが大量発生しやすいため、葉や花の様子を確認したり、駆除剤を使用して予防しましょう。
イワカガミダマシの歴史
イワカガミダマシはソルダネラ・アルピナの和名ですが、漢字では岩鏡騙しといい、ヨーロッパのアルプス山脈やピレネー山脈、アペニン山脈などが原産地です。この花は常緑の多年草で、アルプスなどの高山の草原に生えていますので、もともとは日本では見られませんでした。
日本には園芸用としてのちに移入されており、現在では涼しい地域で栽培もされています。日本に来た時に、和名であるイエワカガミダマシという名がつけられましたが、これは花の姿がもともと日本にあったイワウメ科のイワカガミという花によく似ていたことに由来しているといわれています。
原産地であるアルプスなどの高山では、雪解け後の湿っている場所にいち早く咲くことから、春の訪れを告げる花とも言われており、その可憐な姿は多くの登山者の気持ちを和ませています。美しい青紫色の花は山野草の愛好家にも人気があり、
国内外を問わず環境の合う場所で栽培されています。日本でもその姿が愛されており、アルプスの少女ハイジのアニメでは、クララが歩けるようになって山の牧場でつんだ花がイワカガミダマシに非常によく似ていることで知られています。
日本に移入してきた時期は不明ですが、それほど品種改良などは行われておらず、アルプス地方で咲いているそのままの花を国内で楽しむことができます。ただし、涼しく湿った場所を好みますので、国内でも暑い場所には向きませんし、育て方もやや難易度が高いです。
イワカガミダマシの特徴
イワカガミダマシの特徴は、その名の通りイワカガミに似ている姿です。花弁の先端が細かく裂けており、下向きに赤紫色のベルのような形の花を咲かせます。葉は常緑で光沢があり、長い柄がついた丸い形をしており、次々と開きながら横に広がっていきます。
それほど大きい花ではなく、茎の高さが5~15㎝、花冠が直径1~1.5㎝程度で、先端は細かく裂けています。イワカガミダマシは、新芽ができるのと同じ時期に細い花茎をのばし、花が数輪ずつ咲きます。夏の間にも新芽を出して株を増やしながら広がり、秋を過ぎたころから花芽を作り出します。
晩秋には花芽ができた状態で冬を迎え、雪解けのころから開花します。自生している生息地では6~8月頃に花を咲かせますが、国内のように栽培しているところでは、4月中旬から5月下旬にかけて開花します。この花は多年草ではあるものの、
日本国内では雪解け水のある場所がほとんどありませんので、長期的に自宅で栽培するのは困難です。そのため、ポット苗が多く流通しており、自宅でもある程度育てやすくなっていますが、こちらの苗も寒冷地で作られたものであるため、夏場などを上手に乗り切らせる必要があります。
逆に、寒冷地では寒さに強くどんどん成長していくことができますので、高山ではそれほど手間をかけなくても自生していきます。雪解けのころに咲くことから、春を告げる野草としても知られており、国内外で多くの人に愛されています。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:イワチドリの育て方
タイトル:イワシャジンの育て方
-

-
キジムシロの育て方
被子植物で、バラ目、バラ科、バラ亜科となっています。特徴としては、梅に似ているだけあって属以外は梅と同じです。被子植物で...
-

-
オヤマリンドウの育て方
オヤマリンドウの特徴は名前の由来にもなっておりますように、ある程度標高の高い亜高山や高山に咲くことが大きな特徴です。そし...
-

-
カラタチの育て方
今から約1300年前に伝来していて、和名の由来はからたちばなという言葉が略されたとする説が実在しています。ただ、からたち...
-

-
ディフェンバキアの育て方
ディフェンバキアはサトイモ科ディフェンバキア属で原産地や生息地は熱帯アメリカです。和名にはハブタエソウやシロガスリソウと...
-

-
シペラスの育て方
シペラスは、カヤツリグサ科カヤツリグザ(シぺラス)属に分類される、常緑多年草(非耐寒性多年草)です。別名パピルス、カミヤ...
-

-
エキノプスの育て方
エキノプスはキク科ヒゴタイ属の多年草植物の総称で、この名前の由来はギリシア語で「ハリネズミ」を意味する「エキノス」と「~...
-

-
にらの育て方
にらの原産地は定かにはなっていませんが、中国西部から東アジアにかけての地域生息地ではなかったかと考えられています。モンゴ...
-

-
西洋クモマソウの育て方
原産地はヨーロッパ北部といわれています。漢字で書くと雲間草で、ユキノシタ科の植物です。雲に届きそうな高い山間部に生息する...
-

-
みつばの育て方
みつばの特徴としてはセリ科に該当します。せりといいますとやはり香りの良い野菜として知られていますから、その系統になってい...
-

-
ボロニアの育て方
ボロニアはミカン科、ボロニア属になります。ボロニアは、3月から4月にかけて綺麗な花を咲かせる樹木になります。ですので、寒...




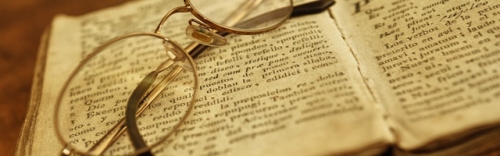





イワカガミダマシはソルダネラ・アルピナの和名ですが、漢字では岩鏡騙しといい、ヨーロッパのアルプス山脈やピレネー山脈、アペニン山脈などが原産地です。この花は常緑の多年草で、アルプスなどの高山の草原に生えていますので、もともとは日本では見られませんでした。