セイヨウムラサキの育て方

育てる環境について
セイヨウムラサキの育成環境について書いていきます。日当たりの良いところよりも、むしろ日当たりがあまりよくないところの方が良いでしょう。実際に、野生のものを見ても、木陰で咲いているところを発見されます。したがって、たとえば、家の庭で育てる場合は、できるだけ日当たりのよくないところが良いでしょう。
直射日光の当たらない家の裏庭が、栽培環境としてはお勧めです。それというのも、温度に弱いという特徴があるからです。直射日光による温度の上昇が成長力を著しく弱くしてしまいますし、生命力も弱くなってしまうわけです。そのため、できるだけ直射日光の当たらない日陰のところに安置することがポイントです。
また、愛好家の中には、肥料として土と石灰を混ぜ合わせたオリジナルの肥料を作ることが多いのですが、セイヨウムラサキの場合は、あまりお勧めできません。たしかに、野生のものをみると石灰岩質に集中して生息していることが多いので、石灰が肥料として最適さと思ってしまいます。しかしながら、野生のセイヨウムラサキがそのようなところに自生しているのは別の理由があるからです。
つまり、そのように石灰岩質のところでは、ほかの植物が育ちにくいということから、ほかの植物との生存競争を避けるために、そのようなところにあえて生息しているわけです。決して肥料として石灰岩質をみずから求めているわけではありませんので、わざわざ石灰を混ぜた土を使う必要はありません。
種付けや水やり、肥料について
育て方の中でも種付け、水やり、肥料について言及していきましょう。肥料としては前述したとおり、特に石灰を混ぜた土を使う必要はありません。ホームセンターなどで売られている通常の肥料で問題ありません。種付けについては、開花受粉が一般的です。隣り合わせに育てるだけで、あとは勝手に受粉されます。種付けは難しいものではありません。
しかしながら、愛好家の中には、雑種化を避けたい人もいます。日本ムラサキと西洋ムラサキを隣りあわせで育てていると、お互いに受粉してしまうからです。つまり、育てている人にとっては、純粋の日本ムラサキや純粋のセイヨウムラサキをずっと育てたいと考える人もいるわけです。そうした人は、隣り合わせで育てるのではなく、距離をとって育てることはもちろん、次のような工夫も必要です。
つまり、種の扱いです。種は熟していくと取れやすくなります。日本のものも西洋のものも数多くの種ができますので、種は採取することは避けましょう。純粋のものを増やす場合は、挿し木を行うことがもっとも効果的です。挿し木の時期は、夏から秋にかけてがお勧めです。
つまり、5月や6月の梅雨の時期や長雨の9月ころがお勧めです。水やりについては、定期的に行うことが大切です。また、やりすぎには注意が必要です。もっとも梅雨の時期にもっとも成長するので、水やりよりも、まわりの環境に気をつけたほうが良いです。近くに根張りの強い植物がいると成長が阻害されるからです。
増やし方や害虫について
セイヨウムラサキの害虫対策や育て方について書いていきます。ムラサキ科は基本的に弱い植物です。つまり、害虫によるダメージがほかの植物に比べて大きいというわけです。そのため、慎重に育てる必要があります。それでは、どのような害虫がつきやすいのかというと、その代表例はアブラムシです。ほかにも、ダンゴムシもそうです。
これらは葉を虫食い状態にするので、ムラサキ科にとっては非常に危険な存在です。葉が食われると植物は体力が落ちます。ムラサキ科も例外ではありません。葉が食われすぎると体力が落ちこんでしまい、時として枯死するケースも珍しくありません。食われた葉は取り去るのが無難です。
それというのも、害虫は病気ももたらすことがあるので、ほかの葉にも悪影響をもたらします。そのため、被害が深刻化しないように、食われた葉はハサミを使って取り去って処分することが良いでしょう。葉や茎を取り去ってもすぐに、わき茎が出てくるので、心配はありません。そして、害虫に対しては、次のようなものをおのおの使用すると解決することができます。
ダンゴムシに対しては天然有機忌避剤を使用すると良いでしょう。アブラムシに対しては、牛乳をかけると良いでしょう。こうした害虫対策を行うことできちんと育成することができるというわけです。最後に、増やし方については、前述しましたが、挿し木がもっとも効果的です。純粋栽培を行うには、挿し木をして増やすことが無難です。
セイヨウムラサキの歴史
セイヨウムラサキの歴史について書いていきます。セイヨウムラサキは日本原産の花ではありません。もともとは日本ではなくヨーロッパやアジアで栽培されていた花です。そういうことから、セイヨウという名前がついているわけです。それでは日本ではセイヨウムラサキは見られないのかというと、そうではありません。
日本でも公園の芝生をみると生息しているのが確認されます。実は、日本にはセイヨウムラサキではありませんが、ムラサキという日本原産の花がずっと生息していました。しかしながら、1970年代頃よりヨーロッパ原産のセイヨウムラサキが公園を中心に多く見られるようになりました。そうはいっても、どこでも見られるというわけではありません。
野生で見つけようとおもっても専門家でなければ、まず見つかることはないと考えたほうがいいでしょう。ただし、最近は日本原産のムラサキと混同されて交雑種が栽培されるようになっています。つまり、純粋な日本原産のムラサキがどんどん少なくなっており、セイヨウムラサキが日本にどんどん進出しているということです。
そのため、近年は純粋なムラサキやセイヨウムラサキはなかなか見つけることが難しくなっている状況です。特に、日本原産のムラサキを保護しようといろいろな運動が起きているのが現状です。しかしながら、その一方でセイヨウムラサキの愛好家も多く、ショップでの購入が増えているのも事実です。以上がこれまでの歴史になります。
セイヨウムラサキの特徴
セイヨウムラサキの特徴について書いていきます。日本を本来の生息地とするムラサキと比較してみると、茎に特徴があります。茎が非常に数多く分枝します。また、葉についてはムラサキに比べて、柄がないのが特徴です。ちなみに、ムラサキという名前がついていることから、紫色をしていると思われがちですが、実際にはそうではありません。
これは人間の用途が関係しています。つまり、人間が紫色の染料の材料として使うことから、この名前がついているということです。高さは一般的には1メートル程にはなります。これは茎は直立する傾向があるから、すっと伸びやすく高さを確保できるためです。また、毛については、全体的に粗い毛があります。触ってみるとわかりますが、ざらざらします。
花については、非常に小さな花を咲かせます。大きさは直径で1センチもありません。日本原産のムラサキに比べてもかなり小さいです。半分以下です。花の色は黄白色です。黄白色というのがわかりにくければ、クリーム色といったほうが良いでしょうか。果実については、これも非常に小さいものが一般的です。
長さが5ミリにも満たないものが多いです。こうした花の特徴以外にも述べておくことがあるとしたら、育てやすさというものが挙げられます。日本在来種のムラサキに比べて非常に栽培しやすいからです。これは種子を非常に数多くつけるからです。こうしたことから、実は中国では栽培用として非常に人気があります。
-

-
リシマキアの育て方
リシマキアは育て方も簡単に行なうことができて、栽培しやすい植物になっています。それに原産国は北半球です。そしてサクラソウ...
-

-
チューリップ(アラジン)の育て方
チューリップにおいては日本に来たのは江戸時代とされています。その時にはほとんど普及することはなかったようですが大正時代に...
-

-
バンレイシの育て方
バンレイシは果実の皮の突起の形が仏教を創設した者の頭に似ているのでシャカトウとも呼ばれているプラントです。ちなみに英語で...
-

-
クレピスの育て方
クレピスは学名で、モモイロタンポポ(桃色蒲公英)というキク科の植物です。ただし、クレピスの名前で呼ばれることも多いです。...
-

-
クリサンセマム・パルドーサムの育て方
クリサンセマム・パルドーサム(ノースポール)は、キク科フランスギク属に分類される半耐寒性多年草です。ただし、高温多湿に極...
-

-
ブンタン類の育て方
ブンタンはミカン科ミカン属の大型の柑橘類の一種でザボン、ボンタンなどと呼ばれ、ブンタン類には柑橘類最大の晩白柚や日本原産...
-

-
ニューギニア・インパチエンスの育て方
ニューギニア・インパチエンスはツリフネソウ科の常緑多年草で、学名を「Impatiens hawkeri」と言います。イン...
-

-
ヨモギの育て方
ヨモギは春に芽を出して50cm~1m程の高さまで成長します。夏から秋にかけて黄色い花粉を付けた小さな花を咲かせます。ヨモ...
-

-
キュウリの育て方のポイント
水分を豊富に含むキュウリは、原産地はインドやヒマラヤであり、そのあたりが生息地と考えられています。栽培されていたのは、さ...
-

-
メギの育て方
メギはメギ科メギ属の仲間に入るもので、垣根によく利用される背の低い植物です。メギ属はアルカロイドという成分を含んだ種類が...




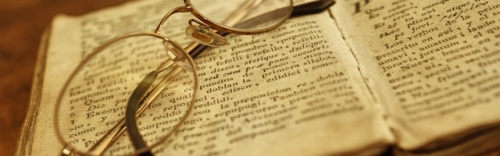





セイヨウムラサキの特徴について書いていきます。日本を本来の生息地とするムラサキと比較してみると、茎に特徴があります。茎が非常に数多く分枝します。また、葉についてはムラサキに比べて、柄がないのが特徴です。ちなみに、ムラサキという名前がついていることから、紫色をしていると思われがちですが、実際にはそうではありません。