ツタ(ナツヅタ)の育て方

育てる環境について
ツタは強い植物ではありますが、害虫には注意しなくてはなりません。虫が住みやすい環境ということもあり、被害のない虫ならばよいですがつたにとって良くない虫も住み着きやすいです。栽培する際には、特に虫の存在には気をつけるようにするべきです。コガネムシなど人間には害のない虫がツタにとっては、被害のある害虫なので育てる際にはしっかり調べておくようにしましょう。
増やす際には、時期も考える必要があります。ツタは夏場には青々としていますが、冬には枯れ落ちてしまうので時期がずれるとうまく増やすことができません。増やすこと自体はそう難しい植物ではありませんが、その中でも増やし方としては挿し木が簡単です。その際には、土は、水はけ水持ちが良いものを選ぶのかポイントです。
温度や湿度変化の多いところはあまり良い環境とは言えないので避けるようにするべきです。かための枝を選び、土はフワフワの状態だと根の張りが弱くなるので土を固めに抑えるようにします。虫の被害もあり、葉が食べられてしまうこともよくあります。葉が少ない時に食べられてしまうと衰弱してしまうことが多いので、
そういった被害がなさそうなところで育てていくことも大切です。もし被害にあった時には、原因となる虫を一匹残らずとらなくてはなりません。大変な時には農薬を使うのが簡単です。キチンと育ってしまった後ならば、強い植物なのでそこまで気にする必要はありませんが、小さな時には気を配るべきです。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては、特に何もしなくても育ってくれるのでとくに手をかける必要はありません。管理しなくてはならないことも特にはありませんが、あえて言うのであれば伸びすぎた枝を切ることくらいです。壁につたっていくので壁さえあれば良いです。あとは生け垣などもよいです。繁殖力の強さもあるし、耐寒性もあります。
それだけではなく潮風にも強く乾燥にも耐え抜くことができるという、素晴らしい植物です。土の質も選ばないし手がかからないのが魅力ともいえますが、乾燥には耐えるとはいえやはり適度に湿地を好んでいるので、できればそういった環境にしたほうが成長が早く、元気なツタに育つことは間違いはありません。壁面緑地化にツタを使いたい場合には、
レンガなどの場合には綺麗になりますが、ただのコンクリートではある一定までで限界があるともいえます。特に年月が経つとツタがまばらになってしまうことがよくあるので、見た目の美しさで問題があるともいえます。ツタにとって良い環境ができたとしても、虫が発生するなどの問題もあります。
植物自体には被害がない虫でも人間からすると被害があるものもいれば、その逆のパターンもあります。植物にとって被害がある虫だとせっかく緑地化した壁のものも枯れてしまうので、人間が大丈夫だからといって放置しておくのではなく、
様々な虫に対して注意しておかなくてはなりません。ツタによる壁面緑地化には、まだまだ課題も残されているといっても良いです、育てる環境として一番良いのはどうなのかというところを考えながら進めていくことがポイントです。
増やし方や害虫について
水やりは成長して壁面に巻きついているものには、そう気にする必要はありませんが、まだそこまでなっていない場合には、たっぷりとした水を与える必要があります。土が乾く前に水をやるのがよいです。根が張るときの場合には、その時だけ水を控えめにするべきです。なぜかというと、そうすることにより水分を求めて根が広く張るからです。
そういったところも考慮しながら育てていくことが強いつたを作る秘訣とも言えます。一般的な植物の場合には、肥料を与えたほうが良いものが多いですが、つたの場合には肥料を与える必要というのは特にありません。生き抜く力が強い植物には、あえて肥料などを与えないというのも一つの手段だということです。
どうしても肥料をという場合には、油粕などの窒素系の肥料をあたえるようにしましょう。こういったタイプのものがつたとの相性はよく、育つための手助けになります。肥料と一口に言っても、合わないものを与えていては効果が得られないどころか悪い方向に進んでしまうパターンも稀にあるので注意が必要です。
水や肥料の与えすぎも枯れる原因となってしまうので与えすぎはよくありません。強い植物なので、自然界に存在している水はなんとか持ちこたえてくれることが大半ですか、肥料は自然界にあるものではなく、そうもいかないので、特に肥料は与えすぎには注意をする必要があります。
与えすぎというところだけではなく与えるタイミングも重要なので、肥料が必要な時には事前にキチンとタイミングをたしかめておくことが確かめておくことが最低限必要なことです。
ツタ(ナツヅタ)の歴史
ツタはナタヅタともいい、ブドウ科ツタ属のツタ植物です。古くから存在していて、日本でもよく使われている植物の一つです。昔から様々な文様などのデザインにもよく使われていて関わりの深さがわかります。原産ということも言われており、自然にあるものだと国内の生息地としては、北海道や本州、四国や九州に分布しています。
海外では中国や朝鮮にも分布しており、林内や林緑にあります。花や実も小さなものなので目立つタイプの植物というわけではなく、昔からメインとしては扱われてはいませんが、紅葉の時期にはとても綺麗な色になります。日のよく当たるところは真っ赤になり、そうではないところはオレンジに近い赤で、色のコントラストも楽しむことができるので、
その面でも人々の目を楽しませてくれる植物といえます。昔は家などでもツタが巻いたものをよく見かけましたが、これはツタにより夏の暑さを和らげるためにしていました。球場などでも使われているところもあるくらいです。こういったところからも、人々の生活との関わりがあった歴史かわかります。
繁殖力も他の植物とくらべると極めて強いので昔から現代に至るまで生き延びてこれたといえます。繁殖力が強いだけではなく、ありとあらゆる環境の中でも枯れてしまうことはほとんどないと言っても良いです。こういった生き延びる力の強さにより、長い歴史の中で大きな変化をすることもなく形を変えずに今のツタの姿をたもっています。
ツタ(ナツヅタ)の特徴
ナツヅタの特徴は、葉は浅くさけるか完全に分かれて複葉になります。落葉性で名前の由来の通り夏には葉がありますが、冬には落ちてしまいます。巻きひげの先が吸盤となっているので、巻きひげを伸ばしてコンクリートなどの壁面に付着しています。無理に壁面から剥がそうとすると吸盤だけが壁に残ることもあります。
それほどまでに強力な吸盤をもっている植物もあまり多くはないのではないでしょうか。花や実については、目立たない花が咲き、小さな紫色の実をつけ、見た目は美味しそうに見えますがとても渋いので人間が食べるものとしては向きません。しかし、鳥などが食べることはよくあります。
葉の一枚一枚に日光が行き届くように伸びていき、自ら葉にとって成長できるようにしています。ありとあらゆる環境に適応できることから、現代社会の壁面緑地化にも有効な手段とされています。他の植物に比べると繁殖もしやすく、放っておいても増えていってくれるので管理がとてもラクといえます。
都心部なとのコンクリートジャングルと呼ばれるところにも対応できるので、高層ビルやタワーマンションなどの屋上などでも活躍が期待されていて、今後その注目度も上がっていくことに間違いはありません。しかし、つたがいくらありとあらゆる環境の中でも大丈夫とはいえ、
日光を必要としている植物ということに違いはないので、日が当たらない北側では一面につたが巻きつくことはあまりありません。こういった面を考えると、まだまだ考えなくてはならないところはたくさんあるともいえます。つたの良い特徴を活かしながら緑地化にも協力をしてもらわなくてはなりません。
-

-
レタスの栽培に挑戦してみませんか。今回はレタスの育て方につい...
今回はレタスの育て方について学んでいきます。レタスの栽培は暑さに弱いので秋蒔きが作りやすいのですが、春蒔きでも可能です。...
-

-
ヤマブキの育て方
春の花が咲き終わる頃になると、濃い黄色の小花をたくさん咲かせ、自然な樹形を保ちやすく、和風な作りの庭などにもよく利用され...
-

-
柑橘類(交雑品種)の育て方
柑橘類は遡ること3000万年という、はるか昔の頃から、インド東北部を生息地として存在していたものです。中国においては、4...
-

-
ドイツアザミの育て方
この花はキク科アザミ属に属します。ドイツとありますが日本原産です。生息地も日本となるでしょう。多年草で、耐寒性があり耐暑...
-

-
バラ(シュラブ・ローズ)の育て方
バラの歴史はとても古く、恐竜が世界を支配していたころから始まります。さらに初めに文字として誕生したのは古代メソポタミア文...
-

-
ゴールデンクラッカーの育て方
この花についての特徴としてはキク科、ユリオプス属になります。花が咲いている状態を見るとキクのようには見えませんが、黄色い...
-

-
ネクタロスコルダム・シクラム・ブルガリカムの育て方
和名はアリウム・シクラムですが、アリウムの仲間ではありません。ネクタロスコルダム・シクラム・ブルガリスは、現在ではネギ科...
-

-
ツツジの育て方
ツツジもまたピンク色のものから赤っぽいもの、紫や白いものがあり、古来より人々の目を楽しませてきました。現在でも春になると...
-

-
カラマツソウの育て方
カラマツソウ(唐松草)/学名:Thalictrum aquilegifolium(唐松草)・Trautvetteria ...
-

-
コトネアスターの育て方
コトネアスターはほとんどがインド北部またはチベットを原産としています。生息地はこれらの国に加えて中国まで広がっています。...




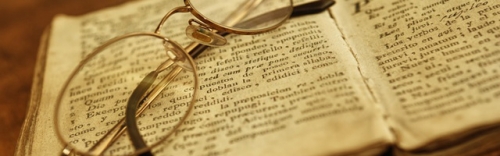





ツタはナタヅタともいい、ブドウ科ツタ属のツタ植物です。古くから存在していて、日本でもよく使われている植物の一つです。昔から様々な文様などのデザインにもよく使われていて関わりの深さがわかります。原産ということも言われており、自然にあるものだと国内の生息地としては、北海道や本州、四国や九州に分布しています。