ヤブヘビイチゴの育て方

育てる環境について
ですので食べられる実では、黄色い花のヘビイチゴはまずくて、その他の花のヘビイチゴ類は美味しいということになります。そしてそれぞれの種類でも花が違うので、ガーデニングの栽培でも、色々な種類を栽培すると花で楽しめますし、美味しい実の花を栽培すると、果実ということでも楽しめます。
ガーデニングの作業をしながら、摘んで食べるということでも面白い体験ができて、満足もできるということになります。またこれらの野いちご類でも、何十種類もあるので、その点も色々と調べてみると面白いですが、このヘビイチゴ類は春先になると黄色い花が目につき、そして赤い実がみのるようになるので、
春になってきたということも肌で感じることができる植物でもあります。この植物の原産地は日本や南西アジアなどですが、珍しくもない一般的な植物ということになります。ですので栽培も簡単で、日本に自生しているのですから、環境さえ極端でなければ、誰にでも育てることができる植物ということになります。
庭がないマンションなどでもプランターなどで、ベランダでも育てることができますので、案外楽しむことができるのではないかという感じもします。なかなかヤブヘビイチゴをベランダで育てているという話は聞かないので、そのことでも面白いということになります。また室内では赤い色の配色はあまりないですし、植物の赤はまた独特の自然な柔らかさがあるので、緑とともに効果的な癒心もアイテムにもなります。
種付けや水やり、肥料について
また葉は三枚で、花は五花弁でありますが、他の多くの植物は、子房がふくらんで果実になります。しかしこの花は花床がふくらんで果実になるので、そのことも珍しい植物ということになります。またこの植物では、漢方薬としても効果的で、解熱や神経痛にも効く薬効もあるということです。
そのように漢方薬としても利用できるので、そのような方面の知識も増やして、育ててみるのも面白いです。しかしこの種類は、野原でも目立ちますし、花もきれいなのに食べることができないということでは残念ですが、美味しければ、これほど広く分布はされなかったかもしれません。人間がまずくて手を出さなかったので、このように広がったとも言えます。
また今ではアメリカなどでは帰化植物として有害な植物ということになっている地域もあるということですが、それはそのまま非常に生命力があるということですから、栽培をする場合には、そのことは有利な要件にもなります。そのように植物としては、名前から生き方から果実や花まで非常に興味深い面白い植物ということになります。
その点は興味を惹かれる植物ということで選ぶ条件のひとつにもなります。またそのような事情を知ると興味が湧いてきて、ガーデニングでも育てる甲斐にもなるということでもあります。また育て方としても初心者向きということが言えます。自生出来る環境だと手間いらずということで済ませられもします。庭などでも自然に繁殖をしてくれるからでもあります。
増やし方や害虫について
具体的な育て方ということでは、開花時は4月から10月と長く、植え付けも3月から5月と9月、10月で、春と秋にできます。また繁殖力が旺盛ですので、庭に植えると他の植物を駆逐するほどですので、やはり鉢植えかプランターで、他の影響がないように栽培するのが良いということです。
自然な野原のように庭が美しくなりますが、他の植物に対しての影響がありすぎるので、庭には植えないほうが良いというアドバイスもありました。それほど繁殖力がある植物も珍しいですが、雑草に分類されているだけはあります。なかなか根性がある植物ということでしょう。それでも植物としては、乾燥に弱く、
だからといって水をやりすぎても枯れてしまうということですので、鉢植えでも適度に水を与えて乾燥しないぐらいがよく育つということです。鉢の受け皿に水がたまらないぐらいに与えるということがよいようです。またこのように強い植物ですので、土も選ばないので市販の培養土で十分です。また種でも増えますが、ランナーでも横に広がります。要するに、のびた茎が根付くということでも広がるということになります。
その点も非常に繁殖力がある植物です。庭などで広がりすぎた場合には、その都度抜き取れば、根は深くないので、そのうちに見られなくなるということですが、このような植物ですので庭などでは害虫の心配もなく、そのままにしておけば、自然に広がっていくということですので、特に栽培の必要はない植物ということになります。ほんとうに面白い植物です。
ヤブヘビイチゴの歴史
ガーデニングでは楽しみのひとつに、変わった植物を育ててみたいということがありますが、日本の環境で育てられる植物で、観賞用にも楽しめて、できれば食べることができるような植物が良いとも考えたりします。また日本伝統のどこにでもある植物ということで、わりと珍しいものも楽しめたらということですが、面白いということでは、野いちごの類も面白いという感じもします。
その中でもヘビイチゴは、田舎の子供は誰でも一度は興味を持ちます。田舎では、どこにでも自生している植物で、イチゴという魅力的な名前もついていて、イチゴは高級食材だったので、子供でもなかなか食べられませんでしたし、ショートケーキなどの高級なお菓子の上に乗っていたりして、とても美味しいというイメージがあったので、
イチゴという名前に惹かれて興味を持ったりしましたが、大人たちに聞いてみると、あまり評判は良くはなく、食べたら駄目だよと言われたりしました。毒があるという話や、蛇が近くにいるとか、蛇だけしか食べないとか、色々と言われていました。それで人間が食べるものではないということで、敬遠したりしました。
名前の由来も蛇が消化薬として食べているということで、当然そうなると蛇もいるだろうということになったからですが、その他の説では、あまりにも不味すぎて蛇しか食べないということでついた名前だとも言われています。原産地や生息地も南西アジア全域ということで、日本でもよく見られる植物です。特に山間などの地域ではたくさん見られます。
ヤブヘビイチゴの特徴
ヘビイチゴもヤブヘビイチゴも実際には蛇とは関係なく、果実も食べられますが、確かに食べてみようとは思わないほどの味です。ヤブヘビイチゴは、ほとんど無味という感じですが、ヘビイチゴは不味いということで手も出したくないという感じの味です。しかし栽培用ということでのガーデニングということでは、彩りが赤ということで、
きれいなので緑色の中では映えるのではないかということになります。庭の色彩ポイントということでも人気があるのもうなずけます。分類としては、バラ科キジムシロ属の多年草ということですので、バラの親戚ということになりますが、確かにバラには刺があるということでも、名前からしても毒苺という別名もありますから似ているといえば似ているということになります。
またヤブヘビイチゴの葉もトゲトゲしている感じで周りが覆われていたりします。ヘビイチゴもヤブヘビイチゴも近縁種ですが、非常によく似ていて、素人には区別がつかないという感じです。しかしよくみるとそれぞれ実が違っているということもわかるので慣れると区別ができます。また実の中もヤブヘビイチゴの方が白くて綺麗で、美味しそうな感じもします。
しかし味は殆ど無いので、やはり観賞用として楽しむのが無難です。また食べられるという特徴では面白い特徴もあります。例えは花ですが、クサイチゴ、モミジイチゴ、フユイチゴやシロバナヘビイチゴやエゾヘビイチゴなどは、ヘビイチゴなどのような黄色い花ではなく、白やピンクの花をつけますが、同じ親戚同士なのに、この種類は実が美味しいということで食べても楽しめます。
-

-
ダイコンドラ(ディコンドラ)の育て方
ダイコンドラ(ディコンドラ)は、アオイゴケ(ダイコンドラ・ミクランサ)と言った別名を持ち、ヒルガオ科のダイコンドラ属(ア...
-

-
ナズナの育て方
植物分類としては、アブラナ科のナズナ属となります。高さは20から40センチで、花の時期は2月から6月にかけて。ロゼッタ状...
-

-
スノーフレークの育て方
スノーフレークは、ヨーロッパ中南部が原産です。ハンガリーやオーストリアも生息地になります。スノーフレークは、日本において...
-

-
フラグミペディウムの育て方
フラグミペディウムは常緑性のランの仲間であり、メキシコからペルーやブラジルなどを原産としており、これらの生息地には15種...
-

-
キンカンの育て方
キンカンは、他の柑橘類と同じように、元々の生息地はインドや東南アジアだと考えられています。この地域のものが中国で栽培され...
-

-
ニワトコの仲間の育て方
ニワトコの仲間は、ヨーロッパや中国や朝鮮にもありますが、日本でも、寒い北国を除く、ほとんどを原産地として、分布している、...
-

-
スギ(杉)の育て方
スギが日本に登場したのは200万年前頃で、縄文時代や弥生時代には、すでに日本全国に広く分布していました。日本人が日本人に...
-

-
クルミの育て方
クルミは美味しい半面高カロリーである食材としても知られています。しかし一日の摂取量にさえ注意すれば決して悪いものではなく...
-

-
トマトの栽培における種まきや植え付けの時期及び育て方について
トマトは世界一の需要量を誇る野菜で、日本でも比較的良く食されています。気候的にも栽培に適する事から、家庭菜園レベルであっ...
-

-
ミヤマキンバイの育て方
バラ科のキジムシロ属であり、原産国は日本や韓国、中国の高地になります。日本では、北海道から本州の中部地方にかけて分布して...




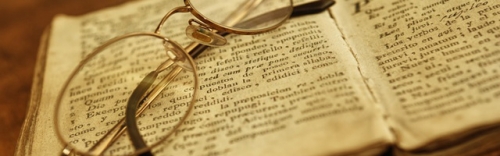





分類としては、バラ科キジムシロ属の多年草ということですので、バラの親戚ということになりますが、確かにバラには刺があるということでも、名前からしても毒苺という別名もありますから似ているといえば似ているということになります。またヤブヘビイチゴの葉もトゲトゲしている感じで周りが覆われていたりします。