シラタマノキの育て方

育てる環境について
シラタマノキを栽培するには環境も大切です。育て方としてはやはり日当たりは重要でしょう。植物によっては日当たりを変えてあげないといけませんので、性質などを知っておく必要があります。シラタマノキの場合は日向が好まれます。ただあまりにも日光があたりすぎるというのも心配です。
地域にもよりますが、比較的暖かい地域の場合は日向ばかりよりも少し日陰なども活用した方がよさそうです。特に夏場は暑すぎるので半日陰などにしてあげるといいでしょう。その他、風通しにも気を配りましょう。風通しが悪いところを避け、いつでも新鮮な空気が流れているようにしてあげます。栽培するなら春頃からがいいでしょう。
この頃に芽をだし花が咲きます。その後夏には白くてかわいらしい実をつけ始めるでしょう。また秋口には緑が生い茂り、冬場は少し休眠にはいります。植物そのものはとても寒さに強いので冬場も枯れる心配などはほとんどないでしょう。もともと高山に生えている植物ですし、耐寒性に優れているためその辺は育てるのは楽なのではないでしょうか。
夏場のぐったりするような季節に白くて美しい実をつけてくれるのはとても癒されるのではないでしょうか。日当たりに少し気を配り、風通しのいい場所を確保してあげるといいでしょう。寒さには強いので冬場はほとんど手がかからないかもしれません。そういう意味ではシラタマノキは比較的育てやすい植物と言えるのではないでしょうか。
種付けや水やり、肥料について
シラタマノキは適度に日光があたり風通しのいい場所を好みます。また水はたっぷりとあげるようにしましょう。特に春先は水やりには気を配るようにしましょう。芽がでてくる時期でもありますし、花を咲かせようとする大事な時です。季節の変わり目などは乾燥しやすいというのもあるのですが、毎日状態を確認し土の表面が乾かないようにしっかりと水を補給してあげます。
だいたい1日か2日に1回程度でも大丈夫ですが、状態をみながら適宜水分を補ってあげるようにしましょう。ただ夏場は特に水をあげすぎると枯らしてしまう事もありますので量にも注意が必要です。確かに暑いのでつい水をあげたくなるのですが、時間帯や量などを考え水やりをしてあげる事が大切です。根腐れを起こさないように気をつけましょう。
春や秋は日当たりのいい場所に置き、夏場は少し陰に置いたり風通しのいい場所を探して置くようにしましょう。また冬場などの休眠時期はあまり水をあげなくてもいいでしょう。もちろん乾いてしまうのはよくありませんので乾かない程度に水分を補給しておきます。その他肥料については春先に補ってあげるといいでしょう。
有機肥料がよさそうです。化学肥料や油かすなどを与えてみましょう。それ以外にも液体肥料を1000から2000倍くらいに薄めて使います。頻度としては1週間から10日に1回程度でいいでしょう。植物の状態をみながらすすめていきますが、夏場は肥料は必要ありませんのであげなくても大丈夫です。
増やし方や害虫について
シラタマノキは寒さに強いので冬場でも比較的育てやすいでしょう。害虫についてはほとんどつくこともありませんので、そういう点でも楽かもしれませんね。害虫がついてしまう植物は何かと手がかかりますし、育てる方もとても気を使います。植物をあまり育てた事がない人にとってはかなり負担に感じるのではないでしょうか。
その点シラタマノキは害虫もほとんどつきませんので安心です。虫が苦手な人にも安心なのではないでしょうか。また増やし方についてですが、この植物の場合は昆虫などに頼らなくてはいけないのでその辺も把握しておくといいでしょう。花が咲いた時点で昆虫に交配を手伝ってもらいますが、その時期に室内に置いておくと交配がうまくいきません。
育てる時はそうした事も含めて置き場所などを考えておく必要があるでしょう。必要な時に必要な環境を整えておく事は大切です。ちょっとした事ですが、花が咲く時期には外に出してあげるようにしましょう。その他、植え替えなどをする際に株を分けてあげる事でも増やす事が可能です。植え替えをするのは、すべての実がなくなった時点でおこなってあげるといいでしょう。
だいたい春頃がよさそうです。またこの他にも挿し木などでも増やす事ができます。時期としては6月頃に行いましょう。増やし方としてはいくつかありますが、手間がかからないのはハチなどの昆虫に任せる方法かもしれませんね。置く場所さえ気をつければいいので始めての人や忙しい人にもやりやすいでしょう。
シラタマノキの歴史
シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白玉の木」という風になりますが、別名シロモノとも呼ばれているようです。逆に赤い場合はアカモノといいますが、シロモノの場合は比較的寒い場所を好むようです。この植物の原産に関しては主にシラタマノキ属のものだと寒い北アメリカあたりになるでしょう。
また日本での生息地としては本州中部よりも北側になります。北海道の亜高山帯から高山帯にかけて生息していますが、その場所でも日当たりのいい場所や尾根にそって見られるようです。またその他にも千島列島やサハリンにも分布しています。シラタマノキという名前は覚えやすいのですが、
寒い地域に多く見られますのであまり見たことがないという人もいるのではないでしょうか。ただこの植物の外観はその名の通り、白い玉のようなものがついていて見ているだけでもとても可愛らしいものとなっています。とても植物とは思えないような外観なのですが、あまり見られないのは少し残念かもしれませんね。
シラタマノキ属になる植物はだいたい200種類ほどありますが、日本でみられるのはそのうちの2種類ほどだと言われています。また草丈は数十センチ程度でとても小さいのですが、寒さにはとても強く、山の尾根などで見つけたなら少し癒しの効果もありそうです。寒い山奥でひそかに生き抜いてきたのかもしれませんね。
シラタマノキの特徴
シラタマノキの特徴としてはやはりその名前にもある白い玉でしょう。玉といっても本当の玉がついているというわけではありませんが、その姿はとても可愛らしく愛らしいです。また白という色はどこにでもあるような感じもしますが、実際に植物がその色をしているととても美しく感じます。
シラタマノキそのものの大きさはとても小さく数十センチしかありません。ほとんど地を這っている様な状態でしょう。そこから少し上に向かって生えてきますので高さもあまりない低草木となります。大きな木々や背の高い植物と比べるととても小さく見えるのではないでしょうか。控え目な印象を受けそうです。白くて可愛らしい実をつけるのですが、
大きさ的にも小さいので見落としてしまうかもしれませんね。またその葉に関してはとてもきれいな緑色をしており光沢もあります。全体の大きさとしては小さい植物ですが、葉っぱの方は意外としっかりとしたつくりになっているようです。葉の葉脈もきれいな模様となってはいっていますので、いろいろな角度から見て興味深いのではないでしょうか。
光沢のある葉も可愛らしい白い実も見ているだけでも十分楽しめそうです。豪華さや華やかさはあまりありませんが、素朴な中にも優しさが感じられる植物です。また時期的にはだいたい5月、6月位に花を咲かせますが、白い玉状になるのは9月頃となりそうです。その他、茎や葉などからはサルチル酸メチルの匂いがするといいます。
-

-
ユキヤナギの育て方
古くから花壇や公園によく植えられているユキヤナギは、関東地方以西の本州や、四国、九州など広範囲に生息しています。生息地は...
-

-
シロヤマブキの育て方
バラ科ヤマブキ属、シロヤマブキ属のような区別がなかった時代には、それが白山吹のことを示すのか、山吹のことを示すのかはわか...
-

-
アイビーゼラニュームの育て方
特徴としては多年草です。基本的には冬にも枯れません。非常に強い花です。真冬においても花を維持することもあります。ですから...
-

-
ワスレナグサの育て方
そのような伝説が生まれることからもわかりますが、原産はヨーロッパで、具体的には北半球の温帯から亜寒帯のユーラシア大陸やア...
-

-
キサントソーマの育て方
この植物の特徴としてはサトイモ科の常緑多年草になります。生息地の熱帯のアメリカにおいては40種類近く分布するとされていま...
-

-
クリンソウの育て方
被子植物で、双子葉植物綱に該当します。サクラソウ目、サクラソウ科、サクラソウ属になるので、かなりサクラソウに近い花といえ...
-

-
エリシマムの育て方
エリシマムはユーラシア大陸からアジア全般に向けた広大な地域に生息している植物であり、比較的温暖な地域に生息する多年草とな...
-

-
ほうれん草の育て方について
ほうれん草は日常の食卓にもよく出てくる食材なので、家庭菜園などで自家製のほうれん草作りを楽しんでいる人も少なくありません...
-

-
プリムラ・マラコイデスの育て方
プリムラは、原産は中国雲南省です。花形からもどこか中国から渡ってきた雰囲気をもっています。和名は化粧桜、一般的 にはサク...
-

-
緑のカーテンを育てよう
ツルを伸ばし、何かに巻き付く性質を持つ植物で作る自然のカーテンのことを「緑のカーテン」と言います。直射日光を遮ることがで...




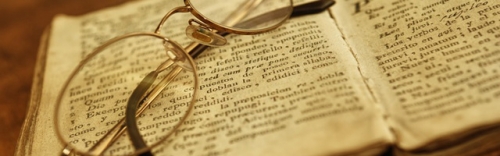





シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白玉の木」という風になりますが、別名シロモノとも呼ばれているようです。逆に赤い場合はアカモノといいますが、シロモノの場合は比較的寒い場所を好むようです。この植物の原産に関しては主にシラタマノキ属のものだと寒い北アメリカあたりになるでしょう。