ダイズの育て方

育てる環境について
そんなダイズの育て方にはどのような方法があるのでしょうか。確かに日本人にとって身近な食材ではありますが、自分で栽培しようとはあまり思わない食材でもあります。その理由は、大規模な農場で大量生産しているイメージが強いからです。しかし、自分で栽培することもできます。重要なのは、自分の住んでいる地域の気候にあった種類の種を選ぶことです。
前途のように、その種類がたくさんある為、適した種を選ぶのも難しいと感じるかもしれません。基本的にはやせ地でも育つので、安心してしまいがちですが、湿地が苦手だったり、水はけの悪い土壌が苦手だったりと、色々な条件があるので注意が必要です。特に生育期の前半には、湿害に弱いとされていて、この問題が起こった場合には、
発芽が揃わず、周囲の雑草を育ててしまうという結果にもなりかねません。もちろん、自宅で小規模に栽培する場合には、それほど気にすることではありません。育て方の条件について調べてみると、どこかの学会の研究資料を見つけることもでき、そこには色々な条件が記載されていますが、
あくまでもそれは大規模な範囲で育てようという人向けです。ただ、自分で育てる場合でも、間引きを定期的に行ったりしないと、なかなか上手く育ってくれません。また、葉が生い茂ってくると風で飛ばされそうになるので、棒を立てることによって支えた方が良いなど、個人で育てる場合に特価した小さな注意点は出てきます。
種付けや水やり、肥料について
大豆の種付けや水やりについて、自宅で栽培を行う場合には、素人でも簡単にできる要素が揃っています。まず、種をまく時に注意すべきは、季節だけです。具体的には、5月から6月が適した時期と言われています。これは、大豆の成長に適した気温が25度から30度、発芽の場合には15度と言われる為、比較的暖かい時期にまくことが好ましいということです。
大豆は高温に強い特徴を持っていて、38度までならば耐えられると言われています。ですから、季節を考えて種をまくだけということになります。次に面倒だと思ってしまうのが水やりですが、これもあまり気を遣う必要はありません。土が乾いていると思ったら、それを湿らせる程度で良いと言われています。
水を頻繁にやらないと枯れてしまうのではないかと心配になってしまいますが、湿害に弱いことからもその必要がないことがわかります。その証拠に、大規模な農場で栽培する場合の注意点として、農場の排水性を確保することは絶対と言われています。つまり、排水をすることによって、水に濡らしすぎない状況を作ることが大切ということです。
これを家庭で栽培する場合に置き換えてみると、水は土を湿らせる程度で、むしろ水を上げすぎるのは良くないということが言えます。また、肥料についても、あまり気にする必要がありません。家庭で作る場合には、山土だけで肥料は必要ないと言われるくらいです。極端な酸性土壌はいけませんが、最近はホームセンターなどで野菜用の土を購入することができるので、それを使うだけで充分です。
増やし方や害虫について
種付けや水やりについての注意点に、専門的なことがないことを考えると、ダイズを栽培するのはとても簡単と思ってしまいますが、色々と注意することがあるのも事実です。その一つとして、害虫などの天敵の存在があります。種付けをした時から多くの外的に狙われる存在と言われているくらいです。
これは、人間の需要が高いのと同様に、外敵にとっても魅力的な栄養素となっているのでしょう。具体的には、カラスや鳩などの鳥類、また、場所によっては猿などの動物も天敵と言える存在になります。また、害虫として具体的な例を出すならば、ハスモンヨトウの幼虫など、幼虫類による食害が挙げられます。
場合によっては、せっかく栽培しているダイズが全滅させられるケースもあるので、注意が必要です。効率的な増やし方をしようと思っても、これらの外敵により被害を受けていたのでは、せっかくの労力も水の泡となってしまいます。効率的な増やし方は、環境によって異なりますが、個人で育てるのであれば畑が一番です。
ただ、作り方について慣れていないのであれば、最初はプランターで少しだけ育ててみる方が良いのではないでしょうか。その方が、注意力が散漫にならず、じっくりとダイズが育つその過程を見ることができます。それを自分の中での成功体験として、
小規模の畑で栽培してみるのが、効率的な増やし方と言えるのではないでしょうか。いずれにしても、育ててみることで色々とわかることもありますし、何しろ収穫することができれば、それは健康にプラスになる栄養素満点の食材ですから、挑戦してみて損はないと言えます。
ダイズの歴史
ダイズの歴史を調べてみると、はっきりとした起源がわからず、いくつかの説によって現代に伝えられていることがわかります。つまり、それほど大昔からある食物で、人間にとって身近で大切なものと言える植物です。一般的に、その原産は中国とされ紀元前2000年以前に栽培されていたという話です。
現代でも良質なタンパク質として注目されていますが、それは昔も同じで、生息地は広範囲に渡り、大規模な栽培が行われていたようです。それだけ需要があったということなのでしょう。そんなダイズが日本に伝わってきたのは、弥生時代と言われています。とは言え、その頃には保存方法や加工方法がわからなかったので、それほど活用されていたわけではありません。
ダイズと言えばお醤油や味噌に加工されますが、これらの方法が伝えられたのが奈良時代、そして、日本で広く栽培が始まったのは鎌倉時代以降と言われています。お醤油や味噌のことを考えると、日本独特のものと考えてしまいがちですが、原産は日本以外の国であり、日本に伝わってきてから、独自の発達を遂げたということです。
大昔から少しずつ進化しながら、日本の食文化を支えてきたわけですが、長い年月を通して人の近くにあり続けたことを思えば、現代でも親しまれている理由がわかる気がします。その代表格と言えば、おせち料理に入っている黒豆や、節分に使われるものもそうです。歴史をもった伝統文化の行事に使われていることがわかります。それほど、深い関わりを持っているもので、今後どのようになるのか気になるところでもあります。
ダイズの特徴
ダイズの特徴としては、やはり栄養豊富なことが挙げられます。特に重要なのはタンパク質です。タンパク質というのは、肉や魚など脂質の多い食材からしか摂ることができないと思われがちです。つまり、たくさん食べ過ぎてしまうと、太ってしまう可能性があります。現代で成人病や生活習慣病などが問題になっていることからも、それは明らかです。
しかし、日本では古くから必須アミノ酸がバランスよく含まれた食物として親しまれており、肥満の改善効果など、健康にプラスとなる作用が確認されています。コレステロールを含んでいないのに、食物繊維や亜鉛、鉄など健康に欠かせない栄養素が入っていることが魅力のひとつです。また、近年問題になっている一つの症状としてガンが挙げられますが、
がん予防に効果が期待できる食材として、最上位に位置する8種類の食材の中の一つに入っています。これだけ技術が発達した現代において、大昔から存在したダイズが、未だに人間の健康の為に欠かせない食材として考えられているというのは不思議なことです。もちろん、その種類は一つではなく、国に地域によって適したものがあります。
日本だけでも多様な品種があり、品種については農林水産省が発表している品種の辞典を確認するのが理解しやすいです。そうは言っても、100種類近くあるので、なかなか全てを把握することはできません。大昔から存在し続け、なおかつ今でも進化を続けていると言ってもいいのかもしれません。
-

-
サルナシの育て方
見た目が小さなキウイフルーツの様にも見える”サルナシ”。原産国は中国になり、日本でも山間部などを生息地とし自生している植...
-

-
アッツザクラの育て方
アッツザクラはアッツという名前はつきますが、アッツ島にあるものではなく、原産や生息地は南アフリカです。ではなぜアッツザク...
-

-
ヘメロカリスの育て方
ヘメロカリスの生息地はアジア地域で、原種となっているものは日本にもあります。ニッコウキスゲやノカンゾウ、ヤブカンゾウなど...
-

-
フッキソウの育て方
フッキソウは日本原産のツゲ科の植物です。北海道から九州まで日本のどこでも見つけることができます。フッキソウは半低木で、そ...
-

-
ツバキの育て方
ツバキ属は科の1属で、生息地は日本や中華人民共和国、東南アジアからヒマラヤにかけてです。日本原産の花で日本国内においては...
-

-
小松菜の育て方
小松菜の原産地は、南ヨーロッパ地中海沿岸と言われています。中国などを経て江戸時代の頃から小松川周辺から栽培が始まり、以降...
-

-
レシュノルティアの育て方
レシュノルティアは世界中で見ることが出来ますが、生息地であるオーストラリアが原産国です。この植物は世界中に26種類あると...
-

-
ダイズの育て方
ダイズの歴史を調べてみると、はっきりとした起源がわからず、いくつかの説によって現代に伝えられていることがわかります。つま...
-

-
カツラの育て方
カツラは日本特産の植物で大昔である太古第3紀の頃から存在します。日本とアメリカに多く繁茂していましたが、次第にアメリカに...
-

-
マンションやアパートでの植物栽培
マンションやアパートなどに住んでいる場合も植物を栽培することはできますが、その際はベランダも小さかったりと小規模ながらも...




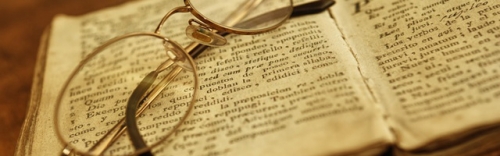





ダイズの歴史を調べてみると、はっきりとした起源がわからず、いくつかの説によって現代に伝えられていることがわかります。つまり、それほど大昔からある食物で、人間にとって身近で大切なものと言える植物です。一般的に、その原産は中国とされ紀元前2000年以前に栽培されていたという話です。