ディケロステンマの育て方

育てる環境について
育て方としては暖地のところでは野放しにしておいても栽培できます。日照環境としては秋口の10月中旬から翌年の6月上旬の生育期は戸外の直射日光下で育ち、冬場の越冬中の時期には霜除けする必要がありますが休眠期間は日光に当てなくてもよいとされています。日当たりの良い所を好むので、そのようなところで育てます。
寒さに対してはあまり強いほうではありませんが、暖地においては路地植えで冬を越します。鉢植で育てる場合は霜の当たらない、かつ日当たりのよい軒下などに置いておくと良いとされています。植え付けの時期は気温の下がる10月から11月中頃に行うのがよいとされています。
鉢に植える場合は5号ぐらいの大きさの鉢に3つぐらいの球根を目安にして約5センチぐらいの深さに植え付けます。鉢植えの土は赤玉土5に対して腐葉土3、パーライト2などの割合で混ぜて水はけの良い土に植付けを行います。庭植えの場合には苦土石灰、元肥に牛糞などを、水はけが悪いようであれば腐葉土を混ぜ込んで、
約5センチぐらいの間隔で深さ5センチ間隔ぐらいに植え付けを行います。花茎切りに関しては、花が咲き終わったら即花茎を切り取っておきます。6月頃になって葉が枯れたら、球根を掘り上げて涼しい日陰で夏を越させて秋には植え付けを行います。鉢植えは葉が枯れたら、鉢植えのまま雨の当たらない日陰で水を切って休眠させてもよいとされています。
花茎切りに関しては、花が咲き終わったら即花茎を切り取っておきます。6月頃になって葉が枯れたら、球根を掘り上げて涼しい日陰で夏を越させて秋には植え付けを行います。鉢植えは葉が枯れたら、鉢植えのまま雨の当たらない日陰で水を切って休眠させても良いとされています。増やし方としては分球を行って増やす事ができます。
種付けや水やり、肥料について
生育期は、土の表面が乾けば与えるようにします。休眠期は、断水状態に置くのが良いとされています。秋の元肥の他に2月から5月にかけて、固形肥料の置き肥、又は7日から10日に一度の液肥を与えると良いとされています。水やりでは鉢植えの場合は鉢土の表面が乾くごとに与えるようにします。
庭に植える場合は普通は必要ないものですが、長らくの間に雨が降らないようであれば与えるようにします。6月頃になって葉が枯れて休眠状態になったら水やりは止めます。肥料に関しては鉢植えの場合植え付けの時に緩効性の化成肥料や固形油粕などを置いてゆき、3月頃に1回だけ追加施肥すれば良いとされています。
花壇で育てる場合は堆肥などの元肥を入れて植え付け、3月頃に化成肥料などを追加施肥するぐらいで良いとされています。その他の場合は肥料の使い方を参考に行うことになります。水やりでは鉢植えの場合は鉢土の表面が乾くごとに与えるようにします。庭に植える場合は普通は必要ないものですが、長らくの間に雨が降らないようであれば与えるようにします。
6月頃になって葉が枯れて休眠状態になったら水やりは止めます。肥料に関しては鉢植えの場合植え付けの時に緩効性の化成肥料や固形油粕などを置いてゆき、3月頃に1回だけ追加施肥すれば良いとされています。花壇で育てる場合は堆肥などの元肥を入れて植え付け、3月頃に化成肥料などを追加施肥するぐらいで良いとされています。その他の場合は肥料の使い方に従うことになります。
増やし方や害虫について
水はけのよい用土で植えつけ、日当たりのよい場所で育てます。乾かし気味に管理し、鉢植えは、葉が黄変し始めたら掘り上げて乾燥貯蔵するか、鉢ごと乾燥させます。D・コンゲスタム、D・ムルティフロラムは、水はけのよい場所を選べば庭植えにできます。そして増やし方としては分球を行って増やす事ができます。普通は適度に灌水を行うと根がついて活着するとされています。
たいていの球根は1作で堀上げると自然に分球して増えて来るので根っこからを分離して適切な時期に植えると良いとされています。ただ自然に分球することが少ない場合には、それを切断したりあるいは鱗片をかきとったりして人手を加えて分球することもあります。根茎は芽の数が増えて大きくなりますが、新規に球根を別には作らないので簡単には分けることは出来ません。
球根の数が笛はしますが付け根ですべてくっつくものもあり、自然に離れることがないものもあります。こういうときはナイフのようなもので切断するものですが、分球するタイミングについては植えつける直前で少なくとも1ヶ所は芽が出る部分を付けておく着ることがコツとなっています。
分球とは球根を分離して増やす方法をいいもしも芽が出る部分を付けずに切り取ってしまった場合はそれは単に根の塊となってしまい植え付けてしまっても芽が出ることはありません。これは無駄な行為に終わります。よって芽が出る部分をちゃんと付けて切断することが大切です。
植物の種類によって芽が出る位置は異なっています。分球がスムーズに行かないという場合もあります。そのような場合には球根に子株ができやすいように手を加えたり球根を強引に分ける場合もあります。これらを行う場合は慎重に行わないと球根そのものを損ねてしまうことがあるので注意する必要があります。害虫については特に気を使うところはないようです。
ディケロステンマの歴史
ディケロステンマは原産が北アメリカ西海岸のワシントン州西部からカリフォルニア州中部に分布しています。別名をブローディア・イダマイアとも呼ばれ、多年草で明るい丘陵地で草地などのところに生えるモノです。学名ではDichelostemmacongestum、英名はOokow,Forktoothookowと呼ばれています。ディケロステンマは2つの王冠を意味し、外花被片につく仮雄しべが2つに裂けて王冠のようにみえることによるとされています。
図鑑ではディケロステンマをヒガンバナ科と掲載されている例も見られますが、アメリカやカナダではヒガンバナ科植物が見られない地帯であり、ヒガンバナ科という分類は適切ではないとされています。ディケロステンマは地植えの場合は草姿中性のアリウム中性品種で他にトリテレイア、ブローディア、オトメユリ、スカシユリ、シラー・カンパニュラータ、シラー・ペルビアナなどが知られています。
ちなみにカマッシア、ワトソニア、球根アイリス、テッポウユリなどは草姿高性のアリウム高性品種であり、初夏咲きオキザリス、ブリメウラ、チリアヤメ、ムスカリ晩生品種などは草姿低性品種に当たります。市場に出回っているのは、カランコエに似たベル形の花を咲かせるD・イダマイアとその園芸品種があります。
この2つは耐寒性がやや弱く室内栽培向きとなっています。強健で戸外で栽培できるD・コンゲスタムあるいはD・ムルティフロラム等もあります。ピンク色の鼻を咲かせるものはピンクダイアモンド、赤色の鼻を咲かせるのはイダマーヤ、藤色の花を咲かせるものはコンゲスタムと呼ばれています。
ディケロステンマの特徴
ディケロステンマの特徴としては、半耐寒性から耐寒性の球根植物で花の色は赤、ピンク、紫などがよく知られています。ユリ科ネギ亜科に属し分類としては球根植物で花期は4月から6月で生息地としては明るい丘陵の草地などに生え、高さは30センチから100センチぐらいになります。よく出回っているのはカランコエに似た鐘状の花を咲かせるD。
イダマイアとその園芸品種です。どちらかというと室内栽培に適しています。茎は強く真直ぐに伸び、少しの線形をした葉が根生します。4月から6月頃に茎の先の球状花序に青紫色の筒状の花を咲かせます。花冠は6つに分かれ、雄蕊は3個あってそれぞれに白いフォーク状の鱗片がつきます。日当たりの良い所を好み、それらの場所で育てます。
寒さに対してはあまり強いほうではありませんが、暖地においては路地植えで冬を越します。鉢植で育てる場合は霜の当たらない、かつ日当たりのよい軒下などに置いておくと良いとされています。植え付けの時期は気温の下がる10月から11月中頃に行うのがよいとされています。
鉢に植える場合は5号ぐらいの大きさの鉢に3つぐらいの球根を目安にして約5センチぐらいの深さに植え付けます。鉢植えの土は赤玉土5に対して腐葉土3、パーライト2などの割合で混ぜて水はけの良い土に植付けを行います。庭植えの場合には苦土石灰、元肥に牛糞などを、水はけが悪いようであれば腐葉土を混ぜ込んで、約15センチぐらいの間隔で深さ5センチ間隔ぐらいに植え付けを行います。
-

-
シモツケの育て方
シモツケ/学名:Spiraea japonica/和名:シモツケ、下野/バラ科・シモツケ属、シモツケ属は約70種が北半球...
-

-
ヒコウキソウの育て方
ヒコウキソウ(飛行機草)はマメ科、ホオズキバ属(クリスティア属)の植物で、東南アジア原産です。別名コウモリホオズキハギと...
-

-
チグリジア(ティグリディア)の育て方
チグリジアは別名ティグリディアとも呼ばれるユリに似た植物ですが実際にはアヤメ科の仲間になっています。チグジリアの仲間アヤ...
-

-
宿根アスターの育て方
アスターは、キク科の中でも約500種類の品種を有する大きな属です。宿根アスター属は、中国北部の冷涼な乾燥地帯を生息地とす...
-

-
チングルマの育て方
チングルマは高山に咲く高山植物の一つです。白い花弁の中心には、黄色い色をした無数の雌蕊や雄蕊を持つ花で、登山をしていると...
-

-
オキナグサの育て方
オキナグサはキンポウゲ科に属する多年草です。日本での歴史は、万葉集の随筆から江戸時代中期後期にかけて書かれた書物の中にも...
-

-
ディサの育て方
ディサは、ラン科ディサ属、学名はDisaです。南部アフリカを中心とした地域が原産で、そのエリアを生息地としている地生ラン...
-

-
ニチニチソウの育て方
ニチニチソウに日本に渡来したのは1780年頃のことだといわれています。渡来してからの歴史が浅いので日本の文献などに出てく...
-

-
ミソハギの育て方
種類としては、バラ亜綱、フトモモ目、ミソハギ科となります。水生植物、山野草として分類されるようになっています。花は多年草...
-

-
ナツハゼの育て方
ナツハゼはジャパニーズブルーベリーや山の黒真珠と呼ばれており、原産や生息地は東アジアです。日本はもちろん朝鮮半島や中国な...




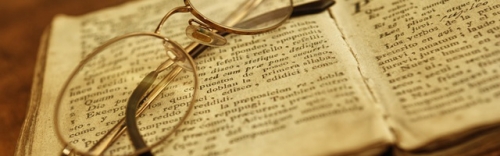





ディケロステンマは原産が北アメリカ西海岸のワシントン州西部からカリフォルニア州中部に分布しています。別名をブローディア・イダマイアとも呼ばれ、多年草で明るい丘陵地で草地などのところに生えるモノです。学名ではDichelostemmacongestum、英名はOokow,Forktoothookowと呼ばれています。