シャコバサボテンの育て方

育てる環境について
サボテンという名前が付いていることから「暑い環境が良いのではないか」というように思われることもありますが、シャコバサボテンは高地に生息する植物が親となっているため、通常の砂漠に生えるサボテンのような環境に置いてしまうとすぐに枯死してしまいますから注意が必要です。
そのため育てる環境として最も適しているのは、15~25℃程度の風通しが良い直射日光の当たらない場所ということになります。春から夏にかけては屋外に置いて育てても問題ありませんが、それでも夏場の気温が30℃以上になってくるのであれば、様子を見つつ涼しい場所に移した方が良いこともあります。
また一般的な植物において風通しの良い場所と言うと屋外であればどこでも良いというように考えられることもありますが、シャコバサボテンの場合は植物の下部にも風が当たった方がよく育つため、鉢の下にレンガを置くなどの工夫を行い、下部にもしっかり風が当たるようにした方が良いでしょう。
鉢を木やベランダなどにつるしておくと、外見的にも美しいうえ風通しも良くなるのでベストです。ただシャコバサボテンは落蕾を起こしやすい性質がありますから、蕾がまだ未成熟の段階で木やベランダに吊るしておくと、風に吹かれた際に蕾が堕ちてしまうこともありますので、ケースバイケースで判断をするようにしましょう。
またシャコバサボテンは短日植物、つまり日照時間が少なくなると花を咲かせる植物なのですが、蛍光灯などの光も日照時間に含みますから、夜間でも電気の明かりがあるようなリビングなどに置いておくと上手く開花することが出来なくなります。そのため夜間は光が当たらない場所に置くように注意しましょう。
種付けや水やり、肥料について
基本的にシャコバサボテンは挿し芽で増えるため、種を植えることはありません。差し芽の適切な時期としては4~7月ごろ、木質化していない茎節を3節ほど切り取って鉢に差すことが必要です。用土としては水はけと通気性の良さが非常に重要となります。
特に通気性が悪くなると上手く生育せず、開花期になっても花をつけないということがあり得ますから、バーミキュライトやパーライト、ピートモスなどを配合した土を使用するのがベストでしょう。水やりは4~9月の生育期には用土の表面が乾いた段階でたっぷりと与え、
10~11月の蕾が大きくなる時期は用土の表面が乾いた1~2日後にたっぷりと与えるようにします。ただ開花期である12月から3月までの間はそこまで多くの水は必要としませんので、やや乾燥気味で育てるようにすると良いでしょう。5℃以下の環境で越冬させる場合は、
サボテン自体が休眠期に入り生育が鈍りますから、水を与える必要はほぼありません。
そのため状態を確認しつつ判断するようにし、月に1回、もしくは2回程度の水やりを行うようにしてください。肥料に関しては春から梅雨ごろまでの季節には与える必要がありますが、
花芽が見え始める9月上旬までに肥料が切れている状態を作ることが必要です。そのため梅雨が終わるころには肥料を与えないようにした方が良いでしょう。肥料のバランスとしては固形肥料を月に一回ほど、液体肥料を2週間に1回ほどのペースがベストです。
増やし方や害虫について
増やし方は基本的に差し芽になります。4~7月ごろに差し芽を行うことで効率的に増やすことができ、また差し芽を行った後もそのまま生育することになりますから、同心円状に芽を挿していくと丸くまとまった形のシャコバサボテンを作ることができるようになります。
花を人工交配することによって種を作り、それから新しい品種を作るということも出来ないわけではありませんが種ができるまでには半年以上かかり、また花を咲かせるまでには5~6年ほどがかかりますから、あまり一般的な方法であるとはいえません。
家庭で増やすとすればやはり差し芽で行うようにするのが無難でしょう。病気・害虫に関してはそこまで心配する必要はないものの、4~10月ごろ、シャコバサボテンに新芽がつくころには害虫に関してやや注意が必要です。
発生する害虫としてはナメクジやヨトウムシ、ケムシといったような虫になります。放置していると新芽がたべられてしまうこともありますから、被害が確認された場合には早期に対応をすることが必要です。ナメクジ・ヨトウムシは夜行性であるために夜間に状態を確認し、
葉についていたのであれば補殺することがベストです。ナメクジに関してはビールの飲み残しに駆除剤を入れた空き缶などを植物の近くに置いておくとナメクジを誘引して駆除することができますので、ナメクジに触りたくない、
なるべく見たくないという場合にはそうした手段を取るのも有効です。ケムシは基本的に時間を問わずに活動している可能性がありますから、食害を見つけた時点で周囲を確認し、もしそれで見つからなかった場合には薬剤を使って防除すると良いでしょう。
シャコバサボテンの歴史
現在観葉植物として流通しているシャコバサボテンはブラジルのリオデジャネイロを原産地とする観葉植物であり、標高1000~1800メートルほどの高地を生息地とするカニバサボテンと、そこよりもやや低い地域を生息地とする野生種のシャコバサボテンが自然交配した結果生まれた植物であるとされています。
そのため植物に関する情報をまとめた本などにはシャコバサボテンをカニバサボテンの交配品として紹介していることもあります。ただ現在観葉植物として流通しているシャコバサボテンについては、やはり人為的に交配が繰り返されて観葉植物としての美しさを作ってきたわけですから、
カニバサボテンと野生種のシャコバサボテンとは別の種類の植物であるというように考えた方が良いでしょう。シャコバサボテンの異名は「クリスマスカクタス」、つまりクリスマスのサボテンということになりますが、これはシャコバサボテンの花が12月ごろに開花することからつけられたものです。
現在では日本国内においてもさほど珍しい植物では無いと言えますが、原産地がブラジル地域であるため、当然ながら日本国内で自生していたわけではありません。日本国内に初めて持ち込まれたのは明治初期であるとされており、
この頃から日本国内では観葉植物として栽培されるようになりました。その後日本国内においても交配が進められて完成した園芸品種もあったのですが、戦争などの歴史の中で多くが失われており、現在では記録が残るのみとなってしまっています。
シャコバサボテンの特徴
シャコバサボテンの特徴はその多肉質な葉にあります。これはシャコバサボテンが分類されるサボテン科の植物の特徴でもありますが、シャコバサボテンの場合は茎のような葉、茎節が繋がるように伸びていくという特徴があります。
茎節は外見的には茎に近いものがありますが本来の役割としては葉となっていますから、茎では無いということには注意が必要です。さて、この点は一般的にサボテンという言葉から連想される様子、球型サボテンや柱型サボテンとはやや異なる特徴的な部分であると言えます。
加えてサボテンの一般的なイメージとしてはトゲが植物全体を覆っているというものがありますが、この品種はそうしたイメージとは異なり、トゲを生やすことがない品種となっています。こうした特徴は生息地による特徴であり、また観葉植物としてより適した形にするために、
改良が加えられてきた結果であるとも言えます。次いで植物の特徴として言えるのが、その様々な花の色です。園芸品種として改良が加えられた結果ではありますが、品種によって赤色やピンク、桃色、朱色といったような赤みがかかった様々な色を持つ花を咲かせることができます。
また低温化で開花させることで花の色が変わるような品種もあり、非常に奥が深いということも特徴だと言えるでしょう。植物としてはややデリケートなところがあり育て方もやや難しく、初心者がすぐに完璧に育てられるようなものではないというのは確かですが、継続していくつも育てている人がいるほど、魅力を持った植物でもあるのです。
-

-
ポテンティラの育て方
この花の科名としてはバラ科になります。キジムシロ属、ポテンティラ属ともされています。あまり高くまで成長することはなく、低...
-

-
アエオニウムの育て方
アエオニウムはアフリカ大陸の北西の北アフリカに位置するカナリー諸島原産の植物です。生息地は亜熱帯を中心に多くく見られる植...
-

-
緑のカーテンに最適な朝顔の育て方
ここ数年毎年猛暑が続き、今や日本は熱帯よりも熱いと言われています。コンクリートやアスファルトに覆われた環境では、思うよう...
-

-
リューココリネの育て方
分類としてはヒガンバナ科になります。ユリ科で分類されることもあります。ユリのようにしっとりとしているようにも見えます。園...
-

-
ファイウスの育て方
花においては、ラン目、ラン科、カンゼキラン属とされています。園芸上はランになり、多年草として育てることができます。花の高...
-

-
ナイトフロックスの育て方
ナイトフロックス(nightphlox)とは属名に「ザルジアンスキア」という名前を持ったゴマノハグサ科の植物です。原産国...
-

-
大きなサツマイモを育て上げる
サツマイモは特別な病害虫もなく農園での育て方としては手が掛からないし、家族でいもほりとして楽しむことできる作物です。
-

-
プルメリアの育て方
プルメリアの原産地は熱帯アメリカで、生息地も熱帯がほとんどですので、日本では基本的に自生していませんし、植物園などに訪れ...
-

-
カトレア・コクシネアの育て方
カトレア・コクシネアは、ブラジルの中でも、標高1,000mから1,500mという高地の中の雲霧林に自生している樹木に着生...
-

-
アルストロメリアの育て方
アルストロメリアは、南米原産の単子葉植物の属の一つで、アルストロメリア属、または別名をユリズイセン属とします。




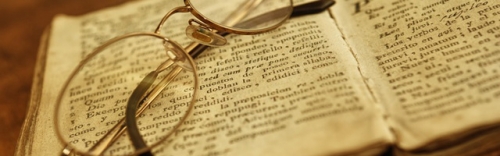





現在観葉植物として流通しているシャコバサボテンはブラジルのリオデジャネイロを原産地とする観葉植物であり、標高1000~1800メートルほどの高地を生息地とするカニバサボテンと、そこよりもやや低い地域を生息地とする野生種のシャコバサボテンが自然交配した結果生まれた植物であるとされています。