金のなる木の育て方

金のなる木の育てる環境について
金のなる木の育て方は、まず日当たりの良い場所を好むため、できるだけ日に当ててやることです。とはいえ、ある程度の耐陰性があり、室内に一年中置いてあっても育たないことはありません。しかし日光が足りないと茎が細長くなり、葉と葉の間隔が開いてしまうことがあります。
強い株にしたいなら、たっぷりと日に当てることが大切です。暑い地方の植物ですが、真夏の極端な暑さには弱いので、そのときは日陰を作ったほうが良いでしょう。特に斑入りの品種は、直射日光にさらすと葉が日焼けすることがあるため、風通しのいい半日陰に置いてやります。
乾燥には強く、少しぐらい水やりを忘れても枯れません。逆に湿度が高すぎると、根腐れを起こす場合があります。一年中乾燥気味の環境で育てるのが基本です。アフリカ原産の植物としては、寒さにも強いほうです。だいたい0度ぐらいまでは耐えることができ、
日本でも南の地方なら軒先で冬を越すことが可能です。しかし霜が降りたり0度以下になったりすると凍傷を起こすので、そのときは室内に取り込んだほうが安全でしょう。暖房は必要ありませんが、最低室温が3度を下回らない、日当たりの良い場所に置くのが適当です。
全般に言って、育てる環境にはそれほど難しい条件はなく、放っておいてもよく育つので、園芸の初心者にも管理しやすい植物です。日常的な手入れもほとんど必要としませんが、日照時間と冬の厳しい寒さにだけは注意してください。
金のなる木の種付けや水やり、肥料について
金のなる木は年間を通じて、水やりを控えめにするのが育てるコツです。そうしないと根が腐ってしまいます。まず植える土は水はけが良いものにします。多肉植物用の培養土があれば、そのまま利用することもできますし、川砂を少し混ぜても構いません。
半分ぐらいを川砂にして、残りは赤玉土と腐葉土を混ぜるのも良いでしょう。春から秋は金のなる木の生育期です。この期間は、鉢の土が完全に乾燥してから水を与えます。冬は休眠期なので、水やり回数はもっと少なくします。乾燥してから5~6日に1回以下が標準です。
真夏にまったく水を与えないと、分厚い葉が薄くシワだらけになりますが、そのほうが冬になってから花が咲きやすくなるとも言われています。このときは雨にも濡らさないようにします。5年ぐらい経った大株で、自宅で花を咲かせたい方は参考にしてください。
逆に園芸店で販売されている株は、花を咲かせるために過剰な水と肥料を与えている場合があります。このような株は根が少なかったり根腐れしていたりする可能性があるため、購入の際には注意が必要です。肥料も多すぎるのは良くありません。
春から秋にかけて、固形肥料か緩効性の液体肥料を与えますが、2か月に1回程度で足ります。花を咲かせたいなら、真夏以降はまったく肥料を与えないという方法もあります。この場合の施肥は春だけになります。金のなる木は過酷な環境のほうが、本来の生命力を発揮するとも言えます。
金のなる木の増やし方や害虫について
金のなる木は生命力が強く、さし木や葉ざしで簡単に増やすことができます。そのため、増やすには一般的にさし木が行なわれます。さし木は5月から9月ごろまでにします。まず枝の先端を10cmほど切り取り、下のほうの葉を取って挿し穂とします。
挿した部分が腐らないよう、しばらく日陰で切り口を乾かします。そして水やりの項で述べた用土に挿します。ここでも水をやりすぎると根が腐るので、水やりは控えめにします。水はけの良い川砂を使っても良いでしょう。そのほうが根は伸びやすいかもしれません。
葉ざしは1枚の葉を取って、やはり切り口を少し乾かし、その部分を下にして土に挿します。あまり深く挿すと芽が出ないので、倒れない程度に浅く挿してください。1か月ほどで小さな根と芽が出たら、しばらく育ててから植え替えます。
株が大きくなりすぎたり、根詰まりしたりした場合には、鉢に入りきらなくなるので、植え替えを行ないます。だいたい2~3年に一度が標準的です。時期は春なら4~6月、秋なら9~10月頃が適しています。真夏や真冬は時期的に好ましくありません。また剪定するなら夏以降は避けましょう。
なお植え替えなどを行なうと、一時的に花は咲きにくくなります。金のなる木には特にかかりやすい病気や、つきやすい害虫はありません。そういう意味でも育てやすいと言えます。よく日光に当てることと適度に乾燥させることを守れば、ほとんど手のかからない観葉植物です。
金のなる木の歴史
金のなる木は和名をフチベニベンケイ(縁紅弁慶)といいますが、一般にはカネノナルキ、カゲツ(花月)、成金草、クラッスラなどと呼ばれます。ベンケイソウ科クラッスラ属の植物で、花言葉は一攫千金です。英語でもdollar plantと呼ばれていますが、これは葉の形がお金に似ているためと言われています。
正確には木ではなく多年草の一種ですが、3メートルぐらいまで成長します。原産は南アフリカです。丈夫で暑さ寒さに強く、乾燥にも耐えるので、全世界に生息地が広がっています。日本に入ってきたのは昭和の初めで、比較的新しい園芸植物です。
新芽を5円硬貨の穴に通し、そのまま成長させると、枝の間にお金がなったように見えることから、このような方法で栽培されたものが縁起物として流行しました。金のなる木の名前が定着した理由です。ただし流通名としては花月のほうが一般的です。
最近では普通の種類のほか、葉に斑が入った品種も流通するようになりました。代表的なのは黄色い斑入りの「黄金花月」ですが、「花月錦」「落日の雁」といった品種も販売されています。また通常の品種は栽培方法にもよりますが、家庭で花を咲かせるのは簡単ではありません。
特に草丈が低いうちは花芽がつかないのですが、近年では小さくても花が咲きやすい「桜花月」という品種も見られます。金のなる木は観葉植物としてだけでなく、花を楽しむ園芸植物としても、安定した人気を保っています。
金のなる木の特徴
金のなる木は分厚い葉を持つ多肉植物で、葉や茎の中にたっぷりと水を蓄えているため、乾燥に強いのが特徴です。茎は木質化し、硬い枝のように見えるため、「木」と呼ばれていますが、本来は草に分類されます。楕円形の葉は3~4cmほどの長さで、
ワックスのような光沢のある緑色をしており、周辺が赤く縁取られています。冬には全体が赤く染まります。ただし巻いた葉や細い葉を持つ品種もあります。棒状の葉をした品種はウチュウノキと名づけられています。ベンケイソウ科の植物は、多肉質の葉に水分を貯められるという点が共通しており、
南アフリカなどの乾燥地域に多く見られます。これらは一般に丈夫で手がかからず、また交配が簡単で品種改良を行いやすいという特徴があります。さらに品種ごとに異なる魅力があり、園芸植物として多くの人に愛されています。
金のなる木もその一種で、多くのバリエーションが存在します。草丈の低い「ミニ花月」や葉の小さい「姫花月」などもあります。園芸店では一年中出回っていますが、花が咲くのは冬季です。11月下旬ごろから花芽がつきはじめ、遅ければ3月頃まで開花します。
かわいらしい5弁の花は、白や淡いピンク色をしており、茎の先にまとまって咲きます。普通は大きく育たないと花が咲かないとされており、育て方によっては10年たっても咲かない場合もあります。手軽に花を楽しめる改良品種は、別物と考えたほうが良いかもしれません。
多肉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:クラッスラの育て方
タイトル:セダムの育て方
-

-
エゴポディウムの育て方
セリ科・エゴポディウム属の耐寒性多年草です。和名はイワミツバと呼ばれ、春先の葉の柔らかい部分は食用にもなります。エゴポデ...
-

-
小松菜の栽培に挑戦してみよう。
今回は、小松菜の育て方について説明していきます。プラナ科である小松菜は、土壌を選ばず寒さや暑さにも強いので、とても作りや...
-

-
ファセリアの育て方
ファセリアはハゼリソウ科の植物で双子葉植物として分類されていて280種ほどが世界中で栽培されていて、南北アメリカ大陸を生...
-

-
モミジの育て方
モミジは日本人に古くから愛されてきた植物です。色づいたこの植物を見に行くことを紅葉狩りといい、秋の風物詩として古くからた...
-

-
ライスフラワーの育て方
ライスフラワーの特徴として、種類としてはキク科、ヘリクリサム属になります。常緑低木です。草丈としては30センチぐらいから...
-

-
玉レタスの種まき時期と育て方
レタスは一番馴染みのあるのが玉レタスで、夏に涼しい気候の高原でよく育つ高原野菜といわれています。レタスの栽培方法は、種を...
-

-
フクジュソウの育て方
雪に覆われたり、冬の間は殺風景な庭に、どんな花よりも早く顔を出して春の訪れを知らせてくれる、それがフクジュソウです。フク...
-

-
シロバナタンポポの育て方
シロバナタンポポの特徴は、花の色が白色であることです。舌状花の数は他のタンポポと比べると少なく、1つの頭花に100個程度...
-

-
ホタルブクロの育て方
ホタルブクロの特徴として、まずはキキョウ目、キキョウ科であることです。花の色としては真っ白のものがよく知られていますが、...
-

-
エリンジウムの育て方
エリンジウムはセリ科のヒゴタイサイコ属の植物です。同じヒゴタイサイコ属の植物にはE.maritimum やオオバコエンド...




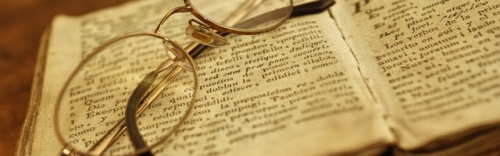





金のなる木は和名をフチベニベンケイ(縁紅弁慶)といいますが、一般にはカネノナルキ、カゲツ(花月)、成金草、クラッスラなどと呼ばれます。ベンケイソウ科クラッスラ属の植物で、花言葉は一攫千金です。