フィロデンドロンの育て方

フィロデンドロンの育てる環境について
フィロデンドロンは育て方が簡単で丈夫な植物です。日光を好みますが、直射日光に当たると葉焼けを起こしてしまうこともありますので、夏場など日差しが強い時期はレースカーテン越しの柔らかな日差しが射すところに置いてあげましょう。
耐陰性があるので多少日陰気味でも育てることは可能ですが、葉の色が悪くなったり、間延びしてしまったりするのであまりお勧めはしません。特にレモン・ライムなどの葉の色が薄めのタイプのものは出来るだけ日光に当てるように心がけましょう。
蔓性のタイプのものは、こまめに蔓の手入れをしてあげることによって理想的な樹形に整えることが出来ます。伸びすぎた蔓は切り落としてあげましょう。切り落とした部分からはまた新しいワキ芽が出てきますので、その性質を利用して美しい仕立てにしていくことが出来ます。
自立性のものは伸びすぎた場合には切り戻しを行います。5月〜7月頃が適期です。丈夫な植物ですので思い切って切り戻しても再生します。鉢の底から根が伸びてきている場合は根詰まりを起こしている可能性があるので、植え替えをしてあげる必要があります。
また2年以上植え替えをしていない場合も新しい用土に植え替えてあげます。植え替えの用土は赤玉土と腐葉土を6:4の割合で混ぜたものを使用します。ホームセンターや園芸店などに販売されている観葉植物用の用土でも大丈夫です。
蔓性のものなどはその際にしっかりと支柱を立ててあげましょう。冬場は室内にて管理し、最低でも5度以上になるところで育ててあげます。
種付けや水やり、肥料について
フィロデンドロンは乾燥にも強い植物ですので、頻繁に水をあげなくても大丈夫です。用土が乾いて白くなってきたらたっぷりと与えるようにしましょう。真夏の時期には生育期に入りますので、水をたくさん必要とします。乾かないようにこの時期だけは土が乾く前に水を与えるようにします。
また、霧吹きなどを使って葉水を与えるとよりお勧めです。特に、冷暖房器具などで乾燥しがちな場所に置いている場合はマメに行うようにします。ハダニやカイガラムシといった害虫の予防にもなりますので、定期的に葉の表裏に水を吹きかけてあげましょう。
気温が下がってくると吸い上げる力が弱ってきますので、水やりの頻度を徐々に減らしていきます。特に冬場は乾かし気味にして管理するようにします。水のやり過ぎは根腐れの原因にもなりますので、用土が乾いてから更に2〜3日経過した後に水をあげるくらいで大丈夫です。
春から秋にかけての生育期には2ヶ月に一回程度の割合で、肥料を与えてあげましょう。そうすることによって、より鮮やかな葉色になり、丈夫な株に育ちます。緩効性のある化成肥料や油粕などを置き肥してあげると大丈夫です。
あまり大きな株にしたくない場合は肥料は控えめにしておいた方がよいでしょう。日照不足などによって葉色が悪くなったり、株が弱ってきたと感じた場合は鉢を日当たりの良い場所に移してあげます。即効性のある液体肥料などを与えて栄養をプラスしてあげましょう。
フィロデンドロンの増やし方や害虫について
主な害虫はハダニ、カイガラムシです。これらは乾燥していると発生しやすくなるので、マメに葉水を与えることによってある程度予防することも可能です。もしも発生してしまった場合は、歯ブラシやウェットティッシュなどを使って早めに駆除します。
さらに殺ダニ剤などを併せて散布してあげましょう。フィロデンドロンの栽培は挿し木や株分けによって行います。挿し木によって増やす場合は、適期は5月〜8月頃の生育期です。ツル科は2〜4節の蔓を切り取り、水の蒸発を防ぐために下の方の葉は落としておきます。
暫く水につけて十分に吸わせた後、バーミキュライト6、ピートモス4、もしくは等量を混ぜた用土に軽く挿しておきます。切り口に発根促進剤を塗っておくとより発根しやすくなります。しっかりと根を出すまでは明るい日陰において、土が乾かないように注意しながら管理します。
フィロデンドロンは子株が出てきやすいので、株分けによって増やすこともお勧めです。適期は5月〜6月頃です。土の植え替えをする際などに一緒に行ってあげるとよいでしょう。親株を丁寧に土から掘り出し、よく切れる刃物などで子株を切り離してあげます。
切り口には水分が多いため、そのままではその部分から腐ってしまうことがあります。その為、用土に挿す前に風通しの良い日陰などで十分に切り口を乾燥させておきましょう。切り口が完全に乾いてから水はけの良い用土に挿してあげると、しばらくしたら根が生えてきます。
フィロデンドロンの歴史
フィロデンドロンとは、サトイモ科フィロデンドロン属の常緑多年草です。「樹木を愛する」という意味のギリシャ語から名付けられたと言われています。原産はブラジル、パラグアイで、現在も熱帯や亜熱帯地域を生息地としています。
フィロデンドロン属の植物は数百種類にものぼり、葉の形や、大きさ、色なども実に豊富で様々なタイプのものが出回っています。フィロデンドロンは古くから観葉植物として親しまれてきており、多くの場合蔓性で、大木や外壁などに寄り添って成長するためお家のシンボルグリーンとして人気がありました。
中にはフィロデンドロン・セロームのように、しっかりとした茎を持ち、自立して育つタイプのものもあります。こういったタイプのものは主に鉢植えにして鑑賞するのに人気があります。フィロデンドロンが日本に入ってきた経緯は品種によって異なります。
ビロードカズラとも言われるアンドレアヌムは明治時代に日本に入ってきたと言われています。また、大きな葉に筋入りが特徴的なオルナツムなどは戦後に入ってきたと言われております。基本的に原種の特徴は葉が濃い緑色をしているところがあります。
しかし後の品種改良によって、レモン・ライムのように黄色っぽい葉をつけるものや、斑入りの模様のもの、スジ模様のものなど、鑑賞向きのものも出てきました。いずれの種類も育てやすく初心者にもおすすめの植物です。空気浄化の作用があるともされ、最近では更に人気を博しています。
フィロデンドロンの特徴
フィロデンドロンの特徴はなんといってもその種類の豊富さです。形態や葉の形、色や大きさも様々ですので、置きたい場所のイメージに合わせて色々なタイプの中から選べる楽しみがあります。大きく分けると蔓性のものと自立性のものの2種類があります。
蔓性のものは支柱などを立ててシンボルツリーのようにするのが人気で、玄関先や店先に飾られているのを見かけます。吊り鉢に植えて上部から蔓が垂れるようにするのも趣があっていいのではないでしょうか。また、他の植物と寄せ植えをする際などにも素敵なアクセントとなってくれるのでお勧めです。
自立性のものは茎が太めでしっかりとした厚みのある葉を持つものが多いです。葉の形がエキゾチックで存在感があるので、メインの鉢植えとして鑑賞したいときにはこちらのタイプもお勧めです。思い切って大きく育ててみるのもいいですし、コンパクトに仕立ててミニ観葉植物として育ててみるのもいいものです。
あまり大きくしたくない場合はクッカバラなどの品種が大きくなりにくいのでお勧めです。これといった難しい手入れも不必要ですし、半日陰でも育ち、寒さにも強いのでガーデニング初心者にも育てやすいと言えるでしょう。
最近ではフィロデンドロンには空気浄化の効果があるということで、室内浄化の目的として購入される方も増えてきました。鮮やかなグリーンで、観賞用としても楽しめ、なおかつ空気も綺麗にしてくれるというエコさも人気の理由の一つです。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ウラシマソウの育て方
タイトル:シェフレラの育て方
タイトル:オリヅルランの育て方
タイトル:アオキの育て方
-

-
カスミソウの育て方
カスミソウの原産地は地中海沿岸から中央アジア、シベリアなどで、生息地は夏季冷涼なところです。カスミソウの属名ギプソフィラ...
-

-
リトープスの育て方
この植物についてはハナミズナ科とされています。同じような種類としてメセンがあり、メセンの仲間としても知られています。園芸...
-

-
カッコウアザミ(アゲラータム)の育て方
アゲラータムは別名カッコウアザミという和名を持っています。アザミに花はとても似ていて、その関係からカッコウアザミという名...
-

-
ゴメザの育て方
ブラジル原産のラン科の植物です。属名がなんども変えられた歴史を持っています。最初はSigmatostalix(シグマトス...
-

-
メランポジウムの育て方
メランポジウムはメキシコや中央アメリカを原産としていて、その用途は鉢植えや寄せ植え、切り花などに用いられています。なお、...
-

-
ミヤマホタルカズラの育て方
ミヤマホタルカズラはヨーロッパの南西部、フランス西部からスペイン、ポルトガルなどを生息地とする常緑低木です。もともと日本...
-

-
緑のカーテンを育てよう
ツルを伸ばし、何かに巻き付く性質を持つ植物で作る自然のカーテンのことを「緑のカーテン」と言います。直射日光を遮ることがで...
-

-
ミヤマクロユリの育て方
このミヤマクロユリは多年草になり、直立した茎の上部に細長い楕円形の葉を2~3段に輪生させており、茎の先に2~3輪の花を下...
-

-
イチゴの育て方
イチゴは比較的古くから人間に食されていた果物です。その歴史は石器時代にさかのぼります。農耕技術や養殖などを行う前から野生...
-

-
フウセンカズラの育て方
フウセンカズラは、熱帯地方原産の植物です。アメリカ南部、アフリカ、インド、東南アジアなどを生息地とし、湿気の多い雑木林や...




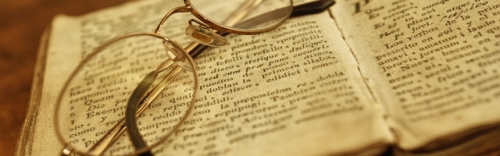





フィロデンドロンとは、サトイモ科フィロデンドロン属の常緑多年草です。「樹木を愛する」という意味のギリシャ語から名付けられたと言われています。原産はブラジル、パラグアイで、現在も熱帯や亜熱帯地域を生息地としています。