バラ(シュラブ・ローズ)の育て方

育てる環境について
生命力が高い花なので、ほとんどの土壌に対応することが出来ます。その中でも水はけが良く、水持ちが良い土が向いています。生育もとても早く剪定や切花に使われることも多いので、養分の消費が早いので養分をたっぷり含んでいる土を用意します。
黒玉土や赤玉土などに培養土を混ぜて、養分が多い土を作ります。水がしっかり染みて、なおかつ水はけを良くするためにも土の粒と粒の間に適度なすき間を作ることが大切です。ビートモスなどを混ぜて、すき間を作ります。ペーハーは弱酸性を好むので、
苦土石灰で弱酸性になるように調整をします。日本の土の多くは弱酸性なので、神経質になる必要はないです。さらに育てるのに良いとされている温度は18度から20度前後で、30度近くなると生育に影響を与えてしまいます。逆に温度が低く、3度以下になってしまうと葉を落として休眠になります。
日本には四季があるので、生育に向いている時期と休眠時期を見極めて植えるようにします。太陽の光が好きなので、1日に5時間以上は太陽の光が当たる場所に植えます。日当たりが悪いとなかなか成長することが出来なかったり、花が咲かないことがあるので注意が必要です。
西日が強い午後の光よりも午前中の柔らかい光を好むので、午前中に良く日光が当たる場所を選びます。風当りが良いことも大切な条件なので、風の通りが良い場所に植えます。風当りが良いと葉から出てくる水分が蒸発されて、その水分を補給するために根元から水分と養分を吸い込むので丈夫になります。
種付けや水やり、肥料について
鉢に種付けや植え付ける場合は鉢の底に石を敷いて、土を入れておきます。土には培養土を混ぜて、根を広げるようにして植え込みを行います。鉢のギリギリまで土を入れるようにして、植えつけたら鉢の下から水が染み出るくらいに水をたっぷり与えます。
庭や畑に植え付けるときには、幅や深さ共に50センチくらいの穴を掘っておきます。10センチくらい埋め戻して、その上に肥料を混ぜておいた土を入れます。さらに10センチほどの土を入れて、根を広げて植え付けます。さらにたっぷりの水を与えて、定着するようにします。
育て方は鉢植えの場合は水を与えると土に含まれている栄養分を一緒に吸い込むので、表面が乾いたタイミングで水やりをするようにします。こまめに水やりをすれば根が養分を吸収しやすくなり、土の中に新しい空気を送り込むことが出来ます。
鉢植えから水がしみ出すまで、しっかり与えるようにします。庭や畑の場合は種付けや植え付けから1週間以降は、ほとんど水やりは必要なくなります。土の中に根が張って茎が太くなるので、頻繁に水を与える必要がなくなるのです。逆に水を与え過ぎると根が弱くなってしまい、病気になってしまいます。
長く乾燥が続いたときなどに、たっぷり水を与えるだけです。肥料は庭や畑の場合は冬の植え替え時期の数週間前に与えて、耕すように混ぜておきます。何年も植え替えていないものは強い酸性に傾きやすいので、秋ごろに苦土石灰を入れておきます。鉢植えのときには、月に1度のペースで肥料を与えるようにします。
増やし方や害虫について
種を蒔いて増やす方法は、実生法です。種を蒔いて増やす方法は一般的ではないのですが、交配して増やすときなどに使われています。果実が赤くなってきた秋ごろに採種をして、冷蔵庫などで乾燥させないように容器に入れて春になったら種を蒔きます。
果実を割って、種だけを取り出して水に浸しておきます。水の中に浮いている種は発芽しないので、事前に取り除いておきます。10センチくらいの箱や鉢に土を入れておいて、5センチ間隔で種を蒔きます。蒔いた上に軽く土をかけて、水やりをします。
温度が下がらないように、新聞紙などで保温しておきます。表面が乾いて来たら水やりをして、数か月で発芽させます。増やし方の中で一般的なやり方は、接ぎ木です。発芽して1年経ったものと、1年目の枝の直径が7ミリのものを使います。台木は休眠の時期に入っていないもの、枝は休眠しているものを選びます。
台木をきれいに洗って枯れていないか、病気になっていないかを確認します。地上部を切り取って、端から3ミリの部分を2センチほどカットします。枝は斜めに切り落として、とがった部分の皮を2センチ程度削ぎ取ります。削ぎ取った部分を台木の切込み部分に差し込んで、接ぎ木用のテープで固定します。
水で湿らせたミズゴケを根に巻き付けて、ビニールで密閉して寒くならない場所に吊るしておきます。乾燥しないように管理して、いきなり寒い場所に移さないようにします。病気や害虫には強いので安心ですが、被害にあってしまったらその部分をカットするようにします。病気の場合には、症状に合った薬品を蒔くなどして対応します。
バラ(シュラブ・ローズ)の歴史
バラの歴史はとても古く、恐竜が世界を支配していたころから始まります。さらに初めに文字として誕生したのは古代メソポタミア文明の時代に書かれた「ギルガメッシュ叙事詩」です。この主人公は紀元前2600年ごろに伝わっていたので、歴史の長さを感じることが出来ます。
紀元前8世紀に誕生したギリシャ神話では女神ヴィーナスの愛と美の象徴として、バラが書かれています。有名な絵画であるヴィーナスの誕生にも、貝の中に立っているヴィーナスの絵にもバラが書かれています。歴史上の人物の中でも絶世の美女として知られているクレオパトラは、
来客をバラの香りでもてなしていたという記録もあります。クレオパトラ自身もバラのエキスを入れたお風呂に入っていたり、バラを食べていたという歴史もあります。さらに香料の植物や薬用の植物として利用され始めて、やがて観賞用としても色々な国で栽培されるようになります。
園芸植物として発展して、中国やヨーロッパ、日本などに伝わったことには品種改良など様々な発展を遂げるようになっていきます。外国が原産や生息地で外国から伝えられたと思いがちなバラですが、日本でも古くから自生していたという記録があります。
万葉集の歌にもバラは登場し、かなり昔から栽培していたということを確認することが出来ます。日本ではイバラも含めて「そうび」と呼ばれていて、品種改良などが何度も繰り返されてシュラブ・ローズなどが誕生したのです。
バラ(シュラブ・ローズ)の特徴
バラは樹形から、ブッシュローズやシュラブ・ローズ、クライミングローズの三種類に分けられます。シュラブ・ローズはフロリバンダとハイブリッドティーのように、枝が自立しているものを指します。ローズの多くの品種は、シュラブ・ローズです。
本来は樹形を指して使われますが、ローズの世界ではどの系統にも含めにくい品種について使われています。野ばらのようにドーム型のものから、横に大きく広がるタイプのものまで種類は様々です。シュラブ・ローズ型のバラの中には、オールドローズとイングリッシュローズがあります。
オールドローズは野生種を品種改良したもので、自然に花をつける性質を持っています。丈夫で育てやすいバラで、初心者にも向いている品種です。イングリッシュローズは自然な美しさが特徴的で、オールドローズの樹形や花型を持っています。
四季咲きの性質を持っていて、モダンローズを品質改良したものとして知られています。どちらの品種とも、自然に育てることが出来ます。シュラブ・ローズ型のはブッシュ型と開帳型、直立型やアーチ型があります。ブッシュ型はイングリッシュローズに多い形で、高さは90センチから2メートルになることがあります。
小枝が多く、密集しながら成長する品種です。開帳型はシュラブ・ローズの代表的な形で、枝が大きく横に広がって優雅な形を作ります。直立型には背が低いものと高いものがあり、枝は横に広がらないで上に伸びていきます。アーチ型はその名の通り、枝の先端がアーチを描くように成長します。
-

-
モチノキの育て方
モチノキは樹皮から鳥や昆虫を捕まえるのに使う粘着性のあるトリモチを作ることができるため、この名前がついたといわれています...
-

-
ナシの育て方
ナシの歴史は、中国の西部から南西部を中心として、世界中に広がりました。原産地となる中国から、東に伝わって品種改良が進んだ...
-

-
ツルウメモドキの育て方
人間や動物には性別があります。見た目ではよく見分けすることができない魚や虫にもあります。植物にまであると知り、意外だと驚...
-

-
キャッサバ(マニホット)の育て方
キャッサバ(マニホット)はブラジル南部からパラグアイの辺りを原産地とする植物であり、茎の根元に付く芋は良質な食料となるた...
-

-
アセビの育て方
アセビは日本や中国が原産で、古くから日本人の生活になじんでいた植物です。その証拠に枕草子や古今集のなかでその名がみられる...
-

-
はじめての家庭菜園で役立つ基本的な野菜の育て方
家庭菜園をやっている人が増えています。また、これからはじめてみたいと思っている人も多いと思います。しかし実際は、なにから...
-

-
ミカニアの育て方
こちらについては比較的身近な花と同じ種類になっています。キク科でミカニア属と呼ばれる属名になります。育てられるときの園芸...
-

-
エラチオール・ベゴニアの育て方
エラチオール・ベゴニアは、日本でもポピュラーな園芸植物のひとつで、鉢植えにして室内で楽しむ植物としても高い人気を誇ります...
-

-
熱帯スイレンの育て方
スイレンは18世紀以前から多くの人に愛されてきました。古代エジプトにおいては、太陽の象徴とされ大事にされていましたし、仏...
-

-
オクラの栽培オクラの育て方オクラの種まきについて
オクラはプランターなどでも手軽に育てることが出来るということもあり、とても人気があります。オクラのの栽培やオクラの育て方...




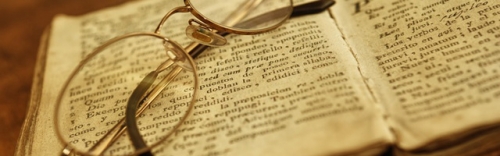





バラの歴史はとても古く、恐竜が世界を支配していたころから始まります。さらに初めに文字として誕生したのは古代メソポタミア文明の時代に書かれた「ギルガメッシュ叙事詩」です。