ヒトリシズカの育て方

ヒトリシズカの育てる環境について
ヒトリシズカは自然界では樹木の下などに自生しています。育て方は少し手間がかかりますが、耐寒性がかなり強いのが良い点です。可能であれば鉢植えにして、芽が出る時から開花後あたりまでは日がよく当たる場所に置いておき、開花後は強い日射しがあたらないように明るい日陰で育てるのがポイントです。
日射しの強さは葉を傷ませやすく、生育を弱らせてしまうからです。もし日陰で良い場所がなければ、60%から70%ほど光を遮光させた場所に置いておくのも良いです。冬はさすがに凍らせてしまうと枯れてしまうこともありますが、そうでなければ棚下などに置いて冬越しさせることが可能です。
地植えもすることができますが、大きめの鉢に入れてまとめて植えてしまうと見た目も良いです。地植えにするのであればいつもある程度の湿り気はある落葉広葉樹の下の辺りが良いでしょう。種まきや植え替えするのは基本的に11月から3月辺りに行ないます。
土は小粒の赤玉土を4、軽石砂を4、腐葉土を2の割合で混ぜ合わせたものを利用するのがオススメです。水はけが良く、有機質なものが向いています。鉢植えに植えていると根茎が育ってくると窮屈になる場合があります。
晩秋の11月頃に植え替えを行い、芽を傷つけないようにします。また根を乾燥させるのは生育させる上ではあまり良くないことなので植え替える場合は掘りあげたら新しい大きめの鉢にすぐに植えてしまうようにするのがポイントです。
種付けや水やり、肥料について
ヒトリシズカは乾燥を嫌うので、秋までの生育期は土が乾燥していたらたっぷりと与えるようにします。真夏は土が乾燥しやすいので水切れさせないようにしなくてはいけませんし、鉢の周りにも水まきをしておくと良いです。冬は地上部分は枯れてしまうものの、
地下部分の根が乾燥しないように時々水を与えるようにしましょう。肥料は年に2回ほど、開花後の5月上旬、涼しくなってくる9月中旬以降です。骨粉と固形の油粕を1回ずつ適量与えます。また10日に1度ほど液体肥料も与えるようにするといいです。
植え替えをする時には元肥としてチッ素やリン酸、カリウムが同じくらい入っている緩効性化成肥料か配合肥料をひとつまみほど施しておきましょう。注意したほうがいいのは肥料を与え過ぎてしまわないようにすることです。肥料を与え過ぎてしまうと花穂の数が多過ぎて見た目があまり良くないからです。
開花後に花茎をそのままにしておくとそこに果実ができます。果実は他の植物とは違って熟しても茶色くなることはなく緑色のままです。熟したことに気づかないとそのままこぼれ種となって地面に落ちてしまっているので、確実に種を採取したいのであれば種付けされたものに、
不織布の袋をかけておくのが良いでしょう。こうすれば種がこぼれてしまうこともなく、袋の中に落ちているので後で採取しやすいです。ちなみに種まきをしてから花が開花するような株にまで育つには2年ほど必要になります。
増やし方や害虫について
害虫はあまりつくことがありませんが、ヨトウムシには注意をしたほうが良いです。ヨトウムシはその名の通り日中は土の中に隠れていて、夜になると這い出てきては株の葉を食害してしまいます。ヨトウムシは食欲が旺盛なのでこれを放置しておくとあっという間に葉が食べ尽くされてしまいます。
ヨトウムシの駆除には夜に株の様子を時々でいいので見ておくことです。ヨトウムシがいるかどうかは株の周りにフンがあったり、土の一部がもこもことしていることでわかります。夜にもし葉を食べているのを見かけたらすぐに取り除くようにします。
ヨトウムシの卵は葉の裏に産み付けられ、孵化したばかりの頃は群棲して表皮以外の葉肉部分を食害してしまいます。その後少し大きくなったら分散して土の中などに隠れて夜に出てくるという感じです。ですから駆除するのであれば孵化直後がベストです。
夜間活動するようになった幼虫退治には誘殺剤を株元にまいておくようにするといいです。もしヒトリシズカを増やしたい場合は種まきでもできますが、株分けをして増やすこともできます。植え替えをする時に芽が3つから5つほどついているものを選んで根茎部分から分けます。
根茎がまだ小さいものは株分けしないで大きくなるまで待つほうがいいです。種まきをする場合はできるだけ種を採取したらすぐに種をまくほうが良いです。来年までもたせるよりもその場でまくほうが発芽率が高いのです。こういう方法をとりまきといいます。
ヒトリシズカの歴史
ヒトリシズカは原産地や生息地が日本を含め、中国や朝鮮半島です。栽培するのは5段階中でいえば4で、かなり難しいといえるでしょう。初心者の方には少し大変かもしれません。草丈は20cmから30cmほどしかなく、センリョウ科チャラン属です。
ヒトリシズカという名前の由来は昔源義経の愛妾であった静御前が吉野山で舞を舞った際の美しさにちなんでいるといわれています。ヒトリとついているのは花穂が1本だからです。属名にはクロランサスは緑色の花という意味があり、ジャポニカスはそのまま日本産のという意味があります。
つまりクロランサス・ジャポニカスで日本産の緑色の花ということになります。同じような名前の植物にフタリシズカというものがあります。こちらもセンリョウ科のものではありますが、こちらもやはり静御前が由来となったといわれており、フタリシズカのほうが花が遅れて咲くという特徴があります。
ヒトリシズカはヨシノシズカという別名がありますが、こちらは吉野山で舞をする静御前のことそのものをあらわした名前です。北海道から九州まで見かけることができます。生息しているのは山地の林の下の辺りや土手などです。
興味があれば探しに出かけても面白いでしょう。ちなみにヒトリシズカは薬草としても昔から用いられていて、陰干しして乾燥させたものを煎じて服用することによって血行を良くして利尿作用もあるので、体調改善にはとても良いとされています。
ヒトリシズカの特徴
根茎が地中を横に伸び、そこからたくさんの芽を出してそれぞれが茎を伸ばし、直立します。花は葉が完全に開ききる前に咲きますが、この花は茎の先端につき、白いブラシのような形をしています。白い糸のようなものが雄しべになります。この花の特徴は花びらや萼がないということです。
このように花びらや萼がない花は裸花と呼ばれます。葉は4枚あり、茎を囲むようにして同じ高さに生えてきます。濃い緑色の光沢がある葉は若葉です。春に芽を出してそこから生育していき、4月から5月頃に花が咲いて、晩秋頃になると地上に出ている部分は枯れてしまい、冬は地下茎の状態で越します。
ヒトリシズカは一般的には白い花を咲かせ、茎は赤紫色になっているのですが、花が紅色っぽくなるものや茎の色素が抜けて緑色になっている青軸と呼ばれる状態になっているものもあります。この青軸というのが見た目も清楚な感じがするということで、とても人気があります。
アイヌでは昔からイネハムと呼ばれ、お茶にして飲まれていました。また中国では古き時代から神経痛やリウマチ、痛風に効果的だといわれていて、アイヌと同じようにお茶として飲まれています。また山菜として食べられることもあり、この場合は新芽や若葉を塩を入れた熱湯で軽くゆで、それをさらしてから辛子じょうゆで食べます。
ヒトリシズカの仲間にはキビノヒトリシズカもあります。このキビノヒトリシズカは四国、九州、朝鮮半島、中国に分布している種で、ヒトリシズカよりも花穂が一回りほど大きく、葉が完全に開いてから花を咲かせます。キビノヒトリシズカのキビというのは吉備のことで、岡山県に自生していることからつけられました。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ヒメリュウキンカの育て方
-

-
ナツズイセンの育て方
このナツズイセンですが、面白いのは植物の系統ではヒガンバナ科のヒガンバナ属ということで、彼岸花の親戚でもあります。また別...
-

-
小松菜の育て方
小松菜の原産地は、南ヨーロッパ地中海沿岸と言われています。中国などを経て江戸時代の頃から小松川周辺から栽培が始まり、以降...
-

-
ウメ(花ウメ)の育て方
ウメの系統をたどっていくと、サクラやモモと同じように、もともとトルコやイランなど、中東の地域を原産とする植物だと考えられ...
-

-
ミニバラの育て方
バラと人間との関わりは古く、およそ7000年前のエジプトの古墳にバラが埋葬されたとも言われています。またメソポタミア文系...
-

-
金時草の育て方
金時草は学名Gynura bicolorと呼ばれています。金時草の名前の由来は、葉の裏面の色が金時芋のように美しい赤紫色...
-

-
ペンツィアの育て方
特徴としては、種類はキク科のペンツィア属になります。1年草として知られています。花が咲いたあとに種をつけて枯れますから次...
-

-
玉レタスの種まき時期と育て方
レタスは一番馴染みのあるのが玉レタスで、夏に涼しい気候の高原でよく育つ高原野菜といわれています。レタスの栽培方法は、種を...
-

-
ジュエル・オーキッドの育て方
種類としてはラン科になります。通常園芸分類においてはランとして分類することが多いですが、葉っぱを中心に楽しむものに関して...
-

-
イングリッシュ ラベンダーの育て方
イングリッシュ ラベンダーは、シソ科のラベンダー属、半耐寒性の小低木の植物です。ハーブの女王としてゆるぎない地位を確立し...
-

-
カンパニュラ・メディウムの育て方
カンパニュラ・メディウムは南ヨーロッパを原産とする花で、日本には明治の初めに入ってきたものとされています。基本的な育て方...




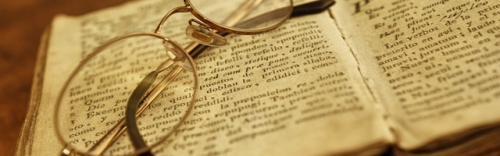





ヒトリシズカは原産地や生息地が日本を含め、中国や朝鮮半島です。栽培するのは5段階中でいえば4で、かなり難しいといえるでしょう。初心者の方には少し大変かもしれません。草丈は20cmから30cmほどしかなく、センリョウ科チャラン属です。