アンスリウムの育て方

水やりの仕方
ある程度の乾燥には耐えられますが、土が過湿さている状態は耐えられません。土の表面が乾くのを待ってから、鉢から水が漏れるまでたっぷりと与えます。ここで注意しなければならないのが、受皿に残った水は捨てることです。そのままにしておくと、土が乾かず過湿の状態になってしまいます。
アンスリウムは、部屋(空気中)の湿度が高いのを好むので、たまに霧吹きで葉や花に水を与えましょう。入浴後の浴室は湿度が高いので、そこで霧吹きで水をあげていいかもしれません。冬は、生育期に比べて水やりの回数を少なくします。気温が低いと水を要求しないんです。気温がある程度保てるなら、霧吹きで葉や花に水をやり続けてもいいでしょう。
置き場所と肥料やりの仕方
直射日光を避けて、カーテン越しの光が当たる室内で育てるのがアンスリウムの育て方です。暗い場所は花が咲きにくくなるので注意してください。また、熱帯地方原産で暖かい国で栽培されることもあり寒さには弱いです。冬は室内のなるべく暖かい場所に移動させてください。窓際は冷気が入るので避けましょう。
乾燥も好まない植物なので、乾燥気味の場合は加湿器等で室内の湿度を保ってあげましょう。冬に花を咲かせたい場合は、室内温度を17度以上の暖かい状態を作ってあげてください。肥料は、生長期の5月~10月に追肥として肥料を与えます。肥料は、花が咲く植物用の水溶性の肥料を与えてください。
寒い時期に肥料を与えても意味がないですし、また、与えすぎても根腐れの原因になりますので、控えましょう。1ヶ月に1回のペースで追肥してあげると、花付きも葉の色味もよくなる効果的な育て方です。
株分けや仕立て直しのやり方
アンスリウムの根が鉢一杯になり根詰まりすると、生育が悪くなり花付きも悪くなります。また、長い間栽培されていると、下の葉が落ちたり、茎が立ち上がって不恰好になります。そんなときは、株分けや仕立て直しをして、長くアンスリウムを栽培できるようにします。
株分け・仕立て直しをする時期は、気温が20度以上になる5月~7月が最適な時期です。まずは、株分けの仕方からです。綺麗に鉢から取り出し、土を取り除きます。根が長すぎて鉢に納まらないようなら、適度な長さに切って下さい。
一鉢に2・3株が適度な量です。用土は、観葉植物用の土や草花用の土の中でも、水はけ・水もちに適している「アンスリウム」に向いている土の物を選びましょう。次に、仕立て直しの仕方です。地上部に出ていた根を多く切りだし、鉢に植え替えます。この時、葉の付け根を埋め込まないように注意してください。
元の鉢に居た子株などは、そのままにして栽培していきます。その子株から、新しく育っていきますので、同じように育ててください。仕立て直す時に一緒に、花色が褪せてきた花を、根元から切り取りましょう。いつまでも咲かせておくと、次の花が咲きにくくなります。
仕立て直し後の水やりは、土の表面がしっかりと乾くまでは与えません。しっかりと乾いたら、水を与えます。葉には毎日水を与え、湿度を高めてあげると元気な新芽がでてきます。元気な新芽が出てきたら、仕立て直しが成功です。アンスリウムを長く育てるには、株分け・仕立て直しをする育て方です。
アンスリウムの種付け
受粉の方法としては、虫たちにお願いするか、人工的に受粉する方法があります。人工的に受粉させるには、やわらかい筆やめんぼうなどで受粉させます。無事にアンスリウムが受粉すると、めしべが膨らみはじめます。種によっては、赤くなったり、白くなったりします。
肉穂花序の所に、小さくてまるっとした実がつきます。触って落ちれば完熟している証拠です。落ちた実を、塗れたキッチンペーパー・コットン・水ゴケなどに蒔いておくと発芽しやすいです。発芽したら、植え付けます。種付け時期や植え付け時期は、5月~7月頃が最適です。
アンスリウムは暖かいのを好む植物なので、せっかく発芽したのに種付け時期を誤ると枯れてしまいます。アンスリウムが花を付けるには、種付けしてから3~4年かかります。発芽し始めた新芽にアブラムシが付きやすいので、薬剤等で駆除しましょう。ナメクジも発生するんですが、葉とかも食べちゃうので見つけ次第駆除してください。
アンスリウムの歴史
アンスリウムは、熱帯アメリカ・西インド諸島原産で、日本には明治の中頃に渡来してきた歴史ある植物です。木の枝などに着生する常緑の非耐寒性多年草で、地生種と養生種を合わせると約900種以上あります。
このアンスリウムは、サトイモ科特有の仏炎苞(*)と呼ばれる苞で、突き出した尻尾のような部分に集まりくっ付いている肉穂花序が本当の花ですが、小さくて目立ちません。
(*)仏炎苞・・・棒状の花を包み込み苞が、まるで仏像の背景にある炎をかたどる飾りに似ていることから、この名が付いています。
語源は、ギリシャ語の「anthosaura(花)+oura(尾)」尾っぽのような花。と言う意味です。別名、アンスリューム、アンスリウム、アンドレアナム、オオベニウチア(大紅団扇)と言います。欧米では、フラミンゴの立ち姿に似ている為「フラミンゴフラワー」という呼称もあります。
アンスリウムの特徴
アンスリウムの特徴は、ハート型の光沢のある花(苞)です。実際の花は、突き出した尻尾のような部分に集まりくっ付いている肉穂花序が花ですが、小さくて目立ちません。花持ちが1ヶ月以上あるので、切花としても人気です。もちろん、鉢植えでも花持ちがとてもよいです。
花の色は、白やピンク、紫やクリーム色のもあります。アンスリウムは、根がいっぱい回り根詰まりすると、生育が悪くなり花付や冬枯れを起こす原因になります。2年に1度は、植え替えをするといいでしょう。植え替え時期は、生息地が高温多湿の熱帯観葉植物なので6月~7月中旬がいいです。
また、株が増えてしまっても、生育や花付きが悪くなりますので、株分けをします。土を綺麗に取り除き、根をきちんと分けて、一鉢に2・3株が綺麗に見えるでしょう。アンスリウムは種類が多いが、育て方は基本的に一緒です。直射日光を避け、カーテン越しの光が当たる程度の室内で育ててください。
暗い場所では、花が咲きにくくなるので、注意してください。また、熱帯地方原産の植物ですので、寒さには弱いです。室内温度は最低でも10度以上は生育には必要なので、冬は室内でも暖かい場所に移動させてあげましょう。窓際は冷気が入り込むので避けましょう。
湿度の高い所を好むので、乾燥気味も注意しましょう。エアコンなどで室内が乾燥する際は、加湿器などで室内の湿度を保つように心がけましょう。やや上級者向きですが、長く楽しめる観葉植物です。光沢のある赤い花が印象的なアンスリウムです。
暖かい地域だと育ちやすいので、ハワイとかでよく見かける方も多いのではないでしょうか。そのハワイでは、バレンタインデーで贈る花のようです。南国のイメージの品種が多い中、清楚なイメージの品種もたくさん増えてきました。
また、外見の変化だけでなく、育てやすさもよくなりました。そのため、公共のスペースにも使われていたり、母の日や引っ越し祝い、会社設立祝いで贈られることも多くなり、人気の品種となっています。
こちらのマーガレットの育て方も凄く参考になります♪
-

-
タイムの育て方について
タイムはインド、北アフリカ、アジアを原産とするシソ科のハーブで、たくさんの品種があります。主に料理用に使われるコモンタイ...
-

-
リクニス・ビスカリアの育て方
リクニス・ビスカリアの歴史はそれほど解明されていません。実際語源はどこから来ているのかははっきりしていませんが、属名のリ...
-

-
ニオイスミレ(スイートバイオレット)の育て方
ニオイスミレは、別名でスイートバイオレットとも呼ばれています。スミレ科のスミレ属に属しています。耐寒性多年草で、原産地は...
-

-
ピメレアの育て方
ピメレアは育てるのに、簡単で丈夫な植物になりますが、どうしても夏場は気をつけてあげないといけないです。夏場は高温になって...
-

-
ツルムラサキの育て方
ツルムラサキがどこに自生していたのかというのは、詳しくは分かっていないのですが、熱帯地域が原産だろうと考えられています。...
-

-
ハツユキソウの育て方
ハツユキソウは背丈がおよそ1メートル程の高さに延び、その葉先に小さな花をつけます。白く色づく葉は花の回りにある唇型の葉で...
-

-
カツラの育て方
カツラは日本特産の植物で大昔である太古第3紀の頃から存在します。日本とアメリカに多く繁茂していましたが、次第にアメリカに...
-

-
イチゴの育て方について
イチゴは粒が大きくて甘味が強いのが当たり前だと思っている人が少なくありませんが、スーパーの店頭などで売られている栽培イチ...
-

-
コマクサの育て方
高山植物の女王とも呼ばれているコマクサは高山に咲く高山植物の一つです。北アルプスなどの山々の中で見ることが出来ますが、比...
-

-
ナンブイヌナズナの育て方
ナンブイヌナズナは日本の固有種です。つまり、日本にしか自生していない植物です。古くは大陸から入ってきたと考えられますが、...





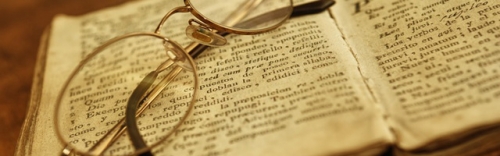





アンスリウムは、熱帯アメリカ・西インド諸島原産で、日本には明治の中頃に渡来してきた歴史ある植物です。木の枝などに着生する常緑の非耐寒性多年草で、地生種と養生種を合わせると約900種以上あります。このアンスリウムは、サトイモ科特有の仏炎苞(*)と呼ばれる苞で、突き出した尻尾のような部分に集まりくっ付いている肉穂花序が本当の花ですが、小さくて目立ちません。