ガマズミの育て方

ガマズミの育て方を知ろう
ガマズミは日当たりの良いところもしくは半日陰くらいの場所に植え付けるのがベストです。日陰でも育てるだけならば問題ありませんが、日陰では枝が間延びしてしまうので見た目があまり良くありません。
根が粗いので植えつける時には周りの土を崩さないようにして植えつけた後はぐらつかないように支柱を立てて支えます。時期は12月か2月下旬から3月頃が良いでしょう。水はけの良い土を用意しておきます。植え付けの前に腐葉土や元肥として遅効性の粒状肥料も一緒に混ぜ合わせておきます。
根鉢の周りには十分に水をまき、棒などでつついて根と土をなじませるのがコツです。樹の伸びる勢いが遅かったり葉の色があまり良くない場合は少量の化成肥料をばらまいておくのが良いです。水は植えつけてから根が張ってしまえば、夏の高温期以外は特に水やりをする必要はありません。
雨水だけで十分です。日陰で風通しが悪い場合はカイガラムシがついてしまうことが考えられるので注意しましょう。カイガラムシは茎などの汁を吸ってひどい場合は枯らしてしまいます。またテッポウムシが発生することもあり、テッポウムシは幹や枝の内部を食い荒らしてしまいますので、もし見つけたらすぐに退治します。しかし基本的には病気や害虫には強いのでそれほど心配しなくても大丈夫です。
栽培する上で行なうと良いこととは?
先端の枝が長く伸びやすいのですが、この枝には花芽はつきません。花芽は枝の基部から出る短枝の先端にできます。どちらかといえば生長のスピードが速く枝もよく伸びるのですが、きちんと適した場所で育てていれば樹形が崩れるほど枝が伸びることはほとんどありません。
木が大きくなってくると細かい枝がたくさん出てくるので、混みあってきた所は風通しと日当たりを良くするために枝を切ったほうがいいです。この作業は枝抜きといいます。もし間延びした枝があれば切ってもいいですし、3、4年たった古い枝は新しい枝を出させるために切りのぞいてしまってもいいです。
剪定をしなくても大きくなってしまうと自然樹形がまとまりも良いですし、美しいです。ですから枝を切る場合は必ず枝分かれしている付け根の部分から切るようにするのが良いです。剪定はほとんど必要ないくらいなのですが、邪魔な枝やいらない枝を取り除く程度の最低限のことはしたほうが良いでしょう。
花芽の付く短い枝ごと大胆に切ってしまうのは避けたほうがよいですが、樹の伸びる勢いは強いので樹高を低くしたい場合は思い切り切り詰めてしまってもOKです。剪定は12月頃から3月頃が目安です。耐寒性はかなり強いです。
種付けをして増やすことができるのか
ガマズミは種まきや挿し木、接ぎ木で増やしていくことができます。種まきは開花後に10月から12月にかけてできる果実が熟した時に果肉部分を取り除いて種だけ取り出してすぐにまいてしまうか、乾燥しないように砂などの中に貯蔵しておき、翌年の3月頃にまくのが良いです。
花が咲くようになるまでは種まきをしてから5年から6年ほどかかります。挿し木の場合、6月頃から8月頃に梅雨ざしや夏ざしが良いでしょう。今年伸びた枝を15cmほどの長さにカットし、先端から2対か3対ほど葉を残して30分ほど水揚げします。切り口に植物成長調整剤を塗っておき、小粒の赤玉土か市販の挿し木用の土に挿しておきます。
深さは土の表面に葉が触れる程度の間隔で挿します。たっぷりと水を与え、風があたらないような日陰に置いて乾燥しないように管理しておきます。発根するのは秋頃になるでしょう。接ぎ木は園芸種を増やしたい時向けの方法です。台木にするのは種まきから2年ほど育てたカマズミの木を使います。そこに増やしたい品種の枝を接ぎます。
カマズミにはいくつかの仲間がありますが、実が黄色く熟すものがあり、その品種はキミノガマズミといいます。山地に自生しているのはミヤマガマズミといいます。葉の部分を揉むことでゴマのような香りがするゴマギという種類のものもあります。最近ではガマズミの絞り汁を商品化したものが飲料として販売されています。
ガマズミの果汁はビタミンCがレモンの4倍、ポリフェノールが赤ワインと同じくらいあります。他にも食物繊維、カリウム、アントシアニン類なども含まれています。ガマズミの粉末を米と一緒に炊いて赤飯のように作ることもできますし、ガマズミ果汁はヨーグルトにかけても甘酸っぱくておいしいです。
同じようにバニラアイスと混ぜて食べてもすっきりとした味わいになります。紅茶にすればレモンティーのような爽やかな味を楽しめます。飲料の他にもポン酢や飲む酢、ジャム、ゼリーやキャンディ、サプリメントなども販売されています。昔マタギたちは山の中で獲物を追いかけて歩き回って疲れた時、食べるものがなかった時にはガマズミを探し出して口にし、体を休めていたといわれています。
ガマズミの歴史を知ろう
ガマズミはその名前の由来がはっきりとわかっていません。一説によるとガマズミのスミは染の転訛ではないかというものがあり、古い時代ではミヤマガマズミの果実を衣類にすって色染めしていたという事実があります。また中国では昔から桃が神聖視されていましたが、日本でも実際に桃が渡来する前から桃の霊力については伝えられていたのです。
実際の桃がなかったので、その代用としていろんな木が使われていました。その一つがこのガマズミだったといわれています。神つ実と呼ばれていたのですが、それが時代が流れると共に訛ってガマズミとなったのではという説もあります。
他にも鎌の柄の材料につかわれていたこと、染物の材料に使われていたことから合わせてガマズミとなったという話もあります。スイカズラ科ガマズミ属の植物で、原産は中国や朝鮮半島ですが、生息地は日本にもあります。樹高は3mほどになり、開花時期は5月から6月頃になります。実が熟す時期は10月頃になります。
ガマズミの枝はとても丈夫で柔軟性があり、折れにくいということから昔は杖や輪かんじきの材料として使われることも多かったです。輪かんじきとは雪国などで雪に沈まないようにして歩くために靴の上から装着するものです。また生け花の花材としても使われるようになっています。
ガマズミの特徴
ガマズミは落葉低木で、新緑の頃になると5ミリ程の白い小花が木全体の枝先に傘状に付き、10月頃には赤く熟した小豆ほどの大きさの実がなります。この実が美しく、花よりも観賞価値があるといわれています。若い枝は星状毛や腺点があってざらざらしており、灰緑色をしているのですが、古くなると色が灰黒色になるのですぐに古いものだとわかります。
大きさが10cmほどある葉は対に生え、細かい鋸歯があって卵型から広卵形をしています。表面には羽状の葉脈が少しだけ出っ張っていて、凹凸があります。しかし脈上にだけ毛があるのは面だけで、裏面は腺点や星状毛などが多くなっています。花は白くて小さな花序を作ります。
開花後にできる赤い実は食用や果実酒の材料になっています。また漬物の天然着色料としても使われます。この赤い実は霜にあたることで甘みを増します。天然クエン酸であるりんご酸をたっぷりと含んでいるので健胃や疲労回復にもとても良いとされています。各地域で呼び名が違っており、関東ではヨツズミやヨツドメ、東北ではジュミやゾーミ、中部ではヨーゾメやカメガラ、四国・九州地方ではナベトーシやイセビ」などと呼ばれています。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ハスカップの育て方
タイトル:モミジの育て方
タイトル:ヒペリカムの育て方
タイトル:スイカの育て方
-

-
フェイジョアの育て方
フェイジョアは1890年にフランス人の植物学者であるエドアールアンドレによってヨーロッパにもたらされた果樹です。元々は原...
-

-
クレマチス ネリー・モーサーの育て方
この花についての特徴としては、まずはキンポウゲ目、キンポウゲ科、キンポウゲ亜科の種類となります。さらにセンニンソウ属に属...
-

-
モミジカラマツの育て方
モミジカラマツの特徴について書いていきます。その名前の由来からして、葉っぱは紅葉のように切れ込む葉が特徴的です。実際に見...
-

-
ガクアジサイの育て方
一般名として、ガクアジサイ(額紫陽花)といい学名はHydrangeamacrophyllaf.normalis。分類名は...
-

-
オトメギキョウの育て方
オトメギキョウの原産地は東ヨーロッパ、クロアチア西部で、カンパニュラの一種となっています。カンパニュラは主に地中海沿岸地...
-

-
育てやすい観葉植物について
観葉植物のある部屋に憧れを持っていたり、お店やオフィスに観葉植物を置きたいと考えている人は多いです。園芸店やホームセンタ...
-

-
ゴンゴラの育て方
花の特徴としては、ラン科になります。園芸分類はランで、多年草として咲くことになります。草の丈としては30センチ位から50...
-

-
カリンの育て方
カリンは昔から咳止めの効果があると言われてきており、現在ではのど飴に利用されていたりします。かつてはカリン酒等に利用され...
-

-
イングリッシュ ラベンダーの育て方
イングリッシュ ラベンダーは、シソ科のラベンダー属、半耐寒性の小低木の植物です。ハーブの女王としてゆるぎない地位を確立し...
-

-
ヘーベの育て方
ヘーベの特徴は次のようになっています。オオバコ科のヘーベ属に分類されており、原産地はニュージーランドになります。分類は常...




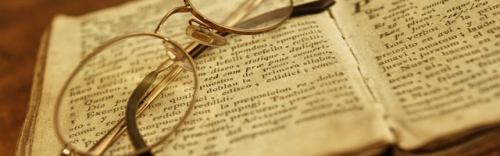





ガマズミはその名前の由来がはっきりとわかっていません。一説によるとガマズミのスミは染の転訛ではないかというものがあり、古い時代ではミヤマガマズミの果実を衣類にすって色染めしていたという事実があります。また中国では昔から桃が神聖視されていましたが、日本でも実際に桃が渡来する前から桃の霊力については伝えられていたのです。