グラジオラス(夏咲き)の育て方

育てる環境について
実際に栽培する環境として、まず意識しておかなければいけないのが、日当たりです。日当たりの良い場所を好む植物の為、しっかりと日が当たる場所を選ぶ事が大切ですが、風によって倒れる事もある為、強風が吹く事が多い、強風が吹く可能性がある場合、風よけとなる物がある場所を意識しておく事も大切です。
更に、寒さに弱い特徴を持つ植物です。暖かい季節になってから植える場合は、問題ありませんが、春先でも3月頃など、まだ寒い日が残る時期に植える場合、霜に注意が必要です。霜が下りても、土の中にある球根は寒さから守られた状態であると考えるのは間違いです。
霜が下りる程、寒い状態の場合、寒さに弱い球根は、土の中でかれてしまい、芽が出なくなる事があります。ですから、気候が不安定で、まだ寒さが残る季節に、球根を植える場合、土の中の球根に対して、寒さ対策を行っておく事も大切です。そして、もうひとつ意識をしておきたいのが、水はけです。
植物を育てる際、水は少しでも多く与える方が良いと考える人も少なくありませんが、グラジオラスの場合、水を与え過ぎる事は、根を腐らせてしまう原因になる他、花が咲きにくい原因にもなってしまいます。ですから、
水を与え過ぎないという育て方を意識するだけでなく、最初から、水はけの良い土壌を作っておく事が大切です。それにより、初めて育てる人でも、成長しない、花が咲かないという事に悩まされる事が少なくなります。
種付けや水やり、肥料について
グラジオラスの球根を植える場合、球根の大きさを目安に植えていく事がお勧めです。深さは、球根の高さの2倍の深さになるまで土を掘り、そこに球根を置き、上に土をかけていきます。球根の上に、ちょうど球根と同じ高さの土がかぶさる状態が目安です。
そして、隣の球根までの距離も、球根の横幅を目安に、1つ分ずつ空けていく状態で植えていく事がお勧めです。同じ時期に一度に植えても良いのですが、植えるタイミングをずらしていくと、長く綺麗な花を楽しめるようになります。植える際、肥料はしっかりと与えた方が良いと考える人もいますが、
与え過ぎると、うまく育たない事があるので、最初の土壌作りの段階で、土に肥料を混ぜ込んだ後は、芽が出て花が咲くまでの間に、追肥として2回から3回程度、根元に少し肥料を撒く程度で構いません。水の与え過ぎも花が上手く咲かない原因となる為、
水は土の表面が乾いてきたら与える程度にしておく事が大切です。そして、もうひとつ、芽が出て葉っぱが育ってきたら、しておきたいのが、支柱立てです。風に弱い植物で、風が吹くと曲がってしまい、そのまま育つことがあります。
ですから、芽が出た後、4枚程度、葉っぱが出揃ってきたら、支柱を立てる他、ネットを張って、その穴からグラジオラスが成長していく状態にしていく事がお勧めです。支柱を立てたり、ネットをしたりすることにより、グラジオラスがまっすぐ綺麗に育ちやすい状態となります。
増やし方や害虫について
球根を持つ植物は、花が咲いた後、そのままにしておくと、自然に枯れ、また春になれば、土の中から芽が出てくるものも少なくありません。ただ、グラジオラスの場合、寒さに弱いという特徴があり、球根も0℃を下回る状態になると枯れてしまう為、増やしたい、
次の年も楽しみたいと考える場合、土の中から球根を取り出し、貯蔵しておく必要があります。貯蔵を考える場合、葉っぱが半分程度枯れてから、球根を傷つけないように、土の中から掘り出していきます。そして、そのまま日陰に置いて、しばらく乾燥させた後、球根を分けていきます。
周辺についている百合根のような小さな球根は、取り外し、そのまま貯蔵します。中心にある球根は、底の部分の古球と上の部分の新球に分け、古い部分は捨て、新しい部分だけを貯蔵に回します。貯蔵をする際、重要になってくるのが、気温です。
0℃を下回らず、風通しの良い場所で、貯蔵をしておくことが大切です。グラジオラスにつきやすい害虫といえば、ナメクジやアブラムシです。梅雨の時期などに多く発生する害虫で、対策をしたいと考える場合、ナメクジ用の薬を土の上に置いておく等が有効です。
更に、落ちた花びらなどが腐敗すると、菌や害虫が発生しやすい原因となってしまいます。ですから、害虫対策の薬などを利用すると共に、綺麗な環境を整えておく事もお勧めです。それにより、害虫に悩まされる事が少ない状態で、綺麗な花を楽しめるようになります。
グラジオラス(夏咲き)の歴史
園芸植物として人気の高いグラジオラスは、200種類前後の種類がある球根植物です。南アフリカのケープ地方が中心に分布している植物ですが、それ以外にも南ヨーロッパや、西アジアにも分布しています。春に植え、7月から8月にかけて花が咲く夏咲きの花は、
南アフリカの東ケープ地方など、熱帯アフリカが生息地だったもの原種となります。この南アフリカ原産の原種を元に、育成されたものが、ヨーロッパを中心に様々な国へと広まっていく事になりました。日本に伝わるよりも、以前からこの花を育てていた地域が、ヨーロッパです。
グラジオラスはヨーロッパでも人気が高い園芸植物で、ヨーロッパでは春に花が咲く早咲きのタイプも多く、それ以外にも冬に花が咲く冬咲きなど、様々なタイプが育てられています。ヨーロッパでは、花を楽しむ他、球根を穀物の粉と混ぜて、焼いて食べていたという記録がある他、
鎧に似た見た目を持つ球根を、お守り代わりとして兵士が持ち歩いていたという記録もあり、観賞用以外の形でも、利用されていました。日本には、江戸時代末期に、オランダから長崎に持ち込まれたのが起源とされており、当時は、トウショウブやオランダアヤメという呼び方をされていました。
明治時代に本格的に輸入が行われ、日本でも栽培が始まりました。日本では花自体を楽しむ他、値は、湿布薬の材料等にも使われています。そして、現在では、園芸植物として、常に安定した人気を誇る植物の一つとなっています。
グラジオラス(夏咲き)の特徴
夏咲きのグラジオラスの特徴は、初心者でも育てやすいという事です。寒さには弱いという特徴がありますが、春先に植えて、6月から8月頃にかけて花を咲かせていく夏咲きのものであれば、誰でも育てやすい事で人気です。更に、夏咲きのものは、花の大きさや色がとても豊富な事でも高い人気を誇ります。
花の大きさは、小さいものであれば6cm前後ですが、大きなものになると15cm近くになるものもあり、そんな花が複数、連なって咲く花は、華やかで見ごたえのあるものとなります。大きさによって、雰囲気も大きく異なる為、花の選び方によって、庭やベランダの雰囲気を大きく変える事も出来ます。
そして、更に豊富なのがその色合いです。オレンジやピンクなど原色に近い華やかな色合いもありますが、それ以外にもピンクと白、オレンジと白など、2色の色が組み合わさったものや、パステルカラーのような淡い色合い、そして淡い黄緑のような色合いなど、サザざまな色を楽しむ事が出来る事でも人気です。
とても豊富な花の形と、色は、一見、同じ種類の花に見えないと感じる事もありますが、この種類の豊富さもまた、夏咲きのグラジオラスの特徴の一つです。庭やベランダに植えて育てる園芸植物としての楽しみ方の他、切花として楽しむ事も出来ます。鮮やかで、存在感のある花は、花束を作る際にも人気で、庭やベランダで育て、花が咲けば、室内で花を楽しむという、楽しみ方も可能となります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:クロッサンドラの育て方
タイトル:クレオメの育て方
-

-
リパリスの育て方
特徴としては、被子植物になります。ラン目、ラン科、クモキリソウ属に該当します。ランの種類の一つとされ、多年草としても人気...
-

-
イクソーラ・コキネアの育て方
この花の特徴は何といっても花です。アジサイのように小さな花が密集してひとつの花のように見えるところです。細かいことを言う...
-

-
クジャクサボテンの育て方
クジャクサボテンはメキシコの中央高原地方で古くから存在していた原種を交配して作り上げた交配種であり、世界的に数百種類の品...
-

-
イチジクの育て方
イチジクのもともとの生息地はアラビア半島南部、メソポタミアと呼ばれたあたりです。文明発祥とともに身近な食物として6000...
-

-
マツバボタンの育て方
原産地はブラジルで日本には江戸時代に入ってきたといわれるマツバボタンは、コロンブスがアメリカに進出したことでヨーロッパに...
-

-
シバザクラ(芝桜)の育て方
シバザクラは北米を原産とするハナシノブ科の多年草です。春先にサクラによく似た可愛らしい花を咲かせますが、サクラのような大...
-

-
オクラの栽培オクラの育て方オクラの種まきについて
オクラはプランターなどでも手軽に育てることが出来るということもあり、とても人気があります。オクラのの栽培やオクラの育て方...
-

-
ゼブリナの育て方
ゼブリナは、ツユクサ科トラデスカンチア属で学名はTradescantia zebrinaです。別名はシマムラサキツユクサ...
-
ピラミッドアジサイ(ハイドランジア・ パニュキュラータ)の育...
ピラミッドアジサイは別名ハイドランジア・_パニュキュラータというアジサイの仲間ですが、もともと日本原産の植物で、昔から自...
-

-
ベゴニア・センパフローレンスの育て方
ベゴニア・センパフローレンスはシュウカイドウ科ベゴニア(シュカイドウ)属に分類される常緑多年草です。ベゴニアはとても種類...




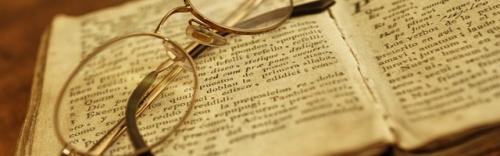





園芸植物として人気の高いグラジオラスは、200種類前後の種類がある球根植物です。南アフリカのケープ地方が中心に分布している植物ですが、それ以外にも南ヨーロッパや、西アジアにも分布しています。