マーガレットの育て方

マーガレットの植えつけ
マーガレットはもともと温暖な地域の植物ですので、日当たりが良いところが大好きで、日本の冬には少し弱く、庭植えにすると冬に凍って枯れてしまう可能性もあります。温暖なところ以外は、鉢植えが無難でしょう。種付けの発芽率はあまり良くないので、春頃に出回る、花の咲いた苗で、花も確認した上で植え付けるのがよいでしょう。
マーガレットは冬も嫌いますが、夏の過湿も嫌います。このため、上手に夏越しをさせるため、水はけの良い用土に植えてあげる必要があります。また、酸性土を嫌うので、苦土石灰を混ぜ込み酸度を中和するようにします。赤玉土小粒:腐葉土:酸度調整済みピートモスを5:3:2の割合で配合し、1リットルあたり1グラムの苦土石灰を混ぜ込んでやると良いでしょう。
植え付けの際に、リン酸分の多い緩効性肥料をやります。そのほか、春と秋には置き肥として緩効性肥料をやります。特に早春から初夏まで休みなく花が咲く期間は、肥料を上げないと花付きが悪くなりますので、気を配ってあげましょう。気温の低い11月~4月は、すぐに吸収される液体肥料を施します。苦手な夏には生育が止まり、株も疲れ気味になりますので、肥料は施しません。
マーガレットの育て方と管理
マーガレットの育て方で一番気を使いたいところは、日の当たるところで育ててあげるということです。半日陰でも育たないことはありませんが、花付きも花色も悪くなりますので、あまり適した場所とはいえません。また過湿も嫌うので、実は日本の夏の高温多湿はマーガレットにとっては良い環境ではありません。
このため、温暖な地域なら庭植えも良いのですが、夏の高温多湿と厳しい冬にさらされてしまうようなら、居心地の良い場所に移動させてあげられる鉢植えが適しています。鉢植えの場合の育て方は、12月~4月頃までは、日当たりの良い室内で管理します。寒い風が当たらない南向きの場所に置いてやり、霜よけをすれば、外で冬を越させることも可能です。5月~11月頃までは、日当たりの良い外で管理します。
過湿を嫌うので、梅雨時は長雨に当たらないような風通しの良いところへ移動させてあげましょう。梅雨明け~8月頃までは半日陰で管理します。庭植えの場合の育て方は、南向きの日だまりなどの寒い風が当たらないところに植え付けます。12月~2月は霜よけを行ってやります。場所が合っていれば、夏も冬も上手に越して、多年草として育ってくれます。
水やりは、秋~春は土の表面が乾いたらたっぷりと、夏は乾かし気味にして過湿にならないようにします。早春から初夏の時期、花がたくさん咲きますので、この時期は花に水がかからないように気をつけてあげましょう。育て方としては、一種類だけでもとても見応えのある華のある植物ですので、寄せ植えなどにするよりも、マーガレットのみ花の形を整えながら、鉢植えで育ててあげるのが適しているでしょう。
そのほか、枝に元気な葉が残るよう、3月~6月、9月~10月頃に切り戻しをしてあげます。葉を残さずに強く切り戻すと、枯れてしまうので気をつけましょう。また、根詰まりを起こしやすいので、毎年植え替えをしてあげます。3月~6月、9月~10月頃が適しています。根鉢を3分の1ほど崩して植え替えます。そのほか、適期以外に植え替える場合は、根鉢は崩さないようにします。
初めてのマーガレットの場合は、春先に出回る花の咲いた苗で花を確認してから購入するようにしましょう。また、入手した苗は根詰まりを起こしていることが多いので、一回り大きい鉢に植え替えてあげると良いでしょう。
マーガレットの種付け、栽培
マーガレットは種でも苗でも流通していますので、増やす場合には、種付けか挿し木で行います。ただ、種付けは発芽率が悪く、栽培方法としてはあまりおすすめできません。また、種の場合、同じ花が咲かない可能性もありますので、栽培の場合は、挿し木が確実です。
6月頃、勢いのある新芽を10センチくらいの長さに切り取り、葉を3、4枚残して後は切り取ってさし穂にします。このさし穂を30分ほど水につけて水あげし、それから切り口に植物成長調整剤をまぶして、挿し木用土に植え付けてあげます。1か月ほどで発根します。
発根したら、ポットに植え替えてあげて、育苗します。この時期は寒さに弱いですので、暖かい場所に置いてあげましょう。栽培環境は根付いたマーガレットと同じく、過湿と厳しい寒さを避け、日当たりの良い場所を選んであげます。
マーガレットの病害虫
連作すると、立枯病が発生しやすくなります。30度を超える日が続くと多発しますので、乾かし気味にしてやり発生しにくくします。そのほか、葉にオレンジ色の斑点ができるサビ病もあります。見つけたら、被害部分を取り除きましょう。
また、株の間を広く取ってあげ、風通しを良くしてあげると予防になります。害虫はアブラムシとヨトウムシが発生します。薬剤で防除するようにします。特にアブラムシは、室内で冬を越させると、若い葉にアブラムシが大発生することがあるので、見つけ次第防除しましょう。
マーガレットの歴史
マーガレットは、大西洋に浮かぶカナリア諸島が原産で、もともとの生息地です。17世紀は、ヨーロッパにおいて色々な花の改良が盛んだった時代ですが、マーガレットもまた、17世紀末にヨーロッパに入り、多くがフランスで改良された歴史を持っています。和名ではモクシュンギクと呼びます。
これには、キク科のマーガレットが春菊に似ていて茎が木のようになるため、名付けられたという由来があります。一般にマーガレットと呼ばれるのは、本来のマーガレットを改良した園芸品種の他、本来のマーガレットと近縁種を交配した園芸品種で、様々な種類があります。
日本には、モクシュンギクとして「在来白」と呼ばれる種類が明治時代に入ってきました。この在来白はあまり種ができないのですが、他の改良された最近の園芸品種は種が簡単にできるものが多くなってきています。明治時代に入ってきて以来、大正時代に多く栽培されるようになりました。現在の日本においては、盛んに育種が行われており、毎年新しい品種が出ては園芸店を飾り立てている親しみやすい植物です。
マーガレットの特徴
一目でキク科と分かる花の形と葉の形をしています。花の形はシンプルな一重から、丁字、八重、ポンポン咲きなどバラエティに富んでいます。基本的に香りはないのですが、ラベンダーのような香りを持つ交配種も一部あります。花の大きさも色々なのですが、一般的に3センチ~5センチくらいのものが多いです。
花色は、白、黄色、ピンク、濃いピンクなどがあります。一重咲きの白花は清楚な感じでよく知られており、ヨーロッパでは結婚式のブーケには必ずといっていいほど使われています。多年草の植物で、日本の夏の高温多湿や冬の寒さは苦手なのですが、上手に冬を越させて何年も育てていると、大きく育ってきて茎が木質状になっていきます。背丈は20~50センチくらい、横幅は25~40センチくらいになります。
開花時期は3月~6月くらいで、長く花を楽しむことができる植物です。種でも苗でも増やすことができるのですが、色々な種類がありますので、初めて植える場合には春頃に扱われる、花の咲いた苗で花の様子を確認してから植えます。
日当たりを好み、本来暖かいところの植物ですので、日本でも暖かいところなら冬を越しますが、冬は得意ではありません。そのため、長く多年草として育てるなら、鉢植えにし、居心地の良いところで管理してあげると、多年草として大きくなっていきます。
花を育てたい方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アンスリウムの育て方
タイトル:ヒヤシンスの育て方
タイトル:フジバカマの育て方
タイトル:ミヤコワスレの育て方
タイトル:シュウメイギクの育て方
-

-
センテッドゼラニウムの育て方
センテッドゼラニウムはフロウソウ科のテンジクアオイ属の植物です。ニオイゼラニウムという別名で呼ばれることがあるように、香...
-

-
キュウリの育て方
どうせガーデニングをするのであれば、収穫の楽しみを味わうことができる植物も植えたいと希望する人が少なくありません。キレイ...
-

-
ディモルフォセカの育て方
ディモルフォセカは、南アフリカ原産のキク科の一年草で、日本名ではアフリカキンセンカと呼ばれています。よく似た花に、多年草...
-

-
トックリラン(Beaucarnea recurvata)の育...
トックリランは、スズラン亜科の常緑高木でトックリランという名前は、幹の下部が徳利のような形に膨らんでいることが由来してい...
-

-
ブリメウラ・アメシスティナの育て方
「ブリメウラ・アメシスティナ」は、南ヨーロッパを原産とした鉱山植物です。花の宝庫と呼ばれ大自然あふれる山脈、ピレネー山脈...
-

-
ロータスの育て方
「ロータス」は、北半球の温帯、主に地中海付近の島国を原産として約100種類もの品種が存在するマメ科ミヤコグサ科の多年草で...
-

-
ジニアの育て方
ジニアはメキシコが原産の植物です。生息地はメキシコあたりで、1,796年にスペインへともたらされます。スペインの首都マド...
-

-
いちごの育て方
いちごの歴史は古く、すでに石器時代から食べられていました。南米や北米が生息地になり、野生の果実は甘味が少なく大きさも小粒...
-

-
ハオルチアの育て方
ハオルチアはもともと南アフリカ地域の原産のユリ科の多肉植物で、水分が多くなると生育できないことが多いので日本で栽培をする...
-

-
マンションやアパートでの植物栽培
マンションやアパートなどに住んでいる場合も植物を栽培することはできますが、その際はベランダも小さかったりと小規模ながらも...





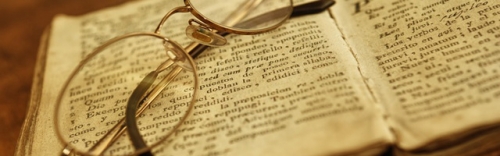





マーガレットは、大西洋に浮かぶカナリア諸島が原産で、もともとの生息地です。17世紀は、ヨーロッパにおいて色々な花の改良が盛んだった時代ですが、マーガレットもまた、17世紀末にヨーロッパに入り、多くがフランスで改良された歴史を持っています。和名ではモクシュンギクと呼びます。