ヒュウガミズキの育て方

育てる環境について
日当たりが良い場所を好みます。ただ、半木陰でも十分花を咲かせてくれます。プランター栽培の場合には東北地方以北でも育てることは出来ますが、庭木で育てる場合には東北以北は難しいです。湿り気のある深い土壌が栽培には適しています。
この土壌には、砂質土にやや粘土が混ざった土が良いです。手触りは滑らかさとザラザラ感が適度にある土です。ただ、ヒュウガミズキは基本的には肥沃、水はけ、水もちが良い、つまりは普通の土の範囲内であれば十分育ちます。植え付けの時には枝を切り詰めて、水をたっぷり与えるようにします。
乾燥には比較的強いですが、カラカラに乾燥してしまうような環境では生育不良を引き起こす可能性があります。特に西日が直接当たるような場所は注意が必要です。そういう場所しかないのであれば、根元にマルチング処理で藁を敷くか、グラウンドカバーを植えるようにします。
東北以北の寒冷地で育てたいのならば、冬場には玄関先にすぐに取り込めるように鉢植えにするのがおすすめです。地植えにしてしまうと成功率が低いです。もっと南の温暖な地方であれば、地植えでも全く問題なく冬越しすることが出来ます。
土には適度な湿り気は必要ですが、基本的にはやや乾燥気味のほうが丈夫に育ちます。鉢植えの場合には土の表面が乾いたら与える、地植えの場合には降雨任せにする、というくらいで大丈夫です。地植えでは基本的に植え付け後だけ水やりすれば十分です。
種付けや水やり、肥料について
庭植えにする場合には、掘った穴の底に完熟堆肥などの有機土を入れるようにします。こうすることで、通気性、水はけ、水もちの良い土壌に改良することが出来ます。徒長した枝は切り詰めて植えつけるようにします。植えた後にはたっぷり水を与えます。
鉢植えの場合には、腐葉土を混ぜた土を使います。植物の土の基本である小粒赤玉土:腐葉土=7:3でも十分育ちます。庭植え、鉢植えのどちらの場合にも、水切れに気をつけるようにします。乾燥しないように、マルチング処理で根元に敷き藁などを施してあげると良いでしょう。
ただし、乾燥気味のほうがよく育つ場合もあります。地植えでは植え付け後だけ水やり、鉢植えでは乾いた時にだけ水やり、ということを基本にすれば良いです。肥料は、庭植えも鉢植えも同じです。寒肥として、堆肥に油かす、鶏ふん、草木灰などの有機質の肥料を加えて施すようにします。
寒肥というのは、花木に寒い時期に与える肥料のことです。開花後には栄養が少なくなっているので、油かすを与えるようにします。もしくは、骨粉:油かす=7:3の割合で混ぜた肥料を追肥として与えてあげると良いです。ちなみに、この作業をお礼肥と言います。
管理については、普段は放任の育て方でも良いです。邪魔な枝が伸びてきた時に剪定作業を行うくらいです。肥料に関しても、絶対に寒肥を与えないと育たないというわけではありません。多少花付きは悪くなるかもしれませんが、ほぼ問題ないです。
増やし方や害虫について
増やし方は3種類から選べます。挿し木、株分け、種まき、の3つです。挿し木は、春挿し(3月中旬〜下旬)と夏挿し(6月中旬〜7月)、秋挿し(9月)で方法が違います。春挿しの場合には、前年の枝を2月の中旬までには採取して貯蔵しておきます。それを使い、3月中旬〜下旬に挿して増やします。
夏挿し、秋挿しの場合には、当年の枝を使います。細い枝は避けて、充実した太めの枝を選ぶようにします。春挿しの土には赤玉土のみの肥料分が含まれていない土を使います。発育を良くするために、発根促進剤、密封挿し、ミスト挿し、などを行うのも効果的です。
株分けするならば、小分けにしないように注意します。小分けにしてしまうと花のつきが悪くなり、株が弱くなってしまいます。種まきでは、とりまき、もしくは春まきのどちらでも可能です。10月頃に種を採取しておきます。春まきする場合には、
種が乾燥してしまわないように3月まで貯蔵管理しておきましょう。害虫はほとんどつきませんが、うどんこ病にかかる事があります。うどんこ病の原因となるのは、枝が密生してしまうことです。枝が混みすぎることにより、風通しと日当たりが悪くなるのが原因です。
病気が発生してしまうとカビで葉が白くなり、見た目が悪くなってしまうので、混み合いすぎている場合には剪定作業を行いましょう。剪定はよほど枝が伸びていない限りは必要ありませんが、病気の予防にもなりますし、アレンジも楽しめるのでやっておいたほうが良いです。
ヒュウガミズキの歴史
原産地は本州の福井県、京都府、兵庫県の北部、です。近畿地方(石川県〜兵庫県)の日本海側の岩場の、ごく限定された地域に自生しています。ヒュウガミズキのヒュウガ(日向)とは現在の宮崎県のことですが、これが直接由来かどうかははっきり分かっていません。
京都の所領に植えられてあったことや、トサミズキよりも小ぶりなヒメミズキが訛ってヒュウガミズキの名がついたとも言われています。昔、日本の植物学者がロシアの学者に標本を送るために、近畿地方の北部の森林で植物採取をしている時に、偶然発見されたのが起源だと言われています。
ヒュウガミズキを漢字で書くと日向水木となりますが、これは今の日向の国(宮崎県)と関係があるのではないようです。丹波(京都〜兵庫のあたり)の国を所領にした明智日向守光秀に由来して、日向という名前がついたのではないかというのが有力な説です。
ミズキの由来はマンサク科マンサク属のマンサク(満作)からです。同様の黄色がかった白い花をつけることから、豊年満作を期待して満木(ミタスキ)と呼ばれていたものが、だんだん訛っていき、最後にはミズキに変化したと言われています。
葉の状態も平行葉脈でミズキの仲間に似ているので、ミズキとなったようです。ミズキの意味には、水木という樹液が多く、春先に枝を切るとそこから水がしたたり落ちることも由来していると言われています。生息地は現在では近畿の北部がメインですが、鉢植えではこれより以北でも栽培されています。
ヒュウガミズキの特徴
マンサク科トサミズキ属の生垣向けの庭木の植物です。別名にはヒメミズキという名前があります。高さ2〜3mの樹高があり、庭木としてよく使われています。新芽は赤くて、葉は柔らかいです。花は葉が出るよりも先に咲きます。だいたい3月下旬に2〜3個ほどの黄色がかった小ぶりの白い花を花序配列でつけます。
花の数が多いため、下に垂れたような姿勢になります。枝が細く分岐して、放っておいても半球状の整った樹形になります。また、刈り込み作業も比較的簡単なので、樹形をアレンジしたい人にとっても楽しめる植物です。耐寒性、耐暑性があり、初心者でも比較的簡単に育てることが可能です。
落葉性で冬には葉を落とします。そして春になると再び花が咲き、遅れて葉を出すというサイクルです。全体的に見れば、それほど派手な花ではありません。どちらかと言えば生垣として家の中の目隠しに使ったり、花の色を見るのに疲れてきたときに使うのが適しています。
花の根元から新芽が出てきます。花がしぼんできた時に花柄摘みをしてしまうと新芽をちぎってしまう恐れがあるので、そのまま放置するのが基本です。自然な樹形が美しいのがヒュウガミズキの特徴ですが、あまりにも枝が混み合ってしまうと、
風通しと日当たりが悪くなってうどんこ病にかかる事があるので、その時は短い枝をさばく作業が必要です。根元から出てくる枝を整理することで、全体がすっきりして花付きがよくなることもあります。
-

-
パンジーゼラニウムの育て方
パンジーゼラニウムはフロウソウ科のテンジクアオイ属の植物です。品種改良によって、南アフリカ原産のトリコロル種とオウァーレ...
-

-
エダマメの育て方
エダマメは「枝豆」と書きますが、ビールには欠かせないおつまみとして人気が高い野菜です。そもそもエダマメと言うのは未成熟の...
-

-
ダイモンジソウの育て方
ダイモンジソウはユキノシタ科ユキノシタ属の多年草で、日本国内では北海道や本州、四国、九州などに分布しています。湿り気のあ...
-

-
ケマンソウの育て方
ケマンソウの生息地は、森林や谷間などの半日陰を中心に広がっています。中国から朝鮮半島一帯を原産とする、寒さに強く暑さに弱...
-

-
フィロデンドロンの育て方
フィロデンドロンとは、サトイモ科フィロデンドロン属の常緑多年草です。「樹木を愛する」という意味のギリシャ語から名付けられ...
-

-
ミナ・ロバータの育て方
花の種類としては、ヒルガオ科、サツマイモ属、イポメア属とされることもあります。さつまいもの仲間であるようです。園芸上の分...
-

-
芝桜の育て方
たくさん増えると小さな花がまるで絨毯のように見えることから公園などにも植えられることが多い芝桜は北アメリカ東海岸が原産で...
-

-
ドウダンツツジの育て方
ドウダンツツジは、かわいらしいふっくらとした見た目の花をつける植物で、灯台躑躅、または満天星躑躅と書くのだか、その漢字の...
-

-
ウスユキソウの育て方
ウスユキソウは漢字で書くと「薄雪草」と書きますが、この植物はキク科ウスユキソウ属に属している高山植物です。因みに、ウスユ...
-

-
アカネスミレの育て方
特徴としてはバラ類、真正バラ類に該当します。キントラノオ目、スミレ科、スミレ属でその中の1種類になります。スミレの中にお...




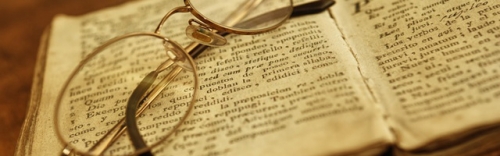





原産地は本州の福井県、京都府、兵庫県の北部、です。近畿地方(石川県〜兵庫県)の日本海側の岩場の、ごく限定された地域に自生しています。ヒュウガミズキのヒュウガ(日向)とは現在の宮崎県のことですが、これが直接由来かどうかははっきり分かっていません。