エラチオールベゴニアの育て方

エラチオールベコニアの育て方
エラチオールベコニアを育てていくのに重要なポイントはずばり温度です。適温は20度ほどで、冬であれば10度は最低でも欲しいところです。日中は日当たりの良い場所に置き、夜になると窓際では気温が低くなってきますので部屋の中央付近までできれば移動させるようにしましょう。
ただし初夏は日差しがかなり強くなり、葉がやけどしてしまうことがあるのでカーテンレース越しなどで日光をあてるようにしたほうがいいです。夏になったら明るい日陰で風通しの良い場所で栽培するのですが、高温多湿になってしまうと病気にかかりやすくなるからです。雨にあたらないように軒下に置いてあげるのが良いです。
そして9月頃になってまた雨がよく降るようになったら家の中に入れてあげ、レースカーテン越しの日光を浴びせます。鉢植えで栽培している時に底皿を使っている場合はその皿に水を貯めておきます。普通の鉢を使っているのであれば土の表面が乾いてきたら天気の良い日の午前中にたくさんあげるようにします。
注意するのはエラチオールベコニアの葉に水がかかってしまわないように、葉をめくってから水を与えることです。肥料はエラチオールベコニアを購入した日から1か月くらいしたら液体肥料を10日に1度ほど与えるようにし、冬でも10度ほどある時には同じように液体肥料をあげるようにしましょう。
元気がない時や温度が保ってない時にはしないほうがいいです。特に6月中旬頃から9月中旬くらいまでは暑さのせいで元気もないので肥料を与えないようにします。育て方はこのように少し手間がかかることもありますが、その分美しい花を長く楽しませてくれますから頑張りましょう。
栽培する上でのコツ
育て方のコツとして梅雨や夏など高温多湿になる時期に病気になってないかマメにチェックすることがその一つになります。かかりやすい病気は斑点細菌病、うどんこ病、灰色かび病などがあります。斑点細菌病は夏にかかりやすい病気で、葉に水浸状の斑点ができてしまいます。
残念ながらこの病気にかかってしまうと改善するということはありませんから、これになってしまったら最後と考えておいたほうが良いです。うどんこ病は春と秋頃、灰色かび病は湿度が高い時期や冬の低温期には注意が必要です。ですから梅雨時期には株の切り戻しをして株元が蒸れないようにしてあげることが大切です。
切り戻しのやり方は側枝もしくはわき芽がある節を残しておき、すでに開花した主茎を地際から3、4節の位置でカットしてしまいます。これによって風通しが良くなりますし、数週間もすれば側枝がのびてまた花を咲かせるようになります。切り戻しをしたら軒下に移動させて病気にかからないようにしてあげます。害虫として心配なのはアブラムシです。
春から初夏にかけてはアブラムシは大量に発生します。というのも、アブラムシは幼虫を一度にたくさん生んでしまうからです。気にならないという方は手でもアブラムシは簡単にとれますから、気がついた時にその都度とってしまうようにすればいいですし、予防策として薬をつけておくのも良いです。また傷んでしまっている葉や花がらをそのまま放置しておくと灰色かび病になりやすくなるのでこまめに取り除いてしまうのがベストです。
種付けをすることはできる?
エラチオールベコニアは基本的に挿し芽で増やしていきます。茎の先端と葉を3、4枚残した状態で花と下葉をとり、肥料をまいていない水はけの良い用土にさしておきます。1か月ほどすれば鉢植えに移植することができるようになります。種付けはもちろんできますが、種付けよりも挿し芽をするほうが容易ですから、増やす目的ということであれば種付けよりもこちらがオススメです。
種を作りたい場合は他の植物同様に花が枯れるのを待って種付けされたか確認してみると良いでしょう。エラチオールベコニアはどんどん新しい品種が出てきていますが、かなり新しい品種にセントレア・イエローというものがあります。この品種は鮮やかな黄色をしていて愛知県を中心としたごくわずかな農家でしか作っていないのです。
2010年に作られた比較的新しい品種にはバラのようにゴージャスなアンジェリカというものもありますし、またかなり大人っぽくシックな品種にアール・ヌーヴォーというものがあります。くすんだ赤色をしていて本当に美しいです。また希少種ということであればジャンヌ・ダルクという薄いピンク色の花を咲かせるものがあります。
品種の名前には外国の女性名がつけられることが多いようです。他にもペギーやルイーズ、クリスティンなどもあります。鮮やかなオレンジ色をしている花が咲くルネッサンス・フローラは贈り物にも喜ばれます。
エラチオールベコニアの歴史
エラチオールベコニアはシュウカイドウ科ベコニア属です。球根ベコニアとベコニア・ソコトラナを交配させてできたのがエラチオールベコニアなので、19世紀後半にイギリスで誕生しました。交配したのはヴィーチ社のジョン・ヒール氏です。エラチオールという名がつけられたのは1909年のことで、ラテン語で背の高いという意味があります。
これはエラチオールベコニアが茎が立ち上がる品種であるからです。これをさらに品種改良したものにリーガースベコニアというものがあります。旧西ドイツの種苗家であるオットー・リーガー氏が作り出したもので、現在ではほとんど同じものとして扱われています。このリーガー氏が品種改良する前はそれほど強い品種ではなかったのですが、現在では病気や暑さにも比較的強い植物として人気が出ています。
日本国内の渡来したのは1960年代のことでした。それ以来、リーガースベコニアやエラチオールベコニア両方の呼び名で市場に出回っていますが、徐々にエラチオールベコニアの名で流通するようになるのではないかとの見方が強まってきています。冬の室内でも花を咲かせているので冬の花というイメージがついていますが、意外にも寒さには弱いのです。原産は熱帯や亜熱帯地方です。
エラチオールベコニアの特徴
豊かな花の色と半八重や八重咲きが主なものになっています。色はピンクや白、赤、オレンジ、黄色などがあります。草丈は10cmから40cmほどで、9月から翌年の6月くらいまではきれいな花を咲かせます。属名であるベコニアはフランス領アンティル諸島の総督であり、植物採集者のミシェル・ベゴンが由来となっています。
小形で花もたくさん咲くことから鉢植えとしてよく園芸店などで売られています。1年の1日1日に花をあてはめてある花カレンダーがありますが、エラチオールベコニアはその中で11月11日の花になっています。多年草であることから室内で育てる花としてはとても人気があります。ちなみに花の直径は5cmから10cmほどです。
室内で育てる場合は常に温度が一定であるほうがベストで、日当たりの良い場所を選んで置いてあげるといいです。生息地は原種は南米の亜熱帯地域になります。現在では改良がいろいろされて品種もとても増えてきています。花が落ちやすいとよく言われていますが、売っているものであればすでに花が落ちにくいように防止策をされていますので安心して育てることができます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:球根ベゴニアの育て方
タイトル:エラチオール・ベゴニアの育て方
タイトル:ベゴニア・センパフローレンスの育て方
タイトル:アガパンサスの育て方
タイトル:キリンソウの育て方
-

-
ハクチョウゲの育て方
ハクチョウゲの特徴は、何と言っても小さくて可愛らしい花を咲かせる事ではないでしょうか。生長が早い植物ですが、刈り込みもき...
-

-
ヒマラヤ・ハニーサックルの育て方
ヒマラヤ・ハニーサックルは、スイカズラ科スイカズラ属の植物です。落葉性の低木です。原産はヒマラヤ山脈で、中国西部からチベ...
-

-
つるありいんげんの育て方
インゲンは17000種に及ぶ植物、多くの渡り鳥の生息地で知られる中米原産です。スペイン人によりヨーロッパに持ち帰られたの...
-

-
アナガリスの育て方
ギリシア語で「楽しむ」や「笑う」を意味する言葉、「アナゲラオ」が名前の由来といわれているアナガリスは、スペインやポルトガ...
-

-
セルリア・フロリダの育て方
”セルリア・フロリダ”は南アフリカケープ地方が原産の植物になります。日本にはオーストラリアから切り花として入ってきた植物...
-

-
フェニックス(Phoenix)の育て方
フェニックスは暖かい地域の植物だと言うことを頭に入れておかなければなりません。ですから、植え付けは5月から7月くらいに行...
-

-
上手な植物の栽培方法
私たちが普段生活している場所では、意識しないうちに何か殺風景だなとか、ごちゃごちゃ物がちらかっているなとかいう、いわゆる...
-

-
ティアレアの育て方
北アメリカを生息地とする植物です。ウェリー種やコルディフォリア種などを原点として様々な園芸品種が生み出されてきました。東...
-

-
バラ(ピュア)の育て方
その特徴といえば、たくさんありますが、特徴を挙げるとすれば、その香りが最大の特徴ではないかと考えられます。もし、いくら花...
-

-
植物栽培の楽しみ方について。
私たちは、身近に植物が生息しているのを知っています。いわゆる雑草は、育て方を教えなくても、年から年中、切っても切っても生...




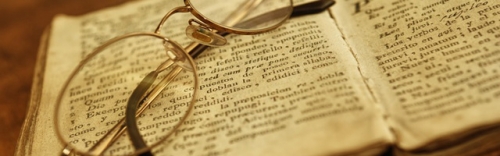





エラチオールベコニアのことをよく知って、育て方をしっかりと学んでおきましょう。栽培をする上ではマメに世話をしてあげることで長持ちします。エラチオールベコニアはシュウカイドウ科ベコニア属です。球根ベコニアとベコニア・ソコトラナを交配させてできたのがエラチオールベコニアなので、19世紀後半にイギリスで誕生しました。交配したのはヴィーチ社のジョン・ヒール氏です。エラチオールという名がつけられたのは1909年のことで、ラテン語で背の高いという意味があります。