ザクロの育て方

ザクロの育てる環境について
ザクロは比較的丈夫な樹木ですので、ガーデニング初心者でもそれほど大きな失敗をすることはほとんどありません。庭植えも鉢植えもできますが、日光を好みますので、いずれの場合でも日当たり良好な場所を選ぶとよいでしょう。どちらかというと、成長がはかばかしくないことに心配するよりも、
成長がよすぎて頻繁に選定しなければならないということもあります。また、風通しが良い場所であることも必要条件で、大きな建物などのそばや日陰になりやすい場所などに植えると、枝が徒長したり虫がつきやすくなるので気を付けましょう。乾燥にも寒さにも強い植物ですが、
湿度が高すぎると腐ったり虫がつくことがありますので、からりとした天気の地域がおすすめです。逆に、寒冷地で庭植えはあまりお勧めできません。鉢植えにして、冬場はなるべく凍らない場所に移動させたほうがよいでしょう。ただし、鉢植えでは庭植えほどの成長が望めずい、
開花や結実は難しくなりますので、枝ぶりの観賞用と割り切って育てることになります。用土は水はけと水もちがよいものであれば、特に土の種類も選びません。そのため、庭植えの時でも特別なものを用意する必要はありませんが、
市販の一般的な用土を用いる場合には、水はけを良くするために赤玉土の小粒を7~8、腐葉土を3~2で配合したものを用いるとよいでしょう。逆に、湿地や酸性の強い土壌は成長を妨げられますので、避けたほうがよいでしょう。
ザクロの種付けや水やり、肥料について
ザクロの植え付けに適しているのは、庭植え、鉢植え共に12~2月の間です。鉢植えをするときには、根詰まりを防いで通気を良くするために、基本的には2年に一度は植え替えを行うようにしましょう。ただし、現在の鉢の大きさやザクロの成長の度合いによっては、
すぐに鉢が小さくなってもっと頻繁に植え替えをしなければならなくなるケースもあります。水やりは比較的たっぷり与えるのがよく、鉢植えの場合には、表面の土が白く乾いてきたら底の穴から水が少し流れ出る程度にしっかり与えるようにしましょう。
庭植えの場合には、夏場にたっぷり水やりをして、枝をしっかり伸ばしておくと幼木が短時間で大きく成長します。秋から冬場には水やりの量はやや控えめにしますが、冬場にも水やりをする必要があります。肥料は3月と10月がおすすめですが、鉢植えの場合にはこれに加えて7月にも与えます。
鶏糞などの有機質肥料か速効性化成肥料などを使用しましょう。植えたときには元肥を施し、苗木を植えてから2~3年の間は肥料をこまめに与えることで、幼木が成長します。ただし、あまり肥料を与えすぎると枝が伸びすぎてしまい、
今度は剪定ばかりをしなければならなくなりますので、ほどほどにしておきましょう。枝が伸びすぎたからといって、あまりにも頻繁に剪定をしすぎると花付きが悪くなりますので、できれば剪定せずに済む程度に肥料を与え、成長の度合いを調整したほうがよいでしょう。
ザクロの増やし方や害虫について
ザクロを増やす方法は、2月中旬から3月下旬の休眠期に接ぎ木をしたり、3月上旬から中旬にかけて、挿し木をするのが一般的です。挿し木の場合には太い枝をさし穂にするのがよく、人の腕くらいの太さの枝を地面に打ち込んでおくと、よく根が広がります。
育て方と同様にそれほど難易度は高くありませんので、時期が来たら挑戦してみましょう。うまく根付いたら、あまり密集させずに適度なゆとりを持って植え替えましょう。害虫に関しても、繊細な植物に比べると比較的耐久性があり、それほど心配するものは見られません。
中でも、通常の植物では深刻な被害を引き起こす病害虫にもつよいため、特別に注意するものはありませんが、一般的な害虫であるアブラムシやカイガラムシがつくと花や果実が傷ついてしまいますので、これらに対しては防虫対策をしておいたほうがよいでしょう。
枝が茂ってきたら、選定で風通しを良くして日に当てることで、これらの害虫を防ぐことにもつながります。剪定する時期は葉が落ちた後の12~2月頃で、前年の枝先付近の数節に花芽が付きますので、切り詰め選定ではなく間引き剪定が主体となります。
枝がやや下垂するように整えることで結実しやすくなりますので、バランスを取りながら切っていきましょう。剪定をしなくても健康に育つ場合には何もせずに自然に任せるのがよいですが、必要となった場合には、株元から芽がたくさん伸びやすいため、大きくならないうちに早めに除きましょう。
ザクロの歴史
ザクロの歴史は非常に古く、古代ギリシャの医学書では、すでにザクロの効能が書かれていました。また、パピルスに記されているエジプトの医学書、中国の漢方書、インド最古の医学書であるアーユルヴィーダなど、文明の発達している地域を中心として、古代からその効能は高く評価されていました。
当時からこの植物は薬効が高く、希少な果物とされており、種子を飲んだり身を食べたり、皮を食べたりと様々な使い方がされていました。日本にも中国からその有用性が伝えられており、本草の書物に多数扱い方や効用などについて書かれています。旧約聖書では、
この植物は人類の文明とともにあり、一説にはアダムとイヴが追放された楽園のエデンの園には、リンゴやブドウ、ナツメヤシ、イチジクなどと共にザクロが栽培されていたといわれています。子孫繁栄や男女の愛の象徴、知識の木とも言われており、やはり貴い存在であったことがうかがわれます。
医学書や聖書、経典などに掲載されているだけでなく、王家や一家一族の繁栄の象徴としても扱われており、果実や木をモチーフとした発掘品も多数見つかっていますし、縁起物としても取り扱われていました。このように、効能や種子の多い見た目などから、
歴史や文明とも深く結びついていたことが明らかになっています。原産地はイランやアフガニスタンなどで、イラン周辺では有史以前から栽培されていました。樹齢200年を超えても果実をつけることから、代々大切に引き継がれています。
ザクロの特徴
ザクロの特徴としては、落葉樹になる果実であり、生息地が多く、世界各地で栽培されているということが挙げられます。日本でも東北以南の各地で栽培されていますが、どちらかというと食用としてよりは、観賞用や薬として栽培されてきました。
一方、海外では果汁や果肉を飲み物や料理に使用していることが多く、この違いは国産品が酸味が強いものが多いのに対し、海外で栽培されている品種は甘味が強く、調理に使用しやすいものが多いことも一因となっています。現在スーパーなどで販売されている果物としても果実は、
ほとんどが海外から輸入したものになっていますし、販売用として栽培をしている農家は国内では見られなくなっています。したがって、国内では家庭で鑑賞を兼ねて育てることが多く、種類は通常のもの以外にも、果実が小さいタイプも流通しています。
開花や結実がやや難しい植物ですが、栽培自体は比較的簡単で、無農薬でも育てることができます。ただし、果実に虫がつくこともありますので、薬剤散布や袋かけはしておいたほうがよいでしょう。幹は褐色でこぶ状の突起があり、古木になってくるとその突起が、
樹齢の長さと相まって味わいのある形になってきます。なお、枝には多くのとげがありますので選定するときなどは注意が必要です。花は新しい枝に鮮やかな朱赤色が美しく、たくさんある雄しべの周りに花弁が取り囲んでいる形になります。基本種は6枚の花弁ですが、八重咲きの花もあります。
果樹の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:スターフルーツの育て方
-

-
ユーフォルビア(‘ダイアモンド・フロスト’など)の育て方
ユーフォルビア‘ダイアモンド・フロスト’などは小さな白い花のようなものが沢山付きます。だからきれいで寄せ植えなどに最適な...
-

-
ドウダンツツジの育て方
ドウダンツツジは、かわいらしいふっくらとした見た目の花をつける植物で、灯台躑躅、または満天星躑躅と書くのだか、その漢字の...
-

-
オリヅルランの育て方
オリヅルランはユリ科オリヅルラン属の常緑多年草で、初心者にも手軽に育てられるため観葉植物として高い人気を誇っています。生...
-

-
エンレイソウの育て方
エンレイソウは、ユリ科のエンレイソウ属に属する多年草です。タチアオイとも呼ばれています。またエンレイソウと呼ぶ時には、エ...
-

-
マルバノキの育て方
木の種類としては、マンサク科、マルバノキ属となっています。別の名称としてベニマンサクと呼ばれています。園芸分類としては庭...
-

-
芝桜の育て方
たくさん増えると小さな花がまるで絨毯のように見えることから公園などにも植えられることが多い芝桜は北アメリカ東海岸が原産で...
-

-
プチアスターの育て方
キク科カリステフ属のプチアスターというこの花は、中国北部やシベリアを原産国とし1731年頃に世界に渡ったと言われておりま...
-

-
チャイブの育て方
チャイブは5000年ほど前から中国で食用として利用されたことが記録として残っています。料理としてのレシピも紀元前1000...
-

-
ナスタチウムの育て方について
鮮やかなオレンジや黄色の花をたくさん咲かせるナスタチウムは、ハーブの一種に分類される植物です。ハーブと言えば、花が咲いた...
-

-
イワギボウシの育て方
名の由来として、日本の昔の木造の付ける欄干や橋寺社などの手すりには飾りがあり、この欄干の先端にある飾りのことを擬宝珠と呼...




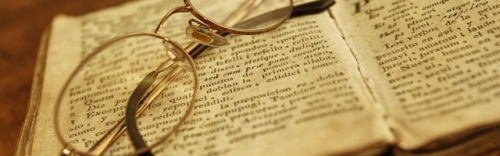





ザクロの歴史は非常に古く、古代ギリシャの医学書では、すでにザクロの効能が書かれていました。また、パピルスに記されているエジプトの医学書、中国の漢方書、インド最古の医学書であるアーユルヴィーダなど、文明の発達している地域を中心として、古代からその効能は高く評価されていました。