ペニセタムの育て方

育てる環境について
栽培をする場合においては、育て方に適した環境に合わせます。日当たりを風通しを好む植物になります。更に水はけも良い所が好まれます。冬に弱いので冬の対策をしっかりしておく必要があります。この植物において、あまり株が大きいと冬越しが難しくなるとされています。小さい株の場合はある程度冬の対応ができるとされます。
このことから、冬の前に株分けをする方法が取られることがあります。そうすれば越すことができます。あまり寒くなる直前で株分けしてしまうと根がまだついていない状態になり傷んでしまうことがありますが、秋に入った時ぐらいに行っておけばなんとか冬前には根の方もしっかりとついてくるでしょう。
そのような状態であれば問題なく冬を越せるようになります。日照不足を避けるように心がけるようにします。日照不足になると葉色が薄くなってしまうことがあります。元々それ程濃いわけでは無いですが、しっかりとした色がついていることで美しさを出す植物でもあります。
赤いタイプの場合には、日当たりが悪いために緑のままになったり、徒長したりすることがあります。花が咲かないこともあります。イネ類の花は咲いた時にはきれいになるので、花が咲かないのは非常に寂しくなるでしょう。そのためにも日当たりには気をつけるようにします。乾いているところに関してはそれ程問題は発生しません。乾いているところをより好むことがあります。ジメジメしたところは避けます。
種付けや水やり、肥料について
用土の調整においては通気性のある土を用意します。市販の草花用培養土を用いる場合があります。自分で調整をするときには、赤玉土6割、腐葉土3割、軽石1を1割いれます。軽石の代わりにパーライトを入れることもあります。こうすればそれなりに水はけ、通気性の良い土を作ることができます。
水やりに関しては夏にしっかりと行い、冬はあまり行わないのが基本の流れになります。秋になってくると徐々に気温が低下してきます。その時に水やりの回数を減らすようにしていきます。夏は1日2回や毎日していたなら、秋は2日に1回、3日に1回などにしていきます。
雨との関係もありますから、雨が降ったなら更に回数を減らすこともあります。冬に水が含んだ状態になるのは致命的なことがあります。水自体よりもその後に凍ってしまうことがあります。それを避けなければいけません。庭植えで行うときには水やりについてはあまり必要ないともされています。
夏に日照りが続いてカラカラ状態で植物の様子もぐったりしているようであれば水をあげるようにします。なぜ庭に水が不要かといえば、しっかりと根を張っていくタイプの植物だからです。肥料についてはあげなくても良いくらいです。
自生においては痩せた土地でもしっかりと育つとされています。肥料を与えるとしたら春に緩効性のタイプの肥料を与えるようにします。鉢植えにおいては春と秋の生育期を狙って施すようにするとちょうどよいかもしれません。
増やし方や害虫について
植え付け、植替えに関しては4月から6月にかけて行います。根鉢を崩して、大きめの植木鉢を利用します。そうしないとどんどん大きくなるからです。鉢の中が根でいっぱいになってしまうことがあります。増やし方としては株分けを行います。行うタイミングは、春の植え替え時に行うことがあります。
大株になってくると非常に硬くなるので人の手などでは簡単には分けられないくらいになっていることがあります。この時の方法としては、スコップを使います。株の中央部分にざっくりとスコップをいれます。デリケートな植物になるとこんなに大胆な方法を取ることはできないかもしれませんが、
そこまでデリケートではありません。多少根の部分が傷ついたからといって問題になることはありません。増やす目的でない株分けを秋ごろにすることがあります。これは大きすぎると冬越しができないことがあります。冬越しのための株分けですが、結果としてそれによって増えることがあります。春の株分けのほうがうまくいくことが多くなります。
株分け以外の方法では種まきがあります。花が夏に咲き、秋に種を取ることができます。更には種については市販されていますからそれを利用して増やすことが出来る場合があります。種まきとして良いのは3月下旬から4月ですからちょうどさくらの咲く時期頃になります。それに合わせてまくことを覚えておきます。病気や害虫に関してはほとんど問題がない植物になります。
ペニセタムの歴史
日本の主食としては米があります。いろいろな種類がありますが、それらは品種改良により生まれたものになります。お米に関しては日本では日本のものがメインで売られていますが、世界においてもたくさんあります。アメリカにおいてカリフォルニア米、アジアではタイ米などが知られています。
韓国は日本と同じようにお米を炊いて食べますから、非常に近い食文化と言えるかもしれません。お米に関してはイネ科に属することになります。このイネ科の植物としてあるのがペニセタムと呼ばれる植物になります。いくつかの言われ方があり、ペンニセツム、ぺニセツムと言われることもあります。
原産は熱帯地方とされていて、流通する種類の多くにおいてはアフリカ産と言われています。雰囲気としてはイネよりもすすきであったりパンパスグラスのようにも見えます。花であったり花の部分よりも、風にそよぐ様子、その時の音などが良い雰囲気を与えるとされています。ベニとの名前がついていることから赤いイメージがあるかもしれません。
確かに赤っぽいものもあるようですが、それが名前の由来ではありません。ギリシア語から来ていて、ペンナが羽を意味します。セタとは剛毛となります。穂が剛毛に覆われている姿としてこの名前が付けられたとされています。日本においても、その他の花などと合わせることでアクセント的な存在になることがあるようです。庭などにこれがあると、他の部分と分けるときに便利そうです。
ペニセタムの特徴
特徴としては、イネ科、ベニセタム属、チカラシバ属とされています。園芸品として売られるときはグラスと分類されることがあるようです。形態としては基本的には多年草です。ただし熱帯の植物なので日本では一年草として管理されることが多いようです。草の大きさとしては30センチぐらいから150センチぐらいまでです。
耐暑性はそれなりにあります。生息地が熱帯あたりになるからこれはだいたい分かるでしょう。しかし寒さにおいてはあまり強い植物ではありません。耐寒性があまりなく、寒さでやられるために冬を越すことができないタイプがあります。使われる用途としてはカラーリーフが多くなるようです。
その他草類を中心としたグラスガーデンをつくろうとするときもこれを入れることが多くなります。冬に弱い種類もありますが、別のタイプになるとそれなりに耐寒性を持っているものもあるので、少しずつ寒さに弱いもので確かめるようにするといいかもしれません。日本に自生する種類としてはチカラシバがあります。
日本ではすっかり雑草として扱われてしまっていますが、海外においては観賞用として利用されることがあります。セタケウムルブラムは赤みがかかった種類です。通常のイネ科のグラスとは少し雰囲気が異なり、色合いを入れるのであればこちらを加える必要があるでしょう。きれいな白い羽毛状のタイプとしてはヴィロムスがあります。銀狐とも呼ばれるもので、こちらも雰囲気を良くしてくれます。
-

-
ソラマメの育て方
世界で最も古い農作物の一つといわれています。生息地といえば例えば、チグリス・ユーフラテス川の流域では新石器時代から栽培さ...
-

-
ハーブを種から巻いて大きくしよう
ハーブは日本語で香草といい、ハーブの種類によって香りの高いものなど様々あります。料理やハーブティーに使えてとても利用効果...
-

-
セキショウの育て方
元々はサトイモ科に属していました。しかし実際の姿とサトイモの姿とを想像してみても分かる様に、全くサトイモとは性質が違いま...
-

-
植物の栽培や育て方の知識と体験
植物の育て方について、十分な知識を持った上で栽培するのがオーソドックスな方法です。この方法だと、失敗が少なくなります。本...
-

-
クロバナロウバイの育て方
クロバナロウバイは北アメリカ南東部原産の低木で、原産地全域の山林や人里周辺を生息地としています。漢字では黒花蝋梅と書き表...
-

-
グラプトペタラムの育て方
グラプトペタラムは様々な品種があり日本ではアロエやサボテンの仲間として扱われることが多く、多肉植物の愛好家の間でとても人...
-

-
オーブリエタの育て方
オーブリエタとは、アブラナ科オーブリエタ属に類する多年草です。多年草とは、毎年生息して育つ植物の事を言います。いわば土の...
-

-
トウヒの仲間の育て方
トウヒはマツ科に属する樹木であり、漢字で表すと唐檜と書き表されます。漢字の由来から日本には、飛鳥時代~平安時代現在の中国...
-

-
モクレンの育て方
中国南西部が原産地である”モクレン”。日本が原産地だと思っている人も多くいますが実は中国が原産地になります。また中国や日...
-

-
ルピナスの育て方
特徴の1つは寒さに強く、暑さに弱い事があります。具体的には寒さであればマイナス5℃程度まで耐えられます。外に置いておいて...




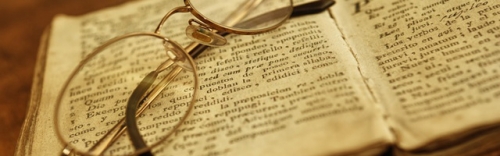





お米に関してはイネ科に属することになります。このイネ科の植物としてあるのがペニセタムと呼ばれる植物になります。いくつかの言われ方があり、ペンニセツム、ぺニセツムと言われることもあります。