アークトチスの育て方

アークトチスの種付け
秋に種付けをして、春から初夏にかけて花を楽しむのが一般的ですが、寒冷地の場合は冬を超えた後の暖かくなってきたころに種付けをすると初夏には花を楽しむことができます。暖地の場合は春まきにすると花が咲くまでに高温多湿になるために弱ってしまうので、できるだけ秋まきにします。
水はけの良い土であればどのような土でも大丈夫です。水はけが悪いと茎が間延びしてしまうのです。種をまいたら土を5mmくらい被せておくと種付けが完了です。その後は乾燥しないように水やりを行います。
種付け時のポイントとして、種は綿毛に覆われているので湿った布などに包んでよくもんでからまくようにすると発芽しやすくなります。そして発芽の適温は20度前後です。その後本葉が3枚か4枚になれば植え替えをします。植え替えは65㎝くらいのプランターなら3個くらいの苗を植えるのが目安です。
植え替えの際、まだ根がしっかりとついていない可能性があったり、直根性で太い根が傷つくと生育不良を起こすこともあるので、土を落とさず崩さないように植え替えるようにします。だから庭に植えた場合には移植はしない方が良いでしょう。寒さの厳しい地域での植え替え、定植は霜の当たらないところにおいて春になってから行うようにします。
アークトチスの栽培法
アークトチスは水をやりすぎると草って枯れてしまうのですが、やるときにはたっぷりとやるようにします。土を触ってみて乾いていたら水やりのタイミングです。夏の間は雨が降らなければ朝夕上げるとよいでしょう。
しかし冬の間は土はなかなか乾かないのでほとんど水やりの必要はありませんが、地域や気候によって異なるので土を触ってみて頃合いを確かめる必要があります。アークトチスは花が咲きだすと次々と開花し、栄養がたっぷり必要になります。
花が咲きだしたら液肥を1週間に1回くらい与えるようにします。それからハモグリバエという害虫がつくことがあります。予防をする薬剤を事前に撒いておくと発生を防ぐことができます。
アークトチスの上手な育て方
日当りを好むのでアークトスを栽培するときにはできるだけ日に当てるようにします。日陰や半日陰の場所では花付きが悪くなってしまうのでたくさん元気な花を咲かせるためには日に当てることが育て方のポイントです。
ただ夏を超えさせるときには直射日光には当てないで風通しの良い涼しいところに移動させるようにします。冬の間は霜よけが必要です。蒸れないようにトンネルを被せたりして霜よけをします。グランティスだけはマイナス12度まで耐えられるのですが、それ以外の品種は半耐寒性のものが多く、霜には弱いことも多いのです。
アークトチスの花が咲いてきたら次々と咲くのですが、そのころにはスタミナ不足にならないように肥料を追加してやることも必要になってきます。そして咲き終わった花柄は摘み取るようにします。
その際は節から折れやすいので、はさみで丁寧に摘みましょう。また茎が伸び過ぎた時には切り戻しをすることでまた新しい芽が出てきてきれいな茎が成長してきます。株の形が悪い時やもっと花を楽しみたい時には切り戻しをすることも上手な育て方のポイントです。
アークトチスの利用法
水はけの良い土を用い、よく日が当たり風通しの良いところで栽培し、土が乾いたらたっぷりと水やりを士、花が咲きはじめたら肥料を多い目に与えていくことを育て方のポイントとして栽培をすれば長期にわたって花を楽しませてくれます。
庭の土で育ててもよいのですが、季節や気候によって日の当たるところや涼しいところ、霜の当たらないところなどに移動させたりすることを考えれば、鉢やプランターなどに植えるほうが良いでしょう。
そして寄せ植えに利用することも多いです。植え替えの際も根の部分を崩したり、傷つけないように丁寧に植え替えをします。アークトチスがやや乾燥気味に育てるので、同じように乾燥気味に育てる植物と一緒に寄せ植えをするとよいでしょう。またアークトチスはカラフルな花が多いので、淡い色の花と組み合わせるのもよいでしょう。
また草丈の高い品種のアークトチスなら切り花として室内で飾っておいてもきれいです。室内で飾っていても明るい時にはひらき暗くなるとしぼむのです。このようにアークトチスの育て方はそれほど難しいものではなく、寄せ植えや切り花としても楽しむことができます。
最近はいろいろな品種が交配された交雑種がたくさん出回っています。グランティスは寒さに強く他の品種はそれほど強くはないのですが、たとえばグランティスと他の品種のものが交配されたことによって寒さに強い品種がたくさんできていくということもあります。
同じアークトチスでも品種によって性質が違ってくるものもあるので育て方が変わってくることもありますが、高温多湿に弱いので日当りは必要ですは加湿にはならないようにすることを念頭に置いて栽培すればよいでしょう。
アークトチスの歴史
南アフリカ、熱帯アフリカを原産地とし、そこにはおよそ65種類ものアークトチスが分布しています。その中でも日本に初めて入ってきたのはグランティスという品種のもので昭和の初期に渡来してきたといわれています。
花弁が白で中心部が青の品種ですが、現在もよく寄せ植えなどに利用されています。またアカウリスという品種のアークトチスも入ってきていて、カラフルな花の色なので園芸品種としてよく栽培されています。
アークトチスの特徴
南アフリカでは多年草とされていますが、日本は高温多湿な夏には枯れてしまうことが多く、一年草扱いをされています。もともと一年草の品種もあります。キク科の植物で、一重のガーベラによく似た花が咲きます。別名はハゴロモギクと言います。
開花の時期は4月から7月ごろです。種は秋か春に撒いて育てます。草丈は品種によっても違いますが20cmから70㎝くらいで、その先端に5cmから10cmくらいの大きさの花を一輪咲かせます。開花の時期には何本も花茎を出すので、長期間花を楽しむことができますが、花は明るい日中は開いていて暗い雨の日や夜は閉じているという特徴があります。
葉は細長く野や肉厚で、キクの葉のように切れ込みが入っています。また葉には毛が生えています。もともとアークトチスは南アフリカが原産で寒さには弱いのですが、耐寒性のある植物と掛け合わせた品種が多く出回っているので半耐寒性といえます。
霜にあたらなければ大丈夫なので、秋に種をまいた場合には寒さが厳しくなる前に十分根を張らせ、霜よけをするとよいでしょう。暖地では種は秋まきにし、寒冷地では春に撒くのが良いでしょう。
それよりも真夏の暑さが苦手なので風通しが良く涼しい場所で管理をするようにします。暑さは苦手ですが、生息地の南アフリカでは多年性の植物とされているので必ず枯れるという訳ではありません。暑さを避けてうまく管理をすると夏越えができる可能性もあります。
日当りが良く風通しの良いところで管理し、蒸れないようにしてやや乾燥気味に育てるようにします。グランティス葉白い花の中心部に青い色があるので、花言葉は「若き日の想い出」とされています。
そんなグランティスや色とりどりでカラフルな品種を栽培してみて春から夏にかけて庭を鮮やかに彩ってみるとよいでしょう。一輪一輪の花の命は長くはないのですが、次々と花が咲くので長期にわたって楽しむことができます。
花の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ティアレアの育て方
タイトル:ガザニアの育て方
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ガーベラの育て方
-

-
コリアンダーの育て方
地中海東部原産で、各地で古くから食用とされてきました。その歴史は古く、古代ローマの博物学者プリニウスの博物誌には、最も良...
-

-
レモン類の育て方
レモンと言えば黄色くて酸っぱいフルーツです。レモン類には、ライムやシトロンなどがあります。ミカン科、ミカン属になっており...
-

-
カラント類の育て方
カラント類は、ヨーロッパが原産です。フサスグリ全般のことをトータルで、英語ではカラントと呼んでいます。カラント類は真っ赤...
-

-
ゴンズイの育て方
この植物はミツバウツギ科の植物で、落葉樹でもあり、樹高は3メートルから6メートルぐらいということです。庭木としても見栄え...
-

-
クロッサンドラの育て方
クロッサンドラは、促音を抜いたクロサンドラとしても呼ばれ、その名前の由来はギリシャ語で房飾りを意味する「Krossos」...
-

-
ひめゆずりはの育て方
この植物は被子植物で真正双子葉類となります。その中でもコア真正双子葉類にも該当します。ユキノシタ目、ユズリハ科、ユズリハ...
-

-
ミムラスの育て方
種類としてはゴマノハグサ科、ミムラス属となっています。園芸分類としては草花として扱われます。生息地においては多年草として...
-

-
ムスカリの育て方
ムスカリは、ユリ科ムスカリ属の球根植物で、ヒヤシンスの近縁とも言える植物です。約30~50ほどの品種があるといわれ、その...
-

-
オニバスの育て方
本州、四国、九州の湖沼や河川を生息地とするスイレン科オニバス属の一年生の水草です。学名をEuryaleferoxと言いま...
-

-
ブライダルベールの育て方
ブライダルベールは吊り下げるタイプの観葉植物が流行した昭和50年代に日本に登場しました。英語での名称は「タヒチアンブライ...





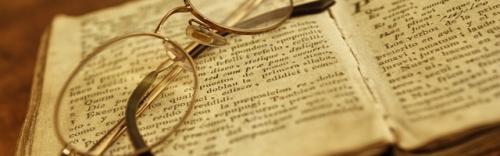





南アフリカ、熱帯アフリカを原産地とし、そこにはおよそ65種類ものアークトチスが分布しています。その中でも日本に初めて入ってきたのはグランティスという品種のもので昭和の初期に渡来してきたといわれています。