スモモの育て方

スモモの自家不和合成
スモモは育ちやすさが異なり、育てやすいものもあれば育てるのが難しいものもありますから、まず品種を選ぶことが必要です。たとえば、太陽や大石早生は、比較的育てやすい品種です。ただ、自家不和剛性が高いと言うことは頭に入れておかなければなりません。
自家不和合成とは、自分の花粉では受粉しないことを指します。受粉しませんから、それによって結実することはありません。これは何のためにあるのかと申しますと、遺伝子の多様性を確保するためだと考えられます。詳細は省きますが、動物にしても植物にしても、多様性が確保されているものは環境が変化しても生き残りやすいという特徴があるため、自分の花粉を受粉しない仕組みを作り上げたわけです。
これがスモモの育て方で最も注意する点だと言えるでしょう。ただ、この程度は品種によって異なっています。スモモを種付けから行う人は少ないと思いますが、もしも種付けから行うことができれば自家不和合成の傾向は小さくなると考えられます。
というのも、種の遺伝子型は基本的には異なりますから、種付によって得られたものと、別の種付けによって得られたものとでは品種が異なり、受粉しやすいからです。自然の中では種付けが行われることで受粉できるようになっているのです。
植えるときには品種を選ぼう
スモモには自家不和合成の高い品種もありますから、栽培するときには注意しなければなりません。具体的にはどうすれば良いのかというと、複数の品種を植えるのが良いです。花粉を出すために別の品種のスモモを植えるのが育て方の基本です。ですから、2本は植えなければならないと考えておいた方が良く、これを忘れるとなかなか結実しないといった状況が長く続くことになるでしょう。
ただ、この程度は品種によって異なりますから、複数を植えることのできない場合には、育て方の簡単な品種を栽培するのが良い方法です。自家不和合成の程度は品種によって異なっていて、どうしても1本しか植えることができない場合には、自家不和剛性の低い品種を選ぶのが良いです。たとえば、サンタローザやメスレーは、1本だけで植えても結実しやすい傾向があります。
受粉樹の選び方も把握しておく必要があって、異なるものを植えれば良いというものではありません。たとえば、メスレーはビューティーやソルダムとの相性が悪いですから、組み合わせても結実しない可能性が高くなりますから育て方には注意が必要です。もしも栽培できるスペースが非常に広いのであれば、様々な品種を近くに植えるというのは良い方法です。
こうすることによってそれぞれが受粉樹となりますから、自家不和剛性の低いスモモの栽培方法として果て来ていると考えられます。なお、鉢で育てることもできます。10号くらいの鉢でも結実するくらいまでに育ちますから、スペースが小さい場合にはこのような方法をとるのも良い方法です。
この場合に注意しなければならないのが水やりです。特に夏の暑い時期には水分が不足しがちで、この時期に水分が不足すると成長が遅くなってしまいます。できることなら1日に2回くらい水やりをするべきでしょう。それ以外の時期には、土の表面が乾くくらいになれば水やりをするくらいで十分で、やりすぎるのは良くありません。
スモモの育て方のコツ
スモモに限ったことではありませんが、受粉がうまくいかないと結実しませんし、受粉がうまくいくとたくさんの実ができます。受粉がうまくいかないのも問題なのですが、うまくいきすぎるのもの代です。もしも果実が増えすぎると、株自体の負担が非常に大きくなってしまい、養分を果実で取り合うことになります。その結果、小さい果実がたくさんできるという状況になってしまいます。
これを防ぐためには、間引くのが良いです。小さい果実ができたときに、少しずつ間引いていきます。開花してから1ヶ月くらいが敵下地木田です。この際、収穫のことなども考えておくのが良いです。たとえば、枝の上に伸びているものは収穫しにくいですし傷つきやすいという特徴がありますから、これは間引く対象にしましょう。虫に食われたものもこの時点で取り除いておくのが良いです。
間引きは2回くらいにわけて行うのが良くて、最初は上向きのものや虫食いのものだけを取り除くようにするのが良いです。そして、2回目くらいで、10センチから15センチ間隔になるように間引いていくのが良いです。スモモの花芽形成は8月から9月頃です。この時期は成長する時期でもあるのですが、栄養が多すぎると枝の伸張が促進されますから、花芽形成が抑えられる傾向があります。
そのために、身が少なくなってしまう可能性があるわけです。そうならないようにするためには、8月から9月の時点での肥料を少なくすることが重要です。特に、窒素が多いと成長が早くなる傾向がありますから注意が必要です。
スモモの歴史
スモモにはいくつかの種類があり、日本、ヨーロッパ、アメリカの3つに分類されます。ヨーロッパではカスピ海沿岸が生息地だったと考えられていて、すでにローマ帝国の時代には栽培されていたそうです。カスピ海のコーカサス地方が原産のものがヨーロッパに広がり、そしてそれがアメリカにも広がることになります。一般的にプルーンと呼ばれるものはこのようにしてアメリカに渡ったものです。
日本で栽培されているものは、元々の生息地は中国だったと考えられています。中国でも栽培は行われていて、それが奈良時代に日本へ伝えられたと考えられます。栽培が行われるようになったのは明治時代になってからですが、その当時はそれほど重要なものとは考えられていませんでした。酸っぱい桃という意味でスモモと名付けられたことからも分かるように、メジャーな果物ではなかったそうです。
これが大正時代に入ると本格的に栽培されるようになります。日本からアメリカに渡ったものがアメリカで品種改良され、それが日本に再びやってきます。これが現在栽培されているスモモの起源ですから、つまり一度アメリカに行って帰ってきたものが現在の日本のスモモなのです。
スモモの特徴
スモモは貼るに白い花の咲く植物で、花芽文化は7月から8月頃です。この時期に花芽ができますから、その後に強剪定を行うと花芽を飛ばしてしみ合うことにもなりかねませんから注意が必要です。6月から8月頃に収穫するのが一般的ですが、プルーンの系統のは9月頃に収穫します。
果肉は薄黄色から赤みがかった色のものが多くいですが、品種によって異なります。大石早生やソルダム、サンタローザ、メスレーなどが有名ですが、新しいものもいくつも作られていて、月光や秋姫などがあります。かつては酸っぱさが強いためにスモモと名付けられたのですが、新しいものは従来のものよりも甘みが強くなるように改良され、そのままでも食べられるようになっています。
自家不和合成が強いのも特徴の一つです。つまり、自分の花粉では結実しにくいという特徴があるために、受粉樹が必要となりいます。最近では梅や桃などの花粉を利用して人工授粉をすることもあります。これは梅や桃がどちらも近縁の種で、バラ科サクラ属の植物だからです。相性が良い受粉樹がないと結実しにくく、また霜がつくと結実しにくいという特徴もありますから、晩霜にあわない地域が栽培に適しています。
果樹の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:ネクタリンの育て方
タイトル:アンズの育て方
タイトル:桃の育て方
タイトル:キウイフルーツの育て方
タイトル:ロウバイの育て方
-

-
チシマギキョウの育て方
チシマギキョウは、キキョウ科ホタルブクロ属に属している多年草のことを言います。キキョウ科は、真正双子葉植物の科で大部分が...
-

-
パキラの育て方について
大鉢仕立てにすることもできれば、手のひらサイズのミニ観葉に仕立てることもできるので、いろいろな場所で目にすることができま...
-

-
ニシキウツギの育て方
ここでは、「ニシギウツギ」の特徴について、いくつかピックアップして書いていきます。ご参考程度にご覧いただけますと幸いでご...
-

-
リトープスの育て方
この植物についてはハナミズナ科とされています。同じような種類としてメセンがあり、メセンの仲間としても知られています。園芸...
-

-
より落ち着いた雰囲気にするために 植物の育て方
観葉植物を部屋に飾っていると、なんとなく落ち着いた雰囲気になりますよね。私も以前、低い棚の上に飾っていましたが、飾ってい...
-

-
ジャノヒゲの育て方
ジャノヒゲはユリ科ジャノヒゲ属の多年草植物です。アジアが原産で、日本を含む東アジアに生息地が多く分布しています。亜熱帯気...
-

-
ミニゴボウの育て方
ミニゴボウにかぎらず、野菜の中で形の小さい種類のものは昔からあったのですが、あまり受け入れられてきませんでした。育ちが悪...
-

-
ヒアシンソイデスの育て方
ヒアシンソイデスはヨーロッパの南西部原産の多年草です。原産や主な生息地はヨーロッパ南西部ですが、様々な交配や品種改良が行...
-

-
球根ベゴニアの育て方
ベゴニアの原種は、オーストラリア大陸を除いたほぼ世界中の熱帯や亜熱帯地域に分布しています。ベゴニア自体は日本でも原種が存...
-

-
植物の栽培によるビジネス
農業の次世代化は、これまでの従来型の農業からの改革案として、農家離れによる休耕地をいかに活用していくか、食糧難に対応させ...




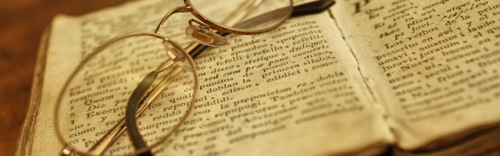





スモモにはいくつかの種類があり、日本、ヨーロッパ、アメリカの3つに分類されます。ヨーロッパではカスピ海沿岸が生息地だったと考えられていて、すでにローマ帝国の時代には栽培されていたそうです。カスピ海のコーカサス地方が原産のものがヨーロッパに広がり、そしてそれがアメリカにも広がることになります。一般的にプルーンと呼ばれるものはこのようにしてアメリカに渡ったものです。