ホワイトレースフラワーの育て方

育てる環境について
栽培するにあたって、育て方として必要な環境はどのようにしていくかです。乾燥しているところで育つ植物になるので、そういった環境を作る必要があります。夏は基本的には越すことができないとされているので、暑さに関しては諦めたほうがいいでしょう。日本でも北部の方などであれば夏を何とか越せることがあるかもしれません。
本州ぐらいだとなかなか越すのは難しくなるようです。良い環境としては、日当たりのいいところ、水はけのいいところになります。日当たりについては好むもののあまり暑すぎるのは問題になります。夏以外においては日が出ていたとしてもそれ程暑くならないでしょう。また湿度に関してもそれほど高くならないので問題は少ないかもしれません。
この花が枯れてしまうのが梅雨の時期とされています日本では北海道を除いて冬があります。高温多湿の状態です。これがあるかぎりは夏を越すことができないので、どうしても夏を越したいのであれば梅雨になる前に自宅などに入れるなどして対処することがあります。そうすることで多少は対応できる場合があります。
春にまく方法と秋にまく方法とがあるとされ、どちらのほうが良いかといえば秋まきになるようです。春にまくタイプだとどうしても夏を超えないといけません。ここで弱ってしまう場合があります。まいたあとの場合はその夏に枯れてしまうことはありませんが、どうしても花の付き方が減るので、注意しなければいけません。
種付けや水やり、肥料について
育てるときに土をどのようにしていくかですが、よく売られている草花用の培養土で十分とされています。土に関してはそれ程細かい制約を与えられているわけではありません。ただし水はけなどは適度に考える必要があるので、どうしても気になるのであれば自分で配合するのが勧められるでしょう。赤玉土が7割、腐葉土3割などの配合があります。
軽石を1割入れる方法などもありますので、成功した方法を使うようにします。日本列島は広いですから、必ずしもこの方法が良い答えは見つかりません。ある程度は参考にできることもありますが、細かい部分に関しては自分なりの方法を取っていく必要があります。そうしないとすべての地域でおなじになってしまいます。
水やりをどのようにするかですが、多湿状態はあまり好みません。そのため、あまり水をあげ過ぎたために根腐れしてしまう場合があります。この花については多湿は厳禁と頭に入れておきます。梅雨が苦手で梅雨と同時に枯れるとされますが、雨が多い時としては秋であったり春先などもあります。
雨が多くなりそうなときは事前に対応しておいたほうがよいでしょう。肥料については生育していく時にあげていくようにします。この時には途切れないように与えていくのがうまく成長させるコツになります。順調に育っているとそれで良いと考えてしまうことがありますが、それでは足りない場合もあります。液体肥料であれば与えやすいので便利です。
増やし方や害虫について
植え替えをすることができないので増やし方としては種まきが重要になります。種をいつどのように取るかですが、花が咲いて終わった時に取るようにします。この花においてはあまり古い種は発芽が悪くなってしまいます。よく種がとれた時のものを後に残すことがありますがあまり意味がありません。
その年にとれた種をその年の秋にまくなどするのが良いとされています。余った時においては残念ですが処分しないと使うことはできません。種まきとしていいのは9月から11月の秋です。この頃になると暑さも湿度も押しついてきますから、この花としては生育しやすい環境になっています。
春にもまくことができますが、この場合は夏を越す必要が出てくるので多少問題があります。できれば秋のうちにしてしまいます。9月にまくときの注意としては、湿らせた種を1週間ぐらい冷蔵することです。そしてその後にまきます。すると発芽が良くなるので何度か実験してみましょう。実感することができれば、それ以降は必ずその方法を取ることができます。
病気として出やすいのが立ち枯れ病になります。日当たりと水はけを良くすることでこの病気に関しては対応することが出来るとされています。しっかりと管理をするようにします。栽培場所を変えるなどすれば以前起きたところで病気になることはなくなります。害虫で出やすいのがハダニとアブラムシです。春頃に出てくることがあるので、出だしたら駆除します。
ホワイトレースフラワーの歴史
野菜の花においては白い花を咲かせるものが多いです。じゃがいもも白い花ですし、そばなどにおいても白い花を咲かせます。野菜などがメインになるのでその花のことを知ることはあまりないかもしれませんが、花が咲く時期にそれらを見ると結構きれいな様子を見ることが出来る場合があります。
常に見ることが出来るわけではないので、いつ花が咲く家などを調べておく必要があるでしょう。野菜などでなくても白い花を咲かせる植物はあります。白色がメインになる場合にはそれが花の名前になることがあります。非常にきれいな花の名前がついているものにホワイトレースフラワーがあります。
実際に咲いている様子を見ると、確かにホワイトレースで編まれたように見えることがあります。この花の原産、生息地としては地中海沿岸地方から西アジアにかけてとされています。気候としては暖かいところが原産になっているようです。空気としては乾燥気味のところになりそうです。日本においてはどのような名称がついているかですが、ドクゼリモドキとなっています。
まずセリとドクゼリとの植物があり、そのうちのドクゼリと呼ばれる植物に非常に似ているからそのように名付けられたようです。ドクゼリに関しては猛毒があるとのことで、非常に恐れられています。食用として知られるセリに似ていることから気をつけないといけないとされています。よく似ている植物に関しては、正確な知識を持って採取する必要があります。
ホワイトレースフラワーの特徴
この植物においてはセリ科になります。ドクゼリモドキ属となっています。宿根草ですから何年も花をつけることができますが、あまり夏に強くありません。日本の夏には弱いようで、夏になるとすっかり枯れてしまいます。そこで日本においては一年草として扱われています。日本の暑さに対して弱いわけなので、うまく育てることができればもう少し長く育てられることもあるようです。
挑戦してみても良いかもしれません。草の高さに関しては50センチぐらいから高いものになると2メートルぐらいになることもあります。一般的には1メートルぐらいの高さになるでしょう。花が咲く時期としては5月から6月ぐらいになります。耐寒性があるのでそれなりに冬に関しては対応できるようです。しかし夏はあまり強くありません。
高温多湿に弱いとされます。東南アジアや日本といいますと西アジアとはかなり気候が異なります。夏は気温が高く湿度も高くなります。この花としては非常に過ごしにくい状態になります。そのこともあって枯れてしまうことが多いです。花においては非常に小さい花がたくさん咲きます。
レース状に咲いていますが、一本の本の茎からたくさんの茎が別れ、更にその茎の先端に小さい花が咲く状態になっています。一つの茎を取ってみるとそれだけで花束のようになるくらいたくさんの花をつけていることもあります。葉っぱに関してはそれほど大きい物がついているわけではなく、細かくついているのみです。
-

-
長ネギの育て方
昔から和食をメインとしてきた日本にとって、長ネギは馴染みのある食材です。メインディッシュでバクバク食べるというより、添え...
-

-
月下美人の育て方
月下美人とは、メキシコを中心とした中南米を原産地とする多肉植物です。名前は、夜に咲き始めた美しい花が翌朝にはしぼんでしま...
-

-
オクラの栽培オクラの育て方オクラの種まきについて
オクラはプランターなどでも手軽に育てることが出来るということもあり、とても人気があります。オクラのの栽培やオクラの育て方...
-

-
スモモの育て方
スモモにはいくつかの種類があり、日本、ヨーロッパ、アメリカの3つに分類されます。ヨーロッパではカスピ海沿岸が生息地だった...
-

-
マルバストラムの育て方
特徴としてどのような属性になっているかです。名前としてはアオイに似ているとなっていますが、種類としては同じと考えられます...
-

-
ヒメノカリスの育て方
ヒメノカリスはヒガンバナ科の植物で原産地は北アメリカ南部や南アメリカで、日本では一般的には球根を春に植えると夏には白く美...
-

-
マクワウリの育て方
マクワウリと言えば、お盆のお供えには欠かせない野菜です。メロンの仲間で、中国や日本で古くから栽培されるようになりました。...
-

-
ガザニアの育て方
ガザニアはキク科ガザニア属で勲章菊という別名を持っています。ガザニアという名前はギリシャ人が語源とされており、ラテン語の...
-

-
鉢植え乾燥地帯原産地「パキラ」の栽培方法について
鉢植え「パキラ」は東急ハンズ等で購入できる乾燥地地帯である中東が原産地の鑑賞植物です。高さが5cm以下の小型の植物で、手...
-

-
プチヴェールの育て方
プチヴェールは、1990年に開発された、歴史の新しい野菜です。フランス語で「小さな緑」と意味の言葉です。アブラナ科である...




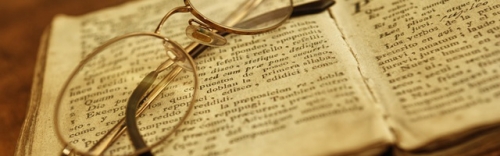





この植物においてはセリ科になります。ドクゼリモドキ属となっています。宿根草ですから何年も花をつけることができますが、あまり夏に強くありません。日本の夏には弱いようで、夏になるとすっかり枯れてしまいます。