ディクソニア(Dicksonia antarctica)の育て方

ディクソニアの栽培に適している場所
雪が降るような地域でも耐える強さを持っているので日本でも屋外での栽培が可能というメリットがあります。寒冷地では難しいケースもありますが、関東以南なら庭植えでもしっかりと育てることができます。
ただしディクソニアは本来10メートルもの大木になる性質がありますが、こうした雪が降るような地域では十分な大きさにはならないことがあります。静岡以西の場合かなり成長し大きな幹となるでしょう。
またこの植物は耐陰性があるため、観葉植物として室内栽培ができるのも特徴です。室内をエキゾチックな印象に演出できるので高い人気があります。一般的な鉢植えの他にも丸太状の幹を輸入して芽吹かせたものなどユニークな形状のものも流通しており自分らしく演出しながら育てることができます。
ディクソニアの育て方
ディクソニアは木性のシダ植物ですので種付けはできません。一般的には鉢植えとして販売されているものを購入して育てることができます。植え付けをする際には水はけのよい肥沃な用土を好みますので用土につぶ状の緩行性の肥料を混ぜてやると育成が良くなります。
用土1リットルあたりに5グラムの粒状肥料を混ぜて植え付けます。用土は赤玉土に腐葉土を混ぜたものやモスを混ぜ込んだものが良いでしょう。水はけを重視して用土を作らないと、根腐れしてしまうことがあるので要注意です。室内で栽培する場合にはレースのカーテン越しなど半日陰になる場所で育てるのが最適です。
弱い日光が安定して当たるような場所で最も育成が良くなります。また、夏の強い日光は葉焼けを起こしてしまう可能性があるので、真夏の時期には窓際を避けてさらに弱い日差しのもとで管理するのが安全です。水やりに関してはたっぷり上げるのが良いでしょう。
葉の上にも水が掛かるようにまんべんなくやることが必要です。エアコンや暖房設備の影響で葉がカサカサに乾いてしまっているケースがありますがこれでは葉が焼けてしまうことがあります。太い幹や新芽が出ている幹の上の成長点にも十分水やりをしましょう。
冬場に屋外に置いておくと葉がなくなり、一見枯れたように見えてしまいますが、こうした株に関しても暖かい日に時々水やりをしていれば春になるとまた芽吹いてきます。室内で栽培する場合には空気が乾燥しているので株元に水をたっぷり上げるのはもちろんのことですが、葉にも葉水をやって乾燥から守りましょう。
肥料に関しては最も育成が盛んな5月から10月に行うようにします。用土1リットル当たり5グラムの緩行性のつぶ状肥料を2ヶ月に一回の割合でばら撒きましょう。または2週間に1回程度即効性のある液体肥料を水やり替わりにやるのも効果的です。
冬越しに関しては寒さにはかなり強い植物ですので庭植えのままでも冬越しができるのが特徴です。ただし寒冷地では鉢植えにして育てて、冬場は室内に取り込んで管理するのが良いでしょう。また成長途中の小さな株の場合には冬場は室内で管理したほうが育成が良くなります。
ディクソニアの増やし方はナーサリーでは胞子で増やしますが、一般的には大変難しいので苗を購入して育てるのが確実です。葉の裏にカイガラムシなどの害虫が発生することがありますので殺菌剤、殺虫剤を定期的に散布するのが良いでしょう。
ディクソニアの魅力
ディクソニアの魅力の一つが芽吹く段階のくるくると渦巻いた芽です。まるでゼンマイのようにくるくると巻いた芽が徐々に伸びて葉を伸ばしていく様子は生命の神秘を思わせるワクワクする瞬間です。このようなユニークな芽吹きから、のびのびとした美しいグリーンの葉が出てくるのは栽培するうえで大きな楽しみとなります。
この植物が分布しているニュージーランドやオーストラリアの森は柔らかいコケがびっしりと生えていて、地面が常に湿っているような状態の場所です。まさに恐竜が暮らしていた太古を思わせる雰囲気のあるところですから、ディクソニアが部屋にあることでそのようなエキゾチックな印象を演出することができます。
タカワラビ科ディクソニア属のディクソニアは木立性シダ植物ですからまさに太古に育つたくましい植物の印象を与えてくれます。絶滅危惧植物ではありませんので、輸入が頻繁に行われ容易に入手できるところも魅力となっています。
栽培も用意で耐寒性、耐陰性があるので日本でも栽培しやすいのもメリットです。屋内でも屋外でも育てられる魅力のある植物です。水切れだけには注意してこまめに水を与え育てることで何年もこの植物のゆっくりとした成長を楽しむことができるのです。
ディクソニアの歴史
ディクソニアは木性シダの仲間で、日本では観葉植物として高い人気がります。シダ植物は見た目も原始的な印象ですが実際最古の陸上植物でもあります。化石の記録としては古生代シルル紀の4億年前までさかのぼります。この植物がシダの仲間で葉のない細い茎の先に胞子のうを付けた状態で、まさに4億年前の最初の植物の姿です。
人類の歴史が400万年前からだということを考えてもこうしたシダ植物の長い長い歴史に圧倒されます。花も種もつけずに増殖していくシダ植物はとても神秘的な植物と昔の人々は考えていました。そのためシダ植物に関するさまざまな俗説や神話が生まれて伝えられています。
目に見えないシダの種を手に入れることができればとてつもない力が手に入ると多くの地方で信じられ伝説となって伝わっています。特にイングランドやオーストリアなどではシダの種にまつわるさまざまな伝承があり手に入れることで40人力になったりと。
黄金を掘り当てることができたり、獣と話ができるようになるなどの言い伝えがあります。その姿のユニークさや増殖方法のユニークさが長い歴史の中でさまざまな言い伝えとなって現在に伝わっているのです。
ディクソニアの特徴
ディクソニアは主に南半球原産の木性シダの仲間で、日本ではアンタルクティカという品種が多く見られます。生息地はオーストラリア、ニュージーランド、ニューギニアなど南半球を中心に分布しているのが特徴です。
現地ではソフト・ツリー・ファーン、タスマニアン・ツリー・ファーンなどの名前があり見上げるほど大きく成長するのが特徴です。中には10メートルを超える大きなものもあり、エキゾチックなムードを演出することができます。
幹は褐色色の根のようなものでびっしりと覆われて、被子植物との違いを実感させてくれます。葉は美しいグリーンで生命力に満ちた艶やかさを持っています。背の高いディクソニアの葉が太陽に透けると輝く美しさでこの植物のたくましさを実感できます。
春になると一斉に芽が吹いてきて次々と葉が開いていきます。シダ植物のため花は咲かないものの、それを補ってあまりある魅力のある植物です。温かいところが分布地域なので寒いのは苦手のように感じてしまいます。
実は耐寒性も強く、雪が積もっても耐えるほどの強さを持っていますので、庭植えにしてエキゾチックな演出をするのも良いでしょう。耐陰性もあるので室内での栽培も容易です。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:プテリスの育て方
タイトル:アスプレニウムの育て方
タイトル:フェニックスの育て方
タイトル:ビカクシダの育て方
-

-
プチトマトの育て方について
今回はプチトマトの栽培の方法と、育て方について説明します。プチトマトは、カロテンとビタミンCという栄養が豊富なので、体に...
-

-
ハゴロモジャスミンの育て方
ハゴロモジャスミンの原産地は中国雲南省ですが、現在では外来種としてニュージーランドやアーストラリアなども生息地となってい...
-

-
ブンタン類の育て方
ブンタンはミカン科ミカン属の大型の柑橘類の一種でザボン、ボンタンなどと呼ばれ、ブンタン類には柑橘類最大の晩白柚や日本原産...
-

-
トリテレイアの育て方
トリテレイアは、ユリ科に属する球根性の多年生植物で、かつてはブローディアとも呼ばれていました。多年生植物というのは、個体...
-

-
ピーマンの栽培やピーマンの育て方やその種まきについて
家庭菜園を行う人が多くなっていますが、それは比較的簡単に育てることができる野菜がたくさんあるということが背景にあります。...
-

-
ウチョウランの育て方
ウチョウランは漢字では「羽蝶蘭」と書きますが、これは当て字で有って和名における語源は確かではないと言います。しかし、淡い...
-

-
小松菜の育て方について
最近はすっかり家庭菜園のブームも一般に浸透して、いろいろな自家製の作物を収穫している人も少なくありません。食品の安全を脅...
-

-
コカブの育て方と種まきの時期
コカブは球の直径が4から5センチのカブで、葉にはビタミンA、Cが多く含まれています。コカブの栽培は、虫の食害にだけ気を付...
-

-
白菜の育て方
白菜は、アブラナ科の野菜で、生息地は他のアブラナ科の野菜類と同様に、ヨーロッパの北東部からトルコ にかけての地域でだと考...
-

-
タチバナモドキの育て方
タチバナモドキはバラ科トキワサンザシ属の常緑低木です。名前の由来は橘(タチバナ)を同じ橙色をしていることから橘もどきとな...




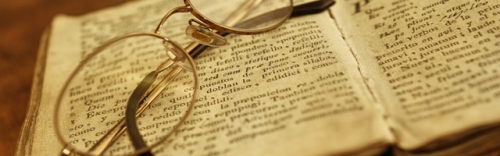





ディクソニアは南半球のオーストラリア東部南部、そしてニュージーランドが原産の温帯を中心に生息している木性シダ植物です。こうして温かいエリアに生息しているので、寒いのが苦手なような印象がありますが、実は耐寒性、耐陰性に優れた植物です。