しだれ梅の育て方

育てる環境について
しだれ梅は、耐寒性と耐暑性が強い植物です。耐寒性よりも耐暑性のほうが、より強いです。ですから花が咲き終わってからのタイミングで、風通しをよくするために剪定をしても枯れません。梅雨の時期から夏にかけて、勢い良く枝が育って伸びていきます。枝が込み合ってしまうと、虫が寄り付いて繁殖してしまいやすくなりますので、適度に風通しを改善するために剪定したほうが良いでしょう。
耐暑性が強いので、夏に枝を剪定しても枯れにくいのが嬉しいポイントです。ただし、耐暑性も耐寒性も、木の大きさに比例する傾向があります。盆栽で小さく育てている場合は、剪定のタイミングが重要になってきます。しだれ梅には耐陰性も備わっています。日陰でも充分に育ちます。
周辺に建物が多い環境では、日当たりの状況が一年間でも移り変わるものですが、日照時間が少なくなってしまう環境であっても、しっかりとした土に植えられていれば、健康に育ちます。開花を楽しむためには、日照環境よりも、剪定で枝を切るタイミングの選び方が重要です。これは強樹勢と呼ばれる性質が関係しています。
強樹勢とは、樹が育つ勢いが強いということです。剪定して枝を切れば切るほど、しっかりもっと育とうとしてしまう性質があるということです。勢いを増して育っているときは、枝が育つこと栄養分が集中しますので、葉芽のほうが多くなりやすく、花芽が育ちにくくなる傾向になります。日陰の環境であっても、花芽が育ちやすいように強樹勢の性質を把握して剪定していれば、しっかりと開花します。
種付けや水やり、肥料について
しだれ梅を地植えにしている場合は、自然の雨水だけで充分に育ちます。開花の季節に美しい花を多く咲かせたい場合は、年に数回ほど有機性の肥料を株元に撒くと良いでしょう。タイミングとしては、花が咲き終わって新芽が育ち始める5月と、梅雨の季節の6月と、夏の暑さが落ち着き始める9月です。土壌が肥沃であればあるほど、しっかとりした花を毎年咲かせてくれます。
盆栽や鉢植えなどで小さく育てている場合は、液体肥料を利用するのも良い方法です。盆栽や鉢植えにしている場合は、水やりを頻繁に行うように意識しましょう。しだれ梅は水を好む性質があります。畑や溜池の近くが生息地にふさわしく感じられるのも、地下水が豊富な立地であることが影響しています。盆栽や鉢植えの場合は、季節によって水やりの回数が違ってきます。
冬は数日間に一回程度の水やりでも大丈夫です。夏は一日に二回ほど水やりするのが理想的です。朝と夕に分けて水やりすると良いでしょう。朝、水を与えられなかったからといって、夕方になる前の昼に無理をして水を与えなくても大丈夫です。夏の直射日光が当たる時間帯に水を与えてしまうと、水分が高温になってしまい、
少なからず木にダメージとなってしまうからです。水を多めに与えて、鉢底から流れるようにします。ですから土には排水性が備わっているほうが良いでしょう。鉢植えであれば、鉢底石を敷いておくことで、排水性を高められますし、鉢底の穴から虫が侵入してくるのを予防できます。
増やし方や害虫について
しだれ海は、挿し木で増やすことが可能です。挿し木は、枝の切り口から雑菌が入らないように注意しましょう。衛生的な土を使用すると、雑菌の影響を受けません。鹿沼土や赤玉土だけで挿し木をすると、雑菌が侵入してきませんし、発根もスムーズです。鉢植えにしたい場合は、最初は鹿沼土や赤玉土だけで挿し木をして、発根してから培養土や腐葉土を混ぜ合わせて栄養分豊かな土壌に改善していきます。
挿し木に用いるのは、新しく育った枝です。先端のほうを適切な長さに切り、下のほうの葉を落として挿し木として利用します。このとき、アブラムシが付着している枝は、挿し木として利用しないほうが安全です。しだれ梅には、害虫が寄り付きやすい性質があります。新しい枝にはアブラムシが、ある程度育ってきた枝であればハマキムシやカイガラムシなどです。
蛾が寄り付いて産卵し、幼虫が繁殖してしまうことも少なくありません。木そのものに強樹勢が備わっていますので、薬剤には耐えやすく、強めの殺虫剤や除菌剤を使用しても枯れにくいのが嬉しいポイントです。ただし薬剤は、濃度に注意しましょう。植物用の殺虫剤は、農薬に分類されているタイプも多く、適切に希釈をする必要があるからです。
農薬や化学性の薬剤を使用したくない場合は、特に盆栽や鉢植えとして栽培している場合ですが、害虫忌避効果のある天然素材の忌避剤を使用した害虫予防も可能です。無農薬栽培に活用されているニームオイルを希釈して、葉、枝、幹の全体に噴霧しておくと、害虫忌避効果が高くなります。
しだれ梅の歴史
しだれ梅は原産が中国であり、古くから観賞用として親しまれている木のひとつです。しだれ海の原産は中国ですが、現在では日本でも多くの苗木が栽培されています。日本国内で、樹齢が数百年を越える木も多く、開花の季節には花見に多くの人が集うことも多いです。育て方は、地面に直接植えて、大きく育てる場合が多いですが、
江戸時代に盆栽が大人気となった頃からは、小さく育てられることも増えてきました。花を咲かせる観賞用植物としても定番になってきています。しだれ梅は、梅の品種のひとつであり、バラ科サクラ属の植物です。分類は多年草に該当します。落葉性で、放っておくと高木に育ちます。
しっかりと手を入れて栽培すると、小さな姿のまま維持しながら観賞用として育てることも容易です。花が美しく咲きますので、剪定の時期を間違えないようにすることがポイントです。しだれ梅は神社の境内に植えられていることも多く、開花の時期にあわせて梅祭りが開催されることが多いです。開花すると、豪華絢爛な雰囲気を放ちます。
豪華絢爛な開花を楽しむには、ある程度の広い敷地が必要です。限られた敷地面積の自宅の庭では限界がありますが、神社の境内のようにある程度の広さを確保できる環境ならば、バラ科サクラ属の植物にふさわしく、高木に育てることができます。現在では、日本各地の神社の境内や、畑や溜池の近くなどの立地を活かした生息地が多く、それぞれの地元の人を中心に花見として親しまれています。
しだれ梅の特徴
しだれ梅の最大の特徴は、枝が下へと垂れていく姿にあります。しだれとは、漢字で表現すると、枝垂れです。文字通り、枝が垂れていきます。枝先に花が咲きますので、開花の季節には、枝垂れた枝いちめんに花芽が付きますので、咲くと見事です。高木になった姿で一斉に開花すると、風に揺られて豪華絢爛ながら繊細な雰囲気を醸し出します。
基本的に梅の木ですから、育て方は梅の木と同様です。開花の時期、新芽が育つタイミング、花芽と葉芽の見分け方などは、梅と同様です。剪定の時期も、強く剪定するタイミングと、弱く剪定するタイミングがありますので、どのような大きさで維持したいのかを考慮しながら育てることがポイントです。
枝が下へと垂れるからこそ美しさが威力を発揮しますので、もしも上の方向へと伸び始める新しい枝が育ってきた場合には、伸びる方向を下に向けさせましょう。枝が込み合いすぎてしまいますと、虫が寄り付いて繁殖してしまうことも多いので、ある程度の風通しを良くしておいたほうが、健康に育てられます。
限られた敷地面積の中では、剪定が重要ですが、神社の境内や、畑や溜池の近くという立地条件のもとで育てられている場合は、枝を自由に伸ばせますので、新しく育ってきたばかりの枝が上の方向へと育ち始めてしまっても、
枝が育って長くなるにつれて枝そのものの重さで、だんだんと下へ下へと垂れていきます。枝が新しいうちは、柔らかいのが特徴です。枝が新しいうちであれば、どちらの方向へ伸ばしたいのか、自分の好きな方向へと誘引していく育て方も容易です。
-

-
オオイヌノフグリの育て方
気温が下がりつつある秋に芽を出して、冬に生長し春の早いシーズンに小さな花を咲かせるプラントです。また寒い冬でも過ごせるよ...
-

-
レブンソウの育て方
この植物の特徴として、バラ目、マメ科、オヤマノエンドウ属になります。園芸上においては山野草として区分されます。生え方は多...
-

-
ディサの育て方
ディサは、ラン科ディサ属、学名はDisaです。南部アフリカを中心とした地域が原産で、そのエリアを生息地としている地生ラン...
-

-
クレマチス ネリー・モーサーの育て方
この花についての特徴としては、まずはキンポウゲ目、キンポウゲ科、キンポウゲ亜科の種類となります。さらにセンニンソウ属に属...
-

-
オレアリアの育て方
意外と感じますがキク科の植物になるので、日本にも適用するイメージが強くあります。そして大きさは高さというのは25~60c...
-

-
キャッツテールの育て方
キャッツテールの原産地はインドで、ベニヒモノキにも似ています。しかし匍匐性の小型種であり、亜熱帯地方や亜熱帯を生息地とし...
-

-
オニバスの育て方
本州、四国、九州の湖沼や河川を生息地とするスイレン科オニバス属の一年生の水草です。学名をEuryaleferoxと言いま...
-

-
リカステの育て方
この植物の特徴としては、キジカクシ目、ラン科、セッコク亜科になります。園芸の分類においてはランになります。種類としてもラ...
-

-
エロディウムの仲間の育て方
フウロソウ科エロディウム属に属する品種なので、厳密には異なります。和名ではヒメフウロソウと呼ばれており、良く似た名前のヒ...
-

-
イワレンゲの仲間の育て方
イワレンゲの仲間は、ツメレンゲやコモチレンゲなど、葉っぱが多肉状態で、サボテンと育て方と同じ配慮で育てれば、毎年美しい花...




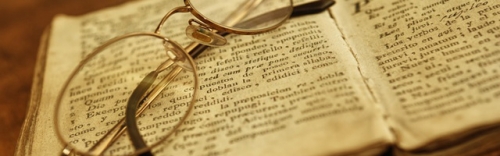





しだれ梅は原産が中国であり、古くから観賞用として親しまれている木のひとつです。しだれ海の原産は中国ですが、現在では日本でも多くの苗木が栽培されています。日本国内で、樹齢が数百年を越える木も多く、開花の季節には花見に多くの人が集うことも多いです。