ユリオプスデージーの育て方

育てる環境について
栽培のときに必要な環境として、生息地として日当たりを好む花とされています。ですからしっかりとした日当たりのところに置く、植えるようにします。花においては半日陰のところで管理した方がいいとされることがあります。この花の場合は半日陰にすると花つきが悪くなることがあります。葉っぱのみを楽しむのであれば半日陰などにおいても問題はありません。
日向が好きですが、真夏の暑さ、直射日光に関しては必ずしも好まないとされています。真夏のみは少し半日陰に移動させたほうがいいことがあります。地植えにおいては特にそのままでも問題ありません。この花の特徴の一つとして真冬でも花をつけることがあげられます。越冬をすることができますが、それにあたっては十分に注意して管理する必要があります。
耐寒性としてはありますが、あまり寒すぎる状態は好みません。何度も霜に当たるような場合、寒風にさらされる様なところです。あまり寒いところだと冬に枯れてしまうことがあります。夏に株が弱ることがありますが、暑さで枯れるところまではいきません。南関東より南であれば越冬することは可能と言われています。
もちろん花も楽しめます。夏において、ベランダなどに置こうとするときにコンクリートの上に直接置いたりすることがあります。そうすると温度が非常に高くなって弱ることがあります。多湿にならないようにするには梅雨の時期の管理を行います。雨に当てないようにすることも必要です。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては用土の配合を行います。一般的な花と野菜の培養土を使えますが、それ以外には赤玉土7割、腐葉土3割で混ぜるようにします。水はけを重視するのではあれば赤玉土を6割、腐葉土を4割にする方法もあります。一部に軽石を混ぜる配合もあります。もう少し考えるなら有機質重視のタイプもあります。
赤玉土を5割、腐葉土を3割、酸度を調整した後のピートモスを2割、それにリン酸分の多い緩効性化成肥料を加えた土の利用があります。水を与えるときは乾燥気味がポイントになります。土が乾いた時はたっぷり与えますが、多湿が苦手な植物なので与え過ぎにならないようにしなければいけません。土が濡れていのに水を与えると根腐れしてしまう場合があります。
春から秋においては夏の暑さと相談しながら与えるようにします。多すぎは禁物になります。12月から2月にはこの花がしっかりと咲く時期になります。だからといって水を増やすわけではなく、暖かい日などを選んで少しずつ与えるようにします。肥料が少ないと葉っぱに影響をあたえることがあります。
通常は濃い目の緑色が少しうすい色になることがあります。逆に黒っぽくなったりすることもあり見た目としては良くなくなります。そこで液体肥料を薄めたものを少しずつ与えるようにしてみましょう。肥料については与えすぎるとどんどん伸びすぎることがあります。全く与えないと心配ですが、与え過ぎにならないようにしなければいけません。
増やし方や害虫について
増やすための方法としてはさし芽を選択します。行う時期としては5月から6月ぐらいです。ちょうど花が終わった後ぐらいに行います。この時期においては枝分かれをさせるために新芽を摘み取ることがあります。それを利用することができます。新芽を10センチから5センチ位にして水を入れたコップから吸水させます。
1時間もすればしっかりと吸水できるのでその芽を赤玉土にさします。この時には赤玉土を少し湿らせておくようにします。この後は1箇月近くは乾かさないように管理をします。日向ではなく日陰での管理を行います。その後根が出てきたら鉢に植え替えて管理を行います。最初の冬は外よりも中で管理した方がいいかもしれません。
さし木も方法としては選択できます。4月頃から行うパターンと9月頃に行うパターンがあります。この花の増やし方として選択できないのが種をとってまくことです。残念ながら種ができないとされています。そのために方法が限られています。行っておきたい作業としては切り戻しを行います。花が終わった6月まで、秋の10月までぐらいに行います。
この植物に関しては強い切り戻しに耐えるとされています。ですから好みの大きさにすることができます。大きくなりすぎているなら少し小さめにするなどがよいでしょう。害虫として出やすいのがアブラムシです。通年発生する事になりますが、対処方法はあります。風通しを良くする、肥料をあげ過ぎないようにするなどです。
ユリオプスデージーの歴史
日本の冬は非常に寒くなります。もちろん世界においてはもっと寒い地域がありますから甘いかもしれません。でも日本は夏は非常に暑くなります。暑くもなり、寒くもなるところとなると結構限られているでしょう。最も生活しやすいとしたらハワイなどのように1年中温暖な気候のところになるのでしょう。
旅行では行けても住むのはお金がかかりそうです。日本には冬があるので、花としては休みの時期になることが多いようです。つまりは、寒くて成長することができないので花が咲けない種類が多くなります。その中でも冬にもしっかりと花を咲かせてくれる花としてユリオプスデージーがあります。花の原産としては南アフリカになります。
暖かいところで咲くので寒さには弱そうですが、冬に元気な花を咲かせてくれるとして知られています。春っぽい花なので、冬に咲いていると元気をもらうことができそうです。この花についての歴史としては、昭和40年代に渡来たとされます。花が渡来する時期としてはまだ国交があまり開かれていなかった江戸時代前、
国交が徐々に開かれるようになった明治以降があります。更には近年の戦後において渡来するケースがあります。この花については戦後、かなり落ち着いたときに渡来してきたようです。鉢花として普及するようになります。この花の名前のユリオプスはユリを意味するわけではありません。ギリシア語で大きな目を持つとされています。花の姿からつけられました。
ユリオプスデージーの特徴
特徴として、キク科、ユリオプス属になります。南アフリカを中心に95種類もある属になります。園芸において分類では草花に該当するとされています。草花として分類されますが、常緑低木になります。小さい木としての扱いになります。樹高は1メートル程度ですから、草花としてのほうが良さそうです。開花時期に特徴があり、11月ぐらいから5月にかけてになります。
晩秋の頃から咲き始め、冬を通して、次の年の春頃までしっかりと咲いてくれる種類になります。花の色は黄色のみのようです。冬に咲きますが耐暑性もあります。冬に咲くことから耐寒性も持っていると言ったほうがいいかもしれません。この花は最初育てるときは草花のような姿で育ちます。芽が出て茎が出て葉っぱが出て花が咲くパターンです。
その後花は取れますがそこからまた花が生えてきたりします。この花に関しては茎が毎年年を追うごとに太くなって表面がゴツゴツしてきます。そのために木に分類されます。葉っぱは羽状に深く切れ込んだタイプで、表面に柔らかい毛が生えています。そのためにきれいな緑色よりも緑色に灰色が混じったような色の葉っぱになります。
花は黄色の花びらを持つ一重の花になります。花の大きさは直径で3センチから4センチぐらいです。茎を15センチぐらいのばして、その先端に1輪の花を付ける形になります。花の中央部分についても黄色っぽい色をしていますから、まさに黄色一色の花と言えます。
-

-
イチジクの育て方
イチジクのもともとの生息地はアラビア半島南部、メソポタミアと呼ばれたあたりです。文明発祥とともに身近な食物として6000...
-

-
コカブの育て方と種まきの時期
コカブは球の直径が4から5センチのカブで、葉にはビタミンA、Cが多く含まれています。コカブの栽培は、虫の食害にだけ気を付...
-

-
お料理に重宝バジルの栽培のコツ
ベランダやお庭でのバジルの育て方は簡単で誰にでも挑戦する事が出来ます。バジルの種まきの時期は春から初夏にかけてがベストで...
-

-
ジャガイモの育て方と植え付けからの仕事
ジャガイモの種まき時期は、春植えと秋植えが出来る1年を通しての栽培が出来る人気の野菜で、8月下旬から9月上旬に植えておく...
-

-
アオマムシグサの育て方
アオマムシグサという植物はマムシグサの一種です。マムシグサというのはサトイモ科テンナンショウ属の多年草です。「蛇の杓子」...
-

-
シュンギクの育て方
キク科シュンギク属に分類されるシュンギクは、20cmから60cmの草丈となる一年草植物であり、春には花径3cmから4cm...
-

-
アベリアの育て方
アベリアはハナゾノツクバネウツギのことで、ラテン語の属名アベリアで呼ばれています。公園などで植え込みとしてよく植えられて...
-

-
コチレドンの育て方
コチレドンはベンケイソウ科コチレドン属で、学名をCrassulaceae Ctyledonといいます。多肉植物の仲間の植...
-

-
ヒオウギの育て方
ヒオウギの名前を聞いて和歌を連想する人、京都の祇園祭を思い浮かべる人、様々ですが、原産国は東アジアとなっています。日本も...
-

-
ルドベキアの育て方
ルドベキアは北米を生息地としており、15種類ほどの自生種がある、アメリカを原産とする植物です。和名ではオオハンゴウソウ属...




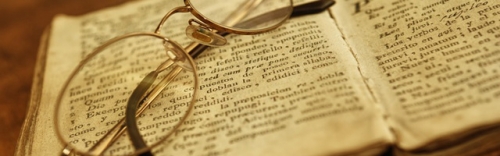





特徴として、キク科、ユリオプス属になります。南アフリカを中心に95種類もある属になります。園芸において分類では草花に該当するとされています。草花として分類されますが、常緑低木になります。