ロシアンセージの育て方

育てる環境について
育てる環境については、まず寒冷地でないかぎり屋外で育てても十分に越冬してくれます。そのため、地植えでも可能です。では外ならどこでもいいかといえば、そうではありません。基本的に日当たりの良い場所を好みます。ただし真夏の強すぎる日差しも決して好みません。真夏に萎れてきたようならば、日陰を作れるような工夫を施すのも必要となってきます。
さらに重要なのは風当たりです。風がないと木全体の湿気が篭ってしまうため、枯れる原因になります。そのため、なるべくガーデニングをするときも壁の横だったり、高い木の横に植えないように心がけなくてはなりません。風の通り道なども考慮しながら植えることが重要となります。
基本的には日当たりと風当たりの2つを重視して植える環境を整えてあげるのが理想的です。ただそれはロシアンセージが育つための環境であって、手入れをする人の環境も考える必要があります。というのも、年に数回は切り戻しをする必要があるからです。鉢植えで育てるのならば、場所を移動させることが可能ですが、地植えだとそうはいきません。
もしもガーデニングの奥のほうに植えたりして手を伸ばさないと届かない位置に置くと切り戻しをするときには苦労をします。無理な体勢で行えば腰を痛める原因にもなります。そのため、なるべく地植えするときは簡単に手が届く場所に植えることで育てる人の負担を軽減させることができます。園芸は楽しみながらするのが大切です。
種付けや水やり、肥料について
冒頭で述べたようにロシアンセージはアフガニスタンやパキスタンといった乾燥地を生息地としていました。その辺りは土は痩せているため、日本で栽培するときもほとんど肥料を与える必要はありません。肥料を与えると元気に育ってはくれますが、根よりも地上部が大きく育ってしまうため倒木の可能性が出てきます。
そのため、肥料を与えるべきではないと主張する人もいます。その一方で、水やりはあまりにも水不足では枯れてしまいます。そのため、カラカラに土が乾いたときに水をしっかりとあげるようにしなくてはなりません。すでに何度も書いていますが、湿度には弱い植物です。常に土壌をジメジメと湿らせている状態だと根腐れを起こす原因となります。
それは地上部が枯れた冬の休眠時期でも同じことです。休眠しているから水を与えなくてもいいと勘違いしている人がいますが、水不足になってしまうと根の方も枯れてしまい春になっても芽を出さなくなってしまいます。特に冬場は乾燥しやすく、休眠状態で木の状態も窺い知ることはできません。
だからこそ、水やりには一層の注意を払う必要があります。もちろん、このときも水のあげ過ぎは厳禁です。また湿気が弱いため、用土はなるべく水はけの良いものがいいとされています。ロシアンセージを植える前に土に川砂などを混ぜておくとベストです。そうすることで、誤って水をあげ過ぎたとしても根腐れを起こす可能性を減らすことができます。
増やし方や害虫について
ロシアンセージは小さな花がたくさん咲く一方であまり種子を作ることがありません。種子から増やそうと考えると種子を見つけるのに相当な手間がかかります。そのため、もしも苗木を買わずに増やしたいと考えているのならば、挿し木によって増やすのが一般的となってきます。挿し木の方法は、新芽を切り取り枝や花などを落とします。
それを一度水に漬けて、挿し木用の土に植えます。根が生えてきたものを植物に刺します。その植物は同じシソ科であるローズマリー・ラベンダー・サルビア(セージ)などが良いとされます。挿し木をする時期は4月から8月と暖かい季節が適しています。9月を過ぎると定着する前に寒さが訪れることもあるので、少し遅いです。
また挿し木をして育っても根は別の植物です。切り戻しをするとき、誤って挿し木の下を切らないように注意する必要があるため、挿し木した場所に何らかのマークをつけておくといいです。また害虫や疫病にはかかりにくいのがハーブの特徴です。ハーブの特有の香りには虫を近づけなかったり、殺菌効果があるからです。
ロシアンセージはハーブのなかでも香りが弱い部類に入ります。しかし、それでもハーブの一種であるため、害虫や疫病に強い植物です。切り戻しなどの手間がかかる一方で、害虫や疫病の心配をする必要がないため、比較的栽培しやすいです。湿気さえ気をつければ、園芸の初心者から中級者でも楽しんで栽培することができるはずです。
ロシアンセージの歴史
ロシアンセージはハーブの一種です。名前からするとロシア原産のセージと勘違いされる人も多いですが、それは間違いです。原産地はアフガニスタンやパキスタンといった中東・南アジアです。ではセージ(サルビア属)かというとそうではなくペロブスキア属です。ロシアンセージという名前の由来は19世紀のロシアの地方長官が広めたことがきっかけだと言われています。
ペロブスキアとはその長官の名前ペロブスキーから名づけられました。花の形状はラベンダーに似ています。ラベンダーと違って夏に咲くため、別名サマーラベンダーと呼ばれています。さらにハーブの一種ではありますが、一般的なハーブと違って食べることはできません。だからといってラベンダーのように香りが強いわけでもありません。
家庭で育てている理由の多くは観賞用ハーブとなります。名前だけだと何かと誤解されやすい植物ではあります。ただし、先ほども述べたようにラベンダーのような可愛らしい花を付けるため観賞用であっても人気です。しかも、ラベンダーと違って育て方が簡単ですし、低木で育つため一斉に開花したときは華やかに見えます。
ハーブとしては食べれませんし香りが強いわけでもありませんが、決して香りがないわけではありません。全体的にミントのような香りがするため、切花にして室内に飾る家庭もあります。一般のハーブのような強い香りが苦手という人は、ロシアンセージくらいがちょうど良いのかもしれません。
ロシアンセージの特徴
すでに述べたようにロシアンセージはハーブとしては香りが弱く、食用にも向かないためほとんど観賞用として栽培されているのが特徴です。ラベンダーと違って一本の木で丈が60cm~1mほど茂ってくれるため管理しやすいです。また、多年草ですが宿根草でもあります。つまり、生長期でない秋から冬にかけては地上部分は茎を残してほぼ枯れたようになってしまいます。
しかしまた春頃になると残っている茎からたくさんの芽が出てきて、元通りに花を咲かせるようになります。1mほどの高さになるため、鉢植えでも育てることはできますが、なるべく地植えしたほうがいいかもしれません。栽培の特徴としては、とにかく切り戻しの工程が続きます。
切り戻しとは枝先を切ることです。これをしなければどんどん上や周囲に広がっていきます。木全体が大きくなるだけではなく、生長にエネルギーが注がれるため観賞用として大切な花が咲かなくなってしまいます。冬には大部分が枯れてしまうため、大きくしたとしてもメリットはありません。
また日本の夏は蒸し暑く、乾燥地帯が生息地だったロシアンセージには大きな負担となってしまいます。そのため、切り戻しによって余分な葉っぱや枝を落として風通しを良くさせて夏を乗り切ることができます。基本的には暑さにも寒さにも強い植物なのですが、湿度だけには弱いため、その点は注意して育てなくてはなりません。そうすることで綺麗な花で多くの人々の目の保養をしてくれます。
-

-
マムシグサの育て方
マムシグサは、サトイモ科テンナンショウ属です。サトイモ科に属するので、毒性はあるものの、用途としては、毒を取り除いて食用...
-

-
シロハナノジスミレの育て方
スミレ科スミレ属の多年草ですが日本ではどこでも比較的見られる品種で、本来のスミレよりも鮮やかな色で、素朴なスミレらしさは...
-

-
ゼラニウムについての説明と育て方
フウロウソウ科であるゼラニウムは、南アフリカに自生する温帯性の宿根草であり、欧米ではベランダや窓辺の花として最も多く目に...
-

-
ダイズの育て方
ダイズの歴史を調べてみると、はっきりとした起源がわからず、いくつかの説によって現代に伝えられていることがわかります。つま...
-

-
レウイシア(岩花火)の育て方
スベリヒユ科であるレウイシアと呼ばれる植物は、原産が北アメリカであり学名はLewisiacotyledonで、この学名は...
-

-
キワーノの育て方
キワーノはウリ科でつる性の植物です。名前については企業の商標登録によってつけられたものですのでこれが正式な名称ではないよ...
-

-
カッコウアザミ(アゲラータム)の育て方
アゲラータムは別名カッコウアザミという和名を持っています。アザミに花はとても似ていて、その関係からカッコウアザミという名...
-

-
洋種サワギキョウの育て方
キキョウは日本で古くから好まれている花の一つです。生息地としては日本だけではなくて中国大陸や朝鮮半島などで、この地域が原...
-

-
トマトの栽培や育て方について
もうすぐ春がやってきます。そうなると、夏野菜の種まきや栽培を始められる方も多いのではないでしょうか。ここでは、初心者でも...
-

-
ロベリアの育て方
ロベリアは熱帯から温帯を生息地とし、300種以上が分布する草花です。園芸では南アフリカ原産のロベリア・エリヌスとその園芸...




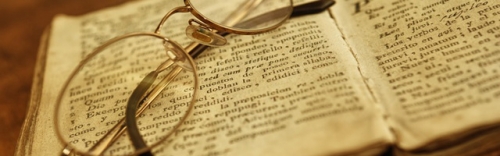





ロシアンセージはハーブの一種です。名前からするとロシア原産のセージと勘違いされる人も多いですが、それは間違いです。原産地はアフガニスタンやパキスタンといった中東・南アジアです。ではセージ(サルビア属)かというとそうではなくペロブスキア属です。