ペペロミア(Peperomia ssp.)の育て方

ペペロミアの育て方
ペペロミアの丈夫な育て方のコツは、一年を通して室内の明るい場所に置くことです。
日陰でも育つ性質があるため、やや暗いような場所でも枯れることはありませんが健康的に育てるためには日光浴が必要となります。長い間日陰に放置されると、間延びしたような姿に育ってしまいます。
夏の暑い時期はレースのカーテン越しの窓辺、その他の季節も気温の変化に気を配りつつ窓辺のガラス越しなど日光が適度に入る場所を置き場所にしましょう。多肉質の葉の場合は、水分をしっかりとためておくことができるため過剰な水やりをするとかえって負担をかけることにつながります。
乾燥には強い性質を持っているため、水の与えすぎは毒です。土の表面がしっかりと乾いていることを確認してから、鉢底からあふれ出すくらいたっぷりと水を与えましょう。土の表面の乾き具合が見た目でよくわからないという場合は、指で表面を触ってみて土がついてこなければ乾いていると判断することが可能です。
ペペロミアの生育期は5月から9月の間です。生育期に、観葉植物用の液体肥料を2週間に一回程度の頻度で与えるといいでしょう。冬場は株に負担を与えるだけなので肥料は与えません。温かい季節はベランダなどの屋外で日光浴をさせると丈夫に育ちます。
栽培中の失敗で多いのが根腐れです。用土は水はけのよい土が適しています。小粒の赤玉土、腐葉土、川砂を配合した用土か市販の観葉植物用の土を使用するといいでしょう。カラーリーフとして寄せ植えに使用するという場合には、同じような性質を持つ多肉植物と同士の寄せ植えがおすすめです。
水分をたくさん欲しがるような草花と一緒に植えると、根腐れを起こしやすくなってしまいます。かごや瓶などを利用した寄せ植えは見た目にも楽しく、インテリアの小さなアクセントとして気持ちを明るくしてくれること請け合いです。
ペペロミアは他にもハイドロカルチャーとして育てることが可能です。購入した苗の根についた土をすべて落としてからゼオライトやハイドロボールを利用し、ガラス瓶などに入れて室内の明るい日陰で管理します。
栽培中に注意したいこと
ペペロミアは強い西日や直射日光に負けやすく、葉焼けを起こしたりなどのダメージを受けやすいため、置き場所には注意が必要です。丈夫に育てるためには日光は絶対に必要ですが、夏場の強すぎる日差しには充分に注意しましょう。
夏場に外に出す場合には直射日光を避けた半日陰などにおき、外で日光浴させる場合も時間帯を決めて西日にあてないように気を配る必要があります。寒さにはやや弱い面があるため、気温が10度以下にならないように秋から冬に浮欠けては室内で管理しましょう。
冬場はほとんど水をやらずに乾かし気味にすることで、耐寒性がアップします。品種にもよりますが、5度以下をにならなければたいていの場合は安心できます。冬場に春や夏の成長期と同じような頻度で水を与えることは厳禁です。ペペロミアの栽培で一番に注意したいことが根腐れです。
しっかりと水を与えているのに葉の色つやが悪くなって、だんだんしおれたようになってしまうのはほとんどの場合根腐れが原因です。冬場に水やりの頻度がよくわからないという人は、鉢の重さで判別する方法があります。充分に乾いていれば軽く、水分が多く残っていれば重いはずです。
乾いている状態の鉢の重さを覚えておき、冬場の水やりのコツをつかみましょう。また、枯れた葉はその都度取り除いて風通しをよくします。根本の方の葉がほとんど落ちて見栄えが悪くなった場合や、同じ鉢で長い間栽培していて根詰まりを起こした場合は植え替えが必要です。
植え替えのタイミングで切り戻しを行うといいでしょう。茎が長く伸びるタイプのものは好みの長さに切り戻しを行い、根元から葉が出てくるタイプのものは株分けを行います。さっぱりとした姿になったら鉢から抜いて、枯れた根や傷んだ根を静かに取り除きます。根についた土は三分の一程度を落としてから、新しい用土で植え替えましょう。植え替えの際に根腐れ防止剤を利用すると、なおいいでしょう。
ペペロミアの増やし方
種付けをして増やすよりも、挿し木や葉挿しをして増やしたり株分けで増やす方法が一般的です。植え替えの際に切り戻した葉や茎を使用することができます。挿し木の場合は5節くらいのところで切断し、根本側の葉をとりのぞき小粒から中粒の赤玉土にさします。
発根するまでは乾かさないように明るい日陰で管理しましょう。葉挿しをする場合は、傷や虫食いのないきれいな葉を切り取り、葉柄を2cmから3cm程度に切断し、川砂やバーミキュライトなどにさして管理するとやがて葉の根本あたりから新しい葉が生えてきます。
株分けは植え替えの際に不要なわき芽を根っこごと切り取って、観葉植物用の培養土にうえつけるだけなので簡単にできます。いずれも適している季節は5月から7月頃です。
ペペロミアの歴史
ペペロミアの原産地はブラジル、ボリビア、エクアドルなどで、主な生息地は熱帯や亜熱帯です。約およそ1400種類もの種類が存在し、種類が多いだけに様々な形態を持っています。ペペロミアはコショウ科の植物で、日本にはサダソウ(佐田草)とシマゴショウ(島胡椒)の二種類が自生しています。
ペペロミアという名前の由来は胡椒を意味する「ペペリ」というギリシア語です。似ているという意味の「ホモイオス」の二つの言葉があわさって、胡椒に似たという意味を持つペペロミアという名前がつけられたといわれています。ベトナムではペペロミアの一種が香辛料として使用されています。
シマアオイソウ(縞葵草)という別名を持っており、葉が縞模様で、葵に似ていることに由来しています。ペペロミアの模様や色合いは多岐にわたります。肉厚の葉に複雑な模様が入ったものなど面白みのある外見は観賞価値が高く、日本では観葉植物として栽培されることが多い植物です。
観葉植物といっても、大型にはならずインテリアのアクセントとして窓辺に飾ったりする用途に使用されることが多いです。品種によって様々な姿をしているため、中には大型に育つものもあります。
ペペロミアの特徴
ペペロミアはコショウ科ペペロミア属の多年草です。草丈は種類によって異なりますが、5cmから40cm程度に育ちます。生息地が幅広いため、その姿は様々です。短い茎を中心として四方向に葉が生えるロゼットタイプ、茎が太くまっすぐに伸びる直立タイプ、地面を這うように伸びるほふくタイプの3つのタイプに大きくわけることができます。
小さな花がたくさん集まって穂のように咲きますが、花弁がないため目立った存在感がない場合があります。スイカペペロミアの別名のとおり葉の表面にまるでスイカのような白い縦縞が入るロゼッタタイプのアルギレイア、直立タイプですが長く伸びると這うように育ち多肉質の濃い緑色の葉を持つオブッシフォリア、3cm前後の小さな卵型の葉が特徴的なオルバなどが人気の園芸種です。
葉が多肉質の種類の中には他にペペロミア・コルメラがあり、多肉質の小さな葉がたくさん集まって棒状に直立する姿は面白く見ごたえがあります。園芸店の多肉植物コーナーで主に販売されていますが、雑貨店などで見かけることもあります。それぞれの特性にあわせて、ハンギングに利用したり、支柱を使ってタワー仕立てにしたり、カラーリーフとして寄せ植えを楽しむことが可能です。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アガベ(観葉植物)の育て方
タイトル:アエオニウムの育て方
タイトル:月下美人の育て方
タイトル:ストレリチアの育て方
タイトル:リュウビンタイの育て方
タイトル:ディクソニアの育て方
-

-
ワダンの育て方
この植物は花から見てもわかりますが、キク科アゼトウナ属でキク科ということですが、キク科の野草は黄色い色や白が多くて、特に...
-

-
グロリオサの育て方
グロリオサはアフリカ、熱帯アジアが生息地で5種が分布するつる性植物です。グロリオサの名前はギリシア語の栄光ある、名誉ある...
-

-
タイサンボクの育て方
タイサンボクはモクレン科モクレン属の常緑高木で、北米中南部が原産です。タイサンボクの木は大山木や泰山木という字も使用され...
-

-
ケラトスティグマの育て方
中国西部を原産としているケラトスティグマは明治時代に日本に渡ってきたとされています。ケラトスティグマの科名は、イソマツ科...
-

-
ピーマンの育て方
現在は家庭の食卓にも馴染み深いピーマンですが、実はナス科の植物だということはご存知でしたか? ピーマンは熱帯アメリカ原産...
-

-
バラ(バレリーナ)の育て方
バレリーナの特徴としてはまずはつる性で伸びていくタイプになります。自立してどんどん増えるタイプではありません。ガーデニン...
-

-
ルッコラの育て方
ガーデニングブームとともに人気になっているのが家庭菜園です。自宅に居ながらにして新鮮な野菜をたべられるというのも人気の秘...
-

-
上手な植物の栽培方法
私たちが普段生活している場所では、意識しないうちに何か殺風景だなとか、ごちゃごちゃ物がちらかっているなとかいう、いわゆる...
-

-
トケイソウの仲間の育て方
トケイソウの仲間は中央アメリカから南アメリカにかけてが原産地とされています。生息地は熱帯地域が中心で、現在では世界中に数...
-

-
トレニアの育て方
トレニアはインドシナ半島原産の植物で、東南アジア・アフリカなどの熱帯の地域を生息地として約40種が分布しています。属名t...




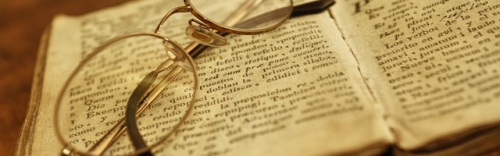





ペペロミアの原産地はブラジル、ボリビア、エクアドルなどで、主な生息地は熱帯や亜熱帯です。約およそ1400種類もの種類が存在し、種類が多いだけに様々な形態を持っています。ペペロミアはコショウ科の植物で、日本にはサダソウ(佐田草)とシマゴショウ(島胡椒)の二種類が自生しています。