デルフィニウムの育て方

デルフィニウムの育てる環境について
庭植えにしても鉢植えにしても楽しめる花ですので、特に決まった置き場所はありません。しかしきれいな花を咲かせるためには、出来るだけ日当たりがよく、涼しい所で育てるようにしましょう。強い日差しには弱いので、真夏には日陰に移動させたり、日除けを利用したりしてあげるとよいでしょう。
寒冷地に向いている植物ですので、冬場に防寒対策をして上げる必要はありません。丈が高めですので、春になって茎が伸びてきたら支柱などを立てて倒れないようにする工夫が必要です。寒冷地にて栽培している場合、植えて3〜4年ほど経過すると大株になってしまいがちです。
窮屈になると花の成長を妨げる原因になりますので、株分けをしつつ、植え替えをしてあげましょう。その際、株と株の間は30センチほどとることをお勧めします。鉢植えにする際も、ひとつの鉢に1株くらいの割合で育てる方がよいでしょう。
一番花が咲き、枯れ始めてきた頃に茎を株の根本から切り落とします。さらに元気のいい芽を少しだけ残して細い枝なども取り除いておきます。そうすることによってワキ芽が成長し、約2ヶ月後には二番花を咲かせてくれます。この作業を繰り返すとさらに3番花、4番花まで楽しめるので、
長い間美しい花を鑑賞することが出来ます。もし、次の年もデルフィニウムを育てたいという場合には種をとっておくことも出来ます。花が咲き終わるとサヤ部分が茶色くなってきますので、種を採取しておきましょう。乾燥剤を入れて冷蔵庫に入れて保管しておきます。
種付けや水やり、肥料について
デルフィニウムは種まきによって増やします。種まきをする場合、適期は夏の暑さが過ぎた9月以降になります。バーミキュライトは赤玉土を入れた鉢に種をまき、軽く土をかぶせます。乾燥しないよう、注意しながら発芽を待ちます。発芽後、本葉が2〜3枚ほど出てきたら園芸用ポットに丁寧に植え替えて育てます。
さらに本葉が増えてきたら、花壇や鉢などに植え替えるようにしましょう。デルフィニウムは大きめの花ですので、植え替える際にはある程度、株間をあけて植えます。水はけの良い土がお勧めですので、赤玉土と腐葉土を7:3くらいの割合で混ぜ合わせたものを使用します。
植え付ける際には元肥が重要になってきますので、こちらの用土に牛フン堆肥を1割ほど混ぜてもよいでしょう。臭いが気になる場合には油かすや緩効性のある化成肥料などを混ぜ込んでも大丈夫です。デルフィニウムを長く楽しむために、
水やりは控えめにしておくのが育て方のポイントです。土の表面が乾いてきたらたっぷりと与えるくらいで大丈夫です。その際、葉や花に水がかからないように注意しましょう。花や茎が傷んでしまう原因になります。鉢植えの場合も同様、水は控えめにし、
土が完全に乾いたら鉢底から水が滲み出るくらいの水を与えるようにします。肥料はあらかじめ用土に混ぜ込んでおく元肥とはまた別に、追肥をしてあげるようにしましょう。時期は3月頃と5月頃が適期です。葉が育ち始めた頃、液体肥料などを与えてあげると元気な花が咲きます。
デルフィニウムの増やし方や害虫について
増やし方は秋に種をまいて増やすのが一般的です。デルフィニウムの種は園芸店などで入手することもできますし、前年度、花が終わった株から採取して保管しておいたものを使うという手もあります。また、種から発芽させるのが待てない、
自信がないという方は園芸店などにデルフィニウムの苗が販売されていることがありますので、こちらを購入して植え替えてあげるとよいでしょう。デルフィニウムの苗は春先に販売されるので、お気に入りの品種の苗を購入して育ててあげましょう。
5月頃、うどんこ病を発生させることがあります。葉や茎が白い粉のようなもので覆われる病気で、生育を妨げ、枯れてしまうこともあります。うどんこ病になってしまった部分を早めに取り除いてあげましょう。また、専門の薬剤も販売されていますので、
殺菌剤を散布しておくことも重要です。古い用土などを使ってしまうと、立枯病も発生しやすくなります。接地面から腐食してどんどん枯れてしまう病気ですので、予防としては植え替える際には必ず新しい用土を使用するように心がけましょう。ヨトウムシやナメクジなどの害虫にも注意が必要です。
ヨトウムシは夜行性で昼間は隠れているので見つけにくいのですが、株が食べられた形跡があればヨトウムシを疑いましょう。根本の土を掘ると隠れていることがありますので、すぐに駆除します。ナメクジも茎や葉を食べて弱らせてしまいますので、ナメクジ専用の薬を使用して、見つけ次第早めに駆除するようにしましょう。
デルフィニウムの歴史
デルフィニウムはキンポウゲ科の花で、5月から6月頃に様々な色の繊細で美しい花を咲かせます。背が高い茎に小さな花をたくさん咲かせるので華やかさがあり、花壇や鉢植えで育てるだけでなく、切り花としても人気があります。
原産地はヨーロッパのピレネー山脈やアルプス山脈、シベリア、アジア、北アメリカなどの寒冷地です。その為高温多湿に弱く、本当は多年草なのですが、日本では夏を越すことが難しいため一年草として扱われています。つぼみの形がイルカに似ているというところから、ギリシア語のイルカ(デルフィン)から名付けられました。
また、日本では花の形がつばめが飛んでいる姿に似ているということからオオヒエンソウ(大飛燕草)と和名がついています。様々な品種改良を経て、現在では北半球を生息地としておよそ200種類ほどが分布しています。
デルフィニウムの改良は17世紀頃に始まったと言われています。その後も盛んに改良は行われ、非常に多くの園芸品種が登場するようになりました。花の形や色、枚数、背の高さなど、バラエティ豊かなデルフィニウムは、今もなお改良が続けられています。
以前は高価な花という印象が持たれがちでしたが、最近では入手もしやすくなり、日本でも高い人気を誇っています。デルフィニウムは非常に存在感のある花で、華やかさと繊細さを併せ持っているため、インパクトのある花壇づくりには特にお勧めです。プレゼントに花束として使用するのも喜ばれることでしょう。
デルフィニウムの特徴
デルフィニウムの特徴はまずその形状と言えるでしょう。一般的な草花に比べても背が高く、大きなものでは2メートル近くになるものもあります。高い茎に沿うように美しい花が咲き、まるでフラワーツリーのようです。品種もバラエティ豊かで、ブルー、紫、白、ピンクなど様々な色の花を咲かせます。
ブルー系の色を咲かせる花自体が少ないため、ブルー系のデルフィニウムは特に人気があります。また、花が一重のもの、八重のものなど、形状が異なるものもあります。原種では、花と花の間に隙間があるものも多いのですが、改良された品種では大きめの花が隙間なく咲くものも増えています。
特に好んで栽培されているのは花穂が大きめのエラツム系といわれるもので、デルフィニウムの主流となっています。こちらは丈が高めで華やかな品種ですので、庭植えや切り花に向いています。またグランディフロラム(シネンセ)系も人気があります。
丈が短めで花穂がまばらにつくので繊細な印象を持つ品種ですので、鉢植えなどで鑑賞したい場合にはこちらがお勧めです。他にもベラドンナ系やユニバーシティー系など、様々なものがありますので、どのような状況下で育てるのかを考えて選ぶとよいでしょう。
本来の生息地である寒冷地では、多年草として親しまれていますが、残念ながら日本の高温多湿の気候では夏越えが難しいため、一年草として扱われています。しかし、日本でも寒冷地であれば問題なく育ちますし、暖地でも出来るだけ風通しの良い涼しい所において管理してあげることによって夏を越せることもあります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:クレマチス(四季咲き)の育て方
タイトル:オキナグサの育て方
タイトル:カーネーションの育て方
-

-
シェフレラ・アルボリコラ(Scefflera arboric...
台湾や中国南部が原産地のウコギ科セイバ属の植物です。生息地は主に熱帯アジアやオセアニアで、およそ150種類ほど存在する低...
-

-
オブッサの育て方
このオブッサとは丸いという意味だそうですが、葉も丸みを帯びていて、独特な柔らかさのある丸い葉なので、穏やかさも演出してく...
-

-
リカステの育て方
この植物の特徴としては、キジカクシ目、ラン科、セッコク亜科になります。園芸の分類においてはランになります。種類としてもラ...
-

-
オニバスの育て方
本州、四国、九州の湖沼や河川を生息地とするスイレン科オニバス属の一年生の水草です。学名をEuryaleferoxと言いま...
-

-
スターチスの育て方
スターチスの花の原産地は、ヨーロッパであり、地中海沿岸地方を生息地としています。いかにも洋風な見た目の花は、日本へ伝わっ...
-

-
ホウセンカの育て方
ホウセンカは、ツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草で、東南アジアが原産です。中国では、花を鳳凰に見立てて羽ばたいているよ...
-

-
ダイモンジナデシコの育て方
ダイモンジナデシコの歴史や由来をたどってみると、ダイモンジナデシコはナデシコ科に属しますが、ナデシコはトコナツの異名をと...
-

-
ボダイジュの育て方
ボダイジュは、シナノキの木科シナノキ属中国原産の落葉高木です。学名は、TiliamiquelianaTiliaで、Til...
-

-
サルビア(一年性)の育て方
サルビアの正式名称はサルビア・スプレンデンスであり、ブラジルが原産です。生息地として、日本国内でもよく見られる花です。多...
-

-
アラマンダの育て方
アラマンダはキョウチクトウ科 Apocynaceaeのアリアケカズラ属 Allamanda Linn. の植物です。原産...




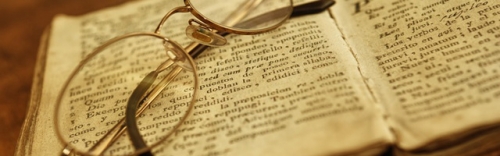





デルフィニウムはキンポウゲ科の花で、5月から6月頃に様々な色の繊細で美しい花を咲かせます。背が高い茎に小さな花をたくさん咲かせるので華やかさがあり、花壇や鉢植えで育てるだけでなく、切り花としても人気があります。