ブリメウラ・アメシスティナの育て方

育てる環境について
もともと高山地帯を生息地とする鉱山植物であるため、寒さに強く、日当たりを好む傾向があり、育て方としてはそこまで難易度は高くありません。冬場の積雪に耐えることができるので、落葉樹の下など、夏の直射日光を避けられるような場所であれば植えっぱなしにすることも可能です。
暑さと加湿には弱いので夏場の直射日光を避け、通気性の良い腐葉土を土に混ぜ込みます。年間を通して気温の高い地域や、海からの湿った風を浴びやすい地域での栽培は、温度管理や湿度管理など、やや配慮が必要です。そういった環境の屋外で栽培をする場合は、庭植えではなく移動の可能な鉢植えにすることで季節や天候の変化に対応しやすくなります。
日本国内では梅雨時期が少なく、年間を通して平均気温の低い東北~北海道のような環境が栽培には向いています。そのほか、山間部などの地域も栽培に向いているといえます。庭植えをする際は、ロックガーデンにすることで「ブリメウラ・アメシスティナ」などの高山植物全般にとって育ちやすい環境をつくることが可能です。ロックガーデンとは岩石を配置し、その隙間に植物を植えて楽しむ庭園のことです。
通常花壇に植えるか鉢植えをする植物も、ロックガーデンでは石と石との間に植えていくことになります。一度植えてしまうと移動が困難な面もありますが植物が本来生息しているべき環境に近いため、ストレスなく成長させてあげることができます。また、土が吸収できる水分と石が吸収できる水分の関係で、植物にとって適度な水分を保つこともできるので「ブリメウラ・アメシスティナ」のような湿度に弱い植物に向いています。
種付けや水やり、肥料について
植えつけは9月から10月、継続的な湿気と球根腐れを避けるため必ず台風シーズンが過ぎてから行うようにします。植えつけ場所は上記の「育てる環境」にもある通り、地域の環境に合わせて決定します。用土は水はけと通気性のよいものを選ぶようにし、酸性の土壌を嫌いますので石灰を撒いて酸性を中和するとよいです。
植えつける球根は重量があり、傷がなくふっくらとしたもの(直径の大きいもの)を選ぶように心がけます。傷があったり、重量が軽い、斑点や変色、分球してしまっているものは上手く発芽しない可能性があるので注意が必要です。球根には「葉が出る」「花が咲く」向きがあるため、植えつけの際は球根の向きに注意をする必要があります。
これを怠ってしまうと成長していく過程で葉が重なり合い、十分な日光が得られず成長しないものが出てきてしまいます。「ブリメウラ・アメシスティナ」は生育に多くの日光を要するので、日光量の差は後の花つきに大きく関係してきます。もともと多くの花を咲かせる植物ではないので、植え付けの際から十分な配慮を行うようにしましょう。球根の頭が少し出るように植えつけます。
庭植えの場合、植え付け~4月くらいまでの生育期の間は、乾燥が続くようであれば水を与えてください。必要以上の水やりは球根腐れ、根腐れの原因になるので避けるようにします。鉢植えの場合は土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えてください。肥料は、植え付けの際にあらかじめ緩効性の肥料を混ぜ込んでおきます。その後芽が伸び、花が咲くまでの間、1週間~10日に1回のペースで液体肥料を追肥として与えます。
増やし方や害虫について
咲き終わった球根を来年咲かせる場合は、葉が黄変し始めたら鉢ごと乾燥させるか、花が終わった後の球根を掘り上げて日陰で乾燥貯蔵します。葉が黄色く変色してから葉をむしり、日陰の風通しのいいところで、管理して9月にまた植えます。掘り上げ後にカビが発生する場合もあるので、梅雨時期に入る前までに堀り上げを行えると理想的です。
増やしたい場合は、掘り上げた球根に傷を付けて増やします。傷を付けた親球根は犠牲になり花は二度と咲きません。方法は、掘り起こした球根を底から半分くらいの深さまで、十文字に深く切れ目を入れます。秋に植え付けるまで風通しのよい涼しい場所に置いておくと切れ目に小さな球根がついてくるので、これをそのまま土に植え付けて育てると2年から3年程で花の咲く大きさの球根になります。
この場合も、カビの発生を避けるため、梅雨入り前に堀り上げを行うようにしましょう。球根の掘り上げや切り込みを入れる際、球根からかぶれる物質が出ているので素手では触らないように注意します。つきやすい害虫はとくにありませんが、かかりやすい病気として軟腐病にかかることがあります。
これは細菌性の病気で、球根に傷があるとそこから入り込みます。発病すると球根が溶けるように腐っていきます。一度被害に遭ってしまうと治療することが難しく、該当する株は処分するのが一般的です。軟腐病の予防として、とにかく水はけをよくして連作を防ぐことが大切です。
ブリメウラ・アメシスティナの歴史
「ブリメウラ・アメシスティナ」は、南ヨーロッパを原産とした鉱山植物です。花の宝庫と呼ばれ大自然あふれる山脈、ピレネー山脈の岩肌に自生していることで有名です。ピレネー山脈はフランス・スペインとの国境沿いに広がる東西約430kmの山脈であり、最高峰のアネト山(標高3404m)を中心に標高約3000m級の山々が連なっています。
氷河や大渓谷を有し、その特殊な環境から、一年を通して珍しい鉱山植物の生息地となっています。幾多の生息地の中でもとくに生育環境が厳しい高山地帯は、冬季の積雪と低気温、日中の温度差、強風、貧弱な養分の土壌、陽射しが強く紫外線が多いことなど、多くの点で植物の生育には向かないことがほとんどです。
今日に至る「ブリメウラ・アメシスティナ」の長い歴史の中で、その種を絶やさず殖え続けられてきたということは、上述の厳しい環境にも屈しない柔軟な適応力と特徴を持っているといっても過言ではありません。現在日本で出回っている「ブリメウラ・アメシスティナ」も、ピレネー山脈を原産とした輸入品種であることがほとんどです。
「ブリメウラ・アメシスティナ」は、旧学名を「ヒアシンサス・アメジスティヌス(Hyacinthusamethystinus)」または「ヒヤシンス・アメシスティヌス」ともいい、現在でも学名や名称にはばらつきがあります。また、和名を「球根釣鐘草」といいます。花弁や葉の形状から「イングリッシュ・ブルーベル(シラーカンパニュラータ)」と間違われることもありますがそれらとは異なる種です。
ブリメウラ・アメシスティナの特徴
「ブリメウラ・アメシスティナ」は、春から初夏(5月~6月)にかけて青いベル形の花を咲かせる多年草、ユリ科の小球根です。花弁は雄べを守るように筒状に開花するため、開花姿がベルのようになっているのが特徴です。歴史についての文で触れているように、開花姿は「イングリッシュ・ブルーベル(シラーカンパニュラータ)」にもよく似ていますが、
雄べの作りが異なっていることや花つきの数、草丈の違いで見分けることが出来ます。「イングリッシュ・ブルーベル(シラーカンパニュラータ)」に比べると、「ブリメウラ・アメシスティナ」の方が草丈が低く、花の数が少ないため上品な印象があります。草丈は10cm前後まで成長し、生育環境によっては25cm程の高さに成長する場合もあります。
一本の太い茎の成長に伴い、茎の先端に上向きに蕾をつけていきますが、開花時は茎にぶら下がるようにやや下向き加減に開花していきます。花つきは少なく、一本の茎に対して5~10輪程の数輪の花を咲かせます。花色は淡い青紫色から濃い青まで様々ですが、そのほとんどが青色系統ということは変わりません。
種小名のアメシスティナはすみれ色(バイオレット)を意味しています。ごく稀に白色の花を咲かせる種が出回っていることもありますが、その入手方法や開花条件は明らかになっていません。花弁に通る脈の色合いによりストライプに見えるため、初夏に見られる開花姿はとても涼しげで凛とした印象があるのが特徴です。
-

-
サルスベリの育て方
サルスベリは、木登り上手のサルですら、すべって登ることができないほど、樹皮がツルツルとなめらかなことからつけられた名前ら...
-

-
リグラリアの育て方
リグラリアは菊科の植物で、原産は東アジアの広い地域を生息地にしています。日本においても、かなり古くからある植物で、中国と...
-

-
たまねぎと夏野菜の育て方
たまねぎは秋に植えて、春に収穫します。一方、夏野菜は春に植えて夏に収穫します。畑を作るときには、この春野菜と夏野菜を両方...
-

-
ニオイバンマツリの育て方
ニオイバンマツリはナス科の植物で南アメリカが原産となっています。生息地はブラジルやアルゼンチンなどの南米の国々となってい...
-

-
オモダカの育て方
オモダカは、オモダカ科オモダカ属の抽水植物、湿生植物で多年草です。草丈は約30〜70cm程度です。原産地はアジアと東ヨー...
-

-
チンゲンサイの育て方
チンゲンサイの原産地は、中国の華中、華南といった地域が原産地ではなかったかと考えられています。アブラナ科で原種とされるも...
-

-
ビフレナリアの育て方
花についてはラン科になります。園芸上の分類もランになります。ランについては多くは多年草です。しかし育て方が難しいのでずっ...
-

-
サルピグロッシスの育て方
サルピグロッシスはナス科サルピグロッシス属(サルメンバナ属)の一年草または多年草です。その名前はギリシャ語のsalpin...
-

-
ヒマラヤユキノシタの育て方
ヒマラヤユキノシタとは原産がヒマラヤになります。おもにヒマラヤ山脈付近が生息地のため、周辺のパキスタンや中国やチベットな...
-

-
ヤブコウジの育て方
こちらの植物は被子植物、真正双子葉類、コア真正双子葉類、キク類になります。更にツツジ目、サクラソウ科、ヤブコウジ亜科とな...




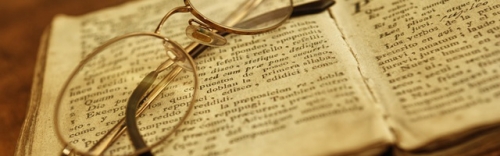





「ブリメウラ・アメシスティナ」は、南ヨーロッパを原産とした鉱山植物です。花の宝庫と呼ばれ大自然あふれる山脈、ピレネー山脈の岩肌に自生していることで有名です。ピレネー山脈はフランス・スペインとの国境沿いに広がる東西約430kmの山脈であり、最高峰のアネト山(標高3404m)を中心に標高約3000m級の山々が連なっています。