ゲンペイカズラの育て方

ゲンペイカズラの育てる環境について
アフリカ原産の熱帯の植物ですから、冬は室内での管理になります。室温が5度を下回らない場所(出来れば10度以上)においてあげてください。窓越しに日の当たる場所が好ましいです。日当たりが花数を左右しますので、春から秋は庭やベランダなどの日当たりがよい屋外で育てます。
斑入りの方は通常の品種よりも寒さに弱い上、真夏の直射日光に当てると葉が日焼けして変色してしまうこともあるので育て方には一層の注意が必要になります。ゲンペイカズラは霜に当たったり、凍ってしまった場合は死んでしまいますが、寒さで葉が落ちてしまった場合なら、春に再び芽吹いて復活します。
ですのであきらめずに水遣りを続けてみてください。つるが長く伸びて来たら、アサガオなどに利用する「あんどん支柱」を立てて、つるを絡ませて行きます。どの植物にも言えることですが、店頭で売られている時には生体に対し若干小さい鉢に植えられているため、水切れが非常に早いのです。
買ってきた時期(主に夏に売られています)はゲンペイカズラの生育期に当たり、一番水を必要としている時期なので、出来れば大きな鉢に植え替え、前述のあんどん支柱も加えてあげるのがベストです。大きな鉢への植え替えは、ほぼ毎年することになります。
鉢の底から根がはみ出して来ている、たっぷり水を遣ったのに水切れしてしまう、という症状が出てきたら、それが植え替えの目安になります。植え替えの際利用する土は、市販されている観葉植物の土で大丈夫です。
種付けや水やり、肥料について
ゲンペイカズラに種付けの必要はありませんが、花弁が落ちた後には、ガクの奥に発生した種と見られるものを観察することができます。しかしゲンペイカズラの増やし方としては、一般的にはさし木で増やして行くことになります。たくさんの水遣りが必要なのは生育期となる春から秋です。
この時期は土の表面が乾いたら、たっぷりと水を与てください。特に夏は水の吸い上げが強いので、毎日朝と夕方の2回あげてください。春と秋は(雨の日を除いて)1日1回あげましょう。しかし、過湿は根腐りの原因になりますので、土が濡れているのであれば水はやらないでください。
冬場はほぼ休眠状態といってよく、水もさほど吸わないので、土の表面が乾いて数日経ってからの水遣りで十分です。 寒さで葉が落ちてしまった株は完全に休眠している状態ですので、特に過湿にならないよう気をつけてください。
水遣りは水の量を調整するよりも回数を調整する方がうまくいきます。肥料は春から秋にかけて与えます。ゆっくりと効いていくマグァンプ・花ごよみ・ エードボールCa等の緩効性肥料を2月に1回、だいたい10~15g程度を土の表面に補充する感じで良いと思います。
しかし開花の時期にはより多くの肥料を必要としますので、ハイポネックスや花工場・ハイポニカなどの液体肥料も併用してあげてください。液体肥料の頻度は月に1~2回で大丈夫です。冬場の肥料は特に必要ありません。
増やし方や害虫について
ゲンペイカズラはさし木で増やします。さし木に適切な時期は気温の高い5月から9月にかけてです。まだ花をつけていない若い新枝を2節ほどの長さに切り、清潔な川砂に挿します。なぜ川砂を使うのかというと、一般的な観葉植物の土などは栄養豊富なため雑菌が沸きやすく、
その土に挿した木が雑菌に侵される心配があるからです。また川砂は土より水ハケが良いため、根腐れの心配がないからです。新たに買い求める場合は建築用の川砂は不向きですので、園芸用の川砂を買ってください。また少し高価になりますが、
殺菌済みの川砂(サボテン・多肉植物専用無菌清浄川砂など)もあるので、さし木の成功率が低い場合は利用すると良いと思います。さし木をしたら、根が出るまでは直接日の光が当たらない明るめの日陰に置いてあげて、乾かさないように管理してください。
なお植え替えに最適な時期は5月~6月になります。病気はほとんど心配ありませんが、よく付く害虫としてはアブラムシ・カイガラムシ・ハダニ・コナジラミなどが挙げられます。アブラムシは茎葉に、コナジラミ・ハダニは葉の裏で吸汁します。アブラムシ・ハダニ・コナジラミはコロマイトやダニ太郎などの殺虫剤で駆除してください。
カイガラムシは殺虫剤だけで駆除するのは難しいので、見つけたら柔らかい布で拭き取ってください。なお殺虫剤の使用に抵抗がある場合は、薬剤を使用せずにデンプンを利用した粘液で虫を捕縛する「粘着くん」という液剤が住友化学から発売されているので、参考にしてください。
ゲンペイカズラの歴史
ゲンペイカズラ(源平蔓) クマツヅラ科クレロデンドロン(クサギ)属シソ目 別名はゲンペイクザギ(源平臭木)。アフリカ西部を原産とするツル性の常緑小低木です。生息地は熱帯ですので戸外での越冬は難しく、冬季は5~10度以上を保てる室内での栽培が必須となります。
ゲンペイカズラが日本へ入ってきたのは明治時代中ごろと云われています。ゲンペイカズラ・ゲンペイクサギの名の由来ですが、カズラの名はいわゆる「ツル性の植物」を意味し、クサギはゲンペイカズラの葉っぱの匂いからきています。
そして「ゲンペイ」は源平合戦の源平から由来しており、白いガクを源氏の白旗に、赤い花弁を平家の赤旗にみたてたものだと云われています。白いガクから飛び出した真っ赤な花弁は、とても華やかに咲き誇るのですが、やがて散り落ちてしまい、白いガクのみの姿になります。
壇ノ浦の戦いで敗戦を悟った赤旗の平家の武将たちが、次々と海へ身を投じていき、平家が滅びてしまうという歴史を体現したお花だといえます。英名である「Bleeding glory-bower」は、直訳すれば「血を流す八重咲き臭木」となります。
鮮やかな赤い花弁を血という言葉で表現したものですが、私たち日本人からすると、この名はちょっとオドロオドロしい感じがしてしまいますね。ちなみにglory-bowerはクレロデンドロンに属する植物の英名で、これにJapaneseがつくとJapanese glory-bower=「ヒギリ」(緋桐)になります。
ゲンペイカズラの特徴
ツル性の常緑木ですので、他の植物などに巻きつきながら上へと成長していきます。高さは2mほどまで成長しますが大きいものだと4mに達することも。伸びたつるを支柱へと絡ませてあげると、大変多くの花を付ける様になります。好みの大きさに選定してしまうと花数が減ることになるので、
バランスを見ての選定を心がけてください。開花期は初夏~秋です。アフリカ原産の熱帯の植物の為、日本では戸外での越冬は出来ません。クサギの名の通り、葉っぱを揉むと少し異様な匂いがしますが、育てるのに気になるほどでは無いので安心して下さい。
一番の特徴となる花は、白色のガクと赤い花弁で構成されています。ほおずきのような形に膨らみ先端が尖った袋状になった白いガクは、2センチほどの長さになると、先が5つに割れ、中に丸く赤いつぼみが見えてきます。そのつぼみはやがてガクの外に出て来て花開いて行きます。
丸かったつぼみは1.5センチほどの大きさになると先端が5つに割れて平らに開いていき、中心からは雄しべ4個と雌しべ1個が長く突き出してきます。花弁が散ったあと、白かったガクはやがて紫色に色づいていきます。ゲンペイカズラの園芸品種である
「フイリゲンペイカズラ(斑入り源平蔓)」は葉に覆輪の斑が入ったもの。花が無い時期でも観葉植物として楽しめるため人気がありますが、ガクと花弁の白赤のコントラストを楽しむには、ゲンペイカズラの緑の葉の方が白と赤が引き立ち美しいとする声もあります。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ノウゼンカズラの育て方
-

-
ニガナの育て方
ニガナはキク科の多年草で、原産地及び生息地は日本や東アジア一帯ということで、広く分布している植物でもあります。日本でも道...
-

-
コメツガ(米栂)の育て方
コメツガは、昔から庭の木としても利用されてきましたが、マツ科のツガ属ということで、マツの系統の植物ということになります。...
-

-
フヨウの育て方
原産地は中国で、日本には室町時代に鑑賞の記録が残っています。そのことから、古くから栽培されていたのではないかと考えられて...
-

-
アイビーゼラニュームの育て方
特徴としては多年草です。基本的には冬にも枯れません。非常に強い花です。真冬においても花を維持することもあります。ですから...
-

-
主婦の間で密かなブームとなっている栽培方法
現在、主婦の間で密かなブームとなっているのが、お金のかからない種取り栽培です。これは、スーパーで買ってきた野菜や果物のタ...
-

-
家庭菜園や花壇の作り方において大事な事
家庭菜園や家庭花壇などを作る場合においては、まず植物の栽培方法はもちろん、植物の育て方から植物の種まきのやり方の基本まで...
-

-
セキショウの育て方
元々はサトイモ科に属していました。しかし実際の姿とサトイモの姿とを想像してみても分かる様に、全くサトイモとは性質が違いま...
-

-
ビデンスの育て方
アメリカを主とし世界じゅうを生息地としていて、日本でもセンダングサなど6種類のビデンスが自生しています。世界中での種類は...
-

-
フェスツカ・グラウカの育て方
フェスツカ・グラウカは、ヨーロッパ原産の、イネ科の植物です。寒冷地などに多く自生している、細い葉が特徴の植物で、6月から...
-

-
ヤトロファの育て方
特徴としては、被子植物、真正双子葉類に該当します。バラ類、キントラノオ目、トウダイグサ科、ハズ亜科となっています。油の原...




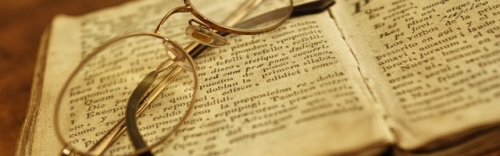





ゲンペイカズラ(源平蔓) クマツヅラ科クレロデンドロン(クサギ)属シソ目 別名はゲンペイクザギ(源平臭木)。アフリカ西部を原産とするツル性の常緑小低木です。