サルスベリの育て方

サルスベリの育て方
サルスベリは、苗木から育てるのが簡単とされ、土壌はとくに選びませんがやはり水はけのよい土が良いとされています。夏に花咲く樹木ですが、夏に極端に乾燥させると、葉先が茶色に変色することがあるので極度の乾燥には気をつけます。日当たりを好むため、日がよく当たる場所での育成がよく、いずれの種類も十分に花を咲かせるために、少なくとも午前中の間は日が当たる場所を選んで植えるようにしてください。
植えつけは、厳冬期を除いた落葉中の10月から11月がふさわしく、または、芽が動き出す前の3月から4月に植え付けるがベストです。庭地に植える場合は、根鉢の倍の深さと幅の植え穴を掘ってから、腐葉土を3分の1ほど入れてから土と混ぜて植えつけます。
水を周りから十分に注ぎ、周りの土を棒などでつつき根と土をしっかりとなじませるのがポイントです。鉢植えでは、赤玉土(小粒から中粒)を6として腐葉土4の割合で植え付けます。面倒であれば樹木専用の土というのを利用してもいいです。
水やりは地植えの場合には、雨の水だけでよいとされますが、干ばつや強い日照りでの水不足の場合は朝、夕と2回ほど水をあげるのがよいです。鉢植えの場合は、乾きやすいので水やりには注意が必要です。表面が乾いたらたっぷりと水をあげてください。肥料ですが、12月から1月に寒肥として粒状肥料をあげてください。
サルスベリの剪定について
サルスベリを育てるにおいて、不可欠なのが剪定です。年に二度行うのがベストとなっており、翌年も花付きをよくするために剪定をしてあげてください。サルスベリは春に出た枝を伸ばしながら、花芽を作っていく特性のため、剪定は落葉して枝ぶりがよく分かる、2月から3月中旬がわかりやすくておすすめです。
花が終わった10月下旬頃に一度、少し剪定して整えるといったことをすればついでに花がらを一緒に取り除くことができます。この花がら摘みも種を付けて木を消耗させないためには重要な作業といえます。ここで注意したいのが、早春から初夏にかけての剪定はしてはいけないということです。
サルスベリは、その年の春から初夏にかけて伸びた枝の先に花をつける性質を持ちますので、この時期に剪定すると花を楽しむことができなくなります。剪定のやり方は、本年枝を付け根から2cmほど残してばっさりと切り詰めます。
枝をごく短く切り詰めると翌春に勢いのある長い枝が伸びやすく、サルスベリはこのような枝にたくさんの花をつけるので先だけを少し切るということはおすすめしません。枝の先端だけを切り詰めるような剪定では、出てくる枝は貧弱で、花付きが悪いという理由があるからです。
本年枝の切り詰める長さで翌春の枝の伸びが変わってくるというのがサルスベリにはあり、剪定がいかに重要なポイントかわかります。どんな樹木にはいえることですが、株の内側にも日が当たるようにするというも大事です。そういったポイントをおさえることで毎年、たくさんの花を咲かせることができるようになります。
ほかにも、剪定をしないとサルスベリ特有である、枝がコブ状になってしまうこともあり、この見た目を不快に思うひともいます。その原因となるのがまさに剪定不足であり、そうならないためにも剪定はしたほうがよいといえます。
剪定しないと、もともと大きくなる性質の木なので7メートルくらいに張り出して成長することもあります。そうなってくると台風であおられて倒れたりすることも考えられます。そういったことにならないためにも剪定をすることがおすすめです。
サルスベリの増やし方と病害
サルスベリは種、もしくは挿し木での種付けで増やすことが可能です。挿し木の適期は3月末から4月はじめとなっており、前の年にのびた枝を先から20cmほどの長さに切ります。そして、切り口を水に1時間ほどつけて水揚げをしてから、赤玉土に斜めにさします。
管理は日陰で水切れを起こさないようにしっかりと管理します。枝ですのでなかなか根がでにくいといったこともあり、だいたい6月くらいに鉢に移植します。種での栽培法もありますが、種だと花が咲くまでに時間が掛かってしまいます。成長する様を見たいなど、じっくり育成してあげたい場合には種で増やすのもよいです。
また、種でいえば一才性の園芸品種「アスカ」は、春にタネをまくと早いものでその年から花を咲かせることもあるようです。こういった品種を選んでみるのも良さそうです。サルスベリは強健な木ですが、風通しが悪いことでうどんこ病になることがあります。うどんこ病が発生すると、葉や花が白い粉のような菌糸に覆われ、生育を弱らせてしまいます。
そのためにも予防するには、風通しをよくすることが必要です。冬には、枝が込み合わないためにもしっかりと剪定しておくことがよく、気になるようであれば、うどんこ病予防の薬剤を散布してください。また、うどんこ病に耐性を持った品種もでているのでそういった品種を選んで植えるのも対策になっておすすめです。
サルスベリの歴史
サルスベリは、木登り上手のサルですら、すべって登ることができないほど、樹皮がツルツルとなめらかなことからつけられた名前らしく、名前のユニークさとは違って花はとても華やかで美しいです。
花びらはフリル状に波打っており、それらの花が集合することでとてもボリュームのある艶やかなものとして見ることができます。日本では、百日紅(ひゃくじつこう)と呼ばれていますが、生息地は中国原産で本来の漢名は「紫薇(しび)花」といいます。
江戸時代頃に日本に伝来したといわれていますが、日本にやってきた正確な時代は不明とされています。おそらくは、1708年以前ではないかと推測されています。この漢字名の「百日」とは100日ほどの長い期間咲くことが由来しており、夏の間を長く楽しめる花としても人気があり、日本でも昔から親しまれています。
また、幹を手で掻くと、木がくすぐったがって、風もないのに枝葉が動くという中国の故事に由来するものとして「コチョコチョノキ」という名前などでも呼ばれていたらしく、たくさんの呼び名が存在します。
サルスベリの特徴
本来は樹高10mになる落葉高木とされていますが、イッサイサルスベリと呼ばれる樹高30cm程度で花を咲かせるものも存在しており、こういった矮性サルスベリが道路や公園に植えてあるのをよく見かけます。サルスベリには白、ピンク、紅、紅紫などの色のものがあり、どの花も夏から秋へと花を咲かせるものとしています。
毎年たくさんの花を咲かせることから庭木としても植えているひとも多く、園芸品種には低木性の「パープル・クイーン」や「サマー&サマー」やタネをまくと1年以内に開花する極低木性の「アスカ」など、人気のものがたくさんあるようです。
またサルスベリの仲間も多数存在し、シマサルスベリ、ヤクシマサルスベリ、オオバナサルスベリ、ムラサキサルスベリなど様々なものがあります。艶やかできれいな花を咲かせる樹木ですが、花が終われば実が次々とできます。この実というのが熟して弾けると花のように開き、ドライフラワーとしても利用するひとがいるようです。
花が咲いている途中にもすぐに実を付ける特性があるため、花をもっと楽しみたいのならすぐに実の付いた枝を剪定すれば、枝から新芽がでてまた花を咲かせるといった楽しみ方ができます。この種が熟せば種としての利用ができ、土などに蒔けば育成することも可能です。
真夏の太陽の下でも元気に咲き続けるサルスベリは、見るひとに強いインパクトを与え、可憐で艶やかな美しさは忘れられない花といえます。こういった風情ある花を庭木にして家の周りを飾るのも大変おすすめです。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:フジの育て方
タイトル:アベリアの育て方
タイトル:テイカカズラの育て方
タイトル:カナメモチの育て方
タイトル:ウメモドキの育て方
-

-
ギョリュウバイの育て方
ギョリュウバイはニュージーランドとオーストラリアの南東部が原産のフトモモ科のギョリュウバイ属に分類されている常緑樹で、日...
-

-
アボカドのたねは捨てずに育てよう
「森のバター」とも呼ばれている果実をご存知でしょうか。これは、アボカドの事を指しますが、栄養価が高く、幅広い年代に人気の...
-

-
スズメノエンドウの育て方
生息地は日本となっていますが、マメ科のソラマメ属に分類しています。後援などに雑草のようにその姿が見られ、古くから周りの草...
-

-
クラッスラの育て方
クラッスラはベンケイソウ科のクラッスラ属に属する南アフリカ、東アフリカ、マダガスカルなどが原産の植物です。クラッスラ属は...
-

-
コバンソウの育て方
コバンソウはイネ科の植物で、大振りの稲穂がしなだれているような姿をして居ます。四月の終わりから七月ごろにかけて徐々に開花...
-

-
エラチオール・ベゴニアの育て方
エラチオール・ベゴニアは、日本でもポピュラーな園芸植物のひとつで、鉢植えにして室内で楽しむ植物としても高い人気を誇ります...
-

-
セネシオ(多肉植物)の育て方
植物としては多年草に分類されます。キク科に属しており、つる植物という独特な分類になっています。これは種類が非常に豊富にあ...
-

-
トウモロコシ(スイートコーン)の育て方
トウモロコシは夏になるとお店の店先に登場する夏を代表する野菜です。蒸かして食べたり、焼きトウモロコシで食べたり、つぶだけ...
-

-
ワイルドストロベリーの育て方
ワイルドストロベリーの特徴は野生の植物に見られる強さがあることです。踏まれても尚踏ん張って生きている雑草に例えることがで...
-

-
カラスウリの育て方
被子植物に該当して、双子葉植物綱になります。スミレ目、ウリ科となっています。つる性の植物で、木などにどんどん巻き付いて成...




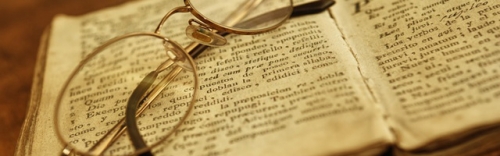





サルスベリは、木登り上手のサルですら、すべって登ることができないほど、樹皮がツルツルとなめらかなことからつけられた名前らしく、名前のユニークさとは違って花はとても華やかで美しいです。