モラエアの育て方

育てる環境について
モラエアの育て方の三大原則はその一、暖かい気候である事その二、水をやり過ぎず乾燥気味の環境である事その三、霜にはなるべく当てない様にする事です。暖かい気候というのは、この花の原産国であるアフリカ南部から来ています。日本では冬から春にかけて咲く花なので寒さには強いと勘違いされやすいのですが、寒さに弱い半耐寒性の植物ですので寒過ぎると枯れてしまいます。
日光によく当たる場所で伸び伸びと育ててあげましょう。次に水をやり過ぎないという点ですが、これも原産国が南半球の乾燥した気候であるがゆえです。使用する球根も予め日陰で乾燥させてから植えると育つ確率がアップします。使用する土も水はけ優先で選びましょう。そして最後の霜に当てない様にする事は大事なポイントです。
関東よりも下の平野部の地域では、霜による枯死は比較的少ないですが心配な場合は花壇への直植えは避けプランターや鉢植えが確実です。よくマンションは、モラエアが育つ環境に適していると言われています。特に上層階は湿気も少なく、ベランダなどの屋外に出していても霜に当たる事もなく立派に咲くそうです。
これを見習い、霜に当たらない様軒下に避難させたり屋内で育てたり出来る様に鉢植えがオススメです。この三大原則さえしっかり把握しておけば、多少放置気味でも綺麗な花を咲かせてくれます。しかし何度も言うようですが、この花は一日花です。放置し過ぎて、開花を見逃さない様気をつけましょう。
種付けや水やり、肥料について
種類にもよりますが、球根の植え付けは10月~11月にします。比較的寒い地域なら11月下旬でも良いです。葉っぱが伸びてしまってから、凍結する様な寒さがやってくると枯れてしまう危険性があるからです。住んでいる地域の春の訪れを逆算して半年前を目安に植え付けましょう。また鉢やプランターに植える際は、10㎝位間隔を取り植えていきます。
7号鉢なら5球位が目安になります。花壇の場合は10㎝~15㎝位を間隔の目安にします。そして深さは鉢やプランターで3㎝、花壇なら5㎝位の深さに植えます。培養土は硬質中粒鹿沼土を基本にピートや川砂を少々混ぜてあげると水はけもよく育ちがいいです。腐葉土を混ぜてあげるのも栄養がたっぷり含まれているので良い方法ですが、コバエが発生する可能性が高くなります。
とは言っても、気候などの環境が良ければ野生でも丈夫に育つ花ですので一般的な培養土でも充分育ちます。肥料はチッ素系の肥料は控え、緩効性の化成肥料を予め元肥料に混ぜておきます。そして成長過程を見ながら固形肥料を置き肥してあげましょう。球根を植え付けた後は、
水をたっぷり目に与え芽が出始めたら日当たりと風通しの良い場所に移動し乾燥気味に水を与えます。表面の土が乾いてきたら、少し湿らす程度に与えましょう。アフリカ育ちの植物ですので、少なめの水でも生命力は強いです。雨があまりにも降り続くようなら根腐れの危険性も出てるので、雨水から避難させてあげるなどの対策も必要です。
増やし方や害虫について
モラエアはあまり害虫被害にはあいにくい植物です。しいて言うならば、アブラムシやハダニには注意が必要です。ダニ退治薬などで除去する事が出来ますの、早めの対処が必要不可欠です。かかりやすい病気はウィルス病です。この病気は別名モザイク病とも呼ばれ、茎や葉に模様が表れます。発見したら速やかに抜き取って処分しましょう。
このウィルス病はアブラムシなどの害虫が運び屋となって伝染します。人や動物に伝染する事はありませんが、植物を枯死させてしまいますので拡大しない様にしましょう。対策としましては、アブラムシなどをすぐに退治する事と剪定用のハサミなどに液汁が付いて媒介してしまう可能性もあるので熱湯消毒をして清潔に保つ事です。
この花の球根は来年もまた植える事ができ、繁殖力も高いのが特徴です。しかし親株がこの病気に感染していると病気も遺伝してしまいます。病気にかかった球根は処分し新しい球根を植える様にしましょう。では最後に増やし方ですが、種が勝手に落ちたり飛んで行って繁殖をする事もあり簡単に増えていく植物です。
一般的には、花が咲き終わったら葉が枯れるまで待ち球根を掘り起こして日陰で干します。網袋などに入れて保管しておきましょう。花壇の場合一度掘り起こして乾燥させた後、そのまま土の中で夏の間は休眠させるのも良い方法です。しかしこの球根はネズミの食害にもあいやすので、食べられない様に引き上げておくのが得策です。
モラエアの歴史
アヤメ科モラエア属であるこの花は球根から育つ多年草の小球根類です。まだまだ謎の多い種類で植物学者や植物マニアの人達が研究している最中だそうです。そんな謎の多いこの花はイギリス人の植物学者ムーアさんによってモレアと名付けられました。今でもモレアと呼ばれたりモラエアと呼ばれたりします。
この花の原産国はアフリカ南部のケープ地方で、傾斜地に冬の時期に自生している姿をよく見かけられます。温暖な気候を好むこの植物は、地中海沿岸や亜熱帯の南半球に生息地を拡大させてきました。その後何年もかけて、植物鑑賞用に育種され日本にも渡来したと言われています。
アヤメ科モラエア属の仲間は100種類あると言われていますが、実際栽培されているのは25種類しかないそうです。日本に多く出回っているのは、「ポリスタキア」と「ビローサ」です。丈夫で繁殖力の高い植物ですが、日本では希少価値が高く球根も意外と高値で売られており予約待ちというケースもある程です。
さらに優雅な雰囲気の漂うエレガンスや、孔雀羽根模様がプリントされた様なアリスタータなど野生種により近いモラエアはもっと入手が困難です。しかしこの華やかでインパクトのある花に魅せられる人は多く、希少価値の高さはまだまだ続くと予想されます。そんな希少価値の高いモラエアの球根ですが、栽培方法は意外とシンプルで勝手に種が蒔かれて道端に野生の様に咲いたというケースもよくある様です。
モラエアの特徴
この花の特徴は、冬から春にかけて咲く事と蜜標にインパクトがある事です。特に日本では、冬に華麗な花が咲く事は珍しいので庭の彩りに欠かせない貴重な存在です。この華麗さを際立たせているのが蜜標です。馴染みが深いであろうポリスタキアという種類のタイプは、薄い紫色の花びらに黄色の蜜標が特徴です。
またビローサは、蜜標が蛇の目の様な孔雀の羽模様の様なデザインが入ってます。まさに一度見たら忘れられない花です。他にもオレンジ色の花びらに青い目がついたネオパボニアという種類や、オレンジ色の花びらに黒い模様のついたツルバゲンスなどとにかく見た目が派手で目立つものが多いです。
蜜標が目立つのには理由があり、受粉の為の昆虫をおびき寄せる狙いがあると言われています。あまりの鮮やかさに虫達が驚いてしまわないかと心配になりますが、繁殖力が強い植物だという事なのでこの蜜標のお陰でしょう。絵に描いたような美しい蜜標にはさらに秘密が隠されており、紫外線を吸収するといつ役割も担っているそうです。
花茎は4㎝程の小ぶりな花ですが、蕾の姿から愛らしく、その存在感は遠くからでも目を引きます。艶やかで、優秀なモラエアの花言葉は「感受性」や「豊かな感性」と言われおり、知的さも感じる植物です。まだまだ日本ではアヤメと間違えられる事が多いですが、アヤメは水辺に咲く花でモレアは乾燥した所を好む花という大きな違いがあります。見分けるポイントとしては蜜標が派手な方です。
-

-
セロジネの育て方
セロジネはラン科の植物でほとんどの品種が白っぽい花を穂のような形につけていきます。古くから栽培されている品種で、原産地は...
-

-
チガヤの育て方
この植物に関しては、被子植物で単子葉植物綱になります。イネ目、イネ科になります。園芸分類上はグラスで、毎年成長する多年草...
-

-
ドラセナ・フラグランス(Dracaena fragrans)...
ドラセナの原産地は、熱帯アジアやギニア、ナイジェリア、エチオピアなどのアフリカです。ドラセナの品種はおよそ60種類あり、...
-

-
シラネアオイの育て方
シラネアオイの原産地は、日本で日本固有の壱属一種の多年草の植物ですが、分類上の位置が二転三転してきた植物でもあります。昔...
-

-
カサブランカの育て方
カサブランカは、大きな白い花が見事なユリの一種です。その堂々とした佇まいから、ユリの女王とも呼ばれています。カサブランカ...
-

-
ニオイヒバの育て方
ニオイヒバはヒノキ科 の ネズコ属に属する樹木です。原産国は北アメリカで、カナダの生息地です。日本では「香りがあるヒバ」...
-

-
クリ(栗)の育て方
クリの歴史は非常に古いものであり、縄文時代の遺跡である三内丸山遺跡からも数多くの栗が出土しています。そのため有史以前から...
-

-
クワズイモ(Alocasia odora)の育て方
涼しげな葉で人気のクワズイモですが、その名はサトイモに似た葉からつけられました。サトイモに似てはいますが、イモに見える茎...
-

-
ステビアの育て方
ステビアは、パラグアイをはじめとする南アメリカ原産のキク科ステビア属の多年草です。学名はSteviarebaudiana...
-

-
アメリカノリノキ‘アナベル’の育て方
白いアジサイはアメリカノリノキ、別名セイヨウアジサイの園芸品種であるアナベルという品種です。アジサイの生息地は世界ではア...




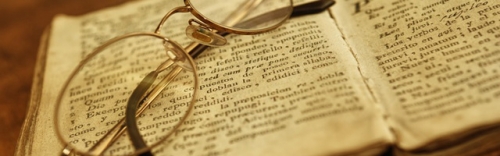





アヤメ科モラエア属であるこの花は球根から育つ多年草の小球根類です。まだまだ謎の多い種類で植物学者や植物マニアの人達が研究している最中だそうです。そんな謎の多いこの花はイギリス人の植物学者ムーアさんによってモレアと名付けられました。今でもモレアと呼ばれたりモラエアと呼ばれたりします。