サルココッカの育て方

育てる環境について
耐陰性が非常に強く暗い場所でも容易に育成が可能なため、建物の北側や樹木の下で陰になってしまう場所でも育成が可能です。日当たりのある場所でも育てることは可能ですが、どちらかというとやや暗い環境を好むため基本的には半日陰から日陰の場所に植えるようにします。季節による移動の心配がないので鉢植え、地植えともに可能です。
また、生育は遅く1年で10センチほどのスピードで成長します。そのため樹高に制限のある場所や十分にスペースの取れない場所でも育成が可能です。特徴の記載にもあるように、一般的には生け垣や花壇、グラウンドカバーなどに用いるとよいです。土は水はけと水持ちのよい、なるべく乾燥のしづらい場所を選ぶようにします。
やせ地にも強いため、乾燥にだけ注意することで自然と大きく成長させることができます。また、病気にかかりにくく耐寒性にも優れた非常に強健な性質を持ちます。日本の気候においては北海道の南部から沖縄まで幅広い気候条件に対応することができます。上記のことから、最低限の条件を整えることで育成が可能なため、
特別な知識や技術を必要とせずに育てることが出来ます。日陰などのくらい場所でも成長し、細かい手入れを必要としない上部な常緑低木は日本では珍しいため、ガーデニングや栽培の経験が浅い方でも手のつけやすい植物といえます。また、年間を通してせん定の手間がかからない常緑低木を必要としている場合にも重宝します。
種付けや水やり、肥料について
一般的に種は出回っていません。既に成長した株の実を野鳥などが食べ、そのフンをした地面から自然発芽したりすることがありますが様々な条件が整わないと難しいため種付けからの生育は一般的ではありません。基本的には、市場で売られている苗木の植えつけか挿し木から初根させたものの植えつけを行いますが、
ここでは一般的な苗木からの植えつけ方法を記載します。土は腐葉土と堆肥を混ぜ込み、水はけのよい状態を保てるようにします。強風があたる場所に植えつける場合、苗木の間は支柱を立てて固定します。成長が遅いため長い間支柱を挿した状態を維持しますが、成長するとともに株元が丈夫で頑丈になりますので、いずれ風にも動じなくなります。
また、やせ地に地植えを行う場合は、開花前の初春に緩効性の置き肥を施します。水やりは、地植えの場合は降雨のみで十分です。晴れ続きで地面が干上がりそうな場合はたっぷりと水やりを行い、地面がやや湿っている状態を保つようにするとよいです。鉢植えの場合は、土の表面が乾いたらたっぷりと水やりを行うようにします。
植えつけ以外での肥料は、株を大きくしたい場合のみ与えます。現状より株を大きく育たせたい場合は2月(開花前)と9月(実がなる前)に緩効性の肥料を根元に施してください。置き肥、液肥は問いません。本来養分の少ない土壌を生息地としている植物ですので、肥料が切れても枯れてしまうことはありません。しかし、肥料が少ないと葉の張りや花つき、実つきに影響が出る場合もあるので基本的には毎年の肥料は欠かせません。
増やし方や害虫について
挿し木もしくは株分けによりふやすことが可能です。その場合は4月から9月頃にせん定を行います。切り落とす枝は新芽を避け、その年に生えた枝を選びます。枝は最低でも数節を残した状態で切り落とし、下部の葉はすべて取り除きます。残っている葉は蒸散を防ぐため半分程度切り落としたのち、十分に水揚げを行います。
用土は必ず新しい物を使用し、病原菌や細菌がいないものを選ぶ必要があります。また目が細かく保水性の保てるものが好ましいです。用土の中に栄養分(肥料)がある場合、発根が遅れる原因となり発根前に枯れてしまうこともあるので培養土や肥料混合土は避けるようにします。
それ以外は特別細かい条件を必要としないので、一般的に販売されている挿し木用の土を用いても問題ありません。株分けの場合は根を傷めないよう慎重に掘り起こし、親株から切り離すように子株を作ります。この時あまり細かく分けてしまうと株自体が弱りやすいので注意が必要です。
分けた子株はそれぞれに見合ったスペースを確保し、元の土あるいは新しい土を足した状態で植え直します。病害虫には強く、目立ったトラブルはありませんが、まれにハマキムシが発生する場合があります。ハマキムシは名前の通り葉を巻いてしまいその内側から葉を食していく虫です。
「サルココッカ」のような硬い葉の場合は、葉を数枚つづっていることが多いため、周りの葉とは明らかにおかしな生え方をしている葉があった場合には注意が必要です。通常葉の内側にこもり、薬剤が効きにくいので、見つけた場合は直接駆除します。
サルココッカの歴史
「サルココッカ」はヒマラヤ、東南アジア、中国南部を原産とするツゲ科コッカノキ属の常緑小低木です。学名を「Sarcococcahookeriana」、英名を「Christmasbox、Sweetbox」といい、甘く香ることから日本でも稀に「スウィートボックス」と呼ばれ、日本国内では洋風のツゲの木と認知されていることが多いです。
この「サルココッカ」という名称は19世紀のイギリスの植物学者によって名づけられ、比較的新しい樹種としても知られています。「サルココッカ」はギリシャ語で「肉質の液果」という意味を持ちます。近年、手間を必要としない育て方や強健な性質から、欧米で多くの人気を集めています。主に庭園ガーデニングや生け垣、街路樹に植栽されています。
日本の気候条件でも栽培が可能で年々その人気を伸ばしつつありますが、日本国内での流通は不定期で、流通量も少なく入手が難しい種でもあります。時期になると優先的に仕入れている販売業者もありますので栽培を検討している場合は事前に取り扱いがあるかの確認をしておくとよいです。
日本で販売されているもののほとんどは、苗木の状態で鉢植えとして出回っており、流通量が少ないわりには日本各地で見かける機会の多い植物でもあります。一般的な鉢植えの他、盆栽やトピアリー、花壇や街路樹、ゴルフ場、学校や公園などの公共施設など、目を凝らすと様々な地域や場所で栽培されています。
「サルココッカ」には大きく分けて二種類の品種があり、庭植え用の「コンフサ」と「フミリス」が出回っています。立ち姿や実の色が若干異なりますが、性質はほとんど変わらないことでも知られています。丈夫な性質で日本の気候にも対応でき、アレンジのしやすさがある点から、日本国内でも今後注目の低木です。
サルココッカの特徴
樹高は約30センチから60センチと、低いものが多いです。品種や育て方によっては樹高2メートルにもなるものが存在しますが、基本的には根元から吸枝と呼ばれる枝を伸ばして広がり、成長していくにつれ株立ち状となるので実際はそこまで背の高い印象を与えません。
また、刈り込みを行うと株もとから芽が伸び、やがて地面を覆うように成長していくのでグラウンドカバーとして利用出来ることも特徴です。葉には厚みがあり、先端の尖った楕円形をしています。また、とても美しいツヤがあり、この光沢は葉が生い茂っている限りほぼ年中眺めることができるので、その美しさも人気の一つです。
通常時は落ち着きがある綺麗な緑色をしていますが秋に気温が下がると紅葉をしますので、季節にともなう変化が優しい印象をつけます。そのため、洋風のアレンジだけでなく日本の風景にも良く馴染みます。開花時期は初春で、早くて2月頃から開花姿を見ることが出来ます。花は甘く強い芳香を放つ、小さな白い花を咲かせます。
晩秋からは赤紫から濃い紫色をした果実をつけますがいずれも時期が短いため、一般的には通年を通して光沢のある丈夫な葉を楽しむ目的で栽培されています。そのため、一般家庭では観葉植物として扱われるほか、実用的な緑化を目的とされることが多いです。また、生育に必要な条件が難しいものではないため、
比較的どんな場所でも管理できることから他の低木の根じめにも向いているといえます。雌雄異株なので、雌株にしか果実はなりませんが、秋に赤~黒紫に色づく果実がなります。雌株だけ植えておけば実がなります。苗木は雌雄の特定ができておりません。通常雌株のみの流通で、真贋は不明ですが、国内に雄はいないとの話も聞いたことがあります。
-

-
ビート(テーブルビート)の育て方
ビートの歴史はとても古く、紀元前より利用されています。始めは野生種の先祖型にあたる植物を薬草として利用されていて、ローマ...
-

-
スノーフレークの育て方
スノーフレークは、ヨーロッパ中南部が原産です。ハンガリーやオーストリアも生息地になります。スノーフレークは、日本において...
-

-
サクランボの育て方
栽培の歴史はヨーロッパでは紀元前から栽培されており、中国に記述が残っていて3000年前には栽培されていました。日本には江...
-

-
リンゴの育て方
リンゴの特徴として、種類はバラ目、バラ科、サクラ亜科になります。確かに花を見るとサクラとよく似ています。可愛らしい小さい...
-

-
トルコギキョウの育て方
長野県は、世界に冠たるトルコギキョウの生産地です。そしてここは、日本で初めてトルコギキョウが栽培された土地でもあります。...
-

-
マンゴーの育て方
マンゴーは、ウルシ科のマンゴー属になります。マンゴーの利用ということでは、熟した果実を切って生のまま食べるということで、...
-

-
カタセタムの育て方
カタセタムの科名は、ラン科、属名は、カタセタム属になります。その他の名称は、クロウェシアと呼ばれることもあります。カタセ...
-

-
ヘリコニアの育て方
ヘリコニアは単子葉植物のショウガ目に属する植物です。大きく芭蕉のような葉っぱから以前はバショウ科に属させていましたが、現...
-

-
バイカウツギの育て方
バイカウツギは本州から九州、四国を生息地とする日本原産の植物になり、品種はおよそ30~70種存在し、東アジアやヨーロッパ...
-

-
ダーウィニアの育て方
ダーウィニアの特徴を挙げていきます。まずは、植物の分類ですが、ダーウィニアはダーウィニア属のフトモモ科に属します。このダ...




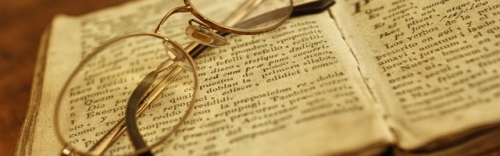





「サルココッカ」はヒマラヤ、東南アジア、中国南部を原産とするツゲ科コッカノキ属の常緑小低木です。学名を「Sarcococcahookeriana」、英名を「Christmasbox、Sweetbox」といい、甘く香ることから日本でも稀に「スウィートボックス」と呼ばれ、日本国内では洋風のツゲの木と認知されていることが多いです。