ホウセンカの育て方

ホウセンカについてと育て方
ホウセンカは、春撒きの一年草として人気のある花です。育て方も比較的簡単で、学校の教材にもなっている植物です。40?70センチの「高性種」と20?25センチほどの「矮性種」の品種があり、花は一重咲き、八重咲き、カメリア咲きなどの種類があります。
園芸用としても人気がありますが、漢方薬としても使われており鎮痛作用や通経、消炎などの効果があるとされています。また、エキスを化粧品に混ぜて使われていたり、虫さされに効果があるとされています。花弁は、アトピー性皮膚炎の予防や治療、リウマチの痛みや腫れに有効な成分を持っているとされています。
ホウセンカは、多湿を好む植物のため、水持ちの良い土がよいとされています。市販されている、花や野菜の土で植え付けるか、赤玉土と腐葉土を混ぜたものを使用します。
種から育てる場合には、種をまいて軽く土を被せ、育って来たら間引いて、株同士が20センチ以上離れるようにします。
苗から育てる場合には、ポリポットなどに土を入れ、そこに種をいれて土を乾かさないように管理します。ポリポットで栽培し根が回る前に、根鉢を崩さないようにして花壇や鉢などに植え替えを行います。
ホウセンカの根は、直根性という根が太いものが生えます。これが傷つくと生育不良を起こしてしまうので、根が傷ついてしまう移植を嫌います。このため、花壇やプランターなどに植えてしまった場合、植え替えることは出来ないのです。これは、ポリポットで育てた場合にも、苗を購入した場合にも同じなため、植え替えたあとは移動しては直根性が傷ついてしまいます。
また、育てるときには水やりはまめに行うことが大切で、水が不足してしまうと草丈が低くなってしまったり、花の数が少なくなったり、蕾が枯れてしまうこともあります。
春はほぼ毎日、夏の暑い時期は一日二回、朝と夕方、場合によっては朝と昼と夕方に三回、水やりを行います。
肥料は、あまり多くせず緩効性化成肥料を置き肥します。生育が悪い場合によっては、追肥をおこないます。多く与えてしまうと、肥料焼けなどの悪影響が出る場合もあり、説明書に書かれた適切な量を与えることが大切です。
ホウセンカをひとつ夏楽しんだあとは、やはり来年も楽しみたい気持ちになります。そのためには、種付けをするために種を取っておきます。ホウセンカの花は、茎にくっつくように腋から生えてきますが、そこから種袋が出て来て熟すと軽く摘んだだけでも弾けるように種が飛んでしまいます。
この種を種付けするために、取って置くことで来年も好きな場所で花を楽しむことができるようになるのです。しかし、種付けするために取ったものだけではなく、こぼれ種でも発芽することがあり、そのまま成長させることもできますが、連作障害の危険性もあるため、そのまま種付けするのではなく、きちんと処理してあげる方がよいとされています。
ホウセンカ栽培の注意点
ホウセンカは、日当りの良い場所で良く育ちますが、基本的に少々日当りが悪くても、少々水はけが悪くても多少育て方が雑でも水さえ与えておけば育つ頑丈な植物です。耐陰性があり、真夏に直射日光に当たったりすると葉焼けを起こしてしまったり、乾燥して痛んだり、乾燥しすぎると枯死してしまう場合もあるので注意が必要です。
プランターの場合は、日当りの良い場所に置き、花壇の場合は最初から半日陰で管理することが良いとされています。栽培後、次の年も栽培する場合には、同じ場所に植えてしまうと連作障害が起きてしまいます。
連作障害が起こると、生育不良や病気などの問題が現れてしまいます。育て方が悪いわけではないため、別の場所で育てることが大切です。また、センチュウ(ネマトーダ)に対する抵抗力が非常に弱いとされ、センチュウのいる土壌では栽培することはできず、対策としてはマリーゴールドと一緒に植えるなどの対策が必要です。
ホウセンカの病気について
ホウセンカは基本的に、害虫はほとんど見られないとされています。しかし、梅雨の時期には「うどんこ病」が発生してしまう可能性があります。
うどんこ病は、ウドンコカビ科の純活物寄生菌による植物病害の総称で、茎がうどん粉をかけたようになる症状が現れ、一カ所から始まって、広がるとともに分生子を形成して、離れた場所でも感染してしまいます。
葉の表面が覆われると、光合成が阻害されたり、葉から栄養が吸収されるのを阻害され生育不良になり、花が咲かなかったり、種を着けなかったり、酷い場合には枯死してしまう病気です。
発生するには、うどんこ病のもとである胞子が風に運ばれて、若い葉や茎、花や蕾などに寄生して発生します。比較的高音で湿度が低いと胞子が繁殖してしまい、風通しの悪いところで多発します。
発生してしまうと、花がダメになってしまうため、風通しの良い環境で育て、薬剤を使用するときには殺虫細菌剤を散布することで、対策をとることができます。
ホウセンカの歴史
ホウセンカは、ツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草で、東南アジアが原産です。中国では、花を鳳凰に見立てて羽ばたいているように見えることから鳳仙花と呼び、和名もこの音読みから来ています。
中国を経由して日本に来たといわれていますが、時期ははっきりとは判明しておらず、室町時代後期に書かれたと言われる花伝書に「法せん花」の名前があり、これがホウセンカだとしたら16世紀ごろには渡来していたとされています。
ツマクレナイ、ツマベニ、ツマグロ、ツマグレ、ホネヌキなどたくさんの別名があり、これは花びらから出る赤い汁にカタバミなどの汁を混ぜ、女の子が爪をマニキュアのように染めるように使っていたからとされています。
ホネヌキには様々な説があり、種を魚と一緒に煮ると骨が柔らかくなる、種を砕いて飲むと喉に刺さった魚の骨が柔らかくなり抜けるからなどとされています。
また、沖縄では「てぃんさぐ」と呼ばれ、民謡「てぃんさぐの花」は、ホウセンカの汁を爪に塗って染めるとマジムン(悪霊)避けとなるとされ、このようなことを教える親や年長者の教えに従うことの重要性を説く教訓歌として、今でも歌い継がれています。
ホウセンカの特徴
ホウセンカの生息地は、多湿を好む植物で、湿り気のある水持ちの良い土が適しています。草丈の高い「高性種」と低い「矮性種」の二つがあり、花は一重と八重咲きのものに分けられます。八重咲きのものは、花びらの多いカメリア咲きと呼ばれるものと、普通の八重咲きのものとがあります。
茎は直立して、葉は互生しており、花は葉の腋に2?3輪ずつほど花をつけてます。花弁は5枚、萼片も5枚つけます。本来の花の色は赤ですが、園芸品種として、赤のほかに白、ピンク、紫や紅色、サーモンピンクや赤や紫に白い絞り咲きの品種などがあります。
現在では、カメリア咲きが大半をしめていますが、矮性種は鉢植えで育てるにも向いています。花が咲いた後、茎にはラグビーボールのような形の果実をつけます。この果実は、熟すと自然に弾け、弾ける寸前のものは軽く触れただけでも弾けて、種を広範囲に飛ばすという特徴を持ちます。
属名であるインパチェンスは、ラテン語で「我慢できない」の意味を持っており、この性質に由来しています。園芸では、春に種を撒いて、夏に花を楽しむのが一般的で、夏の暑さに強くこぼれた種でもよく生えるほど丈夫な植物です。学校の教材としても使われている花です。
花の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ニューギニアインパチェンスの育て方
-

-
ラミウムの育て方
ラミウムは、シソ科、オドリコソウ属(ラミウム属)になります。和名は、オドリコソウ(踊子草) と呼ばれています。ラミウムは...
-

-
ツルニチニチソウの育て方
夾竹桃(きょうちくとう)科に属しているツルニチニチソウは、学名を「Vinca major」「Vinca」といい、ツルニチ...
-

-
トマトの栽培は驚く事ばかりでした
今年こそは、立派なトマトを作ろうと思いながら数年が過ぎようとしていた時、テレビ番組を見た事がきっかけで、自分でトマトを作...
-

-
我が家で行っている家庭菜園のコツを紹介します
我が家では、猫の額ほどの庭ではありますが、自分たちの食べるものは自分たちで出来るだけ作ろうというモットーで家庭菜園を営ん...
-

-
キツリフネの育て方
特徴として、被子植物、双子葉植物綱、フウロソウ目、ツリフネソウ科、ツリフネソウ属になっています。属性までツリフネソウと同...
-

-
ツルウメモドキの育て方
人間や動物には性別があります。見た目ではよく見分けすることができない魚や虫にもあります。植物にまであると知り、意外だと驚...
-

-
いろんなものを栽培する喜び。
趣味としてのガーデニングについては本当に多くの人が注目している分野です。長年仕事をしてきて、退職の時期を迎えると、多くの...
-

-
植物の栽培育て方のコツを教えます。
最近はインテリアグリーンとして植物を栽培するかたが増えてきました。部屋のインテリアの一部として飾るのはもちろん、植物の成...
-

-
エンレイソウの育て方
エンレイソウは、ユリ科のエンレイソウ属に属する多年草です。タチアオイとも呼ばれています。またエンレイソウと呼ぶ時には、エ...
-

-
ファレノプシス(コチョウラン)の育て方
学名はファレノプシスですが、和名をコチョウランとも言い、日本でランと言えば、胡蝶蘭を思い浮かべるくらい有名で、人気がある...




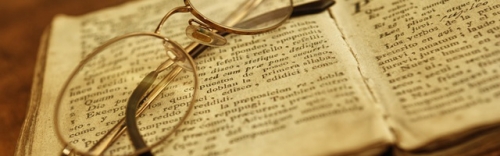





ホウセンカは、ツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草で、東南アジアが原産です。中国では、花を鳳凰に見立てて羽ばたいているように見えることから鳳仙花と呼び、和名もこの音読みから来ています。