エマルギナダ(ヒムネまたはベニゴウカン)の育て方

育てる環境について
育て方としてどういった場所に置くか、植えるようにするかです。生息地は北アメリカの南部から中央アメリカの辺りと赤道に近いところになります。温暖な気候であるのと同時に、湿度としてはあまり高くないような環境になります。1年を通して暖かく、湿度があまりない状況が容易すべき環境になります。
日本においてそのような環境を作れるかですが、まずは日本には四季があります。温暖な気候としては春の終わり、夏の初めから、秋のなかごろまでは得られそうです。しかし晩秋近くから寒くなり始め、冬、春でも4月中旬くらいまでは寒の戻りなどがあるのですっきりしないことが多くなります。そのことからかなり冬がポイントになってきそうです。
一応日本においても夏などについては問題なく育てることができます。1年を通して日当たりのいいところに置くようにします。直射日光に当ててもそれ程問題はありませんし、西日などにもさほど影響はないとされています。過湿気味になることもそれ程問題ではないですが、冬の寒さに対しては注意をします。この植物は耐暑性があまりないとされています。
一定の寒さになると弱くなりますから、管理を気をつける必要が出てきそうです。一般的に言われることとしては、日本で育てるのであれば屋内での管理が良いとされています。ですからあまり地植え、庭植えなどにしないほうが良いようです。南部の地域で常に10度以上であればなんとか冬越ができるかもしれません。
種付けや水やり、肥料について
栽培をする上ではどのように植え付けをしていくかです。あまり出まわることが少ないとされています。ホームセンターや園芸店などでどのように売られているかですが、よくあるのは花がついた状態で売られていることです。すでに一定の大きさにまで成長してある状態なので、後はそれを植えることになるでしょう。
低い木ですから、最初にある程度育っている状態になっているのは助かります。一から育てたいと考える人には少しつまらないところもあるかもしれません。水分に関してはどのようにするかですが、乾かし気味に行うのがよいでしょう。これは土の配合にも言えることです。あまり水がジメジメしているような状態は好みません。
水をかけたらすっとすぐにしみこんでいくような水はけがよいでしょう。夏などに関してはそれなりに水を与えることもありますが、秋や春などになると抑え気味にして、冬になったら室内での管理になるので更に抑えるようにします。水分がそれほどなくてもすぐに枯れることはありません。
もちろん葉っぱの様子などを見て元気が無いと判断した時はそれに応じて水分を与えるようにします。夏などは多めに与えます。冬であれば少し与えて様子を見てと原因を探りながら行うのがよいでしょう。水を与えすぎるのはよくありませんから、一回一回の水の量は多くなり過ぎないようにします。肥料に関しては植え付けのときに腐葉土を混ぜ込み、月に1回程度置き肥をして与えていきます。
増やし方や害虫について
植木鉢で育てるのであればある程度の頻度で植え替えをする必要があります。成長に伴って根が増えてくることがあります。また弱っている根などがあれば取り除く必要があります。その状況を見るためにも植え替えを行います。植え替えをする時期としては、春の初めのほうがいいでしょう。
花が咲く準備が始まる前がいいですから、3月の中旬から4月にかけてが適当とされています。土に関しては新しいものに交換するようにします。この植え替えをするときに同時にしておきたいこととしては切り戻しがあります。この植物に関しては花が美しいですが、木として葉っぱとの兼ね合い、枝ぶりなどが必要とされます。
成長していけばどんどん枝が伸びますが、それがいろいろなところに伸びればあまり美しく見えなくなります。そこで切り戻しをしながらになります。樹形を整えながら切り戻しをし、それを植え替えのときに行うようにします。これは木のバランスにも影響します。枝ぶりが大きくなるとバランスを崩すことがあります。
切り戻しをして、バランスを良くした状態で植え替えをしたら、調度良い形で植えることが出来るようになります。増やし方としては、よく行われる方法としてはさし木があります。たくさん増えてくるとインパクトのある木ですから、余裕がある場合には増やすようにしてみてもよいでしょう。病気に関してはあまりありません。寒さなどに気をつけるようにすれば、枯れたりすることも少ないです。
エマルギナダの歴史
花においては、一見花に見えるけどもそれが花びらではなく別の部分であることがあります。実際の花びらは見えないところに小さくついていたり、ついていたけれどもすぐに落ちてしまうなどのことがあります。その他の部分も無ければ花びらも目立つのでしょうが、あまりその他の部分が目立ってしまうとそれが花のようにみえることがあります。
また花びらのように大きくなっていたり、きれいな色をつけていると余計に花のように見えることがあります。そのような花としてエマルギナダと呼ばれる花があります。原産地としては北アメリカでその中でも南部、中央アメリカにかけてになるようです。テキサス州、カリフォルニア州、メキシコなどを生息地としている植物になります。
この花についてはいくつか別名がついています。どちらも和名でヒムネまたはベニゴウカンとされています。全く関係性のないような2つの言葉ですが、漢字にするとどちらも同じところからとっている事がわかります。緋合歓と紅合歓になります。合歓はネムノキのことです。
なぜこのように名付けられたかの由来ですが、花がねむの木の葉のように見えているからとされています。ネムノキといいますと針のような葉っぱが特徴的です。この花がその葉っぱと同じように針がたくさんあるように見えるからとされています。緋色の花なので緋合歓となり、赤いネムノキのような花を咲かせるから紅合歓と言われるようになったとされています。
エマルギナダの特徴
この花についてはマメ科、カリアンドラ属となっています。和名においてネムが入っていますが、基本的にはネムは全く関係ありません。似ていると言っても花が葉っぱに似ているだけですから全く視点が異なることもわかるでしょう。常緑定期ごして分類されています。花が咲く時期としては6月から11月と比較的長い間花が咲きます。
ネムノキといいますと落葉高木で木の高さは10メートルほどになることもありますが、この木については低木ですからせいぜい1.5メートルほどとなります。ですから十分植木鉢で育てることが可能な植物になります。花の特徴を言うのは非常にむずかしいです。と言いますのも花びらは非常に小さく、
この花に関してはほとんど見えない、わからない状態だからです。この花のメインは雄しべになります。一般的な花の雄しべといいますと花の真ん中に数本出ているだけですが、この花については非常に沢山まるで花のように出ています。そのためにこの部分が花のように見えますが、実際には雄しべが集まっている状態になります。
この雄しべの色は緋色です。真っ赤な色になります。この雄しべ自体は非常にたくさんありますが、長さとしては2センチほどになります。葉っぱに関しては羽状複葉になっています。左右に小さな葉っぱが沢山並んで一つの葉っぱを形成する形になります。葉っぱの付き方としては互生になります。それぞれの小さい葉っぱに関しては披針形で、夜になると閉じる性質があります。
-

-
ディフェンバキアの育て方
ディフェンバキアはサトイモ科ディフェンバキア属で原産地や生息地は熱帯アメリカです。和名にはハブタエソウやシロガスリソウと...
-

-
植物を育てたことがない人でも簡単に収穫できる大葉の育て方
大葉は日本の風土でよく育つ植物です。育て方も簡単で家庭菜園初心者でも簡単に収穫を楽しむことができます。また、ベランダに置...
-

-
モミジカラマツの育て方
モミジカラマツの特徴について書いていきます。その名前の由来からして、葉っぱは紅葉のように切れ込む葉が特徴的です。実際に見...
-

-
スパラキシスの育て方
スパラキシスはアヤメ科の秋植えの球根草として知られています。純粋に和名であるスイセンアヤメとも言います。和名が付いている...
-

-
ネオレゲリア(Neoregelia)の育て方
ネオレゲリアは株を植えつける植物で、種からの栽培方法はありません。株の植えつけを行う際には、ヤシの実チップや水ごけを使用...
-

-
トマトの栽培や育て方について
もうすぐ春がやってきます。そうなると、夏野菜の種まきや栽培を始められる方も多いのではないでしょうか。ここでは、初心者でも...
-

-
ユキヤナギの育て方
古くから花壇や公園によく植えられているユキヤナギは、関東地方以西の本州や、四国、九州など広範囲に生息しています。生息地は...
-

-
カランセの育て方
カランセはラン科エビネ属の多年草です。日本が原産地となっているエビネ属の花もありますが、熱帯原産のものを特にカランセとよ...
-

-
ミヤマクロユリの育て方
このミヤマクロユリは多年草になり、直立した茎の上部に細長い楕円形の葉を2~3段に輪生させており、茎の先に2~3輪の花を下...
-

-
アケビの育て方
アケビはまず中国の歴史に現れます。中国で最古の薬物学と書と言われている「神農本草経( しんのうほんぞうぎょう)」という本...




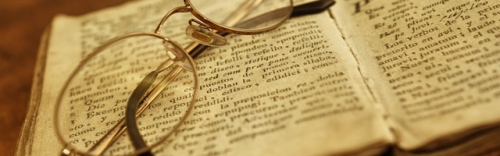





この花についてはマメ科、カリアンドラ属となっています。和名においてネムが入っていますが、基本的にはネムは全く関係ありません。似ていると言っても花が葉っぱに似ているだけですから全く視点が異なることもわかるでしょう。常緑定期ごして分類されています。花が咲く時期としては6月から11月と比較的長い間花が咲きます。