チガヤの育て方

育てる環境について
育て方としては栽培の環境をどのようなところに設定するのが適当になるかです。まず一般的にどういったところに生息しているかを考えてみるといいでしょう。いわゆる草原のようなところです。また河川敷のようなところも多く生息しています。このようなところには大きな木などがありません。つまりは日当たりに関しては十分あるところになります。
まずは日向、日当たりがあるところが良いとされています。直射日光や西日などについては特に何も影響はないとされています。草原においてはどちらも当たる可能性がありますが、そういったところでも特に問題なく育ちます。色が変わるようなこともありませんから、美しい色を維持してくれます。
この植物については一般的な草の色も楽しめますが、赤く色づくタイプでもあり、その色を楽しむこともあります。その色についても特に問題なく楽しめるとされていますから、十分日光に当てられるところにします。良くない環境としてあるのは湿気があるようなところです。土質が粘土質ぐらいのところであればいいですが、
日常的に水がたまっているようなところは良くありません。河川敷であれば、水の近くであればぬかるんでいることがあります。こういったところは好みません。でも水分があっても水たまりのようになっていなければ問題なく育つことが出来るとされています。水たまりなどだと茎も根も水に浸かりますが、それを避ける事ができればある程度のところで育ちます。
種付けや水やり、肥料について
植え付けをする時の用土に関してはあまり考える必要はないでしょう。自然にある土で育っています。そのためにどのような土でないと育たないようなことは少ないです。水分についても、水はけが良くても良いですし、水はけがあまり良くなくても水がたまるようでなければ育てることができます。培養土などを使うとよいでしょう。
盆栽用に作ることがあります。この時には赤玉土のみで土を用意することがあります。栄養分が入っていませんが、わざとそのようにして育てることがあります。水やりに関しては、鉢植えの頻度としては、表面が乾いてきたら与えるようにします。水をどんどん吸う植物ですから、夏場などに蒸発が多い時には通常よりも多めに与えるようにしないといけないかもしれません。
1日2回、朝と夕方に与えるくらい必要になることもあります。庭植えの場合においては特に与えなくても育てることは可能です。雨が降ってくれますから、その雨だけで水分の補給をすることができます。水分が足りない状態になると葉が巻いてくるようになるので、それを見計らって水分を与えるようにすることがあります。
よほど日照りが続いた状態のときに必要になってきます。肥料については、鉢植えで育てるときは春から夏にかけて草花用の肥料を与えます。量は多すぎないように注意します。多すぎるを枝や葉っぱだけが伸びてしまいます。均等に伸びるような肥料の与え方にします。庭に植えるときは肥料は不要です。
増やし方や害虫について
増やしたいときにはどうすればいいかですが、株分けを行います。鉢植えであれば毎年のように植え替えますし、庭植えの場合にも数年に1回は掘りあげて様子を見ることになるでしょう。このときに株が大きく成長していることを確認して、それを分けます。分け方としては3つから5つぐらいに分けるようにします。
あまり株が小さいのに分けようとすれば株が傷みますから、それなりの大きさの株を使うようにします。うまく育つようになるとどんどん大きくなりますから、自ずと株分けが必要になってきます。あまりに増えすぎて困るときには処分をしないといけないこともありますから、そのときによって増やすのか、減らすのかの判断をします。
作業をしておいたほうが良いこととしては葉刈りがあります。これを行うのは5月から6月ぐらいです。根元から一部を残して上部をかるようにします。これは大きくなりすぎるのを防ぐために行います。どんどん成長してしまうからです。もちろん高く成長させたいと考えるならそのままにしておくこともありますが、
全てをそのように成長させるわけにもいかないでしょう。様子を見ながら行います。高さをそろえる作業と考えると良さそうです。病気については特にありません。害虫についても特にありません。植物には害を与えないものの気をつけないといけないクモがいつくことがあります。クモは害虫を食べてくれるので必ずしも捕殺はすればいいわけではありません。
チガヤの歴史
秋をイメージさせる植物としてススキがあります。草原のようなところとなると普段はなかなか見ることができませんが、河川敷などにおいてはたまに見られることがあります。その上に赤とんぼなどが飛んでいたりすると秋を感じることがあります。植物といいますと動物のように弱肉強食のようなことはないように感じますが、
実際のところは植物の世界でも強いものが残って弱いものがどんどん衰退していくようなことがあるようです。ススキといいますと今は非常に多くなっていますが、そのススキに似ている植物としてあるのがチガヤと呼ばれる植物になります。ススキよりもこぶりですが、同じような形の植物になります。
原産としては中国や朝鮮半島など大陸ともされていますが、古代の日本においても存在していたようなので、日本も原産でもあり生息地とも言えそうです。日本を細かく見てみると、北海道から沖縄で広く見られるようになっています。この植物については、多年草の性質を持っていることから、歴史的には1年草の群落にどんどん侵入して安定して草原を形成することがあります。
しかしこの植物よりも強い植物が出てくるとどんどんそれらに追いやられます。それがススキになります。元々この植物があったところに背の高いススキがやってくることで次第に姿を消しているとされています。現在においては定期的な草刈り、どて焼きなどによってススキなどが来られなくすることによりチガヤの草原が残されています。
チガヤの特徴
この植物に関しては、被子植物で単子葉植物綱になります。イネ目、イネ科になります。園芸分類上はグラスで、毎年成長する多年草になります。花が咲く時期としては秋以降になります。耐暑性や耐寒性についてはかなりあるとされています。ですから北海道の寒い地域でも生息しますし、沖縄、本州の暑いところにおいてもそれなりに対応して増えることができます。
地下茎が横に這うように成長します。葉っぱに関しては一枚一枚出るのではなく、まとめて出るようになっています。茎と葉っぱが出ているような状態になっていることが多くなります。葉っぱにおいては細くて硬いタイプの葉柄がついています。先の方は少しですが幅広になります。
葉っぱは一般的な葉っぱのように広がるようにつくのではなく、まっすぐ立つように上を向いています。高さとしては30センチから50センチぐらいになります。ススキは2メートル近くなることもありますから。そう考えるとススキがどんどんどん迫られると後退していくのもわかります。
植物の葉っぱといいますと表が艶があり裏が白っぽいなどが多いですが、この植物の葉っぱは表裏の差があまりありません。多年草ですが、葉っぱは冬には枯れます。穂を出すのは初夏になります。細長い円柱形で、葉よりも高く伸びます。真っ白の綿毛に包まれているのはススキなどと同様になります。種子はこの綿毛に乗って遠くまで飛びます。花穂については白い綿毛に包まれている状態です。
-

-
ブロッコリーの育て方
サラダやスープ、炒めものにも使えて、非常に栄養価の高い万能野菜であるブロッコリーは、地中海沿岸が生息地といわれています。...
-

-
サルビア・レウカンサの育て方
サルビア・レウカンサの原産地はメキシコや中央アメリカです。別名を「メキシカンブッシュセージ」「アメジストセージ」といい、...
-

-
ハバネロの育て方
ハバネロはトウガラシの一種で、原産地はアマゾンかその周辺の地域だといわれており、そこからユカタン半島に伝わったと考えられ...
-

-
ロムレアの育て方
南アフリカはアヤメ科の球根が、たくさん栽培されていて、ロムレアもその仲間のひとつです。手に入りにくい球根と言われていまし...
-

-
ハツユキソウの育て方
ハツユキソウは背丈がおよそ1メートル程の高さに延び、その葉先に小さな花をつけます。白く色づく葉は花の回りにある唇型の葉で...
-

-
クサノオウの育て方
クサノオウは古くから日本に生息している山野草です。聞き慣れない植物ですが、黄色い花を咲かせるヤマブキソウに似ています。ク...
-

-
キクイモの育て方
キクイモは一年中育てることができる多年草の為、一度植えますと基本的に毎年開花する植物です。また、この名前は日本での名称で...
-

-
モクレンの育て方
中国南西部が原産地である”モクレン”。日本が原産地だと思っている人も多くいますが実は中国が原産地になります。また中国や日...
-

-
ラグラスの育て方
ラグラスは、ふさふさした穂がかわいらしく、野兎のしっぽの意味を持つ名前で、イネ科の植物です。原産地は地中海沿岸で、秋まき...
-

-
ラセンイの育て方
”ラセンイ”は畳の原料である「イグサ」と同じ種類の植物になります。葉っぱが退化し、くるくるとらせん状にうねうねと曲がって...




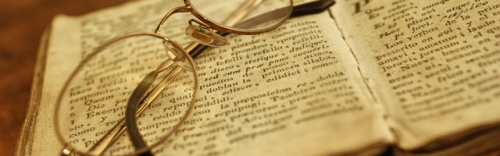





この植物に関しては、被子植物で単子葉植物綱になります。イネ目、イネ科になります。園芸分類上はグラスで、毎年成長する多年草になります。花が咲く時期としては秋以降になります。耐暑性や耐寒性についてはかなりあるとされています。ですから北海道の寒い地域でも生息しますし、沖縄、本州の暑いところにおいてもそれなりに対応して増えることができます。