ルリタマアザミの育て方

ルリタマアザミの育て方
ルリタマアザミは市場ではよくブルーボールという英名で出回ってることが多いです。日当たりの良い場所に植えるのが育て方の基本で、半日陰でも育ちますが、できれば1日中日当たりの良い場所のほうが元気良く育ちます。夏は開花している時期ですが、あまりに暑いのは苦手ですから、できるだけ風通しが良いほうがいいです。
夏でもそういう場所ですと花も長持ちしています。逆に寒さには強いですからよほど寒い地域以外では屋外であっても冬越しすることが可能です。寒冷地の場合は屋外で栽培したままにしておくのは危険なので、地上部が枯れているようであればそこは切り落としてしまいましょう。
そして地下部を掘りあげて鉢にうつしてあげて室内もしくは凍らないような場所で暖かくなるまで置いてあげるのが育て方のコツです。春になったらルリタマアザミも外で日光を浴びたほうがいいので屋外へ出して花壇などに植え替えてあげるといいです。
ただし2年ものや3年ものなど株が大きくなっているものであればルリタマアザミも冬だろうと屋外で冬越しできる可能性が高まります。土は弱アルカリ性の水はけの良いものを用意しましょう。植える前には石灰を混ぜ込んでおきます。
鉢植えの場合は小粒の赤玉土を7、腐葉土を3の割合で混ぜ合わせておき、苦土石灰もあわせておくのがルリタマアザミの育て方の一つです。お水は土の表面が乾いたら与えるというのを栽培する上での基本だと考えておくと間違いありません。
肥料は植える前にゆっくりと効果を発揮するタイプのものを混ぜ合わせておくのが良いです。4月から8月までの間は追肥を行います。化成肥料を1か月半に1度ずつ与えるようにするのがベストです。
栽培する上での注意すること
何年も栽培しているとつい植えっぱなしにしてしまうことがありますが、これは良くありません。ルリタマアザミは植えっぱなしですと枯れてしまうのです。原因は複数の病原菌がいるためだといわれていますが、はっきりとはしていません。ですから少なくとも2年に1度は株分けも兼ねて植え替えをします。
鉢植えの場合は毎年根詰まりを防ぐためにも鉢を一回り大きいものに交換してあげるといいです。あまりに大きいものですと土が乾きにくく、根腐れを起こす原因になるのであくまで一回り程度大きな鉢に植え替えると覚えておきましょう。株分けをする場合は3月から4月頃がいいです。
梅雨時期には多湿になりやすく、うどんこ病の発生に気をつけます。葉などが白くまるで小麦粉をまぶしたようになってしまい、枯れてしまうことが多いです。予防をしておくほうがいいので殺菌剤などをまいておくといいでしょう。
また害虫として要注意なのがアブラムシです。アブラムシは葉や茎、つぼみなどにくっついて栄養を吸い取ってしまい、株を弱らせます。しかもアブラムシは発生したらどんどん増えていくのでとてもやっかいです。見つけたらすぐに駆除するようにしましょう。
種付けで育てられる?
ルリタマアザミは株分けもしくは種付けさせてまくことによって増やすことができます。株分けは3月から4月頃に株を掘りあげて手で2つか3つ程度に分けます。種付けさせたいならば花が枯れた後も花茎をカットせずにそのままにしておき、種が熟すまでそのままで待ちます。
種付けした種が熟したら、紙封筒などを準備して房の部分をさかさまにして袋をそこにかぶせておけば乾燥した時に自然と袋の中に種が落ちていきます。種まきは春まで待ってから行います。種をまく土ももちろん弱酸性にする必要がありますので石灰を混ぜておくのがいいでしょう。
種まきは5月から6月頃がグッドタイミングです。本葉が3枚まで出たらポットに植え替えて秋頃に庭などに植え替えればいいのです。寒冷地の場合はその時期ではなく、春先まで待ちましょう。種から育てた場合、5月くらいに種をまいたとして花が咲くようになるのは翌年の夏くらいになります。
花言葉はいくつかありますが、やはりその見た目を象徴するようなものが多いです。例えば鋭敏という花言葉があり、これは球形のつぼみのとげとげした部分に触れると痛そうだということからつけられたようですし、傷つく心という花言葉も同じくその部分から想像されたことのようです。また権威という花言葉もあります。
エキノプスにはいくつかの品種があり、少し小ぶりで花色が濃いブルーをしているのがヴィーチズ・ブルー、比較的花色が濃く、中型の大きさなのがエキノプス・フミリス、ルリタマアザミは種と苗の両方が園芸店で購入でき、大きさに関しては個体差があります。
プラチナムブルーという品種はつぼみが銀白色をしていて草丈は60cmほどしかありません。しかし花は大輪です。青紫色の中型種であるブルーグローブや白に近い青色の花を咲かせるアークティック・グローなどもあります。色の濃さによっても雰囲気は変わるので何種類か植えて群生させるのも楽しいでしょう。
ルリタマアザミの歴史
ルリタマアザミはアザミという名前がついていますが、アザミ属ではなくヒゴタイ属になります。茎と葉はアザミに似ているのですが、花はその名の通り球型をしているのでアザミとは違います。学名はエキノプスといいますが、ギリシャ語のハリネズミという意味があるエキノスと似るという意味があるオプスから作られた造語です。
まるでハリネズミのようにまんまるに咲くことが由来となっています。ルリタマアザミの原産地は地中海沿岸や西アジアです。日本には昭和初期頃にはすでに渡来していましたが、有名になったのは戦後に生花として利用されるようになってからです。現在ではブルーボールという名前で市場に出ていることもあります。
生息地も原産地と同じですが、草丈が1mから大きいものですと2m50cmほどになります。ただし栽培自体はそれほど難しいものではなく、そのこともあって日本でも人気が高まり、植えている人が増加しています。
生花の花材として使われていたルリタマアザミは現在では切花としても使われ、また個性的なその形からドライフラワーにされていることも少なくありません。葉の裏には綿毛があるので銀白色に見えることからウラジロヒゴタイと呼ばれることもあります。
ルリタマアザミの特徴
ルリタマアザミは7月から9月頃にかけて開花します。約120種類ほどが分布しており、花の大きさは4cmから5cmもあります。花の色は淡いブルーもしくは白い花で、球形になっているのは小さな花がまとまって咲いているからです。中には濃いブルーの花を咲かせるものもあります。
スファエロケファルスは特に大きくなる品種で、2m前後にまで生長します。日本にはヒゴタイという仲間が自生していますが、この種類は環境省のレッドデータブックにおいて近い将来絶滅してしまう可能性が高い種として指定されています。
葉先には少しだけとげがありますが、触っても痛くはない程度です。ハリネズミに例えられていたように花が咲く前の状態はまるでハリネズミのとげのようにも見えます。開花する時にはこの球形の花のてっぺんから徐々に咲いてきます。
ですから咲いたところ以外はとげとげとしたままで面白い見た目になります。ドライフラワーにする場合は風通しの良い日陰で乾かすのですが、できるだけ短期間で乾かしたほうがきれいな仕上がりにできます。切花として使う場合は花が満開になる前に摘み取ってしまうほうがいいです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アザミの仲間の育て方
タイトル:ハナビシソウの育て方
-

-
シネラリアの育て方
シネラリアはキク科の植物で、早春から春にかけての代表的な鉢花のひとつです。原産地は北アフリカの大西洋沖に浮かぶスペイン領...
-

-
キサントソーマの育て方
この植物の特徴としてはサトイモ科の常緑多年草になります。生息地の熱帯のアメリカにおいては40種類近く分布するとされていま...
-

-
ツルバキアの育て方
ツルバキアは、原産、生息地共に南アフリカのものが多くあり、主に24種類が自生しています。ユリ科のツルバキア属に属していま...
-

-
チリアヤメの育て方
チリアヤメ(チリ菖蒲/知里菖蒲 Herbertia lahue=Herbertia amoena=Alophia amo...
-

-
ディエラマの育て方
いろいろな名前がついている花ですが、アヤメ科になります。球根によって生育をしていく植物で、多年草として楽しむことができま...
-

-
ハルジャギクの育て方
ハルジャギクは、キク科ハルジャギク属の一年草になります。学名は、CoreopsisTinctoriaと言います。そして、...
-

-
アピオスの育て方
アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科...
-

-
ホオズキの育て方
ホオズキは、ナス科ホオズキ属の植物です。葉の脇に花径1~2センチ程度の白い五弁花を下向きにつけるのが特徴です。同じナス科...
-

-
ヒマラヤスギの仲間の育て方
ヒマラヤスギはヒンドゥー教では、古来から聖なる樹として崇拝の対象とされてきました。ヒマラヤスギの集まる森のことをDaru...
-

-
オシロイバナの育て方
日本に入ってきたのは江戸時代に鑑賞用として輸入されたと言われており、当時この花の黒く堅い実を潰すと、白い粉が出てきます。...




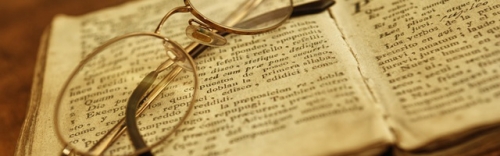





ルリタマアザミはアザミという名前がついていますが、アザミ属ではなくヒゴタイ属になります。茎と葉はアザミに似ているのですが、花はその名の通り球型をしているのでアザミとは違います。学名はエキノプスといいますが、ギリシャ語のハリネズミという意味があるエキノスと似るという意味があるオプスから作られた造語です。