ガーベラの育て方

ガーベラの育てる環境について
比較的日向と好み、水はけの良く風通しの良い環境を好みます。生育環境が悪化している状態では根ぐされをおこし、花を咲かせない可能性もありますので、生育環境の整備は育てる上で非常に重要なポイントとなります。特に水の与えすぎには十分注意が必要ですので、排水の良い土壌環境を準備して、
土の乾きと水分量を調整つしなければなりません。耐寒性はあまり強い方ではありませんが、弱いこともありません。霜が降りないように注意していれば、冬を越すことも可能です。しかし、真冬に0度程度になると休眠に入ります。休眠に入る際には葉や上部が枯れてしまいます。
しかしそれは正常な状態ですので、問題ありません。春になればその株から芽を出して生育し始めますので、部屋の中に入れ、かつ日光の入りやすい環境に移動してあげる方が良いでしょう。また春に向けて新しい芽の生長が必要になりますので、液体肥料などを定期的に適量与えてあげれば暖かくなった時期にまた綺麗な花を咲かせます。
また、夏場の暑い時期には花を咲かせないので、夏場の直射日光には当たらないように遮光してあげることも重要です。梅雨に入ると雨が多すぎて水はけが悪くなりますので、雨が当たらない軒下などに避難させてあげましょう。
春と秋に開花して綺麗な表情を見せてくれる植物ですので、夏や冬は、日光と温度変化、風通し、霜、極度の暑さ、寒さに注意が必要です。鉢植えの場合は移動が容易ですので、季節によって環境を変えてあげれば綺麗な花を咲かせます。
ガーベラの種付けや水やり、肥料について
育て方は難しくありませんが環境には注意が必要です。日当たりの良い場所に置き、生育期や花を咲かせる時期には土の表面が乾いていることを確認してから水を与えます。あまり、土を水浸しにしてしまうと水分量が多すぎて根ぐされを起こしますし、花が咲いている時期には水が花にかからないように注意が必要です。
花が傷んでしまいます。冬場はもし、寒い環境に置かなければならない場合は休眠状態に入りますので、水を与える回数を減らします。ガーベラは基本的に少し乾燥している程度の土壌を好みますので、冬場も水のやり過ぎには注意が必要です。肥料は粒上の肥料を植える時に混ぜ込んでおきます。
遅効性のゆっくり聞くタイプの土を利用します。開花時期にはより多くの栄養分を必要としますので、一週間に一度か二週間に一度程度の割合で液体肥料を与えてください。その際に窒素が多い肥料を与えると葉ばかりが大きく成長してしまい、開花しづらくなる可能性があります。
最近ではガーベラの花を綺麗に咲かせる専用の肥料などがホームセンターの園芸コーナーで販売されています。これを利用すると沢山の綺麗な花を咲かせてくれますので、どの肥料を利用するか迷った場合は専用肥料をりようしましょう。
有機物を含んだ水はけの良い土を利用します。ガーベラ専用の配合土も販売されていますので、慣れていない方や初心者の方はそちらを利用することもお薦めします。自分で配合する場合は小粒の赤玉土と腐葉土、バーミキュライトを5:3:2の割合で混ぜれば生育に十分な配分になります。
ガーベラの増やし方や害虫について
ガーベラの増やし方は一般的に株分けです。鉢から土ごと取り出し、根っこに絡んでいる土を綺麗に落としてから2つか3つに株分けします。この際に根っこを出来るだけ傷付けないように注意する必要があります。根元の方から大きめの葉が伸びていますので、この葉は取り除いて問題ありません。
あまり深く植えず少し浅めに植えてください。小さめの鉢に植えて底に鉢底石を敷いておけば水はけの良い環境が用意できていますので、生育環境に適します。害虫はオンシツコナジラミが発生します。これらは植物に小さな針を刺しこみ直接養分を吸いとりますので、発生し次第除去することが必要となります。
大きさが1ミリ以下の非常に小さな害虫なので、手で一つ一つ取り除くことは不可能と言えます。殺虫剤などを利用して、除去します。さらに他の植物から移ってしまうような非常に拡大性のある害虫なので、他の植物や近くの雑草などを除去することも予防として効果的です。病気ではうどんこ病が発生することがあります。
これは見た目で判断できますので、白い粉がまぶされたような状態を発見したらすぐに対策しましょう。比較的湿った環境にあれば、繁殖力が高いカビの一種ですのでほうっておくと植物そのものを枯らしてしまいます。また胞子により被害が拡大するので、
室内で栽培している場合には被害にあいづらいです。もし発生してしまった場合は出来るだけ初期段階で葉のうどんこ病専用の殺虫剤を利用すると効果的です。また、窒素が多すぎる状態では植物全体が弱ってしまうので、その場合にも発生の可能性が高くなります。
ガーベラの歴史
ガーベラの歴史は比較的新しく、原産地は南アフリカで、元々自生していたキクの一種をイギリス人の植物採集家ジェイムソンらが本土に持ち帰ったことが始まり取れています。アジアやアフリカには40種類が現在でも分布しています。現在園芸で栽培されている品種は19世紀にヨーロッパで紹介された南アフリカを原産とする野生種で、
草丈40センチ程度で、オレンジ色の花を咲かせるジャメソニーという種類を品種改良させたものとされています。名前の由来はドイツ人自然学者ゲルバーから名づけられ、ヨーロッパ品種改良を重ねて様々な品種が発明されました。白や黄色、赤、ピンクなど様々な色の花を咲かせます。
日本には明治時代後期から大正時代初めに渡来しました。日本に渡来したガーベラの種類は一重で短い茎が特徴の種類です。中には花の大きさが10センチ以上に成長する種類も開発されています。現在ではき茎頂培養(メリクロン)の技術開発により、
培養することが非常に簡単になったことで、一般家庭の園芸でも容易に育てることが出来ると人気の植物です。キク科ガーベラ属の多年草で、大きさも一番小さい者では3センチ以下の花を咲かせる種類などもあり、
鉢植えや花壇などで栽培する際に、その大きさや色の配置などを自分で考え配分することで、多種多様な花を咲かせてくれるため、小さな庭や、鉢植え、フラワーガーデンなどを行っている人など、後半にの園芸ファンに好まれて栽培されています。
ガーベラの特徴
キク科ガーベラ属の多年草で草丈は15センチから大きいもので60センチ程度まで成長するものもあります。開花時期は3~5月の春頃か9~11月の秋ごろです。夏の暑い間はあまり花を咲かせません。花のサイズは種類によって大きく異なりますが、小さなものであれば、3センチ程度、大きなもので12センチ程度になります。
色は白やピンク、オレンジ、黄色、赤など様々な色の花を咲かせますが特徴として、比較的鮮やかな色を出します。葉は根元から伸び、長い花茎を伸ばして先端に花を咲かせる植物なので、葉に花が隠れることが少なく、綺麗な花が目立ちます。様々な色の種類があるため、
プレゼントなどにもアクセントをつけるために用いられることもしばしばあります。栽培は比較的簡単な部類ですが、開花させるのに若干のコツが必要となります。主な生息地は南アフリカで、ヨーロッパでも頻繁にガーデニングに用いられる植物です。
種類は非常に多く、中輪、大輪などその大きさによって大きく分類され、カリフォルニアやオレンジディーノなど一般的なオレンジ色の種類からミゲルやブラックジャックパスタファルファッレなど普段目にしない色の種類まであります。
一重咲きだけではなく八重咲き、大輪咲きなど様々あり、大きめの長い葉にはギザギザがあるのが特徴です。広い園芸ガーデンがなくとも室内の小さな鉢植えに植えて鑑賞することもできますので、一般の家庭や集合住宅でも栽培は可能です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:サンギナリア・カナデンシスの育て方
-

-
アキメネスの育て方
アキメネスはアメリカ中部、西インド諸島、南アフリカ北部を生息地として約30種が分布している球根植物です。属名はイワタバコ...
-

-
パンパスグラスの育て方
パンパスグラスの原産地はアルゼンチン・ブラジル南部とされていて、南米のパンパと言われる地域に自生している事からこの名前が...
-

-
アングレカムの育て方
アングレカムはマダガスカル原産のランの仲間です。マダガスカル島と熱帯アフリカを生息地とし、およそ200の種類があります。...
-

-
タデアイの育て方
タデアイはインドシナ半島や東南アジアから中国にかけてが原産地で、そこに自生しています。紀元前の時代から世界各地で青色の染...
-

-
アボカドの種を観葉植物として育てる方法。
節約好きな主婦の間で、食べ終わったアボカドの種を観葉植物として育てるというチャレンジが密かなブームとなっているのをご存知...
-

-
チシマギキョウの育て方
チシマギキョウは、キキョウ科ホタルブクロ属に属している多年草のことを言います。キキョウ科は、真正双子葉植物の科で大部分が...
-

-
フウトウカズラの育て方
フウトウカズラの特徴について書いていきますが、まずは分布地域について触れて起きます。分布地域としては関東以西の暖地に広く...
-

-
ドゥランタ・エレクタ(Duranta erecta)の育て方
ドゥランタ・エレクタは南アメリカ原産の植物ですが、日本でも容易に栽培できるのが特徴です。植え付けをする際には肥沃で水はけ...
-

-
クルクマの育て方
クルクマは歴史の古い植物です。原産としての生息地がどこなのかが分かっていないのは、歴史が古すぎるからだと言えるでしょう。...
-

-
オレンジ類の育て方
インドのアッサム地方が生息地のオレンジ類は、中国からポルトガルに渡ったのは15世紀から16世紀はじめのことでした。地中海...




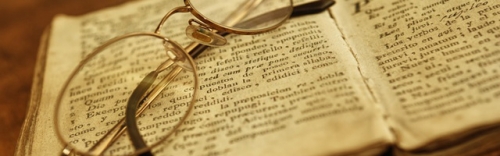





ガーベラの歴史は比較的新しく、原産地は南アフリカで、元々自生していたキクの一種をイギリス人の植物採集家ジェイムソンらが本土に持ち帰ったことが始まり取れています。アジアやアフリカには40種類が現在でも分布しています。