トウガン(ミニトウガン)の育て方

育てる環境について
トウガンの産地は愛知県、沖縄県、岡山県と言った地域の栽培量が多いのが特徴です。冬瓜と書くのは、冬場まで保存が出来ると言う意味を持つもので、旬としては夏場になります。お店などでは6月頃から9月頃にかけて店頭に並んでいますが、
冷蔵庫などの冷暗所に保存をしておけば日持ちがすると言います。また、収穫時期になるとトウガンの表面には白い粉でもあるブルームが現れるので、家庭菜園で栽培をしている場合などでは、収穫時期のタイミングが解りやすいと言った利点も有ります。
一般的なトウガン以外にも、重量が1~2kgほどの小さなミニトウガンも人気が高く、家庭菜園で栽培をしている人も多いと言います。尚、トウガンは生育が旺盛であり、2メートル四方に対して1株植えとなります。本葉が7~8枚になった時に摘心をしますが、
それ以降はそれ程手間がかからないのが特徴です。育てる環境は、日当たりが良い場所であることや、水はけが良い環境を作り出す事です。植え付けを行う2週間前に苦土石灰を1㎡あたり200gを施肥し、牛糞たい肥を2.5kgもしくは鶏糞たい肥を1.2kgと化成肥料を180gをまいて良く耕しますが、
耕す時は、深さが20~30cm程の深さまで耕して土を作ります。尚、肥料などについてはそれぞれの肥料の説明書を読んで適量を与えてあげます。また、ツルが良く伸びる事からも、株元から2mくらいの範囲に施肥を行っておくことが生育を高めることが出来る環境を作り出せます。
種付けや水やり、肥料について
トウガンやミニトウガンの育て方のポイントとして植え付け時期と収穫時期を知っておく必要が有ります。寒冷地においては5月の下旬から6月の下旬が植え付け時期で、収穫時期は8月上旬から9月下旬頃となり、中間地では5月から6月の中旬頃に植え付けを行い、収穫は7月の中旬から9月の中旬頃になります。
暖地においては4月の初旬頃から5月の下旬頃に植え付けを行い、収穫は7月から9月の中旬頃になります。種まきについては発芽を促すために高温が必要となりますが、17度から30度で発芽は可能になります。尚、発芽までに時間を要する事も有りますが、
その間は種が乾燥しないように適度な水やりが大切です。また、発芽と言うのは種の種類により比較的早い時期に発芽をするものと、1か月ほどかかるものが在りますので水をあげて種が乾燥をしないよう管理をしてあげます。
発芽をした後は、土が乾燥をしたら水をあげると言った管理を行う事で成長を促してくれますが、追肥や土寄せはその都度行っておくことで成長を促進することが出来ますし、土寄せを行う事で株が倒れる事も防止出来ます。
因みに、耕した時に肥料を施しておきますが、この時にバークや腐葉土と言った有機質の土壌改良材を入れてあげると、土壌はふかふかした状態になり、水はけも良くなると言います。また、トウガンやミニトウガンは発芽後に4~5本の子蔓を伸ばして育成するケースが多くのが特徴で、
1つのツルに2~3個収穫出来る事も有ります。摘心は、親蔓の勢いが良い段階で、本葉が5~6枚以上の時に行うのが良いのですが、勢いが少ない場合は摘心せずにそのままにしておいても良いと言います。
増やし方や害虫について
発芽が行われるとツルが伸びて来る事になりますが、摘心においてはツルの状態を見て行うかそのままにしておくかを決める事になります。勢いよく伸びる親ツルが在る場合は、本葉が5~6枚の時に摘心をし、そうではない場合はそのままにしておきます。
追肥については気温が上昇して、ツルの勢いが良くなった段階でトウガンやミニトウガンの実がついているか否かを確認し、追肥を施してあげます。元気な状態のミニトウガンやトウガンの場合は、茎の直径が1cm近く在り、葉は顔より大きくなるのが特徴です。
尚、露地栽培の場合は梅雨明けになると急激に成長が早まる事も有ります。実がどんどん大きくなると、色も濃い緑色になり、表面いには産毛のような毛が沢山生えてきます。この産毛の様な毛は棘の様なものであり、直接触ると怪我をするので軍手などを利用して触れるようにします。
また、トウガンやミニトウガンは表面に白い粉が発生した段階が収穫時期とも言われており、秋時期などの気温が低下する時期になると、実の成長は停止しますので、白い粉が発生した段階で収穫をしてあげます。尚、トウガンやミニトウガンは害虫としてアブラムシなどが発生する事が多いのが特徴です。
アブラムシなどが発生した場合は、殺虫剤を散布して退治しますが、食品成分を利用して製造されている殺虫殺菌剤や、天然のヤシ油を利用して製造されている殺虫殺菌剤などを利用して退治をしてあげれば安心して食べることが出来ます。
トウガン(ミニトウガン)の歴史
トウガンは漢字で書くと冬瓜と書きますが、冬の瓜と言う事からも旬が冬のように感じる人も多いものです。しかし、冬瓜と書く理由は、トウガン(ミニトウガン)が冬までもつ、冬まで保管が出来る事からも冬瓜と書くのだと言われています。
原産はインドだと言われており、3世紀頃にインドから中国に伝わり、5世紀頃に中国から日本に伝来したと言われています。奈良時代に書かれたと言われている正倉院文書の中には、冬瓜や冬瓜の和名でもある鴨瓜と言った事が記載されており、
平安時代に書かれたと言われている本草和名の書物では、白冬瓜の項目の中に和名でもある加毛宇利の事が記載されており、古い時代から冬瓜と言う食材が存在していたことが解ります。尚、先ほども説明をしたように、トウガンと言うのは冬場まで保管が出来ると言われている野菜なのですが、
これは夏場に収穫したものを冷暗所で保存を行っておくことで冬まで日持ちがすると言う事です。現代には冷蔵庫と言うものが在りますので、冷暗所となる冷蔵庫の野菜室などに保管をしておけば貯蔵も可能ですが、昔の人はどのように保存をしていたのか気になる話です。
しかしながら、冬瓜と言った漢字で読みを作ったのは現代人ではなく昔の人となりますので、昔の人々は工夫を行って夏に収穫した冬瓜を何らかの形で保存をし、冬場の食材として利用していたのではないかと考えられており、古い時代の人々の知恵が現代に生かされていると言えます。
トウガン(ミニトウガン)の特徴
中国からトウガンは伝来されていたのですが、トウガンと言うのは、ウリ科のつる性一年草になります。別名、シブイやトウガ、カモウリとも呼ばれており、ウリ科のつる性一年草と言っても、実は大きくなると短径30cm、長径80cmになると言われており、このようなサイズになると重量としては15kgになると言います。
また、トウガンにはミニトウガンと呼ばれるものも有り、こちらは重量が1~2kgと小ぶりになっており、ミニトウガンや姫冬瓜と呼ばれるものが在ります。トウガンは、円筒形のもの、丸形のものなどの形状に分類されており、円筒形のものは長冬瓜、
丸形のものは大丸冬瓜と呼ばれており、琉球種は沖縄県などで栽培されています。尚、トウガンやミニトウガンは全国的に栽培が行われており、生息地は幅広いエリアになっています。但し、暑さを好む野菜であることからも、沖縄県や愛知県などでの生産量が多いのが特徴です。
因みに、冬瓜は皮が緑色、完熟すると皮全体に白い粉が出て来ます。この白い粉はブルームと呼ばれるものであり、ブルームが生じる事で完熟したことを教えてくれます。但し、姫冬瓜については皮が濃い緑入れであり、ブルームが生じることは少ないとされています。
収穫時期としては7月中旬~9月中旬頃であり、夏の野菜になります。実の部分を食べる野菜で、果肉は透明感を持ち、淡泊な味で過熱をする事で果肉は柔らかくなるのが特徴で、柔らかくなることで出汁などを染み込ませるのが調理のポイントと言います。
緑のカーテンの育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ヘデラの育て方
タイトル:トケイソウの仲間の育て方
-

-
ハツユキカズラの育て方
ハツユキカズラはキョウチクトウ科テイカズラ属で、日本の本州以南と朝鮮半島が原産の植物になります。名前の由来は、葉に入った...
-

-
グラマトフィラムの育て方
グラマトフィラムの原産は東南アジアで、暑い地域の植物です。生息地では12種の原種があります。洋蘭の一種で、熱帯からヨーロ...
-

-
セイロンライティアの育て方
セイロンライティアはキョウチクトウ科の植物となります。白くてかわいらしい花がとても素敵なのですが、原産はスリランカとなっ...
-

-
シペラスの育て方
シペラスは、カヤツリグサ科カヤツリグザ(シぺラス)属に分類される、常緑多年草(非耐寒性多年草)です。別名パピルス、カミヤ...
-

-
ゴーヤーの育て方のポイント
ゴーヤーというと沖縄原産のような気がしますが、実際はインドを中心とする東南アジアです。それが中国に伝わりそののちに日本に...
-

-
ノリウツギの育て方
ノリウツギはアジサイ科のアジサイ属の落葉する背の低い木で原産国は中国やロシア周辺であると考えられています。和名のノリウツ...
-

-
緑のカーテンの育て方
緑のカーテンの特徴としては、つる性の植物であることです。主に育てるところとしては窓の外から壁などにはわせるように育てるこ...
-

-
ユキヤナギの育て方
古くから花壇や公園によく植えられているユキヤナギは、関東地方以西の本州や、四国、九州など広範囲に生息しています。生息地は...
-

-
カネノナルキの育て方
多年草であるカネノナルキは、大変日光を好む植物です。しかし、日陰で育てても特に枯れるわけではありません。非常に生命力溢れ...
-

-
アリウムの育て方
原産地は北アフリカやアメリカ北部、ヨーロッパ、アジアなど世界中です。アリウムは聞きなれない植物かもしれません。しかし、野...




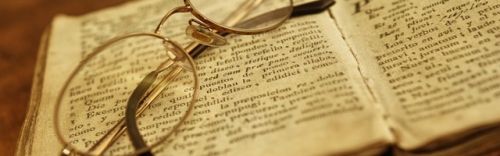





トウガンは漢字で書くと冬瓜と書きますが、冬の瓜と言う事からも旬が冬のように感じる人も多いものです。しかし、冬瓜と書く理由は、トウガン(ミニトウガン)が冬までもつ、冬まで保管が出来る事からも冬瓜と書くのだと言われています。