ニコチアナの育て方

育てる環境について
乾燥には比較的強いですが、高温多湿になると株が弱るので、特に梅雨どきには注意します。本来の原産地である南米の環境なら冬越しして翌年も開花しますが、日本の寒さには弱く、大半の品種は一年草として扱います。植えつける前にはあまり密生しないように離して植える事が必要です。
65cmのプランターなら4株までにし、苗のうちから詰め過ぎないようにしておきます。また、茄子科の植物、花であればペチュニアなどは同じ場所や土で育てると連作障害を発生させるので、植える場合は1年以上時間を置いて植えつけなければなりません。
養分が土の中から欠乏する事で発生すると言われています。日当たりが良くて風通しがいい場所が向いています。鉢植えで室内に置く時は、窓際の日当たりがある場所で楽しみます。また、雨に当たると枯れてしまう事があるので、梅雨の時期は気をつけることが大切です。
雨に当たりすぎで色が剥げてしまわないように管理する必要があります。低温の10度で生育が止まり、5度になると枯れてしまいますが、15度以上なら冬でも花が咲きます。暖地や一部の平地では露地でも冬を越す所があります。
花や葉が枯れていたら早めに除去しておくと、病気になりにくく、長く楽しめます。平均的に暑さ寒さには強い花ですが、高温期の水切れや、種類によっては真夏に花を休める品種もあり、注意が必要です。植え付け時に水やりを適度にすれば、開花の時にたくさんの花を楽しめます。
種付けや水やり、肥料について
種まきは4月か秋ごろが良く、種はとても細かいので、バーミキュライトや種まき用土を使って発芽させるほうがいいです。新しい種ほどよく発芽し、発芽には日光による日当たりを必要とするので、土をかけないで種に日を当てるようにしておきます。
25度が発芽温度で、本葉が3から4枚になったらポットなどへ仮に植え替えておきます。本場が8枚になった頃に植えたい場所へ移しますが、用土は水はけと水もちが良いやや酸性の土壌が向いています。庭植えなら株間は20cm程度が適当です。
鉢植えなら赤玉土の小粒、ピートモス、バーミキュライトを混ぜ込んだものがよく、根付くまでは水を切らさないように管理し、適度に乾かし気味に保ちます。6月末頃まで植えつけることができます。水やりの目安は鉢植えの場合、土の表面が乾いたらたっぷりとあげるようにします。
開花時期はおもに6月から11月ですが、暖かい所では冬も枯れないで翌年に花を楽しむ事ができます。夏の時期に開花する植物があまりないので、春から秋にかけて開花し続けるニコチアナはとても人気がある種類です。植えつける前には化成肥料を土に混ぜ込んでから植えつけます。
植えてからも、開花が全て終わった頃も、肥料を与えておけば翌年にも元気に開花します。肥料の量は月に1回か2回緩効性化成肥料を置き肥しますが、1平方メートルあたり250gを目安に、やや多めに使うか、液肥を使用します。増えてきたら花茎を切って分枝させると株が広がります。
増やし方や害虫について
増やし方は種まきで増やすか、ある程度株が成長してから花茎を切って分枝させる事ができます。分枝させたほうがこんもりとなって形良く開花し、開花の期間も長くなります。ニコチアナは群生する特徴があるので、広い場所にたくさん咲かせたい場合は同じ品種で
草丈を統一しておくと見栄えも良く管理がしやすいです。背丈が高くなる品種は支柱を立てるなど工夫して管理します。開花時期が初夏から秋にかけての長い期間なので、散った花びらなどをこまめに除去する必要があります。また、品種によっては下の位置にある葉などが枯れやすく、
枯れた葉を取り除く事も必要です。密集して植えて気がつかずに枯れた部分を放置してしまうとそこからカビ菌が原因の病気になり枯れてしまうので、注意しておきます。葉が黄色くなって枯れてしまうモザイク病になりやすいので、早めに葉を除去します。
その原因となるウィルスを媒介しているのが3月から新芽に発生するアブラムシで、モザイク病になる前にアブラムシをまず早く発見して取り除く事が大事なポイントです。他には灰色カビ病があり、ウィルス性の病気は他の植物にも伝染する可能性が高く、
枯葉や落ちた花を放置すると菌が発生して被害を広げてしまうので、早めに取り除く事が大事です。他の害虫にオオタバコガがいます。5月から10月に発生して夜間に成虫が蕾に卵を産みつけ、幼虫は蕾を食べます。対処方法は見つけたら捕殺する事が大切です。
ニコチアナの歴史
南北アメリカが原産のニコチアナは、主な生息地が南アメリカで、日本では16世紀にスペイン人によって持ち込まれた歴史があります。園芸鑑賞用のニコチアナはタバコの原材料と同じ品種で、本来茄子科に属していて、亜熱帯から熱帯の地域、
アメリカ、ポリネシア、オーストラリアなどで栽培されています。最初に南アメリカからヨーロッパに医療用や薬用でのタバコの原材料として持ち込まれたのは、15世紀であり、現在残っている品種は2種類、ニコチアナ・ルスチカと、ニコチアナ・タバカムです。
ルスチカは3000m程の高地、エクアドル、ペルー、ボリビア原産と言われていて、タバカムは1500m程の温暖な気候を好み、ボリビアとアルゼンチン国境あたりが原産と言われています。タバカムは世界中に栽培が広がっていて、タバコの代名詞の品種となっています。
日本では、園芸品種にもニコチンが含まれている事から、1985年にタバコの法律が改正され、園芸品種も家庭で栽培する事が認められました。園芸品種として紹介されているニコチアナは、その仲間が70種類ほどあり、花の色も白、ピンク、赤、黄、緑と多く、開花を
次々にするので花壇を豪華に飾る寄せ植え用として、特に、ニコチアナ・アラタが好まれています。また、ジャスミン・タバコと呼ばれる白い花は、良い香りを楽しむ事が出来ます。タバコの薬効を目的とした栽培は紀元前から行われていたので、とても長い歴史がある花となっています。
ニコチアナの特徴
ニコチアナの語源ですが、この花を最初にフランスへ紹介したポルトガル領事ジャン・ニコの名前にちなんで名づけられました。観賞花として、花タバコの名前で販売されています。花が小さな星のように見えて、次々に開花する特徴があり、1年草ですが育て方が簡単で、
園芸品種としては広い場所に群生させる目的で植えられる事もあります。ニコチアナの草丈は本来ならば1mから1.5mですが、矮小品種では70cmほどの丈になり、鉢植えにすると20から30cm程度になります。また、茄子科の植物の特徴として、同じ場所で作り続けない事が大切です。
毎年繰り返して植えると連作障害を起こします。きれいな花を咲かせる為に、終わった花は捨てて、こまめにきれいな状態を保つ事が大切です。花が最後まで終わったら、花穂を折り取っておきます。葉の間から枝茎を伸ばして育ち、その先に枝分かれした花穂をつけるので、
枯れた所は葉の付け根から切り取っておく事が大切です。わきから芽が出て花が咲きますので、バランスの良い格好に整えるなら、このわき芽の手入れを怠らないようにします。また、ニコチアナの園芸品種はアラタが大半で、アラタと他の品種を掛け合わせて作られていて、
サンデラエ、スアウエオレンスがあります。比較的にどの品種も丈夫で作りやすい特徴があります。原産地が高い山などの厳しい環境でも生育できる花ですから、植え込み、鉢植え、どちらでも楽しめる花として人気です。
-

-
トウヒの仲間の育て方
トウヒはマツ科に属する樹木であり、漢字で表すと唐檜と書き表されます。漢字の由来から日本には、飛鳥時代~平安時代現在の中国...
-

-
タイリントキソウの育て方
タイリントキソウは別名タイワントキソウとも呼ばれています。球根性の小型のラン科の植物でプレイオネ属の暖地性の多年草です。...
-

-
ナスタチュームの育て方
黄色やオレンジの大きな花をつぎつぎと咲かせるため、ハーブの利用だけでなく観賞用としても人気のナスタチューム(ナスタチウム...
-

-
ミントの育て方
ミントは3500年ほど前の古代ギリシャですでに生薬として利用されていました。歴史上でも最も古い栽培植物として知られていま...
-

-
ワイヤープランツの育て方
ワイヤープランツは観葉植物にもなって家の中でも外でも万能の植物です。単体でも可愛くて吊るして飾っておくとどんどん垂れてき...
-

-
トロロアオイの育て方
トロロアオイは花オクラとも呼ばれるアオイ科の植物の事です。見た目はハイビスカスみたいなとても美しい花を咲かせます。この花...
-

-
家庭菜園で野菜を育てると収穫の喜びを味わう事ができます
毎日何気ない一日を過ごしていると、何かを始めてみたくなる事は誰でも経験する事です。そんな時にお勧めな事として、自宅で家庭...
-

-
メキャベツの育て方
キャベツを小さくしたような形の”メキャベツ”。キャベツと同じアブナ科になります。キャベツの芽と勘違いする人もいますが、メ...
-

-
スリナムチェリーの育て方
スリナムチェリーはフトモモ科の常緑の低木でこの樹木の歴史は非常に古くブラジルの先住民族が赤い実を意味するスリナムチェリー...
-

-
スモークツリーの育て方
スモークツリーはウルシ科コティヌス属の雌雄異株の落葉樹になり、イングリッシュガーデンなどのシンボルツリーとして多く利用さ...




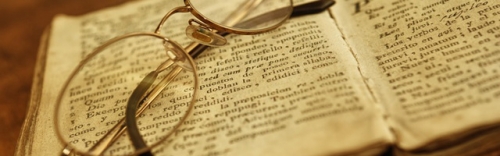





南北アメリカが原産のニコチアナは、主な生息地が南アメリカで、日本では16世紀にスペイン人によって持ち込まれた歴史があります。園芸鑑賞用のニコチアナはタバコの原材料と同じ品種で、本来茄子科に属していて、亜熱帯から熱帯の地域、アメリカ、ポリネシア、オーストラリアなどで栽培されています。